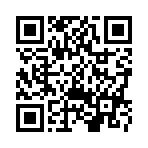2019年05月26日
鉄製AKの普及はココから始まった
以前も申しましたように我輩、過去にカラシニコフを10丁以上買いました。
(以下が過去購入したカラシニコフの数々です↓)
マルイ製AK47・・・8年ぐらい使用、友人に木スト予備マガジン付き5000円で売る
マルイ製AKS47・・・中古で購入、2年ぐらいでストックが折れたので誰かにあげた
マルイ製βスペツナズ・・・外装を殆ど交換してAK74になりながらも現在に至る
マルイ製AK47その2・・・実銃用バイポットを取り付けたロングバレルLMGカスタム
マルイ製AK47Sその2・・・KG9ストックを取り付け、ショートバレルにカスタム
ICS製AK74M・・・初めて購入した海外製電動ガン、ただし台湾製
D-BOY製AKS74U・・・初の中華製品、各部亜鉛部品が面白いように崩壊
CYMA製AKM・・・ストックの木材がクソだったので直ぐに手放した
CYMA製AIMS・・・念願のルーマニアカラシニコフ、3~4年所有
マルイ製AKS74・・・初の次世代電動、転勤記念に同志から贈られる
マルイ製AKS74U・・・殆ど使われることなくRPK購入資金となる
D-BOY製AKMS・・・かなり気に入ってたがメカボックスがいくら調整しても駄目だった
CYMA製RPK74・・・念願の分隊支援カラシニコフ、青森で大活躍!
CYMA製AK47・・・ベトコン装備用に仕入れた中華次世代AK、今でも所有
マルイ製AK74MN(だったと思われるもの)・・・ジャンクをタダで入手、足りない部品買い集めて復活
でも根っからの貧乏性が災いしているのか、それともただの間抜けなのか、
LCTとかE&Lといったメーカーの鉄分含有率の高い
カラシニコフを購入した試しがありませんでした。

AKが好きだと豪語しておきながら、決定版を所有していない。
それってAK好きとしてどうなんだろうかね?と思った結果、
ある日ヤフオクにVFC製AKMSのガワが0.5パットンという
中古とはいえまぁまぁのお値段で転がっていたので買うことにしました。
VFC製AKは過去にAKM、AKMS、AK74、AKS74、AKS74Uが販売され、
中身入りのコンプリートモデルは各ショップで50000円以上で売られていたのですが、
元々はマルイAK47用メカボ、チャンバー、インナーバレルを必要とする
35000円ぐらいの外装キットとして販売されていたものです。
現在では何処のショップにも新品では売っていない
(有名店では取扱はあるみたいだけど、ココ数年SOLD OUT状態)
VFC製AKMSのレビューを綴るのもどうかと思いはしましたが、
ついに決定版のAKを我が手にした悦びのほうが大きいので敢えて掲載します。

VFC製カラシニコフは史上初のマルイコピーではない
独自の構成によって作り上げられたAKでした。
マルイ製みたいなネジ止めの結合ではなく、ピンによる結合、
実銃通りの分解が可能な上下ハンドガードは全てVFCが本家。
それ以前にICSやG&G、CYMAがAKの電動ガンを販売しており、
それらはすべてマルイAK47のコピーだったのですが、
VFC製AKが登場してからというもの、AK47系列はそのままマルイコピーで製造されるも、
AKM、AK74系列のカラシニコフは全てVFC製AKをパクって開発、製造されたのです。
現在ではAKの最高峰として名高いLCTのAKも、元はといえばVFCが母体。
我輩のあやふやな記憶によるとイノカツというメーカーが
VFC製AKを真似たか、それともお互いの間に何らかの良い関係があったのか、
AKのリアルな外装キットをイノカツブランドで販売していましたが、
そのイノカツがLCTに名を変えて中身入りのAKを作るようになって今に至る模様。
つまり、タイトルにもあるようにVFC製AKこそがリアルなカラシニコフトイガンの元祖であり、
現在のAK天国(泥沼地獄とも言う)に至る要因と言っても過言ではない(適当)。

我輩が数あるロシアンカラシニコフの中で一番好きなのがAKMS。
その理由はストックを伸ばしたときの、この無骨でクールなデザイン。
現在では時代遅れ感のあるスイングタイプの折りたたみストックが
古いライフルを好ましく思う我輩の神経を刺激するんですね。
「AKS47も似たようなもんじゃないか?」とおっしゃる方も居られるでしょうが、
AKS47はストックが斜めなのがだらしねぇな、真っ直ぐなAKMSの方が美しい。

とは言ったものの、ナチスドイツのMP40を発端としたこの折りたたみストック、
展開はやり難いし頬付けで構えてもしっくり来るものではありません。
しっかり構えて撃ちたいのなら、固定ストックのAKMを買うべきでしょう。
でもAKは無骨であることこそが真骨頂であると考えれば、
このAKMSこそが数あるAKの中でも無骨さを表現しており
洗練と野暮の中間位置にある途上の美があるというのが我輩の思考。

VFC製AKはグリップ以外、外装に樹脂は使われておりません。
ハンドガードは勿論実銃と同じく合板、外装は全て鉄です。
(一部アウターバレルがアルミ製のものもあるらしい)
フロント周りから見ていきましょう。
斜めにカットされたAKM独特のフラッシュハイダーは
切り口の仕上げが意外と雑で実はLCTの製の方が綺麗。
余談ですがこの斜めハイダー、銃本体側から見ると右傾きの位置で固定されているんですが、
その理由は実銃のライフリングが6条右転のため、
発射される弾丸は右回りに出ると共に斜め右上に反動が生じるので、
発射時の燃焼ガスを斜め右上に逃がし、反動を相殺させる形状なのだとか。
フロントサイト、ガスチューブ周りは鉄ですが、キャストアイアンで出来ています。
質感的にはCYMAのものに近い感じで、出来は良いけどシャープさに欠ける。
我輩的にはLCT、E&Lの方がAKらしい立派な仕上がりな記憶。

合板製のハンドガードはLCT製とは違い、強化ピンが打ち込まれています。
下に水抜き穴も空いており、ニス仕上げもE&L製AKのように厚ぼったくない。
バランスの取れた色具合で美しいの一言です。
リアサイトブロックはキャストアイアンですが、リアサイトは削り出し。
リアサイトは1から10まで数字が書かれているタイプ。
サイトは良いんですが、基部の仕上げはLCTと比べると今ひとつですね。

フレームは鉄板加工、リベットもしっかり再現。
仕上げは他社製AKと比べても遜色ない美しい出来です。
レシーバーカバーも良い感じの仕上がりで素晴らしい。
ココだけは後発のAKに勝る部分と言えるでしょう。
チャージングハンドルは鋳造でバッテリー入れていないとガッタガタ動きやがります。
おそらく、フレーム内部のレールが短くて残念なことになっている模様。
ココの作りの甘さに我輩「VFC、言われていたほどのものじゃねぇな」と落胆。
トリガーガードはリベット留めなので交換するorマグウェル取り付けるには
リベットをグラインダーで削るかドリルでブチ抜くしかありません。
マガジンキャッチもカシメで取り付けているのでドリルでブチ(以下略)

更に残念だったのがグリップ。左がVFC製のもの。
ベークライトの色合いをどうにか表現してはいるものの
表面がテッカテカツルツルのプラ丸出しの残念なグリップだったので、
手持ちのD-BOY製のグリップ(黒い方)と交換しました。
まー恐らく、LCTやE&LのAKがよく出来ているのは、
VFCをコピーしつつ、悪い部分は出来る限り修正した結果なんでしょうね。
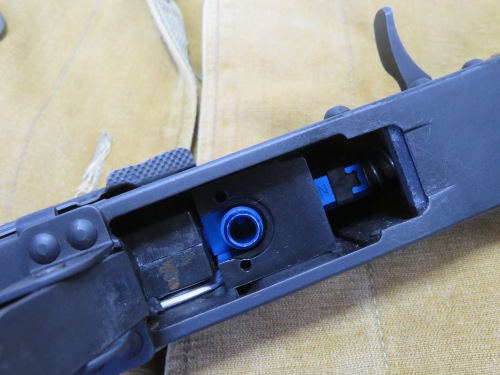
本来のキットではチャンバーはマルイAK47別途必要なのですが、
我輩が落札したブツにはPRO WINのCNCチャンバーが付属していました。
このメタルチャンバーはメカボにも固定するネジ穴があり、
堅固な固定で確実な命中精度が売りらしいんですが、
いざゲームに持ち込んでみると時々弾が出なくて残念な状況に。
手持ちのマルイAK用チャンバーと交換したら弾出るようになったんで、
やっぱマルイの中身は間違いない逸品なんだなと謎の感動。
そして社外カスタムパーツは相性があるんだなと再認識。

回転式のフォールディングストックは伸ばしても畳んでもガタガタします。
そして折り畳むとハンドガードに傷をつけるという・・・
可動させる時はストック取付部のロックボタンをぐっと握って押しながらストックを回す。
尚、バットプレート?に相当する銃尾部分にロックはありません。
そしてこの部分に付属している後部スリングスイベル、
見た目的には回りそうですが残念ながら回転しません。
AKMは1950年代後半に登場したライフルなので、
そこら辺今のライフルと違って優しい作りではありません。

尚、AKMSはフォールディングストックの為&光学?何それ美味しいの?な
時代の銃が故にフレーム左側にはマウントベースはありません。
どーしてもドットサイトorスコープ付けたければ固定ストックのAKMを買いましょう。

VFC製AKMSはLCTやE&L製品同様、マルイAK47用マガジン使用可能です。
キットに同封されていたマガジンはマルイの多弾マガジンと完全一致なブツでした。
最近では海外製で安いAK47用のマガジンが色々出回っておりますが、
少しぐらいお値段が高かろうが王道を征くマルイ製マガジンを買うのがよろしいようで。
でもCYMAのAK用マガジンは案外良い出来でトラブルも少なく、侮れない。

我輩の手元に来た時のVFC製AKMSの姿。
あれ、インナーバレルとチャンバーが写っていない。まあいいや。
元々バラバラ状態で分解する必要がなかったので、
VFC製AKMSの分解手順を紹介することが出来ません。
なので組み立て手順を載せることにしますが、多分需要は無いな。
尚、VFCもLCTもE&Lも構造はほぼほぼ一致なので、
そこら辺のAKをお持ちなら一応参考にはなるはずです。

メカボックスをフレームに突っ込む際は、この引掛け部分に注意。
無理やり押し込むと配線がブチ切れる恐れがあります。
尚この部分、配線が遊ばないようにするためのガードです。
塩梅よくメカボックスをぶっ込んだらグリップを取り付けましょう。

そしてセレクタープレートの取り付け。
LCT製AKのようにメカボックスのセレクターを動かすパーツが
セレクターと一体化しておりますので組付けは簡単ですが、
社外品を取り付ける場合はマルイAKのココの部品が必要。
取り付けたらセレクター固定用のスクリューを締めます。

次に取り付けるのはインナーバレル&チャンバー&スプリング。
ちゃーんとゴム(チャンバーの)を装着してから入れるんだぞ、解ったな?
スプリングを入れ忘れるとチャンバーがガタガタするのでご注意。
そしてフレーム内部のチャンバー固定ブロックにチャンバーをクロスネジで取り付けます。

その後リアサイトブロックと一体化したアウターバレルアッセンブリーを突っ込み・・・

リアサイト基部にあるイモネジを締めてフレームに固定し、
リアサイト基部のピンを叩き込んでガッチリ固定します。

リアサイトの板バネを取り付け、リアサイトを溝に突っ込みながら取り付けたら、
アウターバレルに付いている固定金具を移動させてアンダーハンドガードを取り付けます。
指さしている部分のレバーを回転させると固定されます。

尚、我輩の個体はハンドガードに遊びが無くてギッチギチで、
取り付けに相当苦しい思いをしたので基部が干渉する部分
(ハンドガードの白くなっている部分)を削ったら
1mm程削りすぎて取り付けると少々ガタが出てしまいました。

アッパーハンドガードを取り付けて固定したら
バレル下部にあるクリーニングロッド(何とリアルサイズ!長い!)を取り付けます。

そしてチャージングハンドルをフレーム内にぶっ込み、
チャージングハンドル固定ロッドとスプリングをメカボックスに取り付けて
チャージングハンドルの穴に通して固定し、
レシーバーカバーを取り付ければ完成です。
バッテリーはレシーバーカバー内部に収納します。
使えるのはリポでもリフェでもニッ水でも何でもいいですが細いバッテリーのみ。

ナム戦装備(ただし北側のなw)でAKMSというのは見慣れない感じではありますが、
1974年ぐらいまで続いたヴェトナム戦争で1959年に正式化されたAKMSが
旧ソ連から実験も兼ねて持ち込まれて当時のヴェトナムで使われた可能性は
微粒子レベルで存在しているとは思いますので問題はないでしょう。
メカボックス、インナーバレル、チャンバーと言ったパーツは、
全て手持ちのものを取り付けて調整しているので
VFC製品自体の性能をどうこう語ることは不可能ですが、
過去20数年の実績ある我輩の手で組んだので特に問題なし。
トータル的に見ると希少性や過去の良い評判や噂を元に、
わざわざVFC製AKに手を出す必然性は無いというのが我輩の見解です。
どうしてもAKMSが欲しいなら現在生産されているLCTやE&L製品を買うべき。
そして持ち運びにコンパクトである必然性がないのなら、
敢えてAKMSを選ぶ必要もないというのも我輩の持論。
逆に言えば敢えてコイツを欲する輩は我輩みたく捻くれ者である可能性あり。
でも我輩的にはVFC製AKMS、満足の逸品です。
ただやっぱりチャージングハンドルがガッタガッタなのは気になるなぁ。
(以下が過去購入したカラシニコフの数々です↓)
マルイ製AK47・・・8年ぐらい使用、友人に木スト予備マガジン付き5000円で売る
マルイ製AKS47・・・中古で購入、2年ぐらいでストックが折れたので誰かにあげた
マルイ製βスペツナズ・・・外装を殆ど交換してAK74になりながらも現在に至る
マルイ製AK47その2・・・実銃用バイポットを取り付けたロングバレルLMGカスタム
マルイ製AK47Sその2・・・KG9ストックを取り付け、ショートバレルにカスタム
ICS製AK74M・・・初めて購入した海外製電動ガン、ただし台湾製
D-BOY製AKS74U・・・初の中華製品、各部亜鉛部品が面白いように崩壊
CYMA製AKM・・・ストックの木材がクソだったので直ぐに手放した
CYMA製AIMS・・・念願のルーマニアカラシニコフ、3~4年所有
マルイ製AKS74・・・初の次世代電動、転勤記念に同志から贈られる
マルイ製AKS74U・・・殆ど使われることなくRPK購入資金となる
D-BOY製AKMS・・・かなり気に入ってたがメカボックスがいくら調整しても駄目だった
CYMA製RPK74・・・念願の分隊支援カラシニコフ、青森で大活躍!
CYMA製AK47・・・ベトコン装備用に仕入れた中華次世代AK、今でも所有
マルイ製AK74MN(だったと思われるもの)・・・ジャンクをタダで入手、足りない部品買い集めて復活
でも根っからの貧乏性が災いしているのか、それともただの間抜けなのか、
LCTとかE&Lといったメーカーの鉄分含有率の高い
カラシニコフを購入した試しがありませんでした。

AKが好きだと豪語しておきながら、決定版を所有していない。
それってAK好きとしてどうなんだろうかね?と思った結果、
ある日ヤフオクにVFC製AKMSのガワが0.5パットンという
中古とはいえまぁまぁのお値段で転がっていたので買うことにしました。
VFC製AKは過去にAKM、AKMS、AK74、AKS74、AKS74Uが販売され、
中身入りのコンプリートモデルは各ショップで50000円以上で売られていたのですが、
元々はマルイAK47用メカボ、チャンバー、インナーバレルを必要とする
35000円ぐらいの外装キットとして販売されていたものです。
現在では何処のショップにも新品では売っていない
(有名店では取扱はあるみたいだけど、ココ数年SOLD OUT状態)
VFC製AKMSのレビューを綴るのもどうかと思いはしましたが、
ついに決定版のAKを我が手にした悦びのほうが大きいので敢えて掲載します。

VFC製カラシニコフは史上初のマルイコピーではない
独自の構成によって作り上げられたAKでした。
マルイ製みたいなネジ止めの結合ではなく、ピンによる結合、
実銃通りの分解が可能な上下ハンドガードは全てVFCが本家。
それ以前にICSやG&G、CYMAがAKの電動ガンを販売しており、
それらはすべてマルイAK47のコピーだったのですが、
VFC製AKが登場してからというもの、AK47系列はそのままマルイコピーで製造されるも、
AKM、AK74系列のカラシニコフは全てVFC製AKをパクって開発、製造されたのです。
現在ではAKの最高峰として名高いLCTのAKも、元はといえばVFCが母体。
我輩のあやふやな記憶によるとイノカツというメーカーが
VFC製AKを真似たか、それともお互いの間に何らかの良い関係があったのか、
AKのリアルな外装キットをイノカツブランドで販売していましたが、
そのイノカツがLCTに名を変えて中身入りのAKを作るようになって今に至る模様。
つまり、タイトルにもあるようにVFC製AKこそがリアルなカラシニコフトイガンの元祖であり、
現在のAK天国(泥沼地獄とも言う)に至る要因と言っても過言ではない(適当)。

我輩が数あるロシアンカラシニコフの中で一番好きなのがAKMS。
その理由はストックを伸ばしたときの、この無骨でクールなデザイン。
現在では時代遅れ感のあるスイングタイプの折りたたみストックが
古いライフルを好ましく思う我輩の神経を刺激するんですね。
「AKS47も似たようなもんじゃないか?」とおっしゃる方も居られるでしょうが、
AKS47はストックが斜めなのがだらしねぇな、真っ直ぐなAKMSの方が美しい。

とは言ったものの、ナチスドイツのMP40を発端としたこの折りたたみストック、
展開はやり難いし頬付けで構えてもしっくり来るものではありません。
しっかり構えて撃ちたいのなら、固定ストックのAKMを買うべきでしょう。
でもAKは無骨であることこそが真骨頂であると考えれば、
このAKMSこそが数あるAKの中でも無骨さを表現しており
洗練と野暮の中間位置にある途上の美があるというのが我輩の思考。

VFC製AKはグリップ以外、外装に樹脂は使われておりません。
ハンドガードは勿論実銃と同じく合板、外装は全て鉄です。
(一部アウターバレルがアルミ製のものもあるらしい)
フロント周りから見ていきましょう。
斜めにカットされたAKM独特のフラッシュハイダーは
切り口の仕上げが意外と雑で実はLCTの製の方が綺麗。
余談ですがこの斜めハイダー、銃本体側から見ると右傾きの位置で固定されているんですが、
その理由は実銃のライフリングが6条右転のため、
発射される弾丸は右回りに出ると共に斜め右上に反動が生じるので、
発射時の燃焼ガスを斜め右上に逃がし、反動を相殺させる形状なのだとか。
フロントサイト、ガスチューブ周りは鉄ですが、キャストアイアンで出来ています。
質感的にはCYMAのものに近い感じで、出来は良いけどシャープさに欠ける。
我輩的にはLCT、E&Lの方がAKらしい立派な仕上がりな記憶。

合板製のハンドガードはLCT製とは違い、強化ピンが打ち込まれています。
下に水抜き穴も空いており、ニス仕上げもE&L製AKのように厚ぼったくない。
バランスの取れた色具合で美しいの一言です。
リアサイトブロックはキャストアイアンですが、リアサイトは削り出し。
リアサイトは1から10まで数字が書かれているタイプ。
サイトは良いんですが、基部の仕上げはLCTと比べると今ひとつですね。

フレームは鉄板加工、リベットもしっかり再現。
仕上げは他社製AKと比べても遜色ない美しい出来です。
レシーバーカバーも良い感じの仕上がりで素晴らしい。
ココだけは後発のAKに勝る部分と言えるでしょう。
チャージングハンドルは鋳造でバッテリー入れていないとガッタガタ動きやがります。
おそらく、フレーム内部のレールが短くて残念なことになっている模様。
ココの作りの甘さに我輩「VFC、言われていたほどのものじゃねぇな」と落胆。
トリガーガードはリベット留めなので交換するorマグウェル取り付けるには
リベットをグラインダーで削るかドリルでブチ抜くしかありません。
マガジンキャッチもカシメで取り付けているのでドリルでブチ(以下略)

更に残念だったのがグリップ。左がVFC製のもの。
ベークライトの色合いをどうにか表現してはいるものの
表面がテッカテカツルツルのプラ丸出しの残念なグリップだったので、
手持ちのD-BOY製のグリップ(黒い方)と交換しました。
まー恐らく、LCTやE&LのAKがよく出来ているのは、
VFCをコピーしつつ、悪い部分は出来る限り修正した結果なんでしょうね。
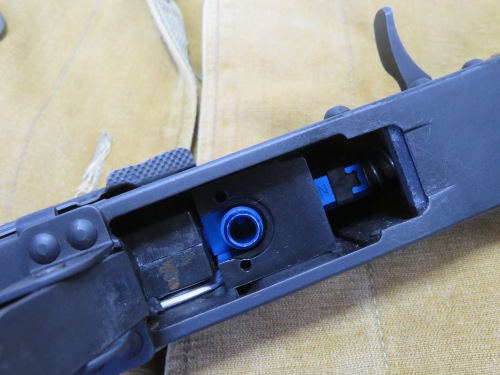
本来のキットではチャンバーはマルイAK47別途必要なのですが、
我輩が落札したブツにはPRO WINのCNCチャンバーが付属していました。
このメタルチャンバーはメカボにも固定するネジ穴があり、
堅固な固定で確実な命中精度が売りらしいんですが、
いざゲームに持ち込んでみると時々弾が出なくて残念な状況に。
手持ちのマルイAK用チャンバーと交換したら弾出るようになったんで、
やっぱマルイの中身は間違いない逸品なんだなと謎の感動。
そして社外カスタムパーツは相性があるんだなと再認識。

回転式のフォールディングストックは伸ばしても畳んでもガタガタします。
そして折り畳むとハンドガードに傷をつけるという・・・
可動させる時はストック取付部のロックボタンをぐっと握って押しながらストックを回す。
尚、バットプレート?に相当する銃尾部分にロックはありません。
そしてこの部分に付属している後部スリングスイベル、
見た目的には回りそうですが残念ながら回転しません。
AKMは1950年代後半に登場したライフルなので、
そこら辺今のライフルと違って優しい作りではありません。

尚、AKMSはフォールディングストックの為&光学?何それ美味しいの?な
時代の銃が故にフレーム左側にはマウントベースはありません。
どーしてもドットサイトorスコープ付けたければ固定ストックのAKMを買いましょう。

VFC製AKMSはLCTやE&L製品同様、マルイAK47用マガジン使用可能です。
キットに同封されていたマガジンはマルイの多弾マガジンと完全一致なブツでした。
最近では海外製で安いAK47用のマガジンが色々出回っておりますが、
少しぐらいお値段が高かろうが王道を征くマルイ製マガジンを買うのがよろしいようで。
でもCYMAのAK用マガジンは案外良い出来でトラブルも少なく、侮れない。

我輩の手元に来た時のVFC製AKMSの姿。
あれ、インナーバレルとチャンバーが写っていない。まあいいや。
元々バラバラ状態で分解する必要がなかったので、
VFC製AKMSの分解手順を紹介することが出来ません。
なので組み立て手順を載せることにしますが、多分需要は無いな。
尚、VFCもLCTもE&Lも構造はほぼほぼ一致なので、
そこら辺のAKをお持ちなら一応参考にはなるはずです。

メカボックスをフレームに突っ込む際は、この引掛け部分に注意。
無理やり押し込むと配線がブチ切れる恐れがあります。
尚この部分、配線が遊ばないようにするためのガードです。
塩梅よくメカボックスをぶっ込んだらグリップを取り付けましょう。

そしてセレクタープレートの取り付け。
LCT製AKのようにメカボックスのセレクターを動かすパーツが
セレクターと一体化しておりますので組付けは簡単ですが、
社外品を取り付ける場合はマルイAKのココの部品が必要。
取り付けたらセレクター固定用のスクリューを締めます。

次に取り付けるのはインナーバレル&チャンバー&スプリング。
ちゃーんとゴム(チャンバーの)を装着してから入れるんだぞ、解ったな?
スプリングを入れ忘れるとチャンバーがガタガタするのでご注意。
そしてフレーム内部のチャンバー固定ブロックにチャンバーをクロスネジで取り付けます。

その後リアサイトブロックと一体化したアウターバレルアッセンブリーを突っ込み・・・

リアサイト基部にあるイモネジを締めてフレームに固定し、
リアサイト基部のピンを叩き込んでガッチリ固定します。

リアサイトの板バネを取り付け、リアサイトを溝に突っ込みながら取り付けたら、
アウターバレルに付いている固定金具を移動させてアンダーハンドガードを取り付けます。
指さしている部分のレバーを回転させると固定されます。

尚、我輩の個体はハンドガードに遊びが無くてギッチギチで、
取り付けに相当苦しい思いをしたので基部が干渉する部分
(ハンドガードの白くなっている部分)を削ったら
1mm程削りすぎて取り付けると少々ガタが出てしまいました。

アッパーハンドガードを取り付けて固定したら
バレル下部にあるクリーニングロッド(何とリアルサイズ!長い!)を取り付けます。

そしてチャージングハンドルをフレーム内にぶっ込み、
チャージングハンドル固定ロッドとスプリングをメカボックスに取り付けて
チャージングハンドルの穴に通して固定し、
レシーバーカバーを取り付ければ完成です。
バッテリーはレシーバーカバー内部に収納します。
使えるのはリポでもリフェでもニッ水でも何でもいいですが細いバッテリーのみ。

ナム戦装備(ただし北側のなw)でAKMSというのは見慣れない感じではありますが、
1974年ぐらいまで続いたヴェトナム戦争で1959年に正式化されたAKMSが
旧ソ連から実験も兼ねて持ち込まれて当時のヴェトナムで使われた可能性は
微粒子レベルで存在しているとは思いますので問題はないでしょう。
メカボックス、インナーバレル、チャンバーと言ったパーツは、
全て手持ちのものを取り付けて調整しているので
VFC製品自体の性能をどうこう語ることは不可能ですが、
過去20数年の実績ある我輩の手で組んだので特に問題なし。
トータル的に見ると希少性や過去の良い評判や噂を元に、
わざわざVFC製AKに手を出す必然性は無いというのが我輩の見解です。
どうしてもAKMSが欲しいなら現在生産されているLCTやE&L製品を買うべき。
そして持ち運びにコンパクトである必然性がないのなら、
敢えてAKMSを選ぶ必要もないというのも我輩の持論。
逆に言えば敢えてコイツを欲する輩は我輩みたく捻くれ者である可能性あり。
でも我輩的にはVFC製AKMS、満足の逸品です。
ただやっぱりチャージングハンドルがガッタガッタなのは気になるなぁ。
2019年05月14日
紳士の国のライフルは真摯じゃないと扱えない?
我輩の浜松研修時代の同期(1個上の先輩だけど)ウズウズさんは西都の三納出身。
何時の日か宮崎に帰りたいと願いながら、まだ帰れない不幸な人です。
そんなウズウズさんの心の癒やしは、我輩同様エアガン集め。
長モノはサバゲー出来る程度の数しか持っていないらしいですが、
ハンドガンは独身貴族の財力をフルに活用して
2ヶ月日替わりで遊べるぐらい所有しているようです。この好き者がw
さて、去年の夏にウズウズさん「ボーナスでG&GのL85買っちゃったんだ(ハート)」と
LINEしてきたんで「今度の盆休み宮崎に帰ってくるんでしょ?持ってきなさい!」と返したら
「高速で警察にパクられた時にコレが後部座席にあったらヤバイやん!」と言ってたんですが、
やっぱ趣味人って基本、面白いものは見せびらかしたいんですよねぇ、
我輩に試射させるために律儀に持ってきてくれましたよ。

新富町近辺でエアガンを思う存分ぶっ放せる場所は嫁の実家の山ぐらいです。
草ボーボーのヂゴンの巣に入る前に道に威風堂々と生えている草を鎌でなぎ倒し、
20分ぐらい時間をかけてヂゴンの巣に到着という間抜けな状況。
尚、この草刈り作業が辛くてヂゴンの巣閉鎖を検討した我輩。
L85というライフルの事を知ってるサバイバルゲームプレイヤーの割合率は、
骨髄バンクに登録している人数の割合率並みに少ないようなので、
(なお、我輩は骨髄バンクに登録しておりますがその話はまた後ほど)
軽く説明をさせていただきますと、コレはイギリス軍の制式採用しているライフルです。
イギリス以外にもジャマイカとボリビアが採用しているらしいです。
特徴は見た目のとおり、ブルパップ方式であること。
ブルパップが何なのか、サバゲーしている人には説明不要でしょうが、
ウチのブログはノンケも多数拝見しておられるようなので軽く説明しますと、
グリップの後ろに機関部を配置する方式のことです。
つまり、本来はストックである部分に機関部が収まるので、
銃本体は小型化されて持ち運びしやすくなる、
銃身はそのままなので命中精度もそのままというのがウリ。
代表的なものではフランス軍のFA-MAS、オーストリア軍のシュタイアAUG、
中国人民解放軍の95式自動歩槍、イスラエルのタボールが挙げられます。

このL85はA2というH&Kが改修したモデル。
(G&Gはこの他にも前モデルのA1、カービンタイプのAFVをモデルアップ)
ジャムが起きやすい、反動がデカい、トリガーが硬い、マガジンがポンコツ、
そしてコッキングレバーの形状が悪くて薬莢が飛び出さないという欠点を
H&Kが工夫と苦労を重ねて改修したモデルがコレになります。
L85のサイズはM4カービンより8cm程短いですが、
ブルパップの形状を生かしてバレルは500mmとM16A2並です。
外装はハンドガードとグリップ、チークパッドとバットプレート以外殆ど金属製。
だからコンパクトではありますが、ソレ以上に重さが図師っときやがります。
デザイン的には他のブルパップ銃と比べると前時代的。
良く言えば無骨、悪く言えば普通のライフルをそのままプルパップにしたような感じ。
(調べてみたところ、L85はAR-18をブルパップ化したライフルらしいです)
更に悪くいうと、プルパップ化にあたって工夫した形跡が全くゼロ。

ハイダーは昔ながらのバードケージ(鳥籠)ハイダー。
先端だけでなく、根本が伸びているというあまり見ない形状のもの。
アウターバレルは多分アルミ製で握ってもぐらつきはゼロ。
剛性感に関しましては文句ない出来です。
ハンドガードは頑丈な樹脂で出来ているのか、安っぽい印象は感じません。
そこら辺は流石、高級電動ガンを売り出すG&Gらしい作りです。

上部ヒートガードを開くと(固いけど工具無しで開きます)バッテリー搭載スペース。
ガスチューブが再現されているのが嬉しい配慮ですね。
見えないところまで作り込まれているとそのメーカーの良心を感じます。
でもガスチューブのお陰でスペースが狭いんですがねw
バレルとハンドガードの隙間にバッテリーを収める様になっているので、
セパレートタイプや細くて短いタイプのリポバッテリーが収納可能です。

フロントサイトはエッジの効いた綺麗な作りで、上下の調整が可能。
ドットサイトを取り付けた時はネジ一つで取り外せるようにもなっています。
でも社外品の折りたたみタイプへの換装は、根本にレール溝を切らないと無理。

M4みたいなキャリングハンドル状のリアサイトは左右の調整が可能です。
取り外すとキャリングハンドル基部には20mmのレールがあるので、
大抵のスコープやドットサイトは取付可能ですが(ただしハイマウントであることが条件)、
M4みたいに工具無しで取り外せない(ネジ緩める必要がある)のが不便です。
ブルパップの欠点その1、機関部が後ろにある分、
フロントサイトとリアサイトの感覚が短くなるので正確な照準が付け難い。
AKシリーズもリアサイトが大分向う側にあるが故、照準が大雑把ですがねw
それを解消するためにプルパップライフルはドットサイト(例:P90)や
スコープ(例:シュタイアAUG)といった光学照準器が標準装備になっているのですが、
銃本体のお値段が光学照準器の分、光学だけに高額になりますので、
大量に武器を発注しなければならない軍隊では予算面がネックとなるが故に
価格を下げるためにアイアンサイトにしているものもあります(例:FA-MAS)。
L85にはSUSATサイトという見た目はドットサイト、でも中身は4倍のスコープ?
クロスラインの代わりに謎のオベリスクが見える光学照準器を付けるのが正当なのですが、
LS製L85に純正別売りの4倍SUSATを載せて使っていた我輩に言わせると
アレはどう考えても英国の暗黒面に満ちたサイトなので、
出来ることならごく普通のドットサイトを載せるのがよろしいでしょう。

スチール製の冷たいフレームの出来栄えも美しい。
バットプレートに構えた時の感触は可もなく不可もない感じ。
チャージングハンドルが変な形なのはH&Kがジャム解消のために
考察した結果の賜物ですがそれ程使いにくくはない。

なお、フレームのココについているレバーは64式みたいなスライド止め。
ホップ調整の際はココでチャージングハンドルを固定し、ホップダイヤルを調整。
尚、G&G製L85は疑似ブローバックが付属しているので、
射撃時にはチャージングハンドルは必ず戻さないとイカンとウズウズさん言ってましたが、
AIRSOFT97のレビューによると固定して撃っても問題ないとのこと?どっちよ?

ブルパップの欠点その2、セイフティ及びセミ/フルのセレクターが妙なところにある。
機関部が後ろにあるが故に当然セレクターも後ろになるのですが、
グリップは機関部よりも前になるので、瞬時に切り替えるのは至難の業。
フレーム後部に設置されるセレクターは上に切り替えるとフルオート、下がセミオート。
セイフティは別のところにあります(後ほど説明)。
マガジンキャッチもそのまま取って付けたような形状で、
見ての通り押さえれば抜けるんですが片手で操作しにくいんですねコレが。
その上、腰だめ撃ちの態勢を取るとマガジンキャッチを押し込んでしまい、
そのまま抜け落ちることがあるという謎ポジション(脱落防止のためにガードは付いている)。
ブルパップの欠点その3、機関部が後ろにあるがゆえにマグチェンジがやり難い。
L85の場合はマグチェンジしやすいようにとサイドにマグキャッチを付けたのでしょうが、
どっちにしてもマガジンが後ろにあるということは不自然な体勢を取らざるを得ないという。
FA-MASやAUGがマガジンの前後に解除するレバーを設けているのには
脱落しにくいポジションに設置するという訳があるのね。
しかも、付属の450連マガジンは抜けにくいと来たもんだ。
脱落防止用にマグウェルを狭くしているのか?
尚、マルイのM4マガジンor他社製STANAGマガジンも使用可能だそうです。

L85はAR18をベースに開発されたライフルなので、
グリップはAR18のものをそのまま使用しているらしいのですが、
握った感触は可もなく不可もなし。
余談ですがグリップの底はスポッと外して小物入れになるけど、
ココに何を入れればいいんか?アメとか入れるか?
尚、トリガー上部の丸いポコッとした部分がセイフティになり、
どちらかに押し込む(どっちかは忘れた)と安全、発射となります。

スリングスイベルの位置は可もなく不可もなし。
ストック根本にスイベルがあるので、マグプルの1点式スイベルは向かないかな?
実銃では悪いと酷評されていた重量バランスは、
電動ガンでは平均的で重量感をあまり感じさせません。
マガジンを突き刺し(銃を構えた状態では意外と面倒)、
チャージングハンドルを動かして装填した気分に浸り、
(変な形状だけど左手で操作するには便利である)
ストックを肩付けし、アイアンサイトで15m先のペプシコーラに狙いを定めて射撃!
弾道は可もなく不可もない、台湾製なので中華に比べるとそこらへんの出来はよろしい。
ただ、照準線が短いせいか、20m以上での精密射撃には向かない。
それでもサバイバルゲームの武器としては短くて収まりの良いサイズなので悪くはない。
ただやはり、敢えてL85を選択するという思考には至らない。
コレは完全に、ロイヤルアーミー(大英帝国陸軍)専用の武器だわ。

ウズウズ先輩が「この銃、左で構えて撃てないんすよ!」というので、
試しに左に構えて撃ってみたらどういうことでしょう、
チャージングハンドルのブローバックが目の前1mmのところまで接近してきて、
迫力がどうとか以前にビビってしまう事態に陥りましたね!
ブルパップの欠点その4、右左兼用デザインじゃないと左手では使い辛い。
FA-MASやAUGはソコのところよーく考えられていて、
イジェクションポートを任意で換えられるような設計ですし、
FA-MASに関してはチャージングハンドルも上部に設置してどちらの手でも使用可能です。
でもL85は左手で運用することを全く考えていない設計。
さて、全体を見渡して我輩が以前所有していたLS製L85電動カスタムと比べていましたが、
G&G製L85の出来栄えは玩具感を払拭するレベルで、クオリティ高い。
フレームの冷たい感触はLCT製品と同様なレベルですし、
樹脂パーツも安っぽさが見受けられないし、細部の作りも確かです。
なのに・・・全く以て欲しいと思えない!
我輩はね、M4系列以外の電動ガンならば人が持っているのを見ると
ソレはソレは羨ましくて多少なりとも物欲が湧き上がるんですよ。
その武器仕入れて、何処のフィールドで、どういう状況下で、
どういう装備に合わせて使えるかなとか、色々妄想を膨らませるんですよ。
でもね、我輩が現在、現用ロイヤルアーミー装備に興味が無いことを差し引いても、
ウズウズ先輩がL85を所有していることに対して全然羨ましさを感じないのです。
そのお値段(1パットンぐらいする)、使いにくさ、それ程格好良くない、
理由は色々あるんでしょうがコレほどマニアックな銃なのに
購入意欲を掻き立てられないブツは久しぶりです。

※写真は我輩が大英帝国陸軍のコスプレをしていた若かりし頃の写真です。
銃はLS製L85A1、FA-MASメカボ換装電動ガンカスタム。
迷彩服はDPM85、でも装備は金が無かったのでP58。(イギリスがFAL使っていた頃の装備)
マズルハイダーに被せるタイプの銃剣が欲しくて仕方なかったあの頃。
この頃の我輩にG&G製L85を見せたら確実に飛びつくでしょうね。
そして装備も思い切ってP90買っちゃうんだろうなぁ。
でも今時点でイギリス軍装備をするつもりは全く無いので、一生買わない。
逆に言うと、イギリス軍装備をやりたい人は是非ともL85を購入して、
ジョンブル魂とは如何なるものであるかを完全に理解してくだされ。
ソレを踏まえた上で「でもさ、SASはM4とかHK416とかMP5使っているから~」
とか言いながらL85に未練を感じている風を装いながらシレッと乗り換えるべし!
何時の日か宮崎に帰りたいと願いながら、まだ帰れない不幸な人です。
そんなウズウズさんの心の癒やしは、我輩同様エアガン集め。
長モノはサバゲー出来る程度の数しか持っていないらしいですが、
ハンドガンは独身貴族の財力をフルに活用して
2ヶ月日替わりで遊べるぐらい所有しているようです。この好き者がw
さて、去年の夏にウズウズさん「ボーナスでG&GのL85買っちゃったんだ(ハート)」と
LINEしてきたんで「今度の盆休み宮崎に帰ってくるんでしょ?持ってきなさい!」と返したら
「高速で警察にパクられた時にコレが後部座席にあったらヤバイやん!」と言ってたんですが、
やっぱ趣味人って基本、面白いものは見せびらかしたいんですよねぇ、
我輩に試射させるために律儀に持ってきてくれましたよ。

新富町近辺でエアガンを思う存分ぶっ放せる場所は嫁の実家の山ぐらいです。
草ボーボーのヂゴンの巣に入る前に道に威風堂々と生えている草を鎌でなぎ倒し、
20分ぐらい時間をかけてヂゴンの巣に到着という間抜けな状況。
尚、この草刈り作業が辛くてヂゴンの巣閉鎖を検討した我輩。
L85というライフルの事を知ってるサバイバルゲームプレイヤーの割合率は、
骨髄バンクに登録している人数の割合率並みに少ないようなので、
(なお、我輩は骨髄バンクに登録しておりますがその話はまた後ほど)
軽く説明をさせていただきますと、コレはイギリス軍の制式採用しているライフルです。
イギリス以外にもジャマイカとボリビアが採用しているらしいです。
特徴は見た目のとおり、ブルパップ方式であること。
ブルパップが何なのか、サバゲーしている人には説明不要でしょうが、
ウチのブログはノンケも多数拝見しておられるようなので軽く説明しますと、
グリップの後ろに機関部を配置する方式のことです。
つまり、本来はストックである部分に機関部が収まるので、
銃本体は小型化されて持ち運びしやすくなる、
銃身はそのままなので命中精度もそのままというのがウリ。
代表的なものではフランス軍のFA-MAS、オーストリア軍のシュタイアAUG、
中国人民解放軍の95式自動歩槍、イスラエルのタボールが挙げられます。

このL85はA2というH&Kが改修したモデル。
(G&Gはこの他にも前モデルのA1、カービンタイプのAFVをモデルアップ)
ジャムが起きやすい、反動がデカい、トリガーが硬い、マガジンがポンコツ、
そしてコッキングレバーの形状が悪くて薬莢が飛び出さないという欠点を
H&Kが工夫と苦労を重ねて改修したモデルがコレになります。
L85のサイズはM4カービンより8cm程短いですが、
ブルパップの形状を生かしてバレルは500mmとM16A2並です。
外装はハンドガードとグリップ、チークパッドとバットプレート以外殆ど金属製。
だからコンパクトではありますが、ソレ以上に重さが図師っときやがります。
デザイン的には他のブルパップ銃と比べると前時代的。
良く言えば無骨、悪く言えば普通のライフルをそのままプルパップにしたような感じ。
(調べてみたところ、L85はAR-18をブルパップ化したライフルらしいです)
更に悪くいうと、プルパップ化にあたって工夫した形跡が全くゼロ。

ハイダーは昔ながらのバードケージ(鳥籠)ハイダー。
先端だけでなく、根本が伸びているというあまり見ない形状のもの。
アウターバレルは多分アルミ製で握ってもぐらつきはゼロ。
剛性感に関しましては文句ない出来です。
ハンドガードは頑丈な樹脂で出来ているのか、安っぽい印象は感じません。
そこら辺は流石、高級電動ガンを売り出すG&Gらしい作りです。

上部ヒートガードを開くと(固いけど工具無しで開きます)バッテリー搭載スペース。
ガスチューブが再現されているのが嬉しい配慮ですね。
見えないところまで作り込まれているとそのメーカーの良心を感じます。
でもガスチューブのお陰でスペースが狭いんですがねw
バレルとハンドガードの隙間にバッテリーを収める様になっているので、
セパレートタイプや細くて短いタイプのリポバッテリーが収納可能です。

フロントサイトはエッジの効いた綺麗な作りで、上下の調整が可能。
ドットサイトを取り付けた時はネジ一つで取り外せるようにもなっています。
でも社外品の折りたたみタイプへの換装は、根本にレール溝を切らないと無理。

M4みたいなキャリングハンドル状のリアサイトは左右の調整が可能です。
取り外すとキャリングハンドル基部には20mmのレールがあるので、
大抵のスコープやドットサイトは取付可能ですが(ただしハイマウントであることが条件)、
M4みたいに工具無しで取り外せない(ネジ緩める必要がある)のが不便です。
ブルパップの欠点その1、機関部が後ろにある分、
フロントサイトとリアサイトの感覚が短くなるので正確な照準が付け難い。
AKシリーズもリアサイトが大分向う側にあるが故、照準が大雑把ですがねw
それを解消するためにプルパップライフルはドットサイト(例:P90)や
スコープ(例:シュタイアAUG)といった光学照準器が標準装備になっているのですが、
銃本体のお値段が光学照準器の分、光学だけに高額になりますので、
大量に武器を発注しなければならない軍隊では予算面がネックとなるが故に
価格を下げるためにアイアンサイトにしているものもあります(例:FA-MAS)。
L85にはSUSATサイトという見た目はドットサイト、でも中身は4倍のスコープ?
クロスラインの代わりに謎のオベリスクが見える光学照準器を付けるのが正当なのですが、
LS製L85に純正別売りの4倍SUSATを載せて使っていた我輩に言わせると
アレはどう考えても英国の暗黒面に満ちたサイトなので、
出来ることならごく普通のドットサイトを載せるのがよろしいでしょう。

スチール製の冷たいフレームの出来栄えも美しい。
バットプレートに構えた時の感触は可もなく不可もない感じ。
チャージングハンドルが変な形なのはH&Kがジャム解消のために
考察した結果の賜物ですがそれ程使いにくくはない。

なお、フレームのココについているレバーは64式みたいなスライド止め。
ホップ調整の際はココでチャージングハンドルを固定し、ホップダイヤルを調整。
尚、G&G製L85は疑似ブローバックが付属しているので、
射撃時にはチャージングハンドルは必ず戻さないとイカンとウズウズさん言ってましたが、
AIRSOFT97のレビューによると固定して撃っても問題ないとのこと?どっちよ?

ブルパップの欠点その2、セイフティ及びセミ/フルのセレクターが妙なところにある。
機関部が後ろにあるが故に当然セレクターも後ろになるのですが、
グリップは機関部よりも前になるので、瞬時に切り替えるのは至難の業。
フレーム後部に設置されるセレクターは上に切り替えるとフルオート、下がセミオート。
セイフティは別のところにあります(後ほど説明)。
マガジンキャッチもそのまま取って付けたような形状で、
見ての通り押さえれば抜けるんですが片手で操作しにくいんですねコレが。
その上、腰だめ撃ちの態勢を取るとマガジンキャッチを押し込んでしまい、
そのまま抜け落ちることがあるという謎ポジション(脱落防止のためにガードは付いている)。
ブルパップの欠点その3、機関部が後ろにあるがゆえにマグチェンジがやり難い。
L85の場合はマグチェンジしやすいようにとサイドにマグキャッチを付けたのでしょうが、
どっちにしてもマガジンが後ろにあるということは不自然な体勢を取らざるを得ないという。
FA-MASやAUGがマガジンの前後に解除するレバーを設けているのには
脱落しにくいポジションに設置するという訳があるのね。
しかも、付属の450連マガジンは抜けにくいと来たもんだ。
脱落防止用にマグウェルを狭くしているのか?
尚、マルイのM4マガジンor他社製STANAGマガジンも使用可能だそうです。

L85はAR18をベースに開発されたライフルなので、
グリップはAR18のものをそのまま使用しているらしいのですが、
握った感触は可もなく不可もなし。
余談ですがグリップの底はスポッと外して小物入れになるけど、
ココに何を入れればいいんか?アメとか入れるか?
尚、トリガー上部の丸いポコッとした部分がセイフティになり、
どちらかに押し込む(どっちかは忘れた)と安全、発射となります。

スリングスイベルの位置は可もなく不可もなし。
ストック根本にスイベルがあるので、マグプルの1点式スイベルは向かないかな?
実銃では悪いと酷評されていた重量バランスは、
電動ガンでは平均的で重量感をあまり感じさせません。
マガジンを突き刺し(銃を構えた状態では意外と面倒)、
チャージングハンドルを動かして装填した気分に浸り、
(変な形状だけど左手で操作するには便利である)
ストックを肩付けし、アイアンサイトで15m先のペプシコーラに狙いを定めて射撃!
弾道は可もなく不可もない、台湾製なので中華に比べるとそこらへんの出来はよろしい。
ただ、照準線が短いせいか、20m以上での精密射撃には向かない。
それでもサバイバルゲームの武器としては短くて収まりの良いサイズなので悪くはない。
ただやはり、敢えてL85を選択するという思考には至らない。
コレは完全に、ロイヤルアーミー(大英帝国陸軍)専用の武器だわ。

ウズウズ先輩が「この銃、左で構えて撃てないんすよ!」というので、
試しに左に構えて撃ってみたらどういうことでしょう、
チャージングハンドルのブローバックが目の前1mmのところまで接近してきて、
迫力がどうとか以前にビビってしまう事態に陥りましたね!
ブルパップの欠点その4、右左兼用デザインじゃないと左手では使い辛い。
FA-MASやAUGはソコのところよーく考えられていて、
イジェクションポートを任意で換えられるような設計ですし、
FA-MASに関してはチャージングハンドルも上部に設置してどちらの手でも使用可能です。
でもL85は左手で運用することを全く考えていない設計。
さて、全体を見渡して我輩が以前所有していたLS製L85電動カスタムと比べていましたが、
G&G製L85の出来栄えは玩具感を払拭するレベルで、クオリティ高い。
フレームの冷たい感触はLCT製品と同様なレベルですし、
樹脂パーツも安っぽさが見受けられないし、細部の作りも確かです。
なのに・・・全く以て欲しいと思えない!
我輩はね、M4系列以外の電動ガンならば人が持っているのを見ると
ソレはソレは羨ましくて多少なりとも物欲が湧き上がるんですよ。
その武器仕入れて、何処のフィールドで、どういう状況下で、
どういう装備に合わせて使えるかなとか、色々妄想を膨らませるんですよ。
でもね、我輩が現在、現用ロイヤルアーミー装備に興味が無いことを差し引いても、
ウズウズ先輩がL85を所有していることに対して全然羨ましさを感じないのです。
そのお値段(1パットンぐらいする)、使いにくさ、それ程格好良くない、
理由は色々あるんでしょうがコレほどマニアックな銃なのに
購入意欲を掻き立てられないブツは久しぶりです。

※写真は我輩が大英帝国陸軍のコスプレをしていた若かりし頃の写真です。
銃はLS製L85A1、FA-MASメカボ換装電動ガンカスタム。
迷彩服はDPM85、でも装備は金が無かったのでP58。(イギリスがFAL使っていた頃の装備)
マズルハイダーに被せるタイプの銃剣が欲しくて仕方なかったあの頃。
この頃の我輩にG&G製L85を見せたら確実に飛びつくでしょうね。
そして装備も思い切ってP90買っちゃうんだろうなぁ。
でも今時点でイギリス軍装備をするつもりは全く無いので、一生買わない。
逆に言うと、イギリス軍装備をやりたい人は是非ともL85を購入して、
ジョンブル魂とは如何なるものであるかを完全に理解してくだされ。
ソレを踏まえた上で「でもさ、SASはM4とかHK416とかMP5使っているから~」
とか言いながらL85に未練を感じている風を装いながらシレッと乗り換えるべし!
2019年04月21日
一応、我輩も長モノガスブロ持っているよ
そろそろ建設的な、アクティブな行動をしてみたい。
そう考えはしたものの精神的にも物理的にも大分腰が重くなっており、
同志クリス・コスッタ氏から頂いたチェーンソーも
試しにエンジン回しただけで創作活動には至れないのが現状です。
というわけで手近なところでブログの更新ぐらいはやってみるかなと思い、
「そ~言えばここはサバゲーのブログだったよね」ということで、
サバゲーのネタ、エアガンのネタをボチボチアップしようと思いました。
最近、ようやく同志一同と顔を合わせて盛り上がれるぐらいの元気は出てきました。
でも、まだサバゲーに行きたいと思えるほど気力はありませんし、
当然、仕事も半ば気が抜けた状態でやっておりますし、
家族とのふれあいも何かぎこちない感じでございます。

ところで皆さん、M1ガーランドってご存知ですか?
詳しい説明をしたところでノンケには興味が無いでしょうし、
知っている人は今更感でしょうから詳しい説明は省きますが、
第二次世界大戦時の米軍の主力小銃です。
要するに「コンバット!」のサンダース軍曹とカービィ以外が持っていた武器ですよ。
或いは「ブラザーフッド」でチャン・ドンゴン様がバンバン撃ちまくっていたアレ。

第2次世界大戦当時といえば日本は勿論、ドイツもイギリスもソ連も、
主力の武器は手動で弾を薬室に送り、発射後手動で薬莢を出すボルトアクションの小銃でした。
あぁん?フランスとイタリア?知らんなそんな国。
しかしアメリカだけはオートマチックのライフルを歩兵の主力武器としていたんですね。
(ドイツとソ連はオートマチックのライフルを前線投入していたが、主力ではなかった)
コレはアメリカが当時から圧倒的な工業力を有していたことの証です。
大戦時既に自動小銃の必要性は何処の軍隊でも理解はしておりましたが、
国内の技術力の限界、生産力の限界、資源の限界という大きな壁の前に、
開発は出来ても試験的配備に留まるか、断念せざるを得ないのが実情でした。
このM1ガーランドはマルシンの8mmガスブローバックです。
同志パットン風に言うと「ガスで動く銃です」。
実銃と同じような形状のクリップ状のマガジンに
「ファッ?」と言いたくなるようなデカスギィな8mm弾を詰め込みます。
確かコイツを購入するまでの流れは・・・
エロ小僧ヂゴンの巣に来訪⇒M1ガーランド持参して見せびらかす
⇒我輩、それを撃って感動する⇒物欲の神が急激に舞い降りてくる
⇒ヤフオクで4丁ぐらいエアガン売却⇒M1ガーランドポチるという感じだった記憶が。
お値段は・・・ごまんえんぐらいですね(適当)?
(マルシンのオフィシャルサイトで調べたところ現在の定価は68000円だが、
我輩が買ったときはもう少し安かったような気がする)
購入後直ぐに三沢への転勤が決まり、
サバゲーで使えないエアガンは置いていこうということになり、
M1ガーランドは写真も撮らず嫁の実家に放置していたのですが、
(ていうか、我輩がエアガンのインプレをブログに載せるようになったのは三沢転勤以降)
嫁の実家が改築をした際に行方不明になってしまいました。
ところが我輩が休業していた時、暇つぶしに嫁の実家の倉庫を整理していたら、
コイツが倉庫の奥から汚い箱に包まれて姿を表したんですね。
箱は使い物にならない状態でしたが、中身は別れる前の姿そのままだったので、
ニヤニヤしながら社宅に持ち帰り、オーバーホールすることにしました。
ある意味、我輩の心の回復の糸口になったのが、
このM1ガーランドだと行っても過言ではない?
だってコイツと再会するまでエアガンを弄るのですら億劫だったのに、
コイツをばらして弄りまくったのをきっかけに
他のエアガンも修理する気分が湧き上がりましたからね。

写真を撮る前にバラして調整をしたので、全体像はすべて事後の写真です。
金属部分の色が剥げているのはバラした時に各部に盛大に傷が入ったんで、
それを誤魔化すためにビンテージっぽく処理した結果です。
尚、マルシンのM1ガーランドはストック以外すべて金属(ダイキャスト)です。
フロント周りはバレルとその下にすぐ、ガスチューブがあります。
そしてガスチューブの下には銃剣を取り付ける着剣ラグ。
その奥にあるスリング取付用スイベルみたいだけど、
真ん中が中途半端にキレているブツは叉銃(さじゅう)のためのスイベル。

昔の戦争映画とか写真を見ると、銃をこのようにして立てている風景があるんですが、
コレをするために引っ掛けるポジションなんですね。
三八式とかモーゼルKar98kの場合はバレル下にクリーニングロッドがあるんで、
それを利用して銃を3丁引っ掛けて叉銃するんですが、
ガーランドの場合はロッドが付いていない代わりにコレがあるという。
我輩も叉銃、ヤりたくて仕方ないんですがねぇ、
宮崎にはガーランドをお持ちの方は我輩以外に
らんたろー氏とピーマン職人ぐらいしか居ないようなので、
その三人が揃わないと叉銃をする夢は叶いませぬ。

実銃を見たことはありますが触ったことがないので確信は持てませんが、
ストックはブローバックメカが入る都合上、気持ち太めかもしれません。
電動のメカボが入るICS製M1ガーランドより少しスリムな程度でしょう。
我輩のM1ガーランドは初期に生産されたものなので、
木製ストックは全体的に真っ黒な仕上げです。
後期に生産されたものは赤っぽいストックのものがある模様。
分解した際、ワトコのマホガニーを上から数回塗ってみたんですが、
なんか中途半端な仕上がりになってしまったので
もう一度全て色落としして塗り直すべきか否か検討中。

機関部周りを見るとまるでM14みたいですが、薬室部分が少し長いです。
M1ガーランドの口径は30-06という、M14や64式よりも薬莢が大きい弾を使用するからです。
チャージングハンドル部分だけは何故かアルミ削り出し。
リアサイトは上下左右に調整可能で、上下ダイヤルはくるくる回りますが、
左右のダイヤルは引っ張りながらじゃないと回らないので注意しましょう。

トリガーガードの前方にあるのがセイフティ。
トリガー側にすると安全状態なのはM14と同様。
動きはかなり軽く、人差し指で操作できます。
トリガー前方の蓋が付いている部分の中にガスタンクがあり、
前方の穴が空いている部分からガスを注入します。
ガスが満タンになるまでには5~6秒ぐらいかかりますが、
満タンで撃てるのは2~3マガジンと激悪な燃費です。

マガジンは実銃のクリップと同じ形状をしたブツの中に
BB弾を詰め込めるようにしたもので装弾数は実銃と同じく8発。
デフォで付いてくるマガジンはガワが樹脂製ですが、
オプションでマグネシウム製マガジンもありました。
我輩の記憶では樹脂製マガジンのお値段が900円ぐらい、
マグネシウム製が1800円ぐらいだったはずなんですが、
もう2個ぐらいマガジン欲しいなと思って探してみたら何処も品切れ、
ヤフオクで探してみると5000円ぐらいのボッタクリ価格で出ているのね。
我輩のマグネシウムクリップ、福岡のSWATで半額の投げ売り価格で買ったというのに。
マルシン製品は暫くするとマガジンが入手困難になるので、
気に入った銃の予備マガジンは直ぐに抑えるべきです。

ストックの蓋、クリーニングキットを入れる部分も開閉します。
とは言っても電動ガンじゃないんでここが開閉しても使い道はないんですが、
ここが開くか否かという問題は、ガーターベルトを付けているか否かと同じぐらい重要。
まあ要するに、弾が出ればいいという問題ではなく、
その気にさせてくれる要素がどれ位含まれているかってことです。

発射手順はまず右手で(ココ重要)チャージングハンドルを引き、機関部を開くと
マガジンが収まる部分の中に銀色のストッパーがあるので(ココ更に重要)、
左手の指先でストッパーを前方に押し込み、チャージングハンドルを静かに戻すと、
イジェクションポートが開いた所謂「くぱぁ」状態になります。

そこに弾が入ったクリップ(マガジン)を「カチッ」というまで押し込み、
チャージングハンドルを引けば装填完了です。
この時、マガジンがカチッと押し込まれない場合や、
チャージングハンドルが戻らない場合がありますが、
その時はフレーム左側の四角い出っ張りを押してマガジンを抜き、
再度指を突っ込んでストッパーを留め直す必要があります。
戦闘中のリロードは冷静ならば結構スムーズに出来ますが、
慌てているとマガジンが装填されずチャージングハンドルで指をはさみ、危険です。

セイフティを解除し、トリガーを引くと「バコッ!」という音とともに弾が発射され、
チャージングハンドルがそれ程でもないスピードで後退します。
リコイルショックは大きいチャージングハンドルが動くが故、
派手な感じではありますが銃そのものが重い(3.8kg位ある)のでマイルドな印象。
ガスが温まっていれば、或いはエアタンクを繋げば結構いい動きをしますが、
ガスが少ないか、冷えている場合はチャージングハンドルが上手く後退しません。
ストロークが長いのでマルイM4のガスブロ程バシバシとブローバックしないんですね。
セミオートなんでそれ程不具合は感じませんが。

最終弾を打ち尽くすと、クリップが外に勢いよく弾き出されます。
クリップは20cmぐらい上昇したら直ぐに足元に落ちます。
樹脂製クリップは「コツン」みたいなナマクラな音しかしませんが、
マグネシウム製クリップは「カキン!」と軽い金属音を奏でます。
そう、このクリップが飛び出すアクションを楽しみたいが故のマルシンガーランド。
このギミックは電動では味わえない、唯一無二のものなのです。
弾が飛ぶ事はある程度重要だけど、クリップが飛ぶ方が最重要。
撃つと思わず頬が緩みそうになるガスガン、
それがマルシンのM1ガーランドなのです。
嫁の実家でマルシンM1ガーランドを発掘したその日は
帰宅後直ぐ様本体にガスをブチ込み、ガスが温まるまで待ち、
8mmBB弾をクリップに詰めて撃ってみたところ、
(8mmBB弾は時々デリンジャーで撃っていたので、直ぐ側に置いていた)
案の定だるそうにスライドが動くブローバックならぬスローバックな動きを見せ、、
4発目以降は弾は出るけどスライドが動かないという体たらくなので手でコッキングして発射。
そうそう、マルシンM1ガーランド、購入時から既に調子悪かったのよね。
購入後すぐにガス注入バルブを外して、エアタンク仕様にしていたんだもん。
ていうかマルシンのエアガンは新品状態でまともに動かないとかザラ。
動かない、弾が出ない、弾が出ても何処に飛ぶか判らない。
それでも愛おしい部分があるから、信者はマルシン製品を欲するのです。

先人の知恵をネットで探してみたところ(殆ど見当たらなかったけど)、
コイツの動きがよろしくない原因はトリガーメカの建付けがよろしくないからだとか?
従ってまず、トリガーメカを取り外して弄ることにします。
トリガーガード後端を下に引けば直ぐに外せるんですねコレが。

金色の部品が付いている部分がハンマー。
トリガーを引くとコイツが倒れることで上の赤丸部分のロッドを押し、ガスは放出されて弾が発射、
その後もう片方、下の赤丸部分のロッドを押してスライドを動かします。
このロッドが当たる部分に板を貼り付けてかさ増しすることで
ガスの放出量が増えて作動が良くなるという情報があったので、
0.5mmのアルミ板を両面テープで貼り付けてみたのですが、
何故か作動不良を起こしてしまいましたので直ぐ様復旧。

マルシンガーランドの作動不良の原因の大半は
このハンマーの内側がシアに干渉している(赤丸部分)が故に
余計なパワーを使うハメになる、或いは動きが悪いそうなのです。
要するにハンマーとシアが擦れながら作動しているから、
その分ブローバックに余計な負荷がかかるということですな。
先人のサイトでは干渉している部分を削るとありましたが、
よーく見てみるとコレ、作りが結構ガバガバで隙間があるんですね。
我輩の個体ではハンマーが右に寄って傾き、シアの根本は左側がガバガバ。

というわけで我輩はハンマーとシアとトリガーをバラしてみました。
全体的に粗い部分を目の細かいヤスリで綺麗にしたり、
ハンマーとシアの引っかかる部分のバリを無くします。
でもこの部分を分解すると組み立てるのにかなり難儀です。
スプリングが太いから、物凄いテンションなんですよ。
正直、我輩のようにハンマーの根本に細工を施すことをしないなら、
そのままの状態で細いヤスリを使って磨いたほうが手っ取り早いです。

要するに写真の赤丸部分の内側が干渉しないようにすればいいだけなので、
内側の当たっている部分(見れば直ぐに解る)を削るだけでもいいようです。

でもやはり、ハンマーやシアの隙間があると気分がよろしくないので、
ピンをずらしてハンマーの根本の赤丸部分にM5ネジに付属していたワッシャーを挟みます。
ワッシャーが入ることで空間が埋まり、ガタツキが無くなります。

そしてトリガーの根本にも隙間があったので、
M3ネジに付属していたワッシャーを挟んでガタツキを無くします。
この加工によってハンマーとシアのお互いが真っ直ぐな位置関係になり、
ハンマーが素直に可動することによって無駄なパワーロスが起こることなく、
スムーズに作動するようになりましたが勢いがないのは相変わらず。
そしてマルシンM1ガーランド、動きは遅くてもブローバックの作動がかなり大きいせいか、
それともネジ締め職人の握力が弱いのか、撃っていると次第に各部のネジが緩み、
それが可動部分の何処かに干渉してジャムを起こしやがるのです。
手に入れて直ぐ、例の法改正によるパワー規制がかかったので、
バレルの交換とガスルートの処置は実施しておりますが、
全体的な確認とブログのネタのために、再度分解をしてみます。
だけどさぁ、今更マルシンM1ガーランドの分解手順なんか載せても、
誰も幸せになれないような気がせんでもないけど・・・まあいいや。

まずはトリガーガード周りを外し、トリガー後部のねじを外します。
コレでストックと機関部が分離しますが、まだまだ先があるんですねコレが。

後ろを外したと思ったら次は前に廻らなければならないという。
バレル下のデカスギぃ!なクロスネジを外さなければいけません。
このために結構太いクロスドライバーが必要ですと言いたいところですが、
直径8mmぐらいのドライバーでも「やろうと思えば」イケん事はありません。
でも組立時、ガチガチに締め込もうとするとネジ頭舐めそうになります。
その後フロントサイトを固定している6角ネジを緩め、
フロントサイトを横にずらして中にあるイモネジを緩めます。

次に写真のようにアウターバレルの先端を握り、緩む方向にギュッと力を入れ、
そのままクルクル緩めればアウターバレルの先っちょ部分だけが外れます。
この部分の正式名称が不明なのでアウターバレル1という事にしときましょう。
それと同時にガスチューブ部分が外れてきます。
我輩の個体は直ぐ回りましたが、回らない場合はバイスプライヤー等で挟む必要があるかも。

その後上部ヒートガードを固定しているパーツの下のイモネジを緩めれば、
ヒートガードが外れるようになりますので固定用パーツも前方に抜いて外します。

アウターバレル2には金色のストッパーが
イモネジ2本で固定されているのでコレを緩めて外し、
一緒にチャージングハンドルも外してしまいます。

チャージングハンドルは赤丸部分の切り欠き部分まで
移動させることで溝から外すことが出来ます。
組み立てる時もこの部分を合わせてチャージングハンドルを溝に収めます。

写真のようにこの部分を握り、機関部側に押し込むと、
ブローバックメカの固定パーツが露出するのでイモネジを緩めて外します。
ココを外すと手で握っている部分とスプリングが抜けます。

アウターバレル2もねじ込みで取り付けられているので、
緩み方向にぐるぐる回して取り外します。

バレルの根元部分は上2個、左右4個のネジで固定されているので、
6つのネジを全て緩めて前方へ抜き取ります。

するとインナーバレルを固定している金色のパーツが現れるので、
平らな面に付いているイモネジを抜き取り、モンキレンチで緩めて外します。

そのままゆっくりと引き抜けば、インナーバレルが外れます。
でもチャンバーパッキンは中に残ったままなのでご注意。
パッキンはチャンバー自体を分解しないと外せないようです。

チャンバー上部にはホップ調整用のベアリングが入っているので、
フレームを分離する前に外すか、テープで止める等の処置を。

赤丸で示した部分のネジを緩めて、フレームと内部メカを分離します。
フレーム両側の同じ部分にネジがあるので、合計4箇所のネジを外します。

写真のようにクリップ取り出しレバーをマイナスドライバー等で持ち上げ、
フレームをずらせば機関部とフレームが分離できますが、
力づくで無理やりやろうとすると破壊の恐れがあるので慎重に。

赤丸部分はチャンバーを固定するネジで、左側も緩めれば外せるはずですが、
パッキンの交換の必要性はないようなので一旦ネジを抜き、
ネジ山にネジロック剤(アロンゆるみ止め)を塗って
射撃の振動でネジが緩むのを防止します。

我輩の個体は左側のプレートを外した奥に見える
赤丸部分のネジが射撃の度に緩んで抜け落ちそうになるので、
ネジロック剤をたっぷり塗って緩まないようにしました。
この部分はマガジンが入る場所であるうえ、
チャージングハンドルを固定する部分にも関係しているので、
ネジが外れるとジャムを起こすか、最悪ぶっ壊れます。

ブローバックメカの部分は今後不具合が出次第、分解するとして、
目に見えるネジというネジにネジロック剤を塗って組み上げることにします。
組み立ての際、まずはスライドをきっちりとセットして、フレームを取り付けます。
後は分解の逆手順で組み立てていけば完成するはずです。
でもね、実はネジの緩みをどうにかするぐらいなら、
ココまで分解しなくてもストックと銃身を分離させて、
目に見えるネジというネジを増し締めしたり、
外してネジロック塗って再取り付けすればいいだけの話なんですよね。

組み上げてから10クリップ(マガジン)ぐらいはぶっ放しましたが、
今のところ不具合はないので暫くは安泰なんでしょうが、
何時の日かハンマー辺りがぶっ壊れそうな気がするので気軽に撃つのも気が引けます。
まあそれよりも、手元の8mmBB弾の在庫が少なくなっているのが当面の問題。
初速はマルシン製(ていうかマルシンしか8mmBB弾作ってねぇ)
0.34gの8mm弾を使用して室内温度22℃の状態で58~73m/sと結構弱い?
夏になって35℃超える環境下でも規制値の95m/sには収まるでしょう。
命中精度は20mぐらい離れた電信柱に当たるか否かなので、お座敷で的撃ちが限界でしょう。
まあそれ以前に宮崎の有料フィールドとかで8mmオッケーな場所って無ぇし。
尚、銃と共に写っている袋はM1ガーランド用のバンダリア。
職場のミリタリーマニアの鬼軍曹がお互いまだ若かりし頃、
「沖縄で仕入れたけど要らないからやる」と言って4個セットで押し付けてきたものです。
その時は「M1ガーランドのクリップ入れなんて何処で使えばよいのやら?」と思ったんですが、
まさかコイツが日の目を浴びる日が来るとは・・・大事に保管しといてよかった。
実はこの度の分解整備、コイツをヤフオクに流すために実施したのですが、
思いのほか気持ち良く作動するM1ガーランドを見ていると
日に日に惜しいという感情が湧き上がり、今では手放したくない気分です。
ていうか、コイツのお陰で我輩の心の暗雲が晴れたと思うと、
ゲームで使えないからと言って無下に手放すのもいい気分ではないかなと。
ま、宮崎に戻って以来「我輩も一端のサバイバルゲームプレイヤーである以上、
ガスブローバックのライフルを1丁ぐらいは所有しとくべきだよなぁ」
と思っていた矢先にこのM1ガーランドを見つけてしまったので、
「まずウチさぁ、M1ガーランドあんだけど・・・撃っていかない?」ってなノリで
我輩らしさの表現の一環として暫くは手元で愛でることにしようと思います。
そう考えはしたものの精神的にも物理的にも大分腰が重くなっており、
同志クリス・コスッタ氏から頂いたチェーンソーも
試しにエンジン回しただけで創作活動には至れないのが現状です。
というわけで手近なところでブログの更新ぐらいはやってみるかなと思い、
「そ~言えばここはサバゲーのブログだったよね」ということで、
サバゲーのネタ、エアガンのネタをボチボチアップしようと思いました。
最近、ようやく同志一同と顔を合わせて盛り上がれるぐらいの元気は出てきました。
でも、まだサバゲーに行きたいと思えるほど気力はありませんし、
当然、仕事も半ば気が抜けた状態でやっておりますし、
家族とのふれあいも何かぎこちない感じでございます。

ところで皆さん、M1ガーランドってご存知ですか?
詳しい説明をしたところでノンケには興味が無いでしょうし、
知っている人は今更感でしょうから詳しい説明は省きますが、
第二次世界大戦時の米軍の主力小銃です。
要するに「コンバット!」のサンダース軍曹とカービィ以外が持っていた武器ですよ。
或いは「ブラザーフッド」でチャン・ドンゴン様がバンバン撃ちまくっていたアレ。

第2次世界大戦当時といえば日本は勿論、ドイツもイギリスもソ連も、
主力の武器は手動で弾を薬室に送り、発射後手動で薬莢を出すボルトアクションの小銃でした。
あぁん?フランスとイタリア?知らんなそんな国。
しかしアメリカだけはオートマチックのライフルを歩兵の主力武器としていたんですね。
(ドイツとソ連はオートマチックのライフルを前線投入していたが、主力ではなかった)
コレはアメリカが当時から圧倒的な工業力を有していたことの証です。
大戦時既に自動小銃の必要性は何処の軍隊でも理解はしておりましたが、
国内の技術力の限界、生産力の限界、資源の限界という大きな壁の前に、
開発は出来ても試験的配備に留まるか、断念せざるを得ないのが実情でした。
このM1ガーランドはマルシンの8mmガスブローバックです。
同志パットン風に言うと「ガスで動く銃です」。
実銃と同じような形状のクリップ状のマガジンに
「ファッ?」と言いたくなるようなデカスギィな8mm弾を詰め込みます。
確かコイツを購入するまでの流れは・・・
エロ小僧ヂゴンの巣に来訪⇒M1ガーランド持参して見せびらかす
⇒我輩、それを撃って感動する⇒物欲の神が急激に舞い降りてくる
⇒ヤフオクで4丁ぐらいエアガン売却⇒M1ガーランドポチるという感じだった記憶が。
お値段は・・・ごまんえんぐらいですね(適当)?
(マルシンのオフィシャルサイトで調べたところ現在の定価は68000円だが、
我輩が買ったときはもう少し安かったような気がする)
購入後直ぐに三沢への転勤が決まり、
サバゲーで使えないエアガンは置いていこうということになり、
M1ガーランドは写真も撮らず嫁の実家に放置していたのですが、
(ていうか、我輩がエアガンのインプレをブログに載せるようになったのは三沢転勤以降)
嫁の実家が改築をした際に行方不明になってしまいました。
ところが我輩が休業していた時、暇つぶしに嫁の実家の倉庫を整理していたら、
コイツが倉庫の奥から汚い箱に包まれて姿を表したんですね。
箱は使い物にならない状態でしたが、中身は別れる前の姿そのままだったので、
ニヤニヤしながら社宅に持ち帰り、オーバーホールすることにしました。
ある意味、我輩の心の回復の糸口になったのが、
このM1ガーランドだと行っても過言ではない?
だってコイツと再会するまでエアガンを弄るのですら億劫だったのに、
コイツをばらして弄りまくったのをきっかけに
他のエアガンも修理する気分が湧き上がりましたからね。

写真を撮る前にバラして調整をしたので、全体像はすべて事後の写真です。
金属部分の色が剥げているのはバラした時に各部に盛大に傷が入ったんで、
それを誤魔化すためにビンテージっぽく処理した結果です。
尚、マルシンのM1ガーランドはストック以外すべて金属(ダイキャスト)です。
フロント周りはバレルとその下にすぐ、ガスチューブがあります。
そしてガスチューブの下には銃剣を取り付ける着剣ラグ。
その奥にあるスリング取付用スイベルみたいだけど、
真ん中が中途半端にキレているブツは叉銃(さじゅう)のためのスイベル。

昔の戦争映画とか写真を見ると、銃をこのようにして立てている風景があるんですが、
コレをするために引っ掛けるポジションなんですね。
三八式とかモーゼルKar98kの場合はバレル下にクリーニングロッドがあるんで、
それを利用して銃を3丁引っ掛けて叉銃するんですが、
ガーランドの場合はロッドが付いていない代わりにコレがあるという。
我輩も叉銃、ヤりたくて仕方ないんですがねぇ、
宮崎にはガーランドをお持ちの方は我輩以外に
らんたろー氏とピーマン職人ぐらいしか居ないようなので、
その三人が揃わないと叉銃をする夢は叶いませぬ。

実銃を見たことはありますが触ったことがないので確信は持てませんが、
ストックはブローバックメカが入る都合上、気持ち太めかもしれません。
電動のメカボが入るICS製M1ガーランドより少しスリムな程度でしょう。
我輩のM1ガーランドは初期に生産されたものなので、
木製ストックは全体的に真っ黒な仕上げです。
後期に生産されたものは赤っぽいストックのものがある模様。
分解した際、ワトコのマホガニーを上から数回塗ってみたんですが、
なんか中途半端な仕上がりになってしまったので
もう一度全て色落としして塗り直すべきか否か検討中。

機関部周りを見るとまるでM14みたいですが、薬室部分が少し長いです。
M1ガーランドの口径は30-06という、M14や64式よりも薬莢が大きい弾を使用するからです。
チャージングハンドル部分だけは何故かアルミ削り出し。
リアサイトは上下左右に調整可能で、上下ダイヤルはくるくる回りますが、
左右のダイヤルは引っ張りながらじゃないと回らないので注意しましょう。

トリガーガードの前方にあるのがセイフティ。
トリガー側にすると安全状態なのはM14と同様。
動きはかなり軽く、人差し指で操作できます。
トリガー前方の蓋が付いている部分の中にガスタンクがあり、
前方の穴が空いている部分からガスを注入します。
ガスが満タンになるまでには5~6秒ぐらいかかりますが、
満タンで撃てるのは2~3マガジンと激悪な燃費です。

マガジンは実銃のクリップと同じ形状をしたブツの中に
BB弾を詰め込めるようにしたもので装弾数は実銃と同じく8発。
デフォで付いてくるマガジンはガワが樹脂製ですが、
オプションでマグネシウム製マガジンもありました。
我輩の記憶では樹脂製マガジンのお値段が900円ぐらい、
マグネシウム製が1800円ぐらいだったはずなんですが、
もう2個ぐらいマガジン欲しいなと思って探してみたら何処も品切れ、
ヤフオクで探してみると5000円ぐらいのボッタクリ価格で出ているのね。
我輩のマグネシウムクリップ、福岡のSWATで半額の投げ売り価格で買ったというのに。
マルシン製品は暫くするとマガジンが入手困難になるので、
気に入った銃の予備マガジンは直ぐに抑えるべきです。

ストックの蓋、クリーニングキットを入れる部分も開閉します。
とは言っても電動ガンじゃないんでここが開閉しても使い道はないんですが、
ここが開くか否かという問題は、ガーターベルトを付けているか否かと同じぐらい重要。
まあ要するに、弾が出ればいいという問題ではなく、
その気にさせてくれる要素がどれ位含まれているかってことです。

発射手順はまず右手で(ココ重要)チャージングハンドルを引き、機関部を開くと
マガジンが収まる部分の中に銀色のストッパーがあるので(ココ更に重要)、
左手の指先でストッパーを前方に押し込み、チャージングハンドルを静かに戻すと、
イジェクションポートが開いた所謂「くぱぁ」状態になります。

そこに弾が入ったクリップ(マガジン)を「カチッ」というまで押し込み、
チャージングハンドルを引けば装填完了です。
この時、マガジンがカチッと押し込まれない場合や、
チャージングハンドルが戻らない場合がありますが、
その時はフレーム左側の四角い出っ張りを押してマガジンを抜き、
再度指を突っ込んでストッパーを留め直す必要があります。
戦闘中のリロードは冷静ならば結構スムーズに出来ますが、
慌てているとマガジンが装填されずチャージングハンドルで指をはさみ、危険です。

セイフティを解除し、トリガーを引くと「バコッ!」という音とともに弾が発射され、
チャージングハンドルがそれ程でもないスピードで後退します。
リコイルショックは大きいチャージングハンドルが動くが故、
派手な感じではありますが銃そのものが重い(3.8kg位ある)のでマイルドな印象。
ガスが温まっていれば、或いはエアタンクを繋げば結構いい動きをしますが、
ガスが少ないか、冷えている場合はチャージングハンドルが上手く後退しません。
ストロークが長いのでマルイM4のガスブロ程バシバシとブローバックしないんですね。
セミオートなんでそれ程不具合は感じませんが。

最終弾を打ち尽くすと、クリップが外に勢いよく弾き出されます。
クリップは20cmぐらい上昇したら直ぐに足元に落ちます。
樹脂製クリップは「コツン」みたいなナマクラな音しかしませんが、
マグネシウム製クリップは「カキン!」と軽い金属音を奏でます。
そう、このクリップが飛び出すアクションを楽しみたいが故のマルシンガーランド。
このギミックは電動では味わえない、唯一無二のものなのです。
弾が飛ぶ事はある程度重要だけど、クリップが飛ぶ方が最重要。
撃つと思わず頬が緩みそうになるガスガン、
それがマルシンのM1ガーランドなのです。
嫁の実家でマルシンM1ガーランドを発掘したその日は
帰宅後直ぐ様本体にガスをブチ込み、ガスが温まるまで待ち、
8mmBB弾をクリップに詰めて撃ってみたところ、
(8mmBB弾は時々デリンジャーで撃っていたので、直ぐ側に置いていた)
案の定だるそうにスライドが動くブローバックならぬスローバックな動きを見せ、、
4発目以降は弾は出るけどスライドが動かないという体たらくなので手でコッキングして発射。
そうそう、マルシンM1ガーランド、購入時から既に調子悪かったのよね。
購入後すぐにガス注入バルブを外して、エアタンク仕様にしていたんだもん。
ていうかマルシンのエアガンは新品状態でまともに動かないとかザラ。
動かない、弾が出ない、弾が出ても何処に飛ぶか判らない。
それでも愛おしい部分があるから、信者はマルシン製品を欲するのです。

先人の知恵をネットで探してみたところ(殆ど見当たらなかったけど)、
コイツの動きがよろしくない原因はトリガーメカの建付けがよろしくないからだとか?
従ってまず、トリガーメカを取り外して弄ることにします。
トリガーガード後端を下に引けば直ぐに外せるんですねコレが。

金色の部品が付いている部分がハンマー。
トリガーを引くとコイツが倒れることで上の赤丸部分のロッドを押し、ガスは放出されて弾が発射、
その後もう片方、下の赤丸部分のロッドを押してスライドを動かします。
このロッドが当たる部分に板を貼り付けてかさ増しすることで
ガスの放出量が増えて作動が良くなるという情報があったので、
0.5mmのアルミ板を両面テープで貼り付けてみたのですが、
何故か作動不良を起こしてしまいましたので直ぐ様復旧。

マルシンガーランドの作動不良の原因の大半は
このハンマーの内側がシアに干渉している(赤丸部分)が故に
余計なパワーを使うハメになる、或いは動きが悪いそうなのです。
要するにハンマーとシアが擦れながら作動しているから、
その分ブローバックに余計な負荷がかかるということですな。
先人のサイトでは干渉している部分を削るとありましたが、
よーく見てみるとコレ、作りが結構ガバガバで隙間があるんですね。
我輩の個体ではハンマーが右に寄って傾き、シアの根本は左側がガバガバ。

というわけで我輩はハンマーとシアとトリガーをバラしてみました。
全体的に粗い部分を目の細かいヤスリで綺麗にしたり、
ハンマーとシアの引っかかる部分のバリを無くします。
でもこの部分を分解すると組み立てるのにかなり難儀です。
スプリングが太いから、物凄いテンションなんですよ。
正直、我輩のようにハンマーの根本に細工を施すことをしないなら、
そのままの状態で細いヤスリを使って磨いたほうが手っ取り早いです。

要するに写真の赤丸部分の内側が干渉しないようにすればいいだけなので、
内側の当たっている部分(見れば直ぐに解る)を削るだけでもいいようです。

でもやはり、ハンマーやシアの隙間があると気分がよろしくないので、
ピンをずらしてハンマーの根本の赤丸部分にM5ネジに付属していたワッシャーを挟みます。
ワッシャーが入ることで空間が埋まり、ガタツキが無くなります。

そしてトリガーの根本にも隙間があったので、
M3ネジに付属していたワッシャーを挟んでガタツキを無くします。
この加工によってハンマーとシアのお互いが真っ直ぐな位置関係になり、
ハンマーが素直に可動することによって無駄なパワーロスが起こることなく、
スムーズに作動するようになりましたが勢いがないのは相変わらず。
そしてマルシンM1ガーランド、動きは遅くてもブローバックの作動がかなり大きいせいか、
それともネジ締め職人の握力が弱いのか、撃っていると次第に各部のネジが緩み、
それが可動部分の何処かに干渉してジャムを起こしやがるのです。
手に入れて直ぐ、例の法改正によるパワー規制がかかったので、
バレルの交換とガスルートの処置は実施しておりますが、
全体的な確認とブログのネタのために、再度分解をしてみます。
だけどさぁ、今更マルシンM1ガーランドの分解手順なんか載せても、
誰も幸せになれないような気がせんでもないけど・・・まあいいや。

まずはトリガーガード周りを外し、トリガー後部のねじを外します。
コレでストックと機関部が分離しますが、まだまだ先があるんですねコレが。

後ろを外したと思ったら次は前に廻らなければならないという。
バレル下のデカスギぃ!なクロスネジを外さなければいけません。
このために結構太いクロスドライバーが必要ですと言いたいところですが、
直径8mmぐらいのドライバーでも「やろうと思えば」イケん事はありません。
でも組立時、ガチガチに締め込もうとするとネジ頭舐めそうになります。
その後フロントサイトを固定している6角ネジを緩め、
フロントサイトを横にずらして中にあるイモネジを緩めます。

次に写真のようにアウターバレルの先端を握り、緩む方向にギュッと力を入れ、
そのままクルクル緩めればアウターバレルの先っちょ部分だけが外れます。
この部分の正式名称が不明なのでアウターバレル1という事にしときましょう。
それと同時にガスチューブ部分が外れてきます。
我輩の個体は直ぐ回りましたが、回らない場合はバイスプライヤー等で挟む必要があるかも。

その後上部ヒートガードを固定しているパーツの下のイモネジを緩めれば、
ヒートガードが外れるようになりますので固定用パーツも前方に抜いて外します。

アウターバレル2には金色のストッパーが
イモネジ2本で固定されているのでコレを緩めて外し、
一緒にチャージングハンドルも外してしまいます。

チャージングハンドルは赤丸部分の切り欠き部分まで
移動させることで溝から外すことが出来ます。
組み立てる時もこの部分を合わせてチャージングハンドルを溝に収めます。

写真のようにこの部分を握り、機関部側に押し込むと、
ブローバックメカの固定パーツが露出するのでイモネジを緩めて外します。
ココを外すと手で握っている部分とスプリングが抜けます。

アウターバレル2もねじ込みで取り付けられているので、
緩み方向にぐるぐる回して取り外します。

バレルの根元部分は上2個、左右4個のネジで固定されているので、
6つのネジを全て緩めて前方へ抜き取ります。

するとインナーバレルを固定している金色のパーツが現れるので、
平らな面に付いているイモネジを抜き取り、モンキレンチで緩めて外します。

そのままゆっくりと引き抜けば、インナーバレルが外れます。
でもチャンバーパッキンは中に残ったままなのでご注意。
パッキンはチャンバー自体を分解しないと外せないようです。

チャンバー上部にはホップ調整用のベアリングが入っているので、
フレームを分離する前に外すか、テープで止める等の処置を。

赤丸で示した部分のネジを緩めて、フレームと内部メカを分離します。
フレーム両側の同じ部分にネジがあるので、合計4箇所のネジを外します。

写真のようにクリップ取り出しレバーをマイナスドライバー等で持ち上げ、
フレームをずらせば機関部とフレームが分離できますが、
力づくで無理やりやろうとすると破壊の恐れがあるので慎重に。

赤丸部分はチャンバーを固定するネジで、左側も緩めれば外せるはずですが、
パッキンの交換の必要性はないようなので一旦ネジを抜き、
ネジ山にネジロック剤(アロンゆるみ止め)を塗って
射撃の振動でネジが緩むのを防止します。

我輩の個体は左側のプレートを外した奥に見える
赤丸部分のネジが射撃の度に緩んで抜け落ちそうになるので、
ネジロック剤をたっぷり塗って緩まないようにしました。
この部分はマガジンが入る場所であるうえ、
チャージングハンドルを固定する部分にも関係しているので、
ネジが外れるとジャムを起こすか、最悪ぶっ壊れます。

ブローバックメカの部分は今後不具合が出次第、分解するとして、
目に見えるネジというネジにネジロック剤を塗って組み上げることにします。
組み立ての際、まずはスライドをきっちりとセットして、フレームを取り付けます。
後は分解の逆手順で組み立てていけば完成するはずです。
でもね、実はネジの緩みをどうにかするぐらいなら、
ココまで分解しなくてもストックと銃身を分離させて、
目に見えるネジというネジを増し締めしたり、
外してネジロック塗って再取り付けすればいいだけの話なんですよね。

組み上げてから10クリップ(マガジン)ぐらいはぶっ放しましたが、
今のところ不具合はないので暫くは安泰なんでしょうが、
何時の日かハンマー辺りがぶっ壊れそうな気がするので気軽に撃つのも気が引けます。
まあそれよりも、手元の8mmBB弾の在庫が少なくなっているのが当面の問題。
初速はマルシン製(ていうかマルシンしか8mmBB弾作ってねぇ)
0.34gの8mm弾を使用して室内温度22℃の状態で58~73m/sと結構弱い?
夏になって35℃超える環境下でも規制値の95m/sには収まるでしょう。
命中精度は20mぐらい離れた電信柱に当たるか否かなので、お座敷で的撃ちが限界でしょう。
まあそれ以前に宮崎の有料フィールドとかで8mmオッケーな場所って無ぇし。
尚、銃と共に写っている袋はM1ガーランド用のバンダリア。
職場のミリタリーマニアの鬼軍曹がお互いまだ若かりし頃、
「沖縄で仕入れたけど要らないからやる」と言って4個セットで押し付けてきたものです。
その時は「M1ガーランドのクリップ入れなんて何処で使えばよいのやら?」と思ったんですが、
まさかコイツが日の目を浴びる日が来るとは・・・大事に保管しといてよかった。
実はこの度の分解整備、コイツをヤフオクに流すために実施したのですが、
思いのほか気持ち良く作動するM1ガーランドを見ていると
日に日に惜しいという感情が湧き上がり、今では手放したくない気分です。
ていうか、コイツのお陰で我輩の心の暗雲が晴れたと思うと、
ゲームで使えないからと言って無下に手放すのもいい気分ではないかなと。
ま、宮崎に戻って以来「我輩も一端のサバイバルゲームプレイヤーである以上、
ガスブローバックのライフルを1丁ぐらいは所有しとくべきだよなぁ」
と思っていた矢先にこのM1ガーランドを見つけてしまったので、
「まずウチさぁ、M1ガーランドあんだけど・・・撃っていかない?」ってなノリで
我輩らしさの表現の一環として暫くは手元で愛でることにしようと思います。
2019年04月18日
我輩の電動ガン散財話、まだ続くよ
我輩が今まで購入したマルイの電動ガンを並べ立て、
それについて軽いインプレッションとおすすめ度合いを述べるという
我輩以外全く得をしないし誰も幸せになれないこの企画ですが、
旧世代電動ガンの購入を検討するサバイバルゲームプレイヤーには
ハナクソ程度の役には立つのかなと思わなくもないですが、
それなら多分ハイパー道楽見たほうが手っ取り早いかも知んない。
うーん、普通の電動ガンには満足できずに変な武器ばかり手を出す傾向の強い
吉六会同志には全く以て役に立たないよねこの企画。
でも今我輩の手元にはこんぐらいしかネタがないんだよ、勘弁してくれ。

さて、我輩がマルイのM4を毛嫌いする理由は分解が('A`)マンドクセなことよりも、
フレームとアウターバレル、ハンドガードの剛性が弱すぎるのが原因です。
上下のフレームは接合部分が頼りなく、使い込んでいるうちに破壊します。
ハンドガードも徐々に結合が弱くなり、ガタガタになります。
永きに渡って使う事が出来ない電動ガン、ソレがマルイの旧世代M4。
実は我輩、M16A2出た時に速攻で飛びついたんですがね、
暫くするとフレームとアウターバレルの結合部がガッタガタになったんで、
社外品外装パーツ色々買い漁って組み込んだ挙げ句、
最終的に固定ストックのM4になってしまった気がする。
我輩が買ったM16A2の最後を、我輩は全然知らない。
しかし弟のググレカスが第一回目のエチゴヤのサバゲー大会の
くじ引きで貰ったSR16ナイツカービンは違いましたね。
そして2年後ぐらいにググレカスがサバゲー辞めたんで、
ほぼ手付かずのコイツを半額ぐらいで譲ってもらいました。
コイツはフレームとアウターの結合がしっかりしていて感心したものです。
M4カービンよりもバレルの結合のパーツが強化されているんです。
それでも不安があったんでフリーダムアートの”SEBONE”を組み込んで
RISとフレームを更にガッチリ固定してみました。
更にスコープやバイポッドまで取り付けて、スナイパー風に仕立てあげましたが、
正直アタッカーの我輩には脚なんてそんなもの飾りですね。
そしてレイルシステム、グリップ以外に特に付けるものナシ。
夜戦とかヤるんならライトが付けられるからイイんですがね。
使い勝手がいいのはアーマライト系列のライフルのお約束。
我輩的にアーマライトが何で操作しやすいと言われるその理由、
ソレはマガジン交換がどのライフルよりも容易でスムーズであることですな。
他のライフルみたいに引っ掛けてマガジンを装填、脱着をレバーでするのではなく、
ボタンを押せばマガジンが抜け、そのままマガジン挿せば装填できる。素晴らしい。
ストックが固定なので今の御時世の観点で見るとナンジャコリャなんでしょうが、
我輩に言わせればラージバッテリーが使えるという利点の方がデカい!
今時ラージバッテリーなんてガンショップでは殆ど見かけなくなりましたが、
ラジコンショップに逝けばでかいリポって売ってることあるみたい。
それと、バッテリーの交換がストックの蓋開ける⇒突っ込むだからメッチャ楽。
まだマルイの商品ラインナップには載っているというのに、
ここ10年ぐらいフィールドで全く見かけないのはどーしてでしょうかねぇ?
他のノーマル電動ガンより1万ぐらい高いですが初心者にはかなりオススメですぜ。
M4カービンRISなんて将来の粗大ゴミ買うぐらいならコレ買え。
でも出来ればフレームは後々メタルに交換するのが望ましい!

我輩、マルイがトンプソンM1A1を出すと聞いた時は耳を疑いました。
だってこういうクラシックな武器ってどういう需要があるのかって話ですよ。
ま、あの頃プライベートライアンが上映された後だったから、
そっちに流れたい人需要を見込んでの販売だったんでしょうが、
結局あまり売れなかったのか今では生産しているのかどーかすら不明です。
余談ですがマルイはその後MP40を販売するつもりだったらしいが、
トンプソンで大コケしたんで開発中止になったとかw
銃自体の素性は悪くないんですよ。
ボディは金属製だからガッチリ、多弾数マガジンは作動も快調、
ラージバッテリー使用可能でバッテリー交換も容易、
メカボックスの信頼も高くパワーもそれなりに出ていましたから、
我輩も自衛隊装備、ベトコン装備用として愛用しておりました。
ただ、古い時代の銃ということで使い勝手は良くない。
サブマシンガンなのにM4カービンぐらいのサイズというのはどうかね?
でもトンプソンが現役だった時代、歩兵の小銃は1m位あるのが当たり前だったんで仕方ないね。
そしてセミフルのセレクタとセーフ・ファイヤのセレクタが別になっている上に、
グリップ握りながら切り替えするのに難がある場所に付いているとか、
アメリカ人体系用のストックは日本人には肩付けすると構えにくいとか。
また、話によると妙な細かいところの剛性感が弱いという噂もあります。
ヒストリカル系の装備を好むプレイヤーには歓喜の商品でしょうが、
純粋にサバゲーの武器と考えるとオススメできない電動ガンですね。
現在古い銃ばかりが好みになっているんで
今更ながら欲しいと思う武器のひとつなんですが、
ストックはやっぱり木製じゃないと嫌なんでマルイのは買わねぇ。

AKの次に我輩が気に入った電動ガン、それがH&K G36C。
長らくG3を使ってきたドイツ連邦軍がようやく更新した5.56mmのライフル。
本体やマガジンの形状的にも(当時は)21世紀感を醸し出しており、
これからはこういう鉄砲が主流になるんだなぁと思っちゃいました。
サイズは適度にコンパクト、ストックを畳むと大きめのバッグにも収納可能、
アウターバレル以外の外装はほとんど樹脂製だから軽く、
しかも樹脂製なのに強度も抜群、ストックも余程ヘマしない限り折れそうにない。
セレクターの位置も使いやすい場所にあり、マガジン交換もしやすい。
バッテリーはハンドガード内蔵ですが、余裕があって入れやすい。
レールシステムっていうほどのものじゃないですが、
ハンドガード下部にレールもあるし、別売りのレイルをハンドガード横にも取り付けられる。
ただ、下のレールは短すぎてフォアグリップが遠かったんで、
写真のようにライラクスのロングタイプのレールと交換。
マウントレールも標準装備だから光学サイトもつけ放題!
でもやっぱ、レールは樹脂より金属製が望ましい。
メカボックスは我輩的に信頼性高きヴァージョン3。
AKのメカボのパーツは大量に所有していたから改造も捗りましたし、
何よりもG3系列と同じぐらいメカボへのアクセスが容易であるのが素晴らしい!
でも、暫く使っていて「コレがG36Kだったらいい感じなのにねー」
そう、我輩は昔からある程度長さがある鉄砲が好きなんです。
なので写真のようにアウターバレルをライラクスのエキステンションタイプと交換したり、
もう1個ハンドガード仕入れて、長いハンドガード自作してみたりとか、
「やっぱラージバッテリー使いたいよね」と思って
ライラクスのラージハンドガード付けてみたら
「うわ・・・」な気分に陥ったのは認めたくない若さゆえの過ち。
他にもG&Pの固定ストックもどきを付けてみたりとか、
メカボックスもギア以外はとっかえひっかえしてみたりとか、
まあそれはそれはAKと同じぐらい弄くり倒しましたね。
それぐらいG36は我輩を惹きつけるものがあったんですよ。
でも結局、ある理由をきっかけに使わなくなりました。
それは・・・マガジンポーチが手に入らない!
G36系列ってマガジンが樹脂製で厚みがあるから、
STANAGマガジン用のマガジンポーチには収まりません。
そして高さ(縦に長さ)があるから、7.62mm用のマガジンポーチにも入らねぇ。
G36のマガジンが収まるポーチってマジで存在していないんすよ。
幸い?マガジンが連結可能なんでそうやって使っていましたけど、
意味もなく予備マガジンを持つ装備を身につけるようになったら我輩的にはお払い箱。
今ならSTANAGマガジン用のマグウェルがあるんで、
それと交換してM4マガジンでバリバリ撃ちまくれるし、
予備マガジンも選び放題なんでそういう改修をして使いこなすのも一つの手段。
我輩も89式と一緒に持っていく、マガジン使い回せる銃として、
レールとサイレンサー付きのSD仕様のG36が時々欲しい衝動に駆られます。
M4は他のプレイヤーと被るから、別のが欲しいけどAKはねぇ・・・と思う人、
そしてヅイマー氏みたいに毎週末メカボを弄り回すような人には適した電動ガンだと思います。
でも外装パーツは現在あまり流通していないみたいなんで、
JGとかの中華製品でM4マガジン仕様の外装カスタムとかを買ったほうがお得。

UZIの電動ガンが出た時はそれはそれはもう、感激しましたよ。
我輩より前の世代でサブマシンガンって言ったらUZIでしたからね。
だから我輩、社会人になってから既に電動全盛期だというのに、
JACのUZI中古で手に入れてエアタンク背負って使ってましたからね。
だから電動のUZI出た時も直ぐに飛びつくと言いたいところでしたが、
実は我輩、マルイよりも先に現れたマルシンの電動UZI持っていたんですわ。
だから悲しいことに食指が全く動かなかったんだけど
後輩に買わせて使わせてもらったら「ああ、やっぱマルイの方が出来はいい(確信)」
グリップ周りもマルシンより細身で握りやすかったし、グリップセイフティもライブ。
うなぎバッテリー仕様だったんでマルシンみたいな専用バッテリー買う必要なし。
バッテリー交換もレシーバーカバー開けてそのまま突っ込むだけ、結構簡単。
グリップにマガジン突っ込む形状のサブマシンガンが使いやすいかと問われると、
正直な話、MP5よりは少々使いづらいブツではありますが
グリップのセレクターは使い難いというほどでもない。
サイズ的にもコンパクトで構えた時も一体感を感じるデザインなので、
特別使い難い銃だと思った記憶はないけど使いやすいってわけでもなかった気ガス。
多弾数マガジンが220連という少し中途半端ではありましたが、
当時の宮崎では何処のフィールドも1ゲーム300発制限があったんで、
別口でノーマルマガジン持って対処すれば問題なし。
パワーはマルシン製の方が80m/s強、マルイは75m/s以上ぐらい。
でも命中精度はマルイのほうが断然上でしたね。
AK程は当たらないけど、MP5とは同等ぐらいという印象。
最大の難点というか、コレが原因で廃盤になったという理由、
それはヴァージョン5メカボックスの拡張性のなさ。
樹脂製の特殊形状なメカボだからスプリングやピストンやギアとかの
カスタムパーツは何処のサードパーティも出さなかったし、出せなかった模様。
バレル交換ですら拒むというのですから、カスタム性は皆無。
当時は「こんな革新的なメカボが出たら、次はもっと面白い銃がモデルアップされる!」
とUZI本体よりもメカボに期待をかけたんですが、基本設計に難があったんでしょうね。
生産中止して年月が経った現在では修理も受け付けてくれない模様ですし、
このメカボを活用した銃が出ることもありませんでした。
この形状に惹かれる御仁が今の御時世どれ位存在しているのか不明ですが、
もしマンガ倉庫とかで見つけても手を出さない方が無難でしょう。
我輩は中華メーカーが出してくれないかなーと微妙に心待しているんですがね。
でも中華で出るとしたら拡張性に富むコンパクト電動ガンメカボでだろうな。

βスペツナズはマルイがAK47をショート化して
ゲームユースに特化した電動ガンとして世に送り出した一品。
なお、この辺からマルイの悪乗りが始まり、
G3 SASとかいうトンデモ銃が出るに至るw
そこまでするんならステアーAUGもクソ短いのだせよって思ったんだけど、
後にステアーHCが出て「あ、やっぱりマルイのセンスって(以下略)」
正直ね、パット見メッチャ格好悪いとは思いましたよ。
でもね、それと同時に「コレはサバゲーで使える!」とも思い、購入。
当時は何処にもAKS74Uの電動ガンがなかったんでね、仕方ないね。
短いレールが付属したハンドガードはグリップを付けると更に不格好に。
標準装備の短い220連マガジンならそれなりの格好ですが、
長いマガジンをぶっ刺すとコレまた格好悪い。
でも良かったんです、短くて軽いからゲームでは使いやすい。
サードパーティのマウントベースを付けないと光学サイトが載せられないのも難点ですが、
まー何より、個人の主観にもよるんでしょうが兎に角格好悪い銃。
どうにかしてこの似非特殊部隊銃を格好良くしてやろうかと
ストックやハンドガードに謎の改造を施して使い続けましたが、
やはり本物のショートモデルであるAKS74Uが出たら要らん子ちゃんでしたね。
我輩的にはストックをAK74みたいなストレートなやつにしてみたり、
ハンドガードはノーマルサイズのままで、レール付きにしておけば、
もう少し魅力のあるAKとして成立した気がすると思うんですがねぇ・・・
ハイサイクルの短いAKもあの短すぎるハンドガードがやっぱりブサイク。
でもAKの利点である分解のしやすさ、弄りやすいヴァージョン3メカボ、
ねじれや破損とは無縁のショートで堅固なボディはコイツでも同様ですので、
AK使いたいけど長いのは嫌、そしてお金がかかるのも嫌って方には丁度いい武器ですね。
余談ですがβスペツナズ、お値段とサイズが手頃であるということで、
有料フィールドの貸出銃に多く使われているという噂を聞いたことがあります。

マルイのM14が出た時「やっとその気になったか」と思った人も少なくないはず。
ブラックホーク・ダウンの影響でコレを買った輩も多数居られるでしょうが、
我輩的にはM14といえばヴェトナム戦争と「フルメタル・ジャケット」の教育隊でのアレ。
コイツを買って「シャーリーン」って名前をつけた人、怒らないから出てきなさい。
ナム戦装備プレイヤーは「とんでもねぇ、待っていたんだ」と呟いたことでしょう。
正直、M14がサバゲー向きかって言われるとそうじゃないですよ。
M1ガーランドがそのまま少しだけ進化したそのボディは
長くて取り回しに難があり、本体重量は電動ガンでもやっぱり重い。
「グリップ?なにそれ美味しいの?」な形状の昔ながらのライフルストックは
慣れればそうでもないけど、やっぱりグリップがある方が撃ちやすいんだと思ふ。
セイフティはトリガーのすぐ前にあるんで使いやすいんですが、
セミ・フルの切り替えはリアサイトの下という取って付けたよーな場所にあるんで、
瞬時に切り替えができないという意地悪設計。
なお、メカボのカスタムパーツは一応ありますが種類が少ない模様。
そしてマガジンはポーチが入手困難な7.62mm。
(発売当時はまだ少し、ヴェトナム戦争時代のコットンポーチがあったけど)
分解は慣れればそうでもないという意見があるようですが、
ほぼ全部バラさないとメカボックスには辿り着けません。
そして個人的にはメカボックスからスイッチやトリガー周りを
取り外すor組み立てるのが面倒と思いましたね。
ただ、多弾数マガジンが450連なので弾数には余裕があるのが救い。
ラージバッテリー仕様なのでバッテリーの搭載も楽で多く撃てる。
そして無駄に長いロングバレルのお陰か、命中精度は電動ガン随一。
細かい部分に弱い部位があるみたいだけど、基本的な剛性感は文句なし。
昔からサバイバルゲームしていた人はコイツを衝動買して、
この長いボディにうっとりしながらゲームに挑んでいたんでしょうが、
人間年令を重ねるとねぇ、長くて重いライフルは疲れるんですよ。
M14に立派なスコープを乗せると、それはそれは格好が良いんですが、
重量が増すので1日中使うのは大変なのですよ。
そのせいか発売当初は石投げると当たるぐらい散見されましたが、
今ではデルタ装備のプレイヤーで気合が入っている人ぐらいしか所有していないみたい。
我輩は取り回し云々ではなく、他の連中と被らないM14が欲しいという思いで、
バレルをぶった切って写真のようなショートモデルにしたんですが、
その後直ぐに「M14 SOCOM」とかいうモデルが出てガクッとしましたね。
結局、我輩は重さが長さがという以前に「この銃に合う装備がない」という理由で手放しましたが
この形が好きだというのであれば、そしてこの長さと重さが苦にならないというのであれば、
積極的にオススメはしなくても後悔はしない、出来のよろしい製品だと言い切れます。

我輩が唯一購入したコンパクト電動ガンがVZ61、通称スコーピオン。
最初に出たマルイのMP7はコンパクト電動ガンの名に
相応しい射程距離の短さで残念な一品でしたが、
VZ61はMP7の悪評を吹き飛ばす出来だったので
東側陣営の武器が好きな我輩は速攻で購入しましたよ。
飛距離はフルサイズ電動ガンには劣るものの、
このサイズでこれだけ飛べば文句はないでしょうと思えるレベル。
ガスのハンドガンよりもよく飛び、よく当たるから文句なし!
サイズはハンドガンより少しかさばる程度なんだもん。
命中精度は30mを超えると厳しいものがありましたが、
それ以下なら狙って当てることが出来る性能。
MP5Kと同程度か、少~~~しだけ劣る程度。
パワーは75m/s前後と物足りなさはあるものの、必要にして充分。
中華コピー品のVZ61はもっとパワーがあるみたいなので、
パーツ次第では80m/s以上までパワーを上げるポテンシャルはあるはず?
セレクターは使いやすい位置にはあるものの、
ポジションを覚えていないとどっちがセミかフルか解らないのが難点。
マガジンはマグウェルが浅いので、上手くなればスポッと突っ込めるけど、
慣れないうちは道程のセッ★スみたいに戸惑うことがあります。
スコーピオンという名称の元となったワイヤーストックは
畳んでいると少し邪魔、伸ばして肩付けするとまー使い難い。
我輩は写真のようにストックは外してハンドガンみたく使っておりました。
純正にはない380連ドラムマガジンを取り付けると、
トリガーハッピー専用アタッカーウェポンとして優秀な逸品だったし、
サイズ的にも予備の武器としてバッグに放り込めるので重宝していたんですが、
北国に転勤してから思考に変化が出て、売り払いました。
(ていうかVZ61、東側の武器だけどロシアやソ連は使ってないし)
装備がどうとか小難しいこと言わないならVZ61、
コンパクトな武器を欲するプレイヤーは見逃してはいけない武器です。
最近、クソ長くてごついマガジンと頑丈そうなストック、
そしてG36みたいなハンドガードと誰得なゴールドバレルを搭載した
「スコーピオンMOD.M」という名称のブツが販売されたようですが、
VZ61はこのコンパクトサイズだからこそ映える武器なので、
無駄にデカイカスタムは正直、何考えてんだって気分ですね。

我輩が89式を所有する理由は唯一つ、陸自コスプレのため。
コレこそまさに我輩的「とんでもねぇ、待ってたんだ」案件。
はっきり言いましょう、陸自装備持っている人以外のプレイヤーが、
89式の電動ガンを仕入れるのは愚の骨頂ですよ。
この形が好きだからとか、日本の小銃だからとか、3点バーストがあるからだとか、
欲しがる理由はそれぞれ個人の自由でしょうが
89式は自衛隊の武器!我輩的に自衛隊迷彩以外での使用は認めん!
(いや別に米軍装備で持っていてもいいけどね、違和感アリアリなのよ)
SIG550系列にような電子制御のバーストとは違い
部品の破損さえなければ確実に作動する機械式3点バースト、
日本人の平均的な体型ならしっくりくるはずのストックサイズ、
ネジさえ締まっていれば電動ガン随一を誇るであろう剛性感、
特筆するほどではないけど、確実性のある命中精度。
電動ガンの1機種として見ても89式は優れた一品ではあります。
だがしかし、自衛隊の要求に沿うべく取り付けられた二脚(バイパッド)、
各国の小銃とは逆の位置にある切り替え軸部(セレクター)と、
近代ライフルとしてはなんでそうなるの的な欠点もしっかり抱えている!
まあ上記の欠点は二脚は直ぐに取り外し可能だから好きにすればいいし、
切り替え軸部もオプションの左側セレクターを買えばいいんだけどね。
コイツの欠点らしい欠点はバッテリーを入れるのにコツが必要なことぐらいですかね。
ハンドガードギリギリにブチ込むもんだから案外キッツいんですよねー。
あと、難点は外装カスタムパーツが少ないことと、
その外装パーツが「コレは自衛隊的にナイでしょ?」なものしか存在しないこと。
フォアグリップ付けられないし、ライトも付けるのに工夫が必要。
そして89式に一番必要であろう外装パーツ?薬莢受けが入手困難であること!
青森に転勤の際は折りたたみストックと固定ストック、2丁所有していましたが、
89式カービン完全版が出来上がった時点で「長いのは要らんな」な気持ちになり、
固定ストックは売り払ってしまいましたが人が持っているのを見るとまた欲しくなる。

最後に、電動ハンドガンも紹介しましょうかね。
我輩が購入したのはH&K USPでした。
電動ハンドガンってサバイバルゲームのツールとして見ると、凄く優秀なんですよね。
ガスじゃないから冬でもパワーが安定しているし、命中精度もこのサイズではダントツ。
バッテリーさえあれば、そして機関部さえ壊れなければ作動も安定している。
「ハンドガンはガス以外使用禁止」とか言うルールの縛りがなければ
ハンドガンは電動一本でいいじゃんって思わなくもありません。
なお、フルサイズ電動ガンほど弾が飛ばないのは、
ハンドガンであるが故に欠点だとは思いません。
ハンドガンサイズで電動並みに飛ぶのが欲しけりゃ、デザートイーグル買え。
本体の価格もそれほど高いわけではありませんし、
バッテリーは1個買えば数年は使えますから、
充電する手間を考慮してもガスよりもコスパに優れています。
でもゲームユースに特化しているというか、電動であるが故にリアルじゃない。
メカボックスを詰め込む都合上、マガジンはリアルサイズじゃないし、
スライドもハンマーもスライドストップも動かないから愛でる楽しみには乏しい。
全盛期のMGC製品やWA製品みたいに少しは実銃感のある出来栄えなら
所有する悦びってぇのもあるんでしょうがねぇ。
そしてコレは個人的主観なんだけど、直ぐに壊れる。
我輩のUSPはノズルが前進しきれなくなって弾が飛ばなくなりましたし、
以前グロック18を所有していた見知らぬプレイヤーからは
「マガジン突っ込んでも機関部に弾が送り込まれない」という話も聞きました。
他にもベレッタM93R を所有していた友人から
「メカボックスが突然動かなくなった」という話を聞いたんで、
少なくとも普通の電動ガンよりメカの寿命は短いんじゃなかろうかと思うのです。
やはり、本来ハンドガン以上の大きさで成立していたメカボックスを、
ハンドガンの内部に収まるようにした結果、耐久性が低くなっているのでしょう。
破損しやすいパーツが入手しやすくて、なおかつ分解結合も容易であれば、
電動ハンドガン1丁ぐらい持っておきたいなと思うのですが、
中にはマルイに部品請求しないとだめなパーツが破壊することもあるようですし、
電動ハンドガンのメカボって面倒臭そうな気がするんで、
我輩的には余程好きなハンドガンがモデルアップしない限り、今後買わないですね。
とまあ、我輩がサバゲー始めて25年、思えば色々な電動ガンに手を出したものです。
だからこそ理解した事項もあるし、改造とか修理のノウハウも蓄積しました。
でも何でコレほどまで買う必要があっ、たのかは未だに理解不能。
まあ、20年以上サバゲーしていれば、
誰でもコレぐらいの数の電動ガンは買っているっしょ?
それに、コレ全部を新品で買ったわけじゃない。
大半は中古屋で安く売っていたのを仕入れていたんで、
皆様方が思うほど金は使ってないはずだ・・・と信じたい。
なお、この企画は三沢に居た頃から手を付けていたもので、
文章を打ち込んでは消し、読み返しては停滞しを繰り返して、
あーでもないこーでもないと試行錯誤しながら練り上げて、
この度の休業中を活用してようやく完成にこぎつけたものであることをご了承くだされ。
それについて軽いインプレッションとおすすめ度合いを述べるという
我輩以外全く得をしないし誰も幸せになれないこの企画ですが、
旧世代電動ガンの購入を検討するサバイバルゲームプレイヤーには
ハナクソ程度の役には立つのかなと思わなくもないですが、
それなら多分ハイパー道楽見たほうが手っ取り早いかも知んない。
うーん、普通の電動ガンには満足できずに変な武器ばかり手を出す傾向の強い
吉六会同志には全く以て役に立たないよねこの企画。
でも今我輩の手元にはこんぐらいしかネタがないんだよ、勘弁してくれ。

さて、我輩がマルイのM4を毛嫌いする理由は分解が('A`)マンドクセなことよりも、
フレームとアウターバレル、ハンドガードの剛性が弱すぎるのが原因です。
上下のフレームは接合部分が頼りなく、使い込んでいるうちに破壊します。
ハンドガードも徐々に結合が弱くなり、ガタガタになります。
永きに渡って使う事が出来ない電動ガン、ソレがマルイの旧世代M4。
実は我輩、M16A2出た時に速攻で飛びついたんですがね、
暫くするとフレームとアウターバレルの結合部がガッタガタになったんで、
社外品外装パーツ色々買い漁って組み込んだ挙げ句、
最終的に固定ストックのM4になってしまった気がする。
我輩が買ったM16A2の最後を、我輩は全然知らない。
しかし弟のググレカスが第一回目のエチゴヤのサバゲー大会の
くじ引きで貰ったSR16ナイツカービンは違いましたね。
そして2年後ぐらいにググレカスがサバゲー辞めたんで、
ほぼ手付かずのコイツを半額ぐらいで譲ってもらいました。
コイツはフレームとアウターの結合がしっかりしていて感心したものです。
M4カービンよりもバレルの結合のパーツが強化されているんです。
それでも不安があったんでフリーダムアートの”SEBONE”を組み込んで
RISとフレームを更にガッチリ固定してみました。
更にスコープやバイポッドまで取り付けて、スナイパー風に仕立てあげましたが、
正直アタッカーの我輩には脚なんてそんなもの飾りですね。
そしてレイルシステム、グリップ以外に特に付けるものナシ。
夜戦とかヤるんならライトが付けられるからイイんですがね。
使い勝手がいいのはアーマライト系列のライフルのお約束。
我輩的にアーマライトが何で操作しやすいと言われるその理由、
ソレはマガジン交換がどのライフルよりも容易でスムーズであることですな。
他のライフルみたいに引っ掛けてマガジンを装填、脱着をレバーでするのではなく、
ボタンを押せばマガジンが抜け、そのままマガジン挿せば装填できる。素晴らしい。
ストックが固定なので今の御時世の観点で見るとナンジャコリャなんでしょうが、
我輩に言わせればラージバッテリーが使えるという利点の方がデカい!
今時ラージバッテリーなんてガンショップでは殆ど見かけなくなりましたが、
ラジコンショップに逝けばでかいリポって売ってることあるみたい。
それと、バッテリーの交換がストックの蓋開ける⇒突っ込むだからメッチャ楽。
まだマルイの商品ラインナップには載っているというのに、
ここ10年ぐらいフィールドで全く見かけないのはどーしてでしょうかねぇ?
他のノーマル電動ガンより1万ぐらい高いですが初心者にはかなりオススメですぜ。
M4カービンRISなんて将来の粗大ゴミ買うぐらいならコレ買え。
でも出来ればフレームは後々メタルに交換するのが望ましい!

我輩、マルイがトンプソンM1A1を出すと聞いた時は耳を疑いました。
だってこういうクラシックな武器ってどういう需要があるのかって話ですよ。
ま、あの頃プライベートライアンが上映された後だったから、
そっちに流れたい人需要を見込んでの販売だったんでしょうが、
結局あまり売れなかったのか今では生産しているのかどーかすら不明です。
余談ですがマルイはその後MP40を販売するつもりだったらしいが、
トンプソンで大コケしたんで開発中止になったとかw
銃自体の素性は悪くないんですよ。
ボディは金属製だからガッチリ、多弾数マガジンは作動も快調、
ラージバッテリー使用可能でバッテリー交換も容易、
メカボックスの信頼も高くパワーもそれなりに出ていましたから、
我輩も自衛隊装備、ベトコン装備用として愛用しておりました。
ただ、古い時代の銃ということで使い勝手は良くない。
サブマシンガンなのにM4カービンぐらいのサイズというのはどうかね?
でもトンプソンが現役だった時代、歩兵の小銃は1m位あるのが当たり前だったんで仕方ないね。
そしてセミフルのセレクタとセーフ・ファイヤのセレクタが別になっている上に、
グリップ握りながら切り替えするのに難がある場所に付いているとか、
アメリカ人体系用のストックは日本人には肩付けすると構えにくいとか。
また、話によると妙な細かいところの剛性感が弱いという噂もあります。
ヒストリカル系の装備を好むプレイヤーには歓喜の商品でしょうが、
純粋にサバゲーの武器と考えるとオススメできない電動ガンですね。
現在古い銃ばかりが好みになっているんで
今更ながら欲しいと思う武器のひとつなんですが、
ストックはやっぱり木製じゃないと嫌なんでマルイのは買わねぇ。

AKの次に我輩が気に入った電動ガン、それがH&K G36C。
長らくG3を使ってきたドイツ連邦軍がようやく更新した5.56mmのライフル。
本体やマガジンの形状的にも(当時は)21世紀感を醸し出しており、
これからはこういう鉄砲が主流になるんだなぁと思っちゃいました。
サイズは適度にコンパクト、ストックを畳むと大きめのバッグにも収納可能、
アウターバレル以外の外装はほとんど樹脂製だから軽く、
しかも樹脂製なのに強度も抜群、ストックも余程ヘマしない限り折れそうにない。
セレクターの位置も使いやすい場所にあり、マガジン交換もしやすい。
バッテリーはハンドガード内蔵ですが、余裕があって入れやすい。
レールシステムっていうほどのものじゃないですが、
ハンドガード下部にレールもあるし、別売りのレイルをハンドガード横にも取り付けられる。
ただ、下のレールは短すぎてフォアグリップが遠かったんで、
写真のようにライラクスのロングタイプのレールと交換。
マウントレールも標準装備だから光学サイトもつけ放題!
でもやっぱ、レールは樹脂より金属製が望ましい。
メカボックスは我輩的に信頼性高きヴァージョン3。
AKのメカボのパーツは大量に所有していたから改造も捗りましたし、
何よりもG3系列と同じぐらいメカボへのアクセスが容易であるのが素晴らしい!
でも、暫く使っていて「コレがG36Kだったらいい感じなのにねー」
そう、我輩は昔からある程度長さがある鉄砲が好きなんです。
なので写真のようにアウターバレルをライラクスのエキステンションタイプと交換したり、
もう1個ハンドガード仕入れて、長いハンドガード自作してみたりとか、
「やっぱラージバッテリー使いたいよね」と思って
ライラクスのラージハンドガード付けてみたら
「うわ・・・」な気分に陥ったのは認めたくない若さゆえの過ち。
他にもG&Pの固定ストックもどきを付けてみたりとか、
メカボックスもギア以外はとっかえひっかえしてみたりとか、
まあそれはそれはAKと同じぐらい弄くり倒しましたね。
それぐらいG36は我輩を惹きつけるものがあったんですよ。
でも結局、ある理由をきっかけに使わなくなりました。
それは・・・マガジンポーチが手に入らない!
G36系列ってマガジンが樹脂製で厚みがあるから、
STANAGマガジン用のマガジンポーチには収まりません。
そして高さ(縦に長さ)があるから、7.62mm用のマガジンポーチにも入らねぇ。
G36のマガジンが収まるポーチってマジで存在していないんすよ。
幸い?マガジンが連結可能なんでそうやって使っていましたけど、
意味もなく予備マガジンを持つ装備を身につけるようになったら我輩的にはお払い箱。
今ならSTANAGマガジン用のマグウェルがあるんで、
それと交換してM4マガジンでバリバリ撃ちまくれるし、
予備マガジンも選び放題なんでそういう改修をして使いこなすのも一つの手段。
我輩も89式と一緒に持っていく、マガジン使い回せる銃として、
レールとサイレンサー付きのSD仕様のG36が時々欲しい衝動に駆られます。
M4は他のプレイヤーと被るから、別のが欲しいけどAKはねぇ・・・と思う人、
そしてヅイマー氏みたいに毎週末メカボを弄り回すような人には適した電動ガンだと思います。
でも外装パーツは現在あまり流通していないみたいなんで、
JGとかの中華製品でM4マガジン仕様の外装カスタムとかを買ったほうがお得。

UZIの電動ガンが出た時はそれはそれはもう、感激しましたよ。
我輩より前の世代でサブマシンガンって言ったらUZIでしたからね。
だから我輩、社会人になってから既に電動全盛期だというのに、
JACのUZI中古で手に入れてエアタンク背負って使ってましたからね。
だから電動のUZI出た時も直ぐに飛びつくと言いたいところでしたが、
実は我輩、マルイよりも先に現れたマルシンの電動UZI持っていたんですわ。
だから悲しいことに食指が全く動かなかったんだけど
後輩に買わせて使わせてもらったら「ああ、やっぱマルイの方が出来はいい(確信)」
グリップ周りもマルシンより細身で握りやすかったし、グリップセイフティもライブ。
うなぎバッテリー仕様だったんでマルシンみたいな専用バッテリー買う必要なし。
バッテリー交換もレシーバーカバー開けてそのまま突っ込むだけ、結構簡単。
グリップにマガジン突っ込む形状のサブマシンガンが使いやすいかと問われると、
正直な話、MP5よりは少々使いづらいブツではありますが
グリップのセレクターは使い難いというほどでもない。
サイズ的にもコンパクトで構えた時も一体感を感じるデザインなので、
特別使い難い銃だと思った記憶はないけど使いやすいってわけでもなかった気ガス。
多弾数マガジンが220連という少し中途半端ではありましたが、
当時の宮崎では何処のフィールドも1ゲーム300発制限があったんで、
別口でノーマルマガジン持って対処すれば問題なし。
パワーはマルシン製の方が80m/s強、マルイは75m/s以上ぐらい。
でも命中精度はマルイのほうが断然上でしたね。
AK程は当たらないけど、MP5とは同等ぐらいという印象。
最大の難点というか、コレが原因で廃盤になったという理由、
それはヴァージョン5メカボックスの拡張性のなさ。
樹脂製の特殊形状なメカボだからスプリングやピストンやギアとかの
カスタムパーツは何処のサードパーティも出さなかったし、出せなかった模様。
バレル交換ですら拒むというのですから、カスタム性は皆無。
当時は「こんな革新的なメカボが出たら、次はもっと面白い銃がモデルアップされる!」
とUZI本体よりもメカボに期待をかけたんですが、基本設計に難があったんでしょうね。
生産中止して年月が経った現在では修理も受け付けてくれない模様ですし、
このメカボを活用した銃が出ることもありませんでした。
この形状に惹かれる御仁が今の御時世どれ位存在しているのか不明ですが、
もしマンガ倉庫とかで見つけても手を出さない方が無難でしょう。
我輩は中華メーカーが出してくれないかなーと微妙に心待しているんですがね。
でも中華で出るとしたら拡張性に富むコンパクト電動ガンメカボでだろうな。

βスペツナズはマルイがAK47をショート化して
ゲームユースに特化した電動ガンとして世に送り出した一品。
なお、この辺からマルイの悪乗りが始まり、
G3 SASとかいうトンデモ銃が出るに至るw
そこまでするんならステアーAUGもクソ短いのだせよって思ったんだけど、
後にステアーHCが出て「あ、やっぱりマルイのセンスって(以下略)」
正直ね、パット見メッチャ格好悪いとは思いましたよ。
でもね、それと同時に「コレはサバゲーで使える!」とも思い、購入。
当時は何処にもAKS74Uの電動ガンがなかったんでね、仕方ないね。
短いレールが付属したハンドガードはグリップを付けると更に不格好に。
標準装備の短い220連マガジンならそれなりの格好ですが、
長いマガジンをぶっ刺すとコレまた格好悪い。
でも良かったんです、短くて軽いからゲームでは使いやすい。
サードパーティのマウントベースを付けないと光学サイトが載せられないのも難点ですが、
まー何より、個人の主観にもよるんでしょうが兎に角格好悪い銃。
どうにかしてこの似非特殊部隊銃を格好良くしてやろうかと
ストックやハンドガードに謎の改造を施して使い続けましたが、
やはり本物のショートモデルであるAKS74Uが出たら要らん子ちゃんでしたね。
我輩的にはストックをAK74みたいなストレートなやつにしてみたり、
ハンドガードはノーマルサイズのままで、レール付きにしておけば、
もう少し魅力のあるAKとして成立した気がすると思うんですがねぇ・・・
ハイサイクルの短いAKもあの短すぎるハンドガードがやっぱりブサイク。
でもAKの利点である分解のしやすさ、弄りやすいヴァージョン3メカボ、
ねじれや破損とは無縁のショートで堅固なボディはコイツでも同様ですので、
AK使いたいけど長いのは嫌、そしてお金がかかるのも嫌って方には丁度いい武器ですね。
余談ですがβスペツナズ、お値段とサイズが手頃であるということで、
有料フィールドの貸出銃に多く使われているという噂を聞いたことがあります。

マルイのM14が出た時「やっとその気になったか」と思った人も少なくないはず。
ブラックホーク・ダウンの影響でコレを買った輩も多数居られるでしょうが、
我輩的にはM14といえばヴェトナム戦争と「フルメタル・ジャケット」の教育隊でのアレ。
コイツを買って「シャーリーン」って名前をつけた人、怒らないから出てきなさい。
ナム戦装備プレイヤーは「とんでもねぇ、待っていたんだ」と呟いたことでしょう。
正直、M14がサバゲー向きかって言われるとそうじゃないですよ。
M1ガーランドがそのまま少しだけ進化したそのボディは
長くて取り回しに難があり、本体重量は電動ガンでもやっぱり重い。
「グリップ?なにそれ美味しいの?」な形状の昔ながらのライフルストックは
慣れればそうでもないけど、やっぱりグリップがある方が撃ちやすいんだと思ふ。
セイフティはトリガーのすぐ前にあるんで使いやすいんですが、
セミ・フルの切り替えはリアサイトの下という取って付けたよーな場所にあるんで、
瞬時に切り替えができないという意地悪設計。
なお、メカボのカスタムパーツは一応ありますが種類が少ない模様。
そしてマガジンはポーチが入手困難な7.62mm。
(発売当時はまだ少し、ヴェトナム戦争時代のコットンポーチがあったけど)
分解は慣れればそうでもないという意見があるようですが、
ほぼ全部バラさないとメカボックスには辿り着けません。
そして個人的にはメカボックスからスイッチやトリガー周りを
取り外すor組み立てるのが面倒と思いましたね。
ただ、多弾数マガジンが450連なので弾数には余裕があるのが救い。
ラージバッテリー仕様なのでバッテリーの搭載も楽で多く撃てる。
そして無駄に長いロングバレルのお陰か、命中精度は電動ガン随一。
細かい部分に弱い部位があるみたいだけど、基本的な剛性感は文句なし。
昔からサバイバルゲームしていた人はコイツを衝動買して、
この長いボディにうっとりしながらゲームに挑んでいたんでしょうが、
人間年令を重ねるとねぇ、長くて重いライフルは疲れるんですよ。
M14に立派なスコープを乗せると、それはそれは格好が良いんですが、
重量が増すので1日中使うのは大変なのですよ。
そのせいか発売当初は石投げると当たるぐらい散見されましたが、
今ではデルタ装備のプレイヤーで気合が入っている人ぐらいしか所有していないみたい。
我輩は取り回し云々ではなく、他の連中と被らないM14が欲しいという思いで、
バレルをぶった切って写真のようなショートモデルにしたんですが、
その後直ぐに「M14 SOCOM」とかいうモデルが出てガクッとしましたね。
結局、我輩は重さが長さがという以前に「この銃に合う装備がない」という理由で手放しましたが
この形が好きだというのであれば、そしてこの長さと重さが苦にならないというのであれば、
積極的にオススメはしなくても後悔はしない、出来のよろしい製品だと言い切れます。

我輩が唯一購入したコンパクト電動ガンがVZ61、通称スコーピオン。
最初に出たマルイのMP7はコンパクト電動ガンの名に
相応しい射程距離の短さで残念な一品でしたが、
VZ61はMP7の悪評を吹き飛ばす出来だったので
東側陣営の武器が好きな我輩は速攻で購入しましたよ。
飛距離はフルサイズ電動ガンには劣るものの、
このサイズでこれだけ飛べば文句はないでしょうと思えるレベル。
ガスのハンドガンよりもよく飛び、よく当たるから文句なし!
サイズはハンドガンより少しかさばる程度なんだもん。
命中精度は30mを超えると厳しいものがありましたが、
それ以下なら狙って当てることが出来る性能。
MP5Kと同程度か、少~~~しだけ劣る程度。
パワーは75m/s前後と物足りなさはあるものの、必要にして充分。
中華コピー品のVZ61はもっとパワーがあるみたいなので、
パーツ次第では80m/s以上までパワーを上げるポテンシャルはあるはず?
セレクターは使いやすい位置にはあるものの、
ポジションを覚えていないとどっちがセミかフルか解らないのが難点。
マガジンはマグウェルが浅いので、上手くなればスポッと突っ込めるけど、
慣れないうちは道程のセッ★スみたいに戸惑うことがあります。
スコーピオンという名称の元となったワイヤーストックは
畳んでいると少し邪魔、伸ばして肩付けするとまー使い難い。
我輩は写真のようにストックは外してハンドガンみたく使っておりました。
純正にはない380連ドラムマガジンを取り付けると、
トリガーハッピー専用アタッカーウェポンとして優秀な逸品だったし、
サイズ的にも予備の武器としてバッグに放り込めるので重宝していたんですが、
北国に転勤してから思考に変化が出て、売り払いました。
(ていうかVZ61、東側の武器だけどロシアやソ連は使ってないし)
装備がどうとか小難しいこと言わないならVZ61、
コンパクトな武器を欲するプレイヤーは見逃してはいけない武器です。
最近、クソ長くてごついマガジンと頑丈そうなストック、
そしてG36みたいなハンドガードと誰得なゴールドバレルを搭載した
「スコーピオンMOD.M」という名称のブツが販売されたようですが、
VZ61はこのコンパクトサイズだからこそ映える武器なので、
無駄にデカイカスタムは正直、何考えてんだって気分ですね。

我輩が89式を所有する理由は唯一つ、陸自コスプレのため。
コレこそまさに我輩的「とんでもねぇ、待ってたんだ」案件。
はっきり言いましょう、陸自装備持っている人以外のプレイヤーが、
89式の電動ガンを仕入れるのは愚の骨頂ですよ。
この形が好きだからとか、日本の小銃だからとか、3点バーストがあるからだとか、
欲しがる理由はそれぞれ個人の自由でしょうが
89式は自衛隊の武器!我輩的に自衛隊迷彩以外での使用は認めん!
(いや別に米軍装備で持っていてもいいけどね、違和感アリアリなのよ)
SIG550系列にような電子制御のバーストとは違い
部品の破損さえなければ確実に作動する機械式3点バースト、
日本人の平均的な体型ならしっくりくるはずのストックサイズ、
ネジさえ締まっていれば電動ガン随一を誇るであろう剛性感、
特筆するほどではないけど、確実性のある命中精度。
電動ガンの1機種として見ても89式は優れた一品ではあります。
だがしかし、自衛隊の要求に沿うべく取り付けられた二脚(バイパッド)、
各国の小銃とは逆の位置にある切り替え軸部(セレクター)と、
近代ライフルとしてはなんでそうなるの的な欠点もしっかり抱えている!
まあ上記の欠点は二脚は直ぐに取り外し可能だから好きにすればいいし、
切り替え軸部もオプションの左側セレクターを買えばいいんだけどね。
コイツの欠点らしい欠点はバッテリーを入れるのにコツが必要なことぐらいですかね。
ハンドガードギリギリにブチ込むもんだから案外キッツいんですよねー。
あと、難点は外装カスタムパーツが少ないことと、
その外装パーツが「コレは自衛隊的にナイでしょ?」なものしか存在しないこと。
フォアグリップ付けられないし、ライトも付けるのに工夫が必要。
そして89式に一番必要であろう外装パーツ?薬莢受けが入手困難であること!
青森に転勤の際は折りたたみストックと固定ストック、2丁所有していましたが、
89式カービン完全版が出来上がった時点で「長いのは要らんな」な気持ちになり、
固定ストックは売り払ってしまいましたが人が持っているのを見るとまた欲しくなる。

最後に、電動ハンドガンも紹介しましょうかね。
我輩が購入したのはH&K USPでした。
電動ハンドガンってサバイバルゲームのツールとして見ると、凄く優秀なんですよね。
ガスじゃないから冬でもパワーが安定しているし、命中精度もこのサイズではダントツ。
バッテリーさえあれば、そして機関部さえ壊れなければ作動も安定している。
「ハンドガンはガス以外使用禁止」とか言うルールの縛りがなければ
ハンドガンは電動一本でいいじゃんって思わなくもありません。
なお、フルサイズ電動ガンほど弾が飛ばないのは、
ハンドガンであるが故に欠点だとは思いません。
ハンドガンサイズで電動並みに飛ぶのが欲しけりゃ、デザートイーグル買え。
本体の価格もそれほど高いわけではありませんし、
バッテリーは1個買えば数年は使えますから、
充電する手間を考慮してもガスよりもコスパに優れています。
でもゲームユースに特化しているというか、電動であるが故にリアルじゃない。
メカボックスを詰め込む都合上、マガジンはリアルサイズじゃないし、
スライドもハンマーもスライドストップも動かないから愛でる楽しみには乏しい。
全盛期のMGC製品やWA製品みたいに少しは実銃感のある出来栄えなら
所有する悦びってぇのもあるんでしょうがねぇ。
そしてコレは個人的主観なんだけど、直ぐに壊れる。
我輩のUSPはノズルが前進しきれなくなって弾が飛ばなくなりましたし、
以前グロック18を所有していた見知らぬプレイヤーからは
「マガジン突っ込んでも機関部に弾が送り込まれない」という話も聞きました。
他にもベレッタM93R を所有していた友人から
「メカボックスが突然動かなくなった」という話を聞いたんで、
少なくとも普通の電動ガンよりメカの寿命は短いんじゃなかろうかと思うのです。
やはり、本来ハンドガン以上の大きさで成立していたメカボックスを、
ハンドガンの内部に収まるようにした結果、耐久性が低くなっているのでしょう。
破損しやすいパーツが入手しやすくて、なおかつ分解結合も容易であれば、
電動ハンドガン1丁ぐらい持っておきたいなと思うのですが、
中にはマルイに部品請求しないとだめなパーツが破壊することもあるようですし、
電動ハンドガンのメカボって面倒臭そうな気がするんで、
我輩的には余程好きなハンドガンがモデルアップしない限り、今後買わないですね。
とまあ、我輩がサバゲー始めて25年、思えば色々な電動ガンに手を出したものです。
だからこそ理解した事項もあるし、改造とか修理のノウハウも蓄積しました。
でも何でコレほどまで買う必要があっ、たのかは未だに理解不能。
まあ、20年以上サバゲーしていれば、
誰でもコレぐらいの数の電動ガンは買っているっしょ?
それに、コレ全部を新品で買ったわけじゃない。
大半は中古屋で安く売っていたのを仕入れていたんで、
皆様方が思うほど金は使ってないはずだ・・・と信じたい。
なお、この企画は三沢に居た頃から手を付けていたもので、
文章を打ち込んでは消し、読み返しては停滞しを繰り返して、
あーでもないこーでもないと試行錯誤しながら練り上げて、
この度の休業中を活用してようやく完成にこぎつけたものであることをご了承くだされ。
2019年04月17日
この玩具たちにどんだけ散財したのやら?
ココ最近、新しいエアガンよりも電動工具色々欲しい砥部良軍曹です。
電動ドライバーとか、ディスクサンダーとかが現在の我輩の物欲。
いや、電動ガンも欲しいものがないわけじゃないけど、
欲しいもののほぼ全てが絶版品だったり、高級品なのよね。
だがしかし、今手元に20万円ぐらいあったら、
ヒトラーの電動ノコギリよりもハスクバーナのチェーンソーが欲しい。
ていうかさー、最近の新作ってM4の変なレールが付いているやつばっかじゃん。
そんな心境なので当分、新しいエアガンのレビューを書くことはないでしょう。
というわけで以前からヤるべきかどーか悩んでいた
我輩がかつて所有していた電動ガンの紹介をすることにします。
需要があるかどーかは別として、一応ここはサバゲーのブログと言う事で、
なお、こんなネタはミリブロでやれよって苦言は聞かないことにします。
サバイバルゲーム趣味人としての我輩のささやかな自慢は
前世代のマルイ製電動ガンは一通り全て所有したことがある!
バリエーション展開の中で必要性を感じなくて買わなかったものもありますが、
(例えばH&K G3A4とかSIG 550とかH&K MP5SD5とかM14 SOCOMとかね)
若かった頃はとにかく新製品が出る度に電動ガンを買い漁ったものでした。
そして独身寮のロッカーの中に電動ガンをズラッと陳列して悦に入り、
サバゲーの前日は「明日はどれを持って行こうかなー」と悩んでいたものです。
というわけで過去に色々仕入れた品々を並べ立てながら
「どや!」と自慢したいわけなのですがそれだけでは記事として成立しないので、
この銃はココがよくてココがダメだったみたいなコメントを織り交ぜながら
色々と紹介していきたいと思いますが何度も言うけど本当に需要あんのかこの企画?

さて、今でこそ我輩と言えばAKというイメージが有るようですが、
実は我輩の電動ガン歴はMP5から始まりました。
まだ電動ガンにホップシステムが搭載されていなかった頃の話で、
電動ガンもFA-MAS、M16A1、XM177、MP5A4、
そしてMP5A5しかリリースされていなかった頃のお話。
写真は宮崎でサバゲーにドハマリした頃に購入したMP5SD6ですが、
我輩が初めて購入した電動ガンはMP5A5。
当時クルマのない我輩、サバゲーに連れて行ってもらうことを考慮して、
出来るだけコンパクトな銃としてコイツを購入したのがきっかけでした。
しかし結局、MP5A5をサバゲーに持ち出すことはありませんでしたね。
パワーアップと飛距離アップを目論んで色々パーツ組み込んだら壊れちゃったからw
暫くして弄る能力に余裕が出てきた頃にメカボ復活させて、
当時よく飲み屋代奢ってくれたイカ焼き職人先輩にプレゼントしちゃいました。
MP5系列は固定ストックのA4とスライドストックのA5、
そして写真のSD6を使いましたが全てに共通する良い点は“軽い!”。
軽いからまあとにかく疲れないし、身体の動きも良くなるんです。
まああの頃は今よりも体重が15kgぐらい軽かったんですがねw
固定ストックのA4はそれに加えてラージバッテリーが使えるのが良い!
ミニバッテリーよりもヘタリは少なく、発射弾数も多いラージバッテリーは、
1日じゅう使いまくってもバッテリー切れの心配がないので心強い味方でした。
リポ全盛の現在でも、バッテリーの形状を問わないという利点があります。
スライドストックのA5とSD6はスライドストックにガタが出るのと、
ミニバッテリーしか使えないのが難点でした。
特にA5はバッテリーを搭載するのにコツを必要とするので、
それがもう嫌で嫌で仕方がなかったのもゲームで使わなかった原因です。
でもSD6はバッテリーをすんなり収めることが出来るので良かった。
但し内側削らないとSDバッテリーとかいう専用のものじゃないと入りませんでしたがね。
(最近再販されたものは純正ニッスイバッテリー搭載可能な模様)
そしてハンドガードを固定するピンがただ差し込んでいるだけなので、
いつの間にかゲーム中に紛失するのも頂けませんでした。
あと、全てのMP5に共通する難点としてフレームがモナカ構造の貼り合わせなので、
使っているうちにマグウェル部分が広がってマガジンが抜けやすくなるんですね。
対処法としてはファーストファクトリー MP5マグキャッチプラスを
組み込む以外に手段はない模様で我輩もコイツを組み込んでおりました。
もう一つ、MP5の難点は200連の多弾数マガジン。
長くて細いという構造のためか一巻きで全ての弾を撃ちきれないし、時々ジャムります。
なのでストイックにノーマルマガジンに徹するか、社外品で手頃なの探すか、
ダブルマグタイプの220連マガジンを使うことをオススメします。
そして案外見落とされているのが、セレクターを止めるイモネジが緩むこと。
ネジロックを塗って対処しておかないと憂き目にあいます。
でもやっぱ我輩的に、MP5の難点はメッチャ分解し難いところ。
バレル交換するだけの為に全部バラさなければいけないというのは耐えられません。
ホップパッキン交換するのも一苦労です。
勿論、メカボックスへのアクセスも完全分解。
ちょくちょく機関部改修したがるヅイマー氏なんかが絶対買ってはいけない銃です。
SD6は当時“オメガ7”のコスプレでサバゲーしていたので購入したのですが、
ほぼ飾りとはいえサプレッサーもそこそこ効果があり、
使い勝手が良かったんでかなり使い倒しましたね。
でも本気で静粛性を追求するなら社外品サプレッサー必須。
我輩がMP5系列でオススメするのはラージバッテリーが搭載可能なMP5A4ですね。
持ち運びに便利なのは全長が短くなるスライドストックのタイプですが、
ゲームで使う分においてコンパクトさはスライドストックと大差ありません。
余談ですがMP5PDWストック&レイル付きのMP5RASは
ストックを折りたたむと220連マガジンが使えなくなるし、
ストックと本体のバランスが悪くてフロントヘビーで持ち難いし、
何よりもバッテリー入れ難いのでオススメしない。
ま、最近は中華電動ガンでも出来が良くてフレームが金属製で
ボディも頑丈で分解も容易なモデルが多数出ているんで、
メカボ弄れるんならそっちを買うほうがよろしいかもしれませんがね。

んで、我輩が本気でサバゲーに参戦するために購入したのがAK47。
ここから今に続く我輩のAKに陶酔した人生が始まりました。
MP5はホップ未搭載だったんで、飛距離的問題でゲームに使えなかったのですよ。
因みに写真のAK47はRPKっぽいのを作りたくて
社外品のロングバレルを組み込んだ挙句、PSG1のインナーバレルを搭載し、
実銃用バイポッドを取り付け、自作フォアグリップ付きハンドガードを取り付けたもの。
フレームはメタル、メカボはエチゴヤの10.8V仕様のハイサイクルカスタム。
他にもクラフトアップル製の木製ストックに換装したベトコン装備用AKとか、
ハンドガード下部に無理やりサンプロジェクトのM203取り付けたやつとか持っていました。
いやね、高校時代からAKという銃には興味があったんですよ。
でもね、昔はファルコントーイが56式とAK47Sのガスガンを出したぐらいで
他はLSのエアコキぐらいしか存在していなかった状況。
そこにマルイが電動ガン第4弾としてAK47を発売したんですぐさま購入。
そしてコイツを使って同期のH田君と一緒に天竜川の河川敷でサバゲーしたんです。
AKには固定ストックのAK47と折りたたみストックのAK47Sがありますが、
オススメは断然、固定ストックの方ですね。
理由はラージバッテリーが使えることと、ストックが壊れにくい。
AK47Sはストックの基部や根本が案外弱っちくて破損率が高いです。
そしてストックに変な角度が付いているので、構えた時に不自然な感じになります。
(AK47自体がストックが曲銃床なんで、どっちも不自然ではあるけど)
ミニサイズのバッテリー使う電動ガンの中では比較的
バッテリーの搭載が楽な機種ではあるんですがね。
AK系列はセレクターが使い難いとよく言われますが、
コイツよりセレクターが使い難い銃をよく知っているのでそれ程気にはならない。
引っ張って回すセレクターに比べればAKのセレクターなんて大分マシよ。
AKの最大の利点はノーマル電動ガンの中でも頑丈であること。
フレームの構成が良く出来ているのでネジさえ締まっていれば揺るぎないボディ。
大抵の電動ガンは何処其処にぶつけたり、
落としたりすると何処かしらぶっ壊れるものなのですが、
AK47はそういう心配は殆どありません。
ぶっ壊れたとしても使えないこともありません。
エアガンとしてのAK47の欠点は各部のネジが緩みやすいことぐらいですね。
特にフロントサイトのネジの緩みやすさは特筆モノ。
対策としてはネジロックを塗ればとりあえず解決。
あと、AK47のストックの蓋は結構外れやすいので、
ファーストファクトリーのAK47 固定ストックバットプレートロックを
組み込むのをオススメしますが我輩決してLAYLAXの回し者じゃないよw
機種ごとにブランド展開する以前のLAYLAXは電動ガンの難点を解消する
良品なパーツを多く販売していたという事実をご存知でしょうか?
AK47に関してはサバゲーで使うことだけ考えれば
マルイ製でも外観的に全く不満はないのですが、
AKの世界にハマると木製ストックが欲しくなるはず。
しかし悲しいことにアフターパーツで木製ストック、あまり見かけないんですよねぇ。

AKに陶酔していた時期が長かったので暫くAK浸りでしたが、
当時一緒にゲームしていたH部さん(我輩のサバゲー恩師)に影響されて
陸自迷彩を仕入れた時に購入したのがMC51と前述のSD6でした。
(余談ではあるがSD6を購入したのもH部さんの影響w)
購入後暫くはラージハンドガードで運用していましたが、
あまりにも格好悪いのでコイツを改造するためだけのためにG3A3を購入して、
ストックをG3A3のものと交換(色も塗りなおし)し、
バレルを少々伸ばしたかったのでアウターバレルも交換し、
実銃用のキャリングハンドルも購入して取り付け、
メカボックス内のパーツはギア意外は全て交換し、
最終的にはハンドガードをRASに交換してマウント取り付け、ドットサイト搭載。
他にもニトロヴォイスの糞長いトップレール付けたやつに
銃口部分を正ネジアダプターにしたやつとか、
(コレも後にラージストック仕様に改修)作って所有していましたね。
そしてコイツを長きに渡って色々弄くり回し、使い倒した結果、
「一番オススメの電動ガンはMC51だ!」という結論に至ったのです。
だからミスターT(鯖芸部の永久名誉リーダーのあの人)と仲良くなり、
初めてサバゲーした時にMC51愛を語られた時は
「ああ、我輩はこの人となら骨の髄まで解り合える!」と確信したものです。
ナニがいいかってボディが軽い割に剛性がしっかりしていること、
そしてMP5のサイズなのに500発のマガジンキャパシティがあること、
そしてストックを入手して(純正パーツで購入可能)付け替えて、
配線を入れ替えればラージバッテリーで運用可能なこと、
(配線の入れ替えは素人でも直ぐに出来るぐらい簡単)
そしてメカボックスへのアクセスがかなり容易である事。
ストック周りとマガジンキャッチ周りのピンさえ抜けば直ぐですからね。
上下分割が容易なので、インナーバレルへのアクセスも簡単。
難点はデフォルトの状態だとスライドストックが構えにくいこと、
(肩を当てる部分が小さいのでがっちり構えにくい)
デフォルトの状態だとハンドガードにミニバッテリーを搭載するので、
発射弾数に難があることとバッテリーが入れにくいこと。
但し、この2つの欠点は上記のストック仕様への改造により解決!
一番の難点はMP5程ではないものの、
セレクターのイモネジが緩みやすいことぐらい。
要するにそれぐらい細かいアラ探しをしなければならないほど、欠点がない。
でも結局我輩がコイツを使わなくなった理由は
「何処の軍隊もコイツを採用していないから」
「サバゲー向きである=ロマンに欠ける」という
どーでもいいけどどーでも良くない理由だったんですね。
やっぱ我輩、少々使い難い鉄砲が好きなんですよ。
因みにコイツよりさらに短いG3 SASとか言う、絶対にSASが使っていない架空銃は、
形状があまりにも現実離れしているんで我輩的には嫌いな銃なのですが、
「このサイズは使えそうだ!」と感じた突撃派な方なら買って後悔はしないはず。

因みにMC51の原点であるG3A3、G3A4、G3SG1に関しましては、
ロングサイズであるが故に剛性感に乏しく、本体が撓みやすいので、
(ハンドガードを握るとギシギシするのがしっかりと解るレベル)
命中精度もAK47に劣り、ゲームで使うと不安を感じるし、
何よりもブッシュに入ると邪魔で仕方がないという難点があります。
メタルフレームとか内部にぶち込むスリーブ等を手に入れることが
出来るのであれば購入してもいいのでしょうが箱出しでは不安がつきまといます。
(ていうかまだG3用のそういうパーツって出回っているのか、甚だ不明)
写真のブツはG3A3にPSG-1のハンドガードを取り付けて、
先端は社外品のHK51アウターバレルに換装、
リアサイトを撤去してファーストファクトリーのマウントベースを搭載、
チャンバーブロックを組み込んで剛性もある程度解消し、
ストックはA3のストックをパテ盛りでPSG-1のミリタリーモデルであるMSG-90風に改造したもの。
インナーバレルをPSG-1のものと交換したらパワーが70m/sぐらいに下がったので、
メカボックスのカスタムに相当手間を掛けた大変な一品でしたが、
命中精度がAK47に劣るというトンデモなやつでございました。
多分おそらく、コイツが一番金かけた電動ガンよ。
余談ですが我輩、大抵の電動ガンは手にしたと豪語しておりますが、
PSG-1だけは購入したことがありません。
PSG-1独特のピストンが後退した状態から発射されるという機構は
電動ガンの難点である発射タイムラグを縮める良いアイデアですが、
全体的な構成もG3譲りでガタが生じやすいので、
フレーム剛性は電動ガンの中でも激弱な部類、
だからバレルがしなって命中精度が低くなるという致命傷。
唯でさえ高額な本体価格なのにメタルフレーム化とか
ピストンやスプリング交換などメカボックス内を弄くり倒すとかすると
本体にかかる費用が原チャリ並みの価格に跳ね上がり、
それでもセミオートしか撃てないから我輩的に戦力的に難があるとみられる上に、
命中精度は他の電動ガンと大差ないというシロモノ、我輩はイラネ。

PSG-1買うぐらいならSG-1買う方が価格的にも性能的にもコスパが良いです。
G3A3やSG-1ならばフルオートも撃てるし、
ラージバッテリーが使えるので沢山弾が撃てるという利点はあるのですが、
スライドストックのA4の場合はミニバッテリーしか使えない上に
ストックは構えにくいので廃盤になったのもさもありなんです。
写真はMC51に飽きて「やっぱ漢(おとこ)は長い鉄砲だよな!」と思った矢先、
中古で転がっていたかなり状態のよろしいG3A3を見つけたんで
「コレ、我輩が買ってあげなかったらこのまま埃かぶるんだろうなー」と思って
捨て猫を拾うような気持ちで購入しちゃったものですが、
試射した後1回もサバゲーに投入することもなくヤフオクに流してしまった一品です。
正直、フルサイズのG3はドイツ軍コスプレする人以外にはオススメしませんですし、
マルイもそこら辺を察したのか、G3のバリエーションはSG1とMC51のみになりました。
でもやっぱ、我輩的にフレームがふにゃふにゃするSG-1は欲しくないですねぇ。
G3欲しい人は海外製を買うほうがよろしいかもしれません(無責任)。

実は我輩がAK47の次に購入したのがMP5K。
福岡のSWATで購入して、コイツを手荷物に入れた状態で宮崎行きの飛行機に乗ろうとしたら、
当然というか、案の定入り口で引っかかって止められたのは良い思ひ出w
写真は大分後に購入したストック付きのMP5K PDWです。
MP5ではありますがフルサイズのMP5とは設計が違うので
フレームは一体型で強度も確保されています。
分解はMP5A5と比べると構造がちょこちょこ違うんで比較的容易です。
欠点はバッテリーが入れにくい事ぐらいですかねぇ。
それぐらいしか思いつきませんがMP5A5程でもない。
強いてもう一つあげるならバレルが短すぎて命中精度が微妙なことと、
箱出しではパワーが少しひ弱であることぐらいでしょう。
でも一応、他の大きい電動ガンと同じぐらい弾は飛びますよ。
ストック無しのKと折りたたみストック付きのPDW、
どちらがオススメかと言われるとストックでしっかりサイティング出来るPDWなんですが、
ストックの分お値段が跳ね上がるので予算を抑えたいならKでもいいでしょう。
ただ、PDWはストックを折りたたむとダブルマガジンタイプの220連が使えません。
我輩はコイツを予備用の武器として常に持ち込んでいたのですが、
当時愛用していたAK47の信頼性が抜群すぎて殆ど出番なし。
でも軽い武器でフィールドを駆け巡りたいという人にはうってつけの武器です。
女性で真剣にサバゲーヤるって人ならこれ買うのが賢いでしょう。

弟ググレカスが先に買ったので買う気が失せていたのですが、
暫くしてからやっぱり欲しくなったのでFA-MAS買っちゃった若かりし頃。
初の電動ガンとしてデビューしたFA-MASは未だに生産されているのですが、
コイツの需要がフランス軍コスプレイヤー以外何処にあるのかさっぱり解かんねぇ。
しかし初めて世に送り出した電動ガンを未だにカタログに残しているという点は
東京マルイの電動ガンに対する一つの姿勢として評価しますね。
ただ、未だに残しているというのならとっととモーターをEG1000に交換しろと。
モーターがEG550であるとか、メカボに一部専用パーツがあるとか、
ボディがプラスチック多すぎて強度が微妙だとか、
マウントベースやスリングやマガジンが入手困難であるとか
色々難点はありますが基本性能は悪くありません。
重量は普通に重いですが使い難いレベルではありませんですし、
長さ的にも使い難いサイズではないと思います。
ラージバッテリーが使えるので沢山弾が撃てますしね。
ただやっぱり、セレクターが大分後ろにあるのは使い難いです。
余計なお世話かも知れませんがフロントサイトがブラブラするのは頂けない。
設計の古さ故か、分解するとなるとほぼ全バラシとなるのですが、
メインスプリングとバレルぐらいしか交換箇所がないのでソコまで致命的でもないか?
あと、我輩とググレカスのFA-MASは使っているうちに配線がヘタってしまい?
フル充電したバッテリーを繋いでも発射速度が遅いというトラブルがありました。
モーターに繋がる配線を交換すれば治ったのですが、
他で同じようなトラブルを聞いたこともないので詳細は不明です。
多分基本設計の何処かに不具合でもあるんじゃなかろうかと?
それとも、配線が長スギィ!なのがよろしくないんでしょうかね?
使っている人が少なく情報も少ないし、未知なトラブルが多く、
何よりもカスタムパーツが少ないということであまりオススメできる武器ではありませんが、
基本性能は悪くないブツであるとは思います。
ただ、メタルギアソリッド2のスネークの武器、何でFA-MASだったんかと?

以前ファントムステアーを改修した時に紹介したステアーAUGは
(我輩的には“シュタイア”という言い方が正しいと思うんだがまあいいや)
AK47、MC51に続いて我輩のツボにハマった電動ガンです。
ダイハードでテロリストの親分?が使っていたのがカッコよかった。
販売当初は細い2倍ぐらいのスコープが付属した“ミリタリー”というモデルと、
写真の任意で光学サイトを載っけられる“スペシャルレシーバー”があったんですが、
いつの間にかミリタリーの方はカタログ落ちしてしまいました。
ま、あのスコープ細すぎて覗きにくいんで不人気なのも仕方がない。
どーしてもあの細いスコープ萌えって人は
JGという中華メーカーが出しているからそれを買いなさい。
コイツは簡単に本体分割可能なので、持ち運びに便利。
バレルを短くしてみたり、長くしてみたりと楽しみ方も色々。
ただ、使いやすいかと言われると微妙というか、少々難アリ。
トリガーを軽く引くと単発、ぐっと奥まで引くと連発というシステムは、
とっさの攻撃時に弾が1発しか出ないという事態に陥ることも多々あり。
マガジンに癖があって給弾不良に陥るというのも頂けなかった。
バレル分解用のラッチレバーがいつの間にか紛失する事案もあり。
でも不具合はファントムステアーの記事に載せた解消法でどーにかなるから無問題。
逆に言うと吊るしでしか電動ガンを使えない人は買っちゃいけない電動ガン。
他にも本体後ろに重心が寄っているためか、重く感じるとか、
分解結合を繰り返すと結合部分がガタガタになるとか、
長銃身の割に命中精度はそれほどでもないとか、
70年代のライフルなのにフォアグリップがついている先見性はあるけど、
今の御時世の武器として見るとレールがないから難を感じるとか、
イマイチな部分が散見されることで定評のあるブルパップです。
外装のカスタムパーツも販売当初に比べると大分少ないのでカスタムするにも限界があるし、
海外製の同じブツにレール付きとかあるからソッチのほうが魅力的かもしれない。
メカボックスはAKと同じバージョン3だから機関部改修すれば性能アップは望めます。
最近(と言っても結構前だが)、ステアーのハイサイクルが販売されたんで、
AUGフィーバー再びか?と少し期待を抱いたりはしたんですが、
実はあのレールが付いた前回り、ぶつけると破損しやすいのでご注意。
欲しい人は買えばいいと思うし、それを止める権利は我輩にないけど、
欲しい程度の軽い気持ちでは使えないというか、いつかどーでも良くなるライフル、
それがステアーAUGというシロモノだと思うんですよ。

新作が出る度に電動ガンに手を出していると、
中には全く使わないまま手放してしまう機種も多々あります。
SIG 550は電動ガン初の3点バースト機能を備えた画期的?ライフルでしたが、
スイス軍の武器が手に入ってもソレに合う装備がないから購入意欲ゼロでした。
(その後ライバーマスターとかいう赤い迷彩服は流通するようになったが
ソレは550の前の世代の装備だったので購入せず)
でもSIG 551なら銃身も少し短くてとくしゅぶたい()も使っているという想定で
興味が湧いてきたのでとりあえず購入はしてみたんです。
任意で2点~7点に設定可能な3点バーストは89式と違い、電子制御式なのですが、
新品時は全く問題なく、設定通りの弾が発射されたので、
「うお、すげぇ」とか思いながら射撃してみたもんです。
でも永きに渡って使用すると基盤がイカれて上手くバーストしないらしいですがね。
セレクターやトリガーの位置も扱いやすく、グリップも握りやすいのも好評価。
多弾数マガジンが220連と中途半端ではありますがプラ製なので安く揃えることが出来、
マガジン同士で連結可能というオモシロ機能も備えておりますが、
マガジンを5個ぐらいバカみたく繋げてサバゲーしている輩なんて
弟のググレカスぐらいしか見たことがありません。
大抵のプレイヤーは2個セットぐらいで運用していましたね。
フロントヘビーなので構えると少し銃身が下る嫌いはあるのですが、
全体的に構えやすいので特に問題は感じませんでした。
しかし最大の欠点は折りたたみストックの強度不足。
我輩の1番弟子、ポチョムキン氏の初サバゲーの時に、
ホイホイ貸してあげたら豪快にずっこけてストックボキッ!
それ以来、我輩はこの銃を2度と買わないことを誓いました。
勿論、SIG 552がデビューした時も完全ガン無視でした。
長期間保有していなかったのでバースト機能がどれぐらいでダメになるのかとか、
外装部分にどれだけ不具合が出るのかとかは全く未知の世界です。
まあ購入時にそれなりの剛性感だったんで、あまり強度ないんだろうな。
ぶっちゃけ、好きでもない限りオススメはしない銃ですね。

FN P90はマルイよりも先にトイテックというメーカーが出していたんですが、
アレはメカボが独特で作動音も何時かぶっ壊れそうなブツだったし、
何よりもドットサイトがバッテリーという謎仕様だから購入意欲湧きませんでした。
でも天下のマルイ様がP90出すとなると、
見逃すわけには逝きませんでしたね。
それに何より、こういうデザインの武器は好き嫌いが分かれそうですが我輩は好き。
この銃を選ぶ利点は今でも多数あると思います。
まずハンドリングしやすいボディデザイン。
一見取っ付きにくそうですが構えてみると身体と一体化する感じでよく馴染む。
身体の内側に銃本体が収まるので周囲にぶつける心配も少ない。
重量バランスも良く、なおかつ本体が軽いという素晴らしさ。
トリガーの下にあるセレクターは人差し指で用意に切替可能、
フルオート固定にして指切りセミオートも容易いトリガープルは絶品。
バッテリーはストックの蓋をずらせばすぐに交換可能。
ストックの蓋は脱落防止が施されているので安心。
ノーマルタイプ(現在絶版)はドットサイトが小さくて狙いにくかったんですが、
現在でも販売中のTRは好みの光学サイトを取付可能で便利。
でもあまり大きめのものを乗せると重量増加して使いにくいという。
TRに付属しているサイレンサーは使っているうちに
内部のスポンジが崩れてきて弾道を乱すので出来れば社外品に換えるか、
我輩みたいに「あんなもの飾りです」と思ってヤフオクに出すのが良いでしょう。
余談ですがノーマルタイプのドットはレンズがプラなので、
被弾すると簡単にぶっ壊れますていうか、3人ぐらい割れたの見たことある。
エチゴヤのサバゲーでレンズ割れたのを目の当たりにして、
ゲームの帰りにエチゴヤでレンズの前に取り付ける強化シールド買いましたからね。
難点は特殊過ぎる形状のマガジンですかね?
マガジン交換に関しては案外、慣れると素早く出来るんですよ。
問題は多弾マガジンの弾上がりが悪く、対策を施さないと使えないこと。
詳しくは「P90マガジン 対策」でググれば出てくるはずです。
更に問題なのはマガジンポーチの選択肢が少ないこと。
Akのマグポーチよりも種類は少ないです。
我輩はTMCのP90用マガジンポーチを使っておりました。
(余談だがそのマガジンポーチは現在グリースガン用に使っている)
脱落する部品が極めて少ないこと、コンパクトで使いやすいこと、
そして何よりマガジン紛失の心配が皆無であるということから、
夜戦用の武器として長年愛用しておりましたが
青森に引っ越したら夜戦の機会が少なくなったので売却。
でも数年前、P90のマガジンが使えるM4、
SR57とか言う変態銃が出たときに「あーやっぱ、P90持っとけばよかった」と
謎の感情が湧いてきたんで今でも少々未練があるぐらい好きだった電動ガン。
さて、ここまで散々グダって役に立たない話をしてきましたが、
実はまだまだ話は続くんで暇な方は次回までお付き合いくだされ。
電動ドライバーとか、ディスクサンダーとかが現在の我輩の物欲。
いや、電動ガンも欲しいものがないわけじゃないけど、
欲しいもののほぼ全てが絶版品だったり、高級品なのよね。
だがしかし、今手元に20万円ぐらいあったら、
ヒトラーの電動ノコギリよりもハスクバーナのチェーンソーが欲しい。
ていうかさー、最近の新作ってM4の変なレールが付いているやつばっかじゃん。
そんな心境なので当分、新しいエアガンのレビューを書くことはないでしょう。
というわけで以前からヤるべきかどーか悩んでいた
我輩がかつて所有していた電動ガンの紹介をすることにします。
需要があるかどーかは別として、一応ここはサバゲーのブログと言う事で、
なお、こんなネタはミリブロでやれよって苦言は聞かないことにします。
サバイバルゲーム趣味人としての我輩のささやかな自慢は
前世代のマルイ製電動ガンは一通り全て所有したことがある!
バリエーション展開の中で必要性を感じなくて買わなかったものもありますが、
(例えばH&K G3A4とかSIG 550とかH&K MP5SD5とかM14 SOCOMとかね)
若かった頃はとにかく新製品が出る度に電動ガンを買い漁ったものでした。
そして独身寮のロッカーの中に電動ガンをズラッと陳列して悦に入り、
サバゲーの前日は「明日はどれを持って行こうかなー」と悩んでいたものです。
というわけで過去に色々仕入れた品々を並べ立てながら
「どや!」と自慢したいわけなのですがそれだけでは記事として成立しないので、
この銃はココがよくてココがダメだったみたいなコメントを織り交ぜながら
色々と紹介していきたいと思いますが何度も言うけど本当に需要あんのかこの企画?

さて、今でこそ我輩と言えばAKというイメージが有るようですが、
実は我輩の電動ガン歴はMP5から始まりました。
まだ電動ガンにホップシステムが搭載されていなかった頃の話で、
電動ガンもFA-MAS、M16A1、XM177、MP5A4、
そしてMP5A5しかリリースされていなかった頃のお話。
写真は宮崎でサバゲーにドハマリした頃に購入したMP5SD6ですが、
我輩が初めて購入した電動ガンはMP5A5。
当時クルマのない我輩、サバゲーに連れて行ってもらうことを考慮して、
出来るだけコンパクトな銃としてコイツを購入したのがきっかけでした。
しかし結局、MP5A5をサバゲーに持ち出すことはありませんでしたね。
パワーアップと飛距離アップを目論んで色々パーツ組み込んだら壊れちゃったからw
暫くして弄る能力に余裕が出てきた頃にメカボ復活させて、
当時よく飲み屋代奢ってくれたイカ焼き職人先輩にプレゼントしちゃいました。
MP5系列は固定ストックのA4とスライドストックのA5、
そして写真のSD6を使いましたが全てに共通する良い点は“軽い!”。
軽いからまあとにかく疲れないし、身体の動きも良くなるんです。
まああの頃は今よりも体重が15kgぐらい軽かったんですがねw
固定ストックのA4はそれに加えてラージバッテリーが使えるのが良い!
ミニバッテリーよりもヘタリは少なく、発射弾数も多いラージバッテリーは、
1日じゅう使いまくってもバッテリー切れの心配がないので心強い味方でした。
リポ全盛の現在でも、バッテリーの形状を問わないという利点があります。
スライドストックのA5とSD6はスライドストックにガタが出るのと、
ミニバッテリーしか使えないのが難点でした。
特にA5はバッテリーを搭載するのにコツを必要とするので、
それがもう嫌で嫌で仕方がなかったのもゲームで使わなかった原因です。
でもSD6はバッテリーをすんなり収めることが出来るので良かった。
但し内側削らないとSDバッテリーとかいう専用のものじゃないと入りませんでしたがね。
(最近再販されたものは純正ニッスイバッテリー搭載可能な模様)
そしてハンドガードを固定するピンがただ差し込んでいるだけなので、
いつの間にかゲーム中に紛失するのも頂けませんでした。
あと、全てのMP5に共通する難点としてフレームがモナカ構造の貼り合わせなので、
使っているうちにマグウェル部分が広がってマガジンが抜けやすくなるんですね。
対処法としてはファーストファクトリー MP5マグキャッチプラスを
組み込む以外に手段はない模様で我輩もコイツを組み込んでおりました。
もう一つ、MP5の難点は200連の多弾数マガジン。
長くて細いという構造のためか一巻きで全ての弾を撃ちきれないし、時々ジャムります。
なのでストイックにノーマルマガジンに徹するか、社外品で手頃なの探すか、
ダブルマグタイプの220連マガジンを使うことをオススメします。
そして案外見落とされているのが、セレクターを止めるイモネジが緩むこと。
ネジロックを塗って対処しておかないと憂き目にあいます。
でもやっぱ我輩的に、MP5の難点はメッチャ分解し難いところ。
バレル交換するだけの為に全部バラさなければいけないというのは耐えられません。
ホップパッキン交換するのも一苦労です。
勿論、メカボックスへのアクセスも完全分解。
ちょくちょく機関部改修したがるヅイマー氏なんかが絶対買ってはいけない銃です。
SD6は当時“オメガ7”のコスプレでサバゲーしていたので購入したのですが、
ほぼ飾りとはいえサプレッサーもそこそこ効果があり、
使い勝手が良かったんでかなり使い倒しましたね。
でも本気で静粛性を追求するなら社外品サプレッサー必須。
我輩がMP5系列でオススメするのはラージバッテリーが搭載可能なMP5A4ですね。
持ち運びに便利なのは全長が短くなるスライドストックのタイプですが、
ゲームで使う分においてコンパクトさはスライドストックと大差ありません。
余談ですがMP5PDWストック&レイル付きのMP5RASは
ストックを折りたたむと220連マガジンが使えなくなるし、
ストックと本体のバランスが悪くてフロントヘビーで持ち難いし、
何よりもバッテリー入れ難いのでオススメしない。
ま、最近は中華電動ガンでも出来が良くてフレームが金属製で
ボディも頑丈で分解も容易なモデルが多数出ているんで、
メカボ弄れるんならそっちを買うほうがよろしいかもしれませんがね。

んで、我輩が本気でサバゲーに参戦するために購入したのがAK47。
ここから今に続く我輩のAKに陶酔した人生が始まりました。
MP5はホップ未搭載だったんで、飛距離的問題でゲームに使えなかったのですよ。
因みに写真のAK47はRPKっぽいのを作りたくて
社外品のロングバレルを組み込んだ挙句、PSG1のインナーバレルを搭載し、
実銃用バイポッドを取り付け、自作フォアグリップ付きハンドガードを取り付けたもの。
フレームはメタル、メカボはエチゴヤの10.8V仕様のハイサイクルカスタム。
他にもクラフトアップル製の木製ストックに換装したベトコン装備用AKとか、
ハンドガード下部に無理やりサンプロジェクトのM203取り付けたやつとか持っていました。
いやね、高校時代からAKという銃には興味があったんですよ。
でもね、昔はファルコントーイが56式とAK47Sのガスガンを出したぐらいで
他はLSのエアコキぐらいしか存在していなかった状況。
そこにマルイが電動ガン第4弾としてAK47を発売したんですぐさま購入。
そしてコイツを使って同期のH田君と一緒に天竜川の河川敷でサバゲーしたんです。
AKには固定ストックのAK47と折りたたみストックのAK47Sがありますが、
オススメは断然、固定ストックの方ですね。
理由はラージバッテリーが使えることと、ストックが壊れにくい。
AK47Sはストックの基部や根本が案外弱っちくて破損率が高いです。
そしてストックに変な角度が付いているので、構えた時に不自然な感じになります。
(AK47自体がストックが曲銃床なんで、どっちも不自然ではあるけど)
ミニサイズのバッテリー使う電動ガンの中では比較的
バッテリーの搭載が楽な機種ではあるんですがね。
AK系列はセレクターが使い難いとよく言われますが、
コイツよりセレクターが使い難い銃をよく知っているのでそれ程気にはならない。
引っ張って回すセレクターに比べればAKのセレクターなんて大分マシよ。
AKの最大の利点はノーマル電動ガンの中でも頑丈であること。
フレームの構成が良く出来ているのでネジさえ締まっていれば揺るぎないボディ。
大抵の電動ガンは何処其処にぶつけたり、
落としたりすると何処かしらぶっ壊れるものなのですが、
AK47はそういう心配は殆どありません。
ぶっ壊れたとしても使えないこともありません。
エアガンとしてのAK47の欠点は各部のネジが緩みやすいことぐらいですね。
特にフロントサイトのネジの緩みやすさは特筆モノ。
対策としてはネジロックを塗ればとりあえず解決。
あと、AK47のストックの蓋は結構外れやすいので、
ファーストファクトリーのAK47 固定ストックバットプレートロックを
組み込むのをオススメしますが我輩決してLAYLAXの回し者じゃないよw
機種ごとにブランド展開する以前のLAYLAXは電動ガンの難点を解消する
良品なパーツを多く販売していたという事実をご存知でしょうか?
AK47に関してはサバゲーで使うことだけ考えれば
マルイ製でも外観的に全く不満はないのですが、
AKの世界にハマると木製ストックが欲しくなるはず。
しかし悲しいことにアフターパーツで木製ストック、あまり見かけないんですよねぇ。

AKに陶酔していた時期が長かったので暫くAK浸りでしたが、
当時一緒にゲームしていたH部さん(我輩のサバゲー恩師)に影響されて
陸自迷彩を仕入れた時に購入したのがMC51と前述のSD6でした。
(余談ではあるがSD6を購入したのもH部さんの影響w)
購入後暫くはラージハンドガードで運用していましたが、
あまりにも格好悪いのでコイツを改造するためだけのためにG3A3を購入して、
ストックをG3A3のものと交換(色も塗りなおし)し、
バレルを少々伸ばしたかったのでアウターバレルも交換し、
実銃用のキャリングハンドルも購入して取り付け、
メカボックス内のパーツはギア意外は全て交換し、
最終的にはハンドガードをRASに交換してマウント取り付け、ドットサイト搭載。
他にもニトロヴォイスの糞長いトップレール付けたやつに
銃口部分を正ネジアダプターにしたやつとか、
(コレも後にラージストック仕様に改修)作って所有していましたね。
そしてコイツを長きに渡って色々弄くり回し、使い倒した結果、
「一番オススメの電動ガンはMC51だ!」という結論に至ったのです。
だからミスターT(鯖芸部の永久名誉リーダーのあの人)と仲良くなり、
初めてサバゲーした時にMC51愛を語られた時は
「ああ、我輩はこの人となら骨の髄まで解り合える!」と確信したものです。
ナニがいいかってボディが軽い割に剛性がしっかりしていること、
そしてMP5のサイズなのに500発のマガジンキャパシティがあること、
そしてストックを入手して(純正パーツで購入可能)付け替えて、
配線を入れ替えればラージバッテリーで運用可能なこと、
(配線の入れ替えは素人でも直ぐに出来るぐらい簡単)
そしてメカボックスへのアクセスがかなり容易である事。
ストック周りとマガジンキャッチ周りのピンさえ抜けば直ぐですからね。
上下分割が容易なので、インナーバレルへのアクセスも簡単。
難点はデフォルトの状態だとスライドストックが構えにくいこと、
(肩を当てる部分が小さいのでがっちり構えにくい)
デフォルトの状態だとハンドガードにミニバッテリーを搭載するので、
発射弾数に難があることとバッテリーが入れにくいこと。
但し、この2つの欠点は上記のストック仕様への改造により解決!
一番の難点はMP5程ではないものの、
セレクターのイモネジが緩みやすいことぐらい。
要するにそれぐらい細かいアラ探しをしなければならないほど、欠点がない。
でも結局我輩がコイツを使わなくなった理由は
「何処の軍隊もコイツを採用していないから」
「サバゲー向きである=ロマンに欠ける」という
どーでもいいけどどーでも良くない理由だったんですね。
やっぱ我輩、少々使い難い鉄砲が好きなんですよ。
因みにコイツよりさらに短いG3 SASとか言う、絶対にSASが使っていない架空銃は、
形状があまりにも現実離れしているんで我輩的には嫌いな銃なのですが、
「このサイズは使えそうだ!」と感じた突撃派な方なら買って後悔はしないはず。

因みにMC51の原点であるG3A3、G3A4、G3SG1に関しましては、
ロングサイズであるが故に剛性感に乏しく、本体が撓みやすいので、
(ハンドガードを握るとギシギシするのがしっかりと解るレベル)
命中精度もAK47に劣り、ゲームで使うと不安を感じるし、
何よりもブッシュに入ると邪魔で仕方がないという難点があります。
メタルフレームとか内部にぶち込むスリーブ等を手に入れることが
出来るのであれば購入してもいいのでしょうが箱出しでは不安がつきまといます。
(ていうかまだG3用のそういうパーツって出回っているのか、甚だ不明)
写真のブツはG3A3にPSG-1のハンドガードを取り付けて、
先端は社外品のHK51アウターバレルに換装、
リアサイトを撤去してファーストファクトリーのマウントベースを搭載、
チャンバーブロックを組み込んで剛性もある程度解消し、
ストックはA3のストックをパテ盛りでPSG-1のミリタリーモデルであるMSG-90風に改造したもの。
インナーバレルをPSG-1のものと交換したらパワーが70m/sぐらいに下がったので、
メカボックスのカスタムに相当手間を掛けた大変な一品でしたが、
命中精度がAK47に劣るというトンデモなやつでございました。
多分おそらく、コイツが一番金かけた電動ガンよ。
余談ですが我輩、大抵の電動ガンは手にしたと豪語しておりますが、
PSG-1だけは購入したことがありません。
PSG-1独特のピストンが後退した状態から発射されるという機構は
電動ガンの難点である発射タイムラグを縮める良いアイデアですが、
全体的な構成もG3譲りでガタが生じやすいので、
フレーム剛性は電動ガンの中でも激弱な部類、
だからバレルがしなって命中精度が低くなるという致命傷。
唯でさえ高額な本体価格なのにメタルフレーム化とか
ピストンやスプリング交換などメカボックス内を弄くり倒すとかすると
本体にかかる費用が原チャリ並みの価格に跳ね上がり、
それでもセミオートしか撃てないから我輩的に戦力的に難があるとみられる上に、
命中精度は他の電動ガンと大差ないというシロモノ、我輩はイラネ。

PSG-1買うぐらいならSG-1買う方が価格的にも性能的にもコスパが良いです。
G3A3やSG-1ならばフルオートも撃てるし、
ラージバッテリーが使えるので沢山弾が撃てるという利点はあるのですが、
スライドストックのA4の場合はミニバッテリーしか使えない上に
ストックは構えにくいので廃盤になったのもさもありなんです。
写真はMC51に飽きて「やっぱ漢(おとこ)は長い鉄砲だよな!」と思った矢先、
中古で転がっていたかなり状態のよろしいG3A3を見つけたんで
「コレ、我輩が買ってあげなかったらこのまま埃かぶるんだろうなー」と思って
捨て猫を拾うような気持ちで購入しちゃったものですが、
試射した後1回もサバゲーに投入することもなくヤフオクに流してしまった一品です。
正直、フルサイズのG3はドイツ軍コスプレする人以外にはオススメしませんですし、
マルイもそこら辺を察したのか、G3のバリエーションはSG1とMC51のみになりました。
でもやっぱ、我輩的にフレームがふにゃふにゃするSG-1は欲しくないですねぇ。
G3欲しい人は海外製を買うほうがよろしいかもしれません(無責任)。

実は我輩がAK47の次に購入したのがMP5K。
福岡のSWATで購入して、コイツを手荷物に入れた状態で宮崎行きの飛行機に乗ろうとしたら、
当然というか、案の定入り口で引っかかって止められたのは良い思ひ出w
写真は大分後に購入したストック付きのMP5K PDWです。
MP5ではありますがフルサイズのMP5とは設計が違うので
フレームは一体型で強度も確保されています。
分解はMP5A5と比べると構造がちょこちょこ違うんで比較的容易です。
欠点はバッテリーが入れにくい事ぐらいですかねぇ。
それぐらいしか思いつきませんがMP5A5程でもない。
強いてもう一つあげるならバレルが短すぎて命中精度が微妙なことと、
箱出しではパワーが少しひ弱であることぐらいでしょう。
でも一応、他の大きい電動ガンと同じぐらい弾は飛びますよ。
ストック無しのKと折りたたみストック付きのPDW、
どちらがオススメかと言われるとストックでしっかりサイティング出来るPDWなんですが、
ストックの分お値段が跳ね上がるので予算を抑えたいならKでもいいでしょう。
ただ、PDWはストックを折りたたむとダブルマガジンタイプの220連が使えません。
我輩はコイツを予備用の武器として常に持ち込んでいたのですが、
当時愛用していたAK47の信頼性が抜群すぎて殆ど出番なし。
でも軽い武器でフィールドを駆け巡りたいという人にはうってつけの武器です。
女性で真剣にサバゲーヤるって人ならこれ買うのが賢いでしょう。

弟ググレカスが先に買ったので買う気が失せていたのですが、
暫くしてからやっぱり欲しくなったのでFA-MAS買っちゃった若かりし頃。
初の電動ガンとしてデビューしたFA-MASは未だに生産されているのですが、
コイツの需要がフランス軍コスプレイヤー以外何処にあるのかさっぱり解かんねぇ。
しかし初めて世に送り出した電動ガンを未だにカタログに残しているという点は
東京マルイの電動ガンに対する一つの姿勢として評価しますね。
ただ、未だに残しているというのならとっととモーターをEG1000に交換しろと。
モーターがEG550であるとか、メカボに一部専用パーツがあるとか、
ボディがプラスチック多すぎて強度が微妙だとか、
マウントベースやスリングやマガジンが入手困難であるとか
色々難点はありますが基本性能は悪くありません。
重量は普通に重いですが使い難いレベルではありませんですし、
長さ的にも使い難いサイズではないと思います。
ラージバッテリーが使えるので沢山弾が撃てますしね。
ただやっぱり、セレクターが大分後ろにあるのは使い難いです。
余計なお世話かも知れませんがフロントサイトがブラブラするのは頂けない。
設計の古さ故か、分解するとなるとほぼ全バラシとなるのですが、
メインスプリングとバレルぐらいしか交換箇所がないのでソコまで致命的でもないか?
あと、我輩とググレカスのFA-MASは使っているうちに配線がヘタってしまい?
フル充電したバッテリーを繋いでも発射速度が遅いというトラブルがありました。
モーターに繋がる配線を交換すれば治ったのですが、
他で同じようなトラブルを聞いたこともないので詳細は不明です。
多分基本設計の何処かに不具合でもあるんじゃなかろうかと?
それとも、配線が長スギィ!なのがよろしくないんでしょうかね?
使っている人が少なく情報も少ないし、未知なトラブルが多く、
何よりもカスタムパーツが少ないということであまりオススメできる武器ではありませんが、
基本性能は悪くないブツであるとは思います。
ただ、メタルギアソリッド2のスネークの武器、何でFA-MASだったんかと?

以前ファントムステアーを改修した時に紹介したステアーAUGは
(我輩的には“シュタイア”という言い方が正しいと思うんだがまあいいや)
AK47、MC51に続いて我輩のツボにハマった電動ガンです。
ダイハードでテロリストの親分?が使っていたのがカッコよかった。
販売当初は細い2倍ぐらいのスコープが付属した“ミリタリー”というモデルと、
写真の任意で光学サイトを載っけられる“スペシャルレシーバー”があったんですが、
いつの間にかミリタリーの方はカタログ落ちしてしまいました。
ま、あのスコープ細すぎて覗きにくいんで不人気なのも仕方がない。
どーしてもあの細いスコープ萌えって人は
JGという中華メーカーが出しているからそれを買いなさい。
コイツは簡単に本体分割可能なので、持ち運びに便利。
バレルを短くしてみたり、長くしてみたりと楽しみ方も色々。
ただ、使いやすいかと言われると微妙というか、少々難アリ。
トリガーを軽く引くと単発、ぐっと奥まで引くと連発というシステムは、
とっさの攻撃時に弾が1発しか出ないという事態に陥ることも多々あり。
マガジンに癖があって給弾不良に陥るというのも頂けなかった。
バレル分解用のラッチレバーがいつの間にか紛失する事案もあり。
でも不具合はファントムステアーの記事に載せた解消法でどーにかなるから無問題。
逆に言うと吊るしでしか電動ガンを使えない人は買っちゃいけない電動ガン。
他にも本体後ろに重心が寄っているためか、重く感じるとか、
分解結合を繰り返すと結合部分がガタガタになるとか、
長銃身の割に命中精度はそれほどでもないとか、
70年代のライフルなのにフォアグリップがついている先見性はあるけど、
今の御時世の武器として見るとレールがないから難を感じるとか、
イマイチな部分が散見されることで定評のあるブルパップです。
外装のカスタムパーツも販売当初に比べると大分少ないのでカスタムするにも限界があるし、
海外製の同じブツにレール付きとかあるからソッチのほうが魅力的かもしれない。
メカボックスはAKと同じバージョン3だから機関部改修すれば性能アップは望めます。
最近(と言っても結構前だが)、ステアーのハイサイクルが販売されたんで、
AUGフィーバー再びか?と少し期待を抱いたりはしたんですが、
実はあのレールが付いた前回り、ぶつけると破損しやすいのでご注意。
欲しい人は買えばいいと思うし、それを止める権利は我輩にないけど、
欲しい程度の軽い気持ちでは使えないというか、いつかどーでも良くなるライフル、
それがステアーAUGというシロモノだと思うんですよ。

新作が出る度に電動ガンに手を出していると、
中には全く使わないまま手放してしまう機種も多々あります。
SIG 550は電動ガン初の3点バースト機能を備えた画期的?ライフルでしたが、
スイス軍の武器が手に入ってもソレに合う装備がないから購入意欲ゼロでした。
(その後ライバーマスターとかいう赤い迷彩服は流通するようになったが
ソレは550の前の世代の装備だったので購入せず)
でもSIG 551なら銃身も少し短くてとくしゅぶたい()も使っているという想定で
興味が湧いてきたのでとりあえず購入はしてみたんです。
任意で2点~7点に設定可能な3点バーストは89式と違い、電子制御式なのですが、
新品時は全く問題なく、設定通りの弾が発射されたので、
「うお、すげぇ」とか思いながら射撃してみたもんです。
でも永きに渡って使用すると基盤がイカれて上手くバーストしないらしいですがね。
セレクターやトリガーの位置も扱いやすく、グリップも握りやすいのも好評価。
多弾数マガジンが220連と中途半端ではありますがプラ製なので安く揃えることが出来、
マガジン同士で連結可能というオモシロ機能も備えておりますが、
マガジンを5個ぐらいバカみたく繋げてサバゲーしている輩なんて
弟のググレカスぐらいしか見たことがありません。
大抵のプレイヤーは2個セットぐらいで運用していましたね。
フロントヘビーなので構えると少し銃身が下る嫌いはあるのですが、
全体的に構えやすいので特に問題は感じませんでした。
しかし最大の欠点は折りたたみストックの強度不足。
我輩の1番弟子、ポチョムキン氏の初サバゲーの時に、
ホイホイ貸してあげたら豪快にずっこけてストックボキッ!
それ以来、我輩はこの銃を2度と買わないことを誓いました。
勿論、SIG 552がデビューした時も完全ガン無視でした。
長期間保有していなかったのでバースト機能がどれぐらいでダメになるのかとか、
外装部分にどれだけ不具合が出るのかとかは全く未知の世界です。
まあ購入時にそれなりの剛性感だったんで、あまり強度ないんだろうな。
ぶっちゃけ、好きでもない限りオススメはしない銃ですね。

FN P90はマルイよりも先にトイテックというメーカーが出していたんですが、
アレはメカボが独特で作動音も何時かぶっ壊れそうなブツだったし、
何よりもドットサイトがバッテリーという謎仕様だから購入意欲湧きませんでした。
でも天下のマルイ様がP90出すとなると、
見逃すわけには逝きませんでしたね。
それに何より、こういうデザインの武器は好き嫌いが分かれそうですが我輩は好き。
この銃を選ぶ利点は今でも多数あると思います。
まずハンドリングしやすいボディデザイン。
一見取っ付きにくそうですが構えてみると身体と一体化する感じでよく馴染む。
身体の内側に銃本体が収まるので周囲にぶつける心配も少ない。
重量バランスも良く、なおかつ本体が軽いという素晴らしさ。
トリガーの下にあるセレクターは人差し指で用意に切替可能、
フルオート固定にして指切りセミオートも容易いトリガープルは絶品。
バッテリーはストックの蓋をずらせばすぐに交換可能。
ストックの蓋は脱落防止が施されているので安心。
ノーマルタイプ(現在絶版)はドットサイトが小さくて狙いにくかったんですが、
現在でも販売中のTRは好みの光学サイトを取付可能で便利。
でもあまり大きめのものを乗せると重量増加して使いにくいという。
TRに付属しているサイレンサーは使っているうちに
内部のスポンジが崩れてきて弾道を乱すので出来れば社外品に換えるか、
我輩みたいに「あんなもの飾りです」と思ってヤフオクに出すのが良いでしょう。
余談ですがノーマルタイプのドットはレンズがプラなので、
被弾すると簡単にぶっ壊れますていうか、3人ぐらい割れたの見たことある。
エチゴヤのサバゲーでレンズ割れたのを目の当たりにして、
ゲームの帰りにエチゴヤでレンズの前に取り付ける強化シールド買いましたからね。
難点は特殊過ぎる形状のマガジンですかね?
マガジン交換に関しては案外、慣れると素早く出来るんですよ。
問題は多弾マガジンの弾上がりが悪く、対策を施さないと使えないこと。
詳しくは「P90マガジン 対策」でググれば出てくるはずです。
更に問題なのはマガジンポーチの選択肢が少ないこと。
Akのマグポーチよりも種類は少ないです。
我輩はTMCのP90用マガジンポーチを使っておりました。
(余談だがそのマガジンポーチは現在グリースガン用に使っている)
脱落する部品が極めて少ないこと、コンパクトで使いやすいこと、
そして何よりマガジン紛失の心配が皆無であるということから、
夜戦用の武器として長年愛用しておりましたが
青森に引っ越したら夜戦の機会が少なくなったので売却。
でも数年前、P90のマガジンが使えるM4、
SR57とか言う変態銃が出たときに「あーやっぱ、P90持っとけばよかった」と
謎の感情が湧いてきたんで今でも少々未練があるぐらい好きだった電動ガン。
さて、ここまで散々グダって役に立たない話をしてきましたが、
実はまだまだ話は続くんで暇な方は次回までお付き合いくだされ。
2018年04月13日
ブローニングは永久に不滅?
前々回の予告通り、我輩の武器庫に新しく仲間入りした銃器の紹介です。
ところで最近サバゲーの過去記事を見ていたら、コイツが販売された頃、
「次はコレを買うぞ!」って心意気を何回か記事に残しているんですね我輩。
という事はコレを手に入れてしまったというこの流れ、ある意味運命だったのかもしれない。

同志たちよ、BAR M1918というライフルをご存知かな?
ウィンチェスターM1887やガバメントやM2重機関銃等の
多数のベストセラー銃器を開発した銃器界の巨匠にして鬼才、
ジョン・モーゼス・ブローニングが第一次世界大戦の最中に生み出したライフルです。
ていうかこの人が現在の銃器の大半の機構を開発したと行っても過言ではないという。
フルオートで弾を撃ち出せる武器が据え付け式の機関銃ぐらいしか無かった時代に、
持ち運び式のフルオートライフルを作ったブローニング恐るべし。
なお、BARはブローニング・オートマチック・ライフルの略で、
「バー」と読むのではなく「ビーエーアール」と読みます。
最近「アローダイナミックのBARが気になる」とブログに書いたところ、
その記事を見た同志ピーマン職人が「シュババババ!」と速攻で
「オレBAR要らないんで、買います?」とLINEしてきたんですね。
我輩も何度か欲しいと言いはしたものの、手持ちの軍事費も乏しい上に、
どーしても欲しいというわけではなかったんで、
「ま、とりあえず現物見てから考えますわ」とお茶を濁していたんですが、
とある日の吉六会の夜会の時にピーマン職人がBARを持参してくれた挙げ句、
「金は後でいいから、そのそびえ立つクソを持って帰ってくれ!」と吐き捨てるように告げ、
我輩の意思と物欲を完全に無視した状態でBARが手元に来てしまったのです。
ま、要するに使いものにならないので引き取れって事だったんですね。
あと、デカスギィで置き場に困っていたというのもあるのかもしれませんが。
まあそう言う経緯がありまして、我輩はBARを手にしてしまったのです。

アローダイナミックのBARは米軍最終型の
1918A2と呼ばれるものを電動ガンでモデルアップしたもので、
以前VFCが販売していたモデルの廉価版的なブツです。
新品価格は大体38000円ぐらいの模様ですが、大半の店では取り扱いなし。
フォースター系列ぐらいしか置いていないみたいですね。
追記:2019年に入ってS&TがBARの電動ガンを販売するようになった模様。
尚、外見も中身も全く同等のブツみたいです。
全長は120cm強、M14よりも若干長いです。そして何度も言うけど重い(6kg)。
まあコイツは今で言うM60やM240みたいな位置付けの武器なんで重いのは仕方がない。
ていうかコイツの実銃がデビューした当時、フルオート撃てる武器はどれもクソ重いのが普通で、
10kgを切る重量(約9kg)だったBARは比較的軽い部類だったそうな。
実銃の口径は7.62mmですが大半のサバゲーやってる連中が知っていると思われる
薬莢長が51mmの308ではなく63mmの30-06と呼ばれるやつです。
(ブローニングM1919やスプリングフィールドM1903、M1ガーランドと同じ弾薬)
BARは第一次世界大戦~ベトナム戦争初期の米軍の武器ですが、
自衛隊でも米軍のお下がりを「30口径自動銃」という名称で使っていましたし、
(10年ぐらい前までは航空自衛隊の基地の武器庫の片隅にあったそうな)
南ベトナム軍やベトコンも使っていたので汎用度はそこそこあるようです。
外観の特徴はクソ長いバレル、銃口付近にそびえるバイポッド、
そしてピストルグリップのないクラシカルな形状。
現代の銃器のような人に優しい設計とは程遠いシロモノですが
我輩的にはこの古臭い外観がたまらない。
でもやっぱ、構えにくいし撃ちにくい。
使われている素材は大半がダイキャスト。
鉄はバイポッドとショルダーレストとマガジンぐらい。
そしてストックやハンドガードは樹脂製です(オプションで木製ストック有り)。

そこそこのお値段の中華電動ガンの例に漏れず、
アローダイナミックBARも塗装や全体の仕上がりはかなり適当です。
フラッシュハイダーやフロントサイトの塗装は
分厚くもったりしていてシャープさに欠けます。
バイポッドは鉄製ですが、錆びてます。
多分新品当時からこんなもんだったんじゃないかな?
余談ですがこのバイポッドだけで1kgぐらいあります。

バイポッドを展開するには根元の蝶ネジを緩める必要があるのが
BARが古い時代のライフルである証です。
スプリングでロックがかかるなんて親切設計、何処にもありません。
バイポッドは写真のように伸ばして使う事も可能ですが、
戦場でいちいち蝶ネジ緩めて伸ばしてまた締めるなんて愚の骨頂ですし、
我輩的には足なんて「あんなもの飾りです」なので
実際の戦場でそう使われていたようにバイポッドは取り外します。

スリットがないハイダーって、実際効果があるのかなぁ?
ていうかこのハイダー、パーティングラインが残ってるのが気になる。
でも塗装が結構分厚いのでサンドペーパーがけするの面倒くさそう。
バイポッドを外すのは逆ネジでねじ込まれているハイダーを外せば外れます。
ハイダーの根元は14mmなので大抵のハイダーが取付可能です。

先程も言いましたが、各部の仕上げがよろしくないのが中華クオリティ。
前方のスリングスイベルがガタガタでみっともないという始末です。
ネジは締まっているけど、何か斜めっている。
取り外してプライヤーと格闘して少しマシな角度に修正。

実銃では木製のハンドガードは樹脂で出来ています。
しかもこの樹脂ハンドガード、厚みがなくてペコぺコしているしモナカ構造。
木目調の仕上がりもコレまた微妙というか、所詮プラ。
木製ストックに買い替えたいけどそれを買う前に
ピーマン職人に払う本体の金を捻出しなければ・・・
キャリングハンドルも樹脂製ですが、バレル取付部は鉄製。
ただこのキャリングハンドル、ガッチリ締め付けると完全に固定されるし、
可動する程度に緩めても綺麗にスイングしない。
この角度で完全に固定してしまったほうがよろしいのかな?
ところでBARのキャリングハンドルって第二次世界大戦末期に採用されたらしいですね。
だから二次大戦装備でキャリハン付いているのは少々オカシイとの事。
でもBARって重たいからキャリハンで持ち運ぶ方が楽なんですよ。
我輩は自衛隊装備或いはベトコン装備で使うんでキャリハンは付ける方向で。

メインフレームは比較的綺麗な仕上がりです。
サイドに出っ張っているチャージングハンドルは
弾倉取り付けていないと動かしてはいけないとのこと。
(理由は後程説明します)
セレクターのポジションはセイフティの他に2箇所ありますが、
AもFもフルオートポジションなのでセミオートでは撃てません。
(実銃ではココで発射速度がHIGHとLOWに切り替えられるようになっている)
クリックは結構ヌルっとしていて、緩いです。しかもセレクターぐるっと一回転するし抜けそうになるし。
その上、左に付いているのに手を持ち替えないと動かしにくいという不親切設計。
ま、この銃は今から100年ぐらい前の設計の銃、使い勝手を求めるものではありません。
そもそもこの銃が生まれた時代はフルオートで撃てるライフル自体が貴重な存在。
トリガーガード内前方に出っ張っているのはマガジンキャッチ。
強く押すと「ポコン!」と勢いよくマガジンが落っこちます。

樹脂製のストックはハンドガード同様肉厚が薄くペコペコしています。
本体への取り付けはしっかりしているようですが、少し頼りない。
バットプレートに64式やM14みたいなショルダーレストが付いているのが特徴。
ていうか64式やM14がBARを真似したというのが正しい。
BAR M1918A2ではストックが多少はスリムな樹脂製なので、
どーせならそれを再現すればよかったのになぁと思うんです。

ところでこのストックの後方スリングスイベルの側にある穴、何だと思います?
実はココにモノポッドを取り付けるようになっているんですね。
でも実際は手持ちで使われることが多かったので、使用例は少ない模様。

バッテリーはバットプレートを固定するネジを2本緩め、ストック内に収納します。
コネクタはミニサイズですがラージもウナギも大半のバッテリーは収納可能です。
但し、デフォルトではミニバッテリーでの運用を考えているらしく、
バッテリーを固定するためのスポンジが入っております。

フレームの反対側はエジェクションポートがあるだけ。
そしてこのエジェクションポートのカバーがまた、頼りない。
薄っぺらい金属板が被さっているだけという体たらくです。
余談ですが実銃のBARの発射機構はオープンボルトです。

チャージングハンドルを引くとホップ調整レバーが現れます。
前に押したら緩み、後ろに引くとテンションが強くなります。
そしてこの調整レバーがまた、動きが渋くて調整しにくいんだな。

リアサイトは立てなくても使えんことはないですが、
切り込みが小さくて狙いにくいので狙う時は立てた方が無難。
しかしテンションを掛けている板バネが弱く、すぐに倒れそうでプラプラします。
上下の調整はサイトの上のダイヤルを回し、
左右の調整は右側のダイヤルを回します。

マガジンはデフォルトでは190連。お値段は大体2500~4000円。
M14やG3並みにデカいマガジンなのにM4のショートマガジン程度の弾数。
それもそのはず、中に入っているマガジンがコレ、
マルイM16ベトナムに付属している190連マガジンの中身のコピーだもんwww。
しかもピーマン職人から渡されたブツはマガジンがぶっ壊れているという有様。

幸い、我輩の手元にM4ショート多弾数マガジンがあったので、
中身を移植することにしましたがそのままでは入らないのね。
写真のようにマガジン先端部分を削る必要があります。
話によるとこのマガジン、ハナっからクオリティ的に難ありなシロモノなので、
最終的にはマルイのマガジンをブチ込むハメになることでしょう。

さて、そのままM4ショートマガジンの具をブチ込んでも装弾数は190発のまま。
そんなんじゃ使いものにならないのでもう少し弾数を増やすべく、
マガジン後部のデッドスペースを活用するために
2cm✕2cmぐらいのプラ板を写真のように貼り付けてみました。
この加工により装弾数が240発に増えましたが、まだ足りねぇなぁ。
いっその事M14のマガジンを加工してブチ込んだ方がいいのかもしれませんが、
それをするとマガジンに対して余計な銭がかかるという難点。

アローダイナミックのBARはマガジン装填していない状態では
チャージングハンドルを動かしてはいけないという話でしたが、
その理由がチャージングハンドルのリターンスプリングが
マガジンハウジング内に飛び出してくるのと、
エジェクションポートのカバーを動かすアクションレバーが曲がるからなんですね。
こうなってしまうとマガジンが突っ込めなくなるので、使い物になりません。
(ドライバーとか突っ込んでガチャガチャすればどーにかならん事もない)

というわけでアローダイナミックのBAR、
気になるところを改善するために分解してみます。
まずはキャリングハンドルの取り外し。
ハンドルの握り部分にあるマイナスネジを外し、ハンドルを引っこ抜くと、
アウターバレルに固定されている部分が二分割で外せるようになります。

キャリングハンドルを外したらハンドガード付けに付近にある
レバーを180度回転させて引っこ抜きましょう。

レバーはハンドガード&ガスバイパス部分の固定ピンになっているので、
コイツを抜けば下回りが外せるようになります。


でもチャージングハンドルのアクションレバーやスプリングが外れないので、
チャージングハンドル側のアクションレバーを固定しているネジを外します。
(もう片方のアクションレバーのネジは分解しなくてもいい)
これで前の下回りが完全に分解できるようになります。

後ろ周りを分解するにはチャージングハンドル下部にある
分解ラッチを90度回してピンを引っこ抜きます。

ストックを下に向けながら引きずり出せばメカボックスとストック部分が外せます。
メカボックスだけ手を付けたい場合はココだけ外せばいいので、
整備性という点に置いてはなかなか優秀なやつです、BAR。

メカボックスを抜くとエジェクションポートのカバーが残っているので、
コイツも摘んで外に出してしまいましょう。
カバー自体はアクションレバーの切欠きと噛み合って
連動して動くだけなので完全フリー状態です。

アクションレバーが外れてしまったチャージングハンドルは
フリー状態になってしまうので勝手に外れます。

アウターバレルとチャンバーを外すためにはこの5本のネジを緩めます。

アウターバレルを前方に引っ張り出して外してしまえば
インナーバレルとチャンバーが取り外せるようになります。

チャンバーはAKのものと似ていますが、ホップ調整レバーの形状が違います。
そしてマガジンへの給弾部分が追加されて伸ばされているという。
ていうかこの赤いチャンバー、何で中途半端に黒塗りされてんのか不明だし汚い。
(追記:前オーナーのピーマン職人がココだけ赤いのが気に入らず塗装したとのこと)
インナーバレルは500mmぐらいの長さなので、ステアーAUGと同じぐらいです。
チャンバーパッキンは多分、ピーマン職人のことだから既に交換済みであろう。
中華電動ガンを分解したらまず、チャンバーパッキンは交換必須ですからね。

チャージングハンドルのリターンスプリングはデフォルトでこのような状態です。
コイツ、何で固定するものがない状態でブラブラしとるんじゃ?

リターンスプリングがブラブラしているのが腹立たしいので、
スプリングとガイドを固定するステイを取り付けることにします。
ホムセンで買ってきた幅10mmぐらい、高さ15mmぐらいのL字型の固定金具をネジ止めします。
この加工により、リターンスプリングがマガジンハウジング内に飛び出さなくなりました。
つまり、マガジン突っ込まなくてもチャージングハンドルが引ける。

ハンドガードやストックは質感がわざとらしくて気に入らないので塗り直します。
サイドの固定ネジを緩めればハンドガードは分解可能です。

ストックは油性ニススプレーをぶっかけて
使い込んだ木製ストックっぽく仕上げてみました。
遠目で見ればプラストックよりはま、多少はね、マシな感じでしょう。

おっと、ストックの取り外しの説明を失念しておりました。
ストックはメカボックス部分のステイに固定されているので、
後ろの2本、反対側と合わせて4本を緩めれば取り外せます。
メカボックスにアクセスするにはロアフレームを固定しているネジを緩めればおk。
メカボックスはM14に似ていますが、モーターの取り付け角度が違います。

アローダイナミック製BARのメカボックスは
メインスプリングだけ単体で取り外し可能です。
スプリングを抜くにはメカボックス上部のピンを抜けば取り外せます。
メカボックスの方は既にピーマン職人が手を付けていたので、
残念ながら分解の写真はありません。
内部パーツはスプリング以外交換していないようですが、
メカボックスとギア洗浄、シム調整を施したとのこと。
そしてスイッチ直押しなのでFET増設。
やはり中華電動ガンのメカボはそのまま使うには難ありなようです。

昔新田原基地の航空祭で見たBARには64式のようなスリングが付けられていたので、
がらくた箱の中にあったKMの古めかしいスリングを取り付けました。
クソ重たいバイポッドは取り外し、キャリングハンドルはこの位置で固定。
7.4V 2250mAのリポバッテリーを接続しての発射速度は
ノーマル旧世代電動ガンより多少遅い感じですが、
初速は80m/s台を叩き出しているしホップもまともで精度もまあまあ。
弾が出る程度の性能は確保されているようなのでサバゲーで使えんことはないでしょう。
とはいえどもやはり近代的なライフルと比べると使い勝手に劣り、
重量的にもサバゲーで使うには少々重すぎるし、長すぎて取り回しが良くない。
装弾数的にもM4に劣るので火力勝負も厳しいところ。
好きでもなければ積極的に選ぶ必然性のない武器である事実は否めません。
正直、ヒストリカルサバゲー以外では出番のない武器です。
でもね、サバゲーに逝くと何処のフィールドでもM4系列しか見かけない。
勝ちに行くこと考えて使いやすい武器しか選ばないっていうの、つまんないと思う。
どーせならこういうバカみたいな武器使って勝ちを目指した方が面白い。
大人のサバゲーってそういう楽しみ方だと思うんです。
ところで、この手のクラシックな銃器を色々弄り回しているとね、
近代的な改修を施して面白くしてみたいって考えちゃうんです。
以前作ったPPSh41の近代化ヴァージョンみたいにね。

んで、BARについて調べてみたら既にコイツを近代化している銃があるんですわ。
HCAR(Heavy Counter Assault Rifle)というヤツ。
SCAR-Hがオモチャに見えてしまう存在感ですな。
格子模様のフレームやディンブルの入ったバレルの再現は厳しいにしても、
ハンドガードやストックをそれっぽくしてみたり、
マウントやグリップを増設するのは出来ないことはない。
M14EBRとキャラが被るけど、趣味人としてはチャレンジしてみたい一品です。
木製ストックが入手出来なかったらチャレンジしてみようかな?
100年近く経った今でも近代改修型が作られて愛されているというBAR、
やはりジョン・ブローニングは偉大であり、不滅の存在なんですね(小並感)。
ところで最近サバゲーの過去記事を見ていたら、コイツが販売された頃、
「次はコレを買うぞ!」って心意気を何回か記事に残しているんですね我輩。
という事はコレを手に入れてしまったというこの流れ、ある意味運命だったのかもしれない。

同志たちよ、BAR M1918というライフルをご存知かな?
ウィンチェスターM1887やガバメントやM2重機関銃等の
多数のベストセラー銃器を開発した銃器界の巨匠にして鬼才、
ジョン・モーゼス・ブローニングが第一次世界大戦の最中に生み出したライフルです。
ていうかこの人が現在の銃器の大半の機構を開発したと行っても過言ではないという。
フルオートで弾を撃ち出せる武器が据え付け式の機関銃ぐらいしか無かった時代に、
持ち運び式のフルオートライフルを作ったブローニング恐るべし。
なお、BARはブローニング・オートマチック・ライフルの略で、
「バー」と読むのではなく「ビーエーアール」と読みます。
最近「アローダイナミックのBARが気になる」とブログに書いたところ、
その記事を見た同志ピーマン職人が「シュババババ!」と速攻で
「オレBAR要らないんで、買います?」とLINEしてきたんですね。
我輩も何度か欲しいと言いはしたものの、手持ちの軍事費も乏しい上に、
どーしても欲しいというわけではなかったんで、
「ま、とりあえず現物見てから考えますわ」とお茶を濁していたんですが、
とある日の吉六会の夜会の時にピーマン職人がBARを持参してくれた挙げ句、
「金は後でいいから、そのそびえ立つクソを持って帰ってくれ!」と吐き捨てるように告げ、
我輩の意思と物欲を完全に無視した状態でBARが手元に来てしまったのです。
ま、要するに使いものにならないので引き取れって事だったんですね。
あと、デカスギィで置き場に困っていたというのもあるのかもしれませんが。
まあそう言う経緯がありまして、我輩はBARを手にしてしまったのです。

アローダイナミックのBARは米軍最終型の
1918A2と呼ばれるものを電動ガンでモデルアップしたもので、
以前VFCが販売していたモデルの廉価版的なブツです。
新品価格は大体38000円ぐらいの模様ですが、大半の店では取り扱いなし。
フォースター系列ぐらいしか置いていないみたいですね。
追記:2019年に入ってS&TがBARの電動ガンを販売するようになった模様。
尚、外見も中身も全く同等のブツみたいです。
全長は120cm強、M14よりも若干長いです。そして何度も言うけど重い(6kg)。
まあコイツは今で言うM60やM240みたいな位置付けの武器なんで重いのは仕方がない。
ていうかコイツの実銃がデビューした当時、フルオート撃てる武器はどれもクソ重いのが普通で、
10kgを切る重量(約9kg)だったBARは比較的軽い部類だったそうな。
実銃の口径は7.62mmですが大半のサバゲーやってる連中が知っていると思われる
薬莢長が51mmの308ではなく63mmの30-06と呼ばれるやつです。
(ブローニングM1919やスプリングフィールドM1903、M1ガーランドと同じ弾薬)
BARは第一次世界大戦~ベトナム戦争初期の米軍の武器ですが、
自衛隊でも米軍のお下がりを「30口径自動銃」という名称で使っていましたし、
(10年ぐらい前までは航空自衛隊の基地の武器庫の片隅にあったそうな)
南ベトナム軍やベトコンも使っていたので汎用度はそこそこあるようです。
外観の特徴はクソ長いバレル、銃口付近にそびえるバイポッド、
そしてピストルグリップのないクラシカルな形状。
現代の銃器のような人に優しい設計とは程遠いシロモノですが
我輩的にはこの古臭い外観がたまらない。
でもやっぱ、構えにくいし撃ちにくい。
使われている素材は大半がダイキャスト。
鉄はバイポッドとショルダーレストとマガジンぐらい。
そしてストックやハンドガードは樹脂製です(オプションで木製ストック有り)。

そこそこのお値段の中華電動ガンの例に漏れず、
アローダイナミックBARも塗装や全体の仕上がりはかなり適当です。
フラッシュハイダーやフロントサイトの塗装は
分厚くもったりしていてシャープさに欠けます。
バイポッドは鉄製ですが、錆びてます。
多分新品当時からこんなもんだったんじゃないかな?
余談ですがこのバイポッドだけで1kgぐらいあります。

バイポッドを展開するには根元の蝶ネジを緩める必要があるのが
BARが古い時代のライフルである証です。
スプリングでロックがかかるなんて親切設計、何処にもありません。
バイポッドは写真のように伸ばして使う事も可能ですが、
戦場でいちいち蝶ネジ緩めて伸ばしてまた締めるなんて愚の骨頂ですし、
我輩的には足なんて「あんなもの飾りです」なので
実際の戦場でそう使われていたようにバイポッドは取り外します。

スリットがないハイダーって、実際効果があるのかなぁ?
ていうかこのハイダー、パーティングラインが残ってるのが気になる。
でも塗装が結構分厚いのでサンドペーパーがけするの面倒くさそう。
バイポッドを外すのは逆ネジでねじ込まれているハイダーを外せば外れます。
ハイダーの根元は14mmなので大抵のハイダーが取付可能です。

先程も言いましたが、各部の仕上げがよろしくないのが中華クオリティ。
前方のスリングスイベルがガタガタでみっともないという始末です。
ネジは締まっているけど、何か斜めっている。
取り外してプライヤーと格闘して少しマシな角度に修正。

実銃では木製のハンドガードは樹脂で出来ています。
しかもこの樹脂ハンドガード、厚みがなくてペコぺコしているしモナカ構造。
木目調の仕上がりもコレまた微妙というか、所詮プラ。
木製ストックに買い替えたいけどそれを買う前に
ピーマン職人に払う本体の金を捻出しなければ・・・
キャリングハンドルも樹脂製ですが、バレル取付部は鉄製。
ただこのキャリングハンドル、ガッチリ締め付けると完全に固定されるし、
可動する程度に緩めても綺麗にスイングしない。
この角度で完全に固定してしまったほうがよろしいのかな?
ところでBARのキャリングハンドルって第二次世界大戦末期に採用されたらしいですね。
だから二次大戦装備でキャリハン付いているのは少々オカシイとの事。
でもBARって重たいからキャリハンで持ち運ぶ方が楽なんですよ。
我輩は自衛隊装備或いはベトコン装備で使うんでキャリハンは付ける方向で。

メインフレームは比較的綺麗な仕上がりです。
サイドに出っ張っているチャージングハンドルは
弾倉取り付けていないと動かしてはいけないとのこと。
(理由は後程説明します)
セレクターのポジションはセイフティの他に2箇所ありますが、
AもFもフルオートポジションなのでセミオートでは撃てません。
(実銃ではココで発射速度がHIGHとLOWに切り替えられるようになっている)
クリックは結構ヌルっとしていて、緩いです。しかもセレクターぐるっと一回転するし抜けそうになるし。
その上、左に付いているのに手を持ち替えないと動かしにくいという不親切設計。
ま、この銃は今から100年ぐらい前の設計の銃、使い勝手を求めるものではありません。
そもそもこの銃が生まれた時代はフルオートで撃てるライフル自体が貴重な存在。
トリガーガード内前方に出っ張っているのはマガジンキャッチ。
強く押すと「ポコン!」と勢いよくマガジンが落っこちます。

樹脂製のストックはハンドガード同様肉厚が薄くペコペコしています。
本体への取り付けはしっかりしているようですが、少し頼りない。
バットプレートに64式やM14みたいなショルダーレストが付いているのが特徴。
ていうか64式やM14がBARを真似したというのが正しい。
BAR M1918A2ではストックが多少はスリムな樹脂製なので、
どーせならそれを再現すればよかったのになぁと思うんです。

ところでこのストックの後方スリングスイベルの側にある穴、何だと思います?
実はココにモノポッドを取り付けるようになっているんですね。
でも実際は手持ちで使われることが多かったので、使用例は少ない模様。

バッテリーはバットプレートを固定するネジを2本緩め、ストック内に収納します。
コネクタはミニサイズですがラージもウナギも大半のバッテリーは収納可能です。
但し、デフォルトではミニバッテリーでの運用を考えているらしく、
バッテリーを固定するためのスポンジが入っております。

フレームの反対側はエジェクションポートがあるだけ。
そしてこのエジェクションポートのカバーがまた、頼りない。
薄っぺらい金属板が被さっているだけという体たらくです。
余談ですが実銃のBARの発射機構はオープンボルトです。

チャージングハンドルを引くとホップ調整レバーが現れます。
前に押したら緩み、後ろに引くとテンションが強くなります。
そしてこの調整レバーがまた、動きが渋くて調整しにくいんだな。

リアサイトは立てなくても使えんことはないですが、
切り込みが小さくて狙いにくいので狙う時は立てた方が無難。
しかしテンションを掛けている板バネが弱く、すぐに倒れそうでプラプラします。
上下の調整はサイトの上のダイヤルを回し、
左右の調整は右側のダイヤルを回します。

マガジンはデフォルトでは190連。お値段は大体2500~4000円。
M14やG3並みにデカいマガジンなのにM4のショートマガジン程度の弾数。
それもそのはず、中に入っているマガジンがコレ、
マルイM16ベトナムに付属している190連マガジンの中身のコピーだもんwww。
しかもピーマン職人から渡されたブツはマガジンがぶっ壊れているという有様。

幸い、我輩の手元にM4ショート多弾数マガジンがあったので、
中身を移植することにしましたがそのままでは入らないのね。
写真のようにマガジン先端部分を削る必要があります。
話によるとこのマガジン、ハナっからクオリティ的に難ありなシロモノなので、
最終的にはマルイのマガジンをブチ込むハメになることでしょう。

さて、そのままM4ショートマガジンの具をブチ込んでも装弾数は190発のまま。
そんなんじゃ使いものにならないのでもう少し弾数を増やすべく、
マガジン後部のデッドスペースを活用するために
2cm✕2cmぐらいのプラ板を写真のように貼り付けてみました。
この加工により装弾数が240発に増えましたが、まだ足りねぇなぁ。
いっその事M14のマガジンを加工してブチ込んだ方がいいのかもしれませんが、
それをするとマガジンに対して余計な銭がかかるという難点。

アローダイナミックのBARはマガジン装填していない状態では
チャージングハンドルを動かしてはいけないという話でしたが、
その理由がチャージングハンドルのリターンスプリングが
マガジンハウジング内に飛び出してくるのと、
エジェクションポートのカバーを動かすアクションレバーが曲がるからなんですね。
こうなってしまうとマガジンが突っ込めなくなるので、使い物になりません。
(ドライバーとか突っ込んでガチャガチャすればどーにかならん事もない)

というわけでアローダイナミックのBAR、
気になるところを改善するために分解してみます。
まずはキャリングハンドルの取り外し。
ハンドルの握り部分にあるマイナスネジを外し、ハンドルを引っこ抜くと、
アウターバレルに固定されている部分が二分割で外せるようになります。

キャリングハンドルを外したらハンドガード付けに付近にある
レバーを180度回転させて引っこ抜きましょう。

レバーはハンドガード&ガスバイパス部分の固定ピンになっているので、
コイツを抜けば下回りが外せるようになります。


でもチャージングハンドルのアクションレバーやスプリングが外れないので、
チャージングハンドル側のアクションレバーを固定しているネジを外します。
(もう片方のアクションレバーのネジは分解しなくてもいい)
これで前の下回りが完全に分解できるようになります。

後ろ周りを分解するにはチャージングハンドル下部にある
分解ラッチを90度回してピンを引っこ抜きます。

ストックを下に向けながら引きずり出せばメカボックスとストック部分が外せます。
メカボックスだけ手を付けたい場合はココだけ外せばいいので、
整備性という点に置いてはなかなか優秀なやつです、BAR。

メカボックスを抜くとエジェクションポートのカバーが残っているので、
コイツも摘んで外に出してしまいましょう。
カバー自体はアクションレバーの切欠きと噛み合って
連動して動くだけなので完全フリー状態です。

アクションレバーが外れてしまったチャージングハンドルは
フリー状態になってしまうので勝手に外れます。

アウターバレルとチャンバーを外すためにはこの5本のネジを緩めます。

アウターバレルを前方に引っ張り出して外してしまえば
インナーバレルとチャンバーが取り外せるようになります。

チャンバーはAKのものと似ていますが、ホップ調整レバーの形状が違います。
そしてマガジンへの給弾部分が追加されて伸ばされているという。
ていうかこの赤いチャンバー、何で中途半端に黒塗りされてんのか不明だし汚い。
(追記:前オーナーのピーマン職人がココだけ赤いのが気に入らず塗装したとのこと)
インナーバレルは500mmぐらいの長さなので、ステアーAUGと同じぐらいです。
チャンバーパッキンは多分、ピーマン職人のことだから既に交換済みであろう。
中華電動ガンを分解したらまず、チャンバーパッキンは交換必須ですからね。

チャージングハンドルのリターンスプリングはデフォルトでこのような状態です。
コイツ、何で固定するものがない状態でブラブラしとるんじゃ?

リターンスプリングがブラブラしているのが腹立たしいので、
スプリングとガイドを固定するステイを取り付けることにします。
ホムセンで買ってきた幅10mmぐらい、高さ15mmぐらいのL字型の固定金具をネジ止めします。
この加工により、リターンスプリングがマガジンハウジング内に飛び出さなくなりました。
つまり、マガジン突っ込まなくてもチャージングハンドルが引ける。

ハンドガードやストックは質感がわざとらしくて気に入らないので塗り直します。
サイドの固定ネジを緩めればハンドガードは分解可能です。

ストックは油性ニススプレーをぶっかけて
使い込んだ木製ストックっぽく仕上げてみました。
遠目で見ればプラストックよりはま、多少はね、マシな感じでしょう。

おっと、ストックの取り外しの説明を失念しておりました。
ストックはメカボックス部分のステイに固定されているので、
後ろの2本、反対側と合わせて4本を緩めれば取り外せます。
メカボックスにアクセスするにはロアフレームを固定しているネジを緩めればおk。
メカボックスはM14に似ていますが、モーターの取り付け角度が違います。

アローダイナミック製BARのメカボックスは
メインスプリングだけ単体で取り外し可能です。
スプリングを抜くにはメカボックス上部のピンを抜けば取り外せます。
メカボックスの方は既にピーマン職人が手を付けていたので、
残念ながら分解の写真はありません。
内部パーツはスプリング以外交換していないようですが、
メカボックスとギア洗浄、シム調整を施したとのこと。
そしてスイッチ直押しなのでFET増設。
やはり中華電動ガンのメカボはそのまま使うには難ありなようです。

昔新田原基地の航空祭で見たBARには64式のようなスリングが付けられていたので、
がらくた箱の中にあったKMの古めかしいスリングを取り付けました。
クソ重たいバイポッドは取り外し、キャリングハンドルはこの位置で固定。
7.4V 2250mAのリポバッテリーを接続しての発射速度は
ノーマル旧世代電動ガンより多少遅い感じですが、
初速は80m/s台を叩き出しているしホップもまともで精度もまあまあ。
弾が出る程度の性能は確保されているようなのでサバゲーで使えんことはないでしょう。
とはいえどもやはり近代的なライフルと比べると使い勝手に劣り、
重量的にもサバゲーで使うには少々重すぎるし、長すぎて取り回しが良くない。
装弾数的にもM4に劣るので火力勝負も厳しいところ。
好きでもなければ積極的に選ぶ必然性のない武器である事実は否めません。
正直、ヒストリカルサバゲー以外では出番のない武器です。
でもね、サバゲーに逝くと何処のフィールドでもM4系列しか見かけない。
勝ちに行くこと考えて使いやすい武器しか選ばないっていうの、つまんないと思う。
どーせならこういうバカみたいな武器使って勝ちを目指した方が面白い。
大人のサバゲーってそういう楽しみ方だと思うんです。
ところで、この手のクラシックな銃器を色々弄り回しているとね、
近代的な改修を施して面白くしてみたいって考えちゃうんです。
以前作ったPPSh41の近代化ヴァージョンみたいにね。

んで、BARについて調べてみたら既にコイツを近代化している銃があるんですわ。
HCAR(Heavy Counter Assault Rifle)というヤツ。
SCAR-Hがオモチャに見えてしまう存在感ですな。
格子模様のフレームやディンブルの入ったバレルの再現は厳しいにしても、
ハンドガードやストックをそれっぽくしてみたり、
マウントやグリップを増設するのは出来ないことはない。
M14EBRとキャラが被るけど、趣味人としてはチャレンジしてみたい一品です。
木製ストックが入手出来なかったらチャレンジしてみようかな?
100年近く経った今でも近代改修型が作られて愛されているというBAR、
やはりジョン・ブローニングは偉大であり、不滅の存在なんですね(小並感)。
2018年03月21日
素人にはオススメできないカラシニコフ
いやー、こないだの日曜日ヂゴンの巣でサバゲーしたんですがね、
相変わらず人集まらなくて3人でサバゲーしちゃいましたよ。
挙句の果てには参加者の1人、タキモト様が安納芋出してきて、
「寒いから焼き芋しましょ!」と言うんでイモ焼いて食っちゃった。
イモ食った後はエアガンの話で盛り上がって解散。
ま、そういうサバゲーと関係ない部分で盛り上がれるのがヂゴンの巣なんですがね、
一応サバゲーフィールドなんだからもう少しサバゲー出来る環境をどーにかせねば。
ところでこのブログがサバイバルゲームのブログであることを
ご認識の上でROMっている同志の皆様方、新しい武器仕入れてますか?
我輩はここんところさっぱりですねぇ。
まずカネがないし、何よりも他に必要なものが多くて武器まで手が届かない。
でも趣味って趣味のものがある程度、必要以上に揃ったら、
次に欲するものはエアガンや装備品じゃなくて予備マガジンとか、
弾速計とか、予備バッテリーとか、メカボ内部の部品とかになっちまうんです。
だから「新しい武器、何買おうかなー」と思案する人達が実に羨ましい。
ていうかパーツとか仕入れてもそんなに気分盛り上がらない。
我輩ピーマン職人とかヅイマー氏みたいに精神まで泥沼に浸かってないから、
エアガンの部品買ってもソコまでワクワクしないんですよねぇ。
マルイのハイスピードモーター(AK用)欲しいんだけど、
手に入れたとしても多分淡々とした気分で組み込むと思う。
でも新しい武器で必要に迫られて欲しいものがあるかって言われても、
それ程「欲しいぃぃぃぃぃ!」って物があるわけでもないんですねコレが。
いや勢いで欲しいものは少々ある(アローダイナミックのBARとか)けど、
冷静に考えて欲しいと思うものはそんなに無いのよね。
でもサバゲー歴はそこそこ長いものの、
現在に至るまで迷走を繰り返していた同志ガーナ殿は
一応AKが好きだけど一歩踏み出せなかった模様。
そこでクリス・コスッタ氏が「吉六会の夜会に呼んで洗脳しましょう」と
提案してきたので彼を呼び出して夜中の12時まで海外製電動ガンの魅力について
吉六会同志で交互に熱く語り合ったところ洗脳成功。

最終的に「木と鉄で出来たAK、欲しいです!」と叫ばせた後、
我輩に2丁のβスペツナズと今まで愛用していたAK74(前回の記事で参照)を
託してきたのでそれらを売り払ってE&LのAKS74Uを購入。
ヤフオクで中古を仕入れたので、購入価格は送料込みで24000円、約1/2パットン。
新品のコンプリートモデルは流通価格は35000円前後、
外装だけのモデル(メカボとバレルとチャンバーが必要)なら25000円弱ぐらいが相場だから、
セコハンとは言え外装に傷も殆ど無い新古レベルのブツを
このお値段で仕入れたのは結構得した気分。
E&Lをというメーカーは以前外装パーツ類を販売していた
“LANDARMS”というメーカーがコンプリート電動ガンを販売するに辺り
立ち上げてしまったメーカーのことらしいです。
現在では先達のLCT程ではないもののロシア系のAKは大抵網羅している模様。
余談ですが大分昔、LANDARMSのAKのルーマニアンストック仕入れたら、
物凄く歪んでいるストックが来てマジ泣きしたことがある我輩。
でもLCT製のAKの素晴らしさはG2所有のAKMとかで既に認識済みなので、
まだ未体験の世界であるE&Lをこの目で見たかったという理由で購入しました。
我輩が買う前に人柱になってもらおうという魂胆も込めて。
そして「調整する」という大義名分を付けて我輩がバラバラにするwww
バラバラにしていたる所まで調べた挙げ句ブログのネタにするwww

箱から出した外観に対する所見は「冷ややかだな」。
良く言えば「AKらしい悪さ」、悪く言えば「綺麗に仕上がっていない」。
まあ正直、LCT製品見た時の「ハァ~」と何とも言えぬ溜息が出る感じではなく、
「ホォ~」と言った感じの何処か引っかかるものがある気分。
色々な部分が荒っぽくて、素直に良いものとは言い難い気がしなくもない。
RSの56式見た時のような実銃感はあまり感じられず、
どちらかと言うとデニックスのモデルガンが小奇麗になった感じ。
でもこの大半が鉄で出来ているが故の重量感、たまらん。
樹脂でできているのはマガジンだけ、金属部分は全て鉄。磁石引っ付く。
重さは2.8kg程度なんで馬鹿みたいに重たくはないけれど、
丁度よい重みが戦いたい気分を掻き立ててくれそう(小並感)。

余談ですが「クリンコフ」とはロシア語で「短いもの」という意味があると
ネット上では言われているようですが確かな情報ではない模様。
ただ、AKS74Uという名称の中にある“U(У)“には
Ukorochennyj (укороченный=短小化)の意味があるとのこと。
はいココ試験に出まーす(大嘘)。
ま、この名称が定着しているという点ではその意味がどうであっても、
それを使うことに問題はなかろうと思うのは我輩だけでしょうか?
マルイの次世代クリンコフはヤフオクで中古が
20000円前後ぐらいのお値段で取引されているようですが、
メカボックスとかを弄る能力があるならLCTやE&Lを買うのが良い選択肢だと思ふ。
マルイの次世代クリンコフにはブローバックとリコイルがありますが、
LCTやE&Lのクリンコフには壊れにくいボディとサイドマウントがありますから。
但し、サイドマウントを使用するとストックが折り畳めないのは仕方ないね。

削り出して作ったと思われるフラッシュハイダーの仕上がりは美しいの一言。
しかし鋳物で作ったと思われるフロントサイト部分はマルイと大差なし。
ハイダー内部を覗くと、インナーバレルがハイダーの手前まで来ております。

LCTとE&LのAKは何処がどのように違うのか、
それを一番理解できる部分が木製ハンドガードやストックの仕上がりでしょう。
明らかすぎるぐらいに厚ぼったく塗られたニス、コレがある意味E&Lの特徴。
LCTの木製ストックはもう少し控えめな塗りです。
どちらが良いのかと言われると好みの問題でしょうね。
実銃がどうなのかはよく解りませんが、もう少し控えめでも良かったんじゃね?

そしてフロントサイトポストの根本に脂っこいカスが付いているのはどうなんでしょ?
前オーナーはそこら辺気が付かなかったのか、それともどーでも良かったのか?

黒染のフレームとレシーバーカバーの仕上がりは鉄感溢れるシャープさ。
塗り仕上げのマルイやCYMAとは雲泥の差です。
もうね、これだけでご飯3杯はイケるよ我輩。
しかしそれと対極的なのがチャージングハンドル。
もう少し綺麗にしろとは言わんが、何か雑。
ただ、ハンドル後付のLCTと比べると全てが一体成型で硬そう。
コレならどっかにぶつけてもハンドルが折れることはないでしょう。
グリップは何処の中華メーカーでも見られる仕上がりのプラ感溢れるシロモノ。
ていうか中華電動ガン用のAK用グリップって
どっかの樹脂加工メーカーが一括して作ってんじゃないのか?
レシーバーカバーと一体化したリアサイトポストは鋳造。
リアサイトはカシメられているので取り外すにはドリルでぶっ壊すしかありません。

マルイのクリンコフは純正マウントが取り付けられないので、
フレームサイドにマウントが付属していないのですが、
中華メーカーの場合は「合うやつ探して付けりゃいいだろ?」と思っているのか、
どのメーカーのクリンコフにも構わずマウントが付属しております。
フレーム各部のリベットの頭がでかいよーな気がせんでもないですが、
ここら辺は実銃知らなければ気にならないところでしょう。
ストック固定用のフックとストック折りたたみ用のボタンのテンションは緩め。
だからストックの開閉はスムースに行なえます。
ストックをロックする部品も頑丈そうなので
マルイの次世代みたいにぶっ壊れる可能性は低そうです。

我輩が感服したのがストックの取り付け。
過去に購入した中華製品やマルイのものよりガッチリしています。
ストック自体も頑丈だし、根元部分も殆どカタカタしません。
ただ、スリングスイベルは片方にしか折り畳めない模様。
スリングの掛け方に少し気を使いそうな予感。

最近のロットのE&L製AKは少しお高く売られているやつを買うと
マグウェル部分にマガジン誤挿入防止のスペーサーが付いているらしいですが、
コイツは初期ロットだったのか、それとも廉価版だったのか、
スペーサーが付属していないので別途購入の必要性があります。
いや別になくても使えんこたぁ無いみたいだけどね、
慌てている時にマガジンが変な刺さり方するんだなコレが。

付属のマガジンはスプリング給弾式の70連のやつ(写真左)。
色はG&PやMAG製のマガジンに似ていてベークライト感ゼロ。
マルイのAK47(次世代じゃないよ)のマガジンはすんなり装着可能でしたが、
写真右にあるCYMA製500連マガジンは少々取り付けに難があります。
でもしっかり撃てたので他社製マガジンもそれなりに使えなくはないでしょう。

さて、我輩は中華の技術は全く信用していないので、
E&L製AKS74U、クリンコフに関しても試射することもなく速攻で分解に入ります。
セコハン物なんで前オーナーがいくらか発射してはいるんでしょうが、
我輩が試射した時点でメカボ破壊したら目も当てられんですからね。
レシーバーカバーを開けると勝手にアッパーハンドガードが外れます。
なお、バッテリーはこのカバーの下に細いやつ(通称ウナギバッテリー)をブチ込みます。

次はロアハンドガードを外すために、根本にあるレバーを起こすのですが、
コイツがなかなか固くて動かないので、ココ外すのに20分ぐらいかかる羽目に。
取り付け位置から180度回転させればハンドガードが外れます。

正ネジで固定されているフラッシュハイダーは外す必要はないのですが、
外してみたところこの様になっておりました。
実銃準拠の22mmのネジ山は別パーツのようですが、
相当固くねじ込まれているようで工具使わないと緩まないようです。

我輩的常識では中華AKはこの部分のピンを抜けば
前回りがズルっと外れるという思考の元、
ピンを叩き抜いてみたんですが全然動きませんでした。

「これもうわかんねぇな」と呟きながら別のところから攻めてみます。
チャージングハンドルからバラしていきましょうという事で、
まずはカバーを固するブロックの根本のイモネジを緩めます。

その後チャージングハンドルを固定&可動させるためのロッドを取り外すと、
チャージングハンドルがフリーになって取り外せます。

その後リアサイトベース内側にある2本のイモネジを緩めるのですが、
あまりにも狭いのでレンチのストロークが稼げず、なかなか緩めるのに難航します。

どうにかして2本のイモネジを緩めたら
チャンバーを固定する2本のネジを緩めます。

一般的に中華メーカーのチャンバーはチャンバー前方にバネが入っており、
そのテンションでメカボックスと密着するようになっているのですが、
E&L製AKのチャンバーはメカボックスに固定する仕様みたいです。
確か社外品のジュラルミンチャンバーがコーいう作りだったはず。
なのでメカボックス前方のネジを緩めてチャンバーが外せるようにします。
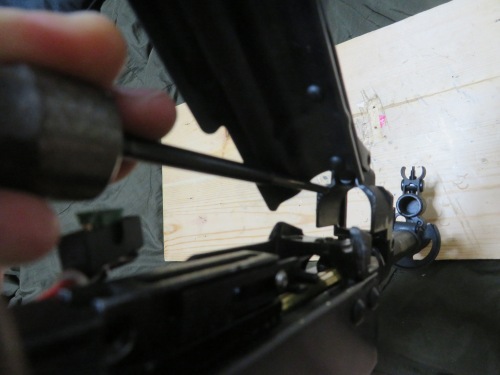
インナーバレルとチャンバーがフリーになったので
アウターバレル部分を引っこ抜こうとしたのですが、
どんだけ固く圧入されているのかハンドパワーでは全く抜ける気配なし。
手でヌケないってどうやってヌケばいいんだよ(声だけ迫真)!
結局、リアサイトブロック内側からポンチとかの固くて長いものを突っ込んで当て、
ハンマーでガンガン叩いたらようやく抜けてきやがりました。

いやしかし、AKのメカボックスにアクセスするのに、
フロント周りバラすのはそんなに苦じゃなかったけどコイツは相当苦難だな。
ここで我輩確信。「素人はE&LのAKに手を出すな!」

無事アウターバレルを分離できたらやっとインナーバレルが取り出せます。
チャンバーのある方向から後ろ斜めに引き抜きましょう。
いやーしかし、マルイのAK47系列の場合は、
フロント周りが全て一体で分離できたから分解超楽だったけど、
VFCを基礎とする中華AK系列の分解方法は意外と手間がかかる事が判明。
とはいえ、他社の中華AKは分解のためのピンやネジや部品がすぐに外せるから、
分解するにもそこまで手間がかかる印象ではなかったんですが、
E&LのAKはピン抜けても部品が外れなくて閉口する仕様なんですね。

兎に角、コレでやっとメカボックスを取り出せるようになります。
グリップ底部のネジを緩めてグリップを取り外し、
セレクターを止めるネジをプライヤー等で緩めてセレクターを外し、
フレーム上部にメカボックスをずらして取り出します。
その際、モーターに繋がっている部分の被膜が破れそうになるので注意。

他の人のブログを見たらメカボックスがシルバーの人がいましたが、
ガーナ氏のAKS74Uのメカボックスは黒ですね。
シリンダーがハマる部分の四隅に割れ防止用の凹みや盛り上がりがあります。
軸受は全部メタルで、ベベルとセクターがベアリングになっています。
ヒューズは小さくて平べったいのが付いています。
メカボ弄るのが好きな人の中にはヒューズ不要論を唱える方も居られるようですが、
我輩的にヒューズ付けないのって風俗でゴム付けないのと同じぐらい不安。
基本的にマルイと同じタイプのヴァージョン3メカボックスなので、
手持ちがあるならマルイ製のメカボックスに換装してしまえば信頼性が上がり、
再びメカボックスに手を付けるために苦難の分解行為を実施する必要が少なくなります。

モーターは“HIGH TORQUE ELM170”とか言うのが付いています。
多分中華モーターの例に漏れず、強いスプリング対応のトルク重視モーターでしょうね。
発射速度はあまり早い感じではなかったです。
ま、我輩的には弾さえ出てくれればサバゲーには使えるんで(適当)。

中華メカボックスの良いところは止めネジがトルクスじゃないところ。
クロスのドライバーで開けられるって便利だよなぁ(小並感)。
余談ですが我輩はマルイメカボックス分解したら
トルクスネジは速攻で捨ててクロスネジに交換します。
シリンダーはAKS74Uのバレル長(300mm弱ぐらい)に合わせた加速シリンダー。
ノズルやタペットプレートは特に問題なさそうなんでそのまま使います。

スプリングはマルイノーマルよりも線径は細いけど少し長め。
両端が削っていない適当仕様なので同じ長さで少し太めなSHSののM90と交換。
ピストンヘッドはサイレントピストンヘッド?なんでしょうかねコレ?
面白いんでそのまま使いますがピストンに突っ込んで先っちょ押さえて
ピストン運動を繰り返したところスッカスカだったんで、
ヘッドのOリングをマルイノーマルのものと交換すると気密アップ。
ピストンの本体は後ろの歯が2枚無い仕様、ピスクラ防止策か?
メカボの溝にハマる部分が一部短いのは多分摩擦抵抗を減らす為?
これもそのまま使って支障はないでしょう。
スプリングガイドはベアリング付きで出来も悪くない、そのまま使える。
うーむ、パーツそれぞれの出来は悪くないみたいですな。

メカボックス開けたら中華お約束の緑色のグリスかと思いきや、
うーん、最近の中華は茶色系グリスが多いみたいなのね。
でもあまり気持ちがいいもんじゃないんでパーツクリーナーで洗浄。
他の人のブログでは青いグリスが付いているのがあった模様。
我輩のエアガン人生で中華ギアが不具合を起こすという事案が
過去に全く存在しないのでギアはそのまま使用します。
ていうか我輩の近辺には中華電動ガンのメカボックスよりも、
マルイの電動ガンぶっ壊す人の方が多いような気がするんですが?
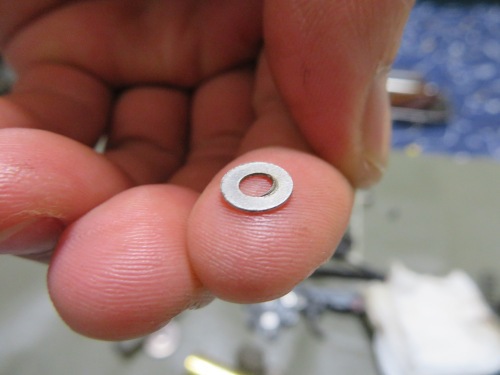
さっきパーツの出来は悪くないと言ったな、アレは嘘だ。
シムの出来は内側が何か捲れていて最悪です。
しかもコレ分厚いやつ以外は全部こんな感じ。交換じゃ!
シムはベベル両側が分厚いの1枚、他は全て中ぐらいの1枚。
そんでもってその状態で仮組みしてシムの具合を確認したところ、
どのギアもガッタガタなんですねコレが。
なので全てのギアに中ぐらいのシム1枚カマしてセットアップ。

しかしメカボックス以上に難航したのはチャンバー。
E&LのAKは金属部分が全て鉄と言った気がしますが、チャンバーは亜鉛のようです。
そしてこのチャンバー、かなり作りがよろしくない模様。
全体的に汚いんですが、ソレ以上にホップレバーがユルユル。
多分コレ、射撃中に振動で緩むなってぐらい酷い。
レバーの裏側に段差があるんでスライド部分の設置が悪く、
いくらネジを締めても埒が明かんので段差部分をプラリペアで埋めて整形し直しました。

写真上のやつはマルイAK47のチャンバー。
ご覧の通り形状的には完全に互換はありますので、
いっそ交換してしまう方が幸せになれるかもしれません。
インナーバレルは外装が少々汚かったんで交換したかったんですが。
手持ちのマルイノーマルバレルが枯渇してしまったんでピカールで磨いて再取り付け。
チャンバーパッキンはホップの出っ張りが切れ込みのあるタイプだったし、
破損も特に無かったんでそのまま使用してみることにしました。

組み立ての際、またアウターバレルをハンマーで叩き込むのは嫌なので、
指差している部分を重点的にヤスリで削り、
バレルがハマる方の穴もサンドペーパーでバリを取ったら
ま、多少はね、すんなりハマるようになりました。
今後の整備性の向上のためにもこの部分、必ず削るべきです。

バッテリーを繋いでS2Sの0.2g弾詰めて射撃してみたところ、
初速の平均は大体86m/sぐらいと少々足りない感じ。
うーん、スプリングは思い切ってM100ブチ込んでも良かったな。
でもパワーが全てじゃないんで良しとしましょう。発射速度はやっぱり遅いが。
E&L製AKはパッと見の印象は悪くありませんが、
細かい部分にアラが見られ、極上の出来栄えとは言い難いです。
でも言い換えればソレがAKらしい雰囲気と言えなくもありません。
厚塗りの赤っぽい木製ハンドガード、我輩的には好きです。
そして中身は相当なもんなのでCYMAやDBOYぐらい手を入れる必要があります。
主要な部品の出来自体は悪くないんでしょうが、細かい部分が微妙。
でも何より、分解するのに手間取るというのはかなり辛いですね。
電動ガンをバラすのが大好きな人だったらオススメしないこともないですが、
多少金額が高くても我輩はLCT製AKの方をオススメしますね。
LCT製なら箱出し状態で使えないこともありませんが、
E&L製は箱出しで使うにはリスクがありそうな気がしますし、
何度もくどいようですが手軽にバラせない鉄砲ってマジ大変。
相変わらず人集まらなくて3人でサバゲーしちゃいましたよ。
挙句の果てには参加者の1人、タキモト様が安納芋出してきて、
「寒いから焼き芋しましょ!」と言うんでイモ焼いて食っちゃった。
イモ食った後はエアガンの話で盛り上がって解散。
ま、そういうサバゲーと関係ない部分で盛り上がれるのがヂゴンの巣なんですがね、
一応サバゲーフィールドなんだからもう少しサバゲー出来る環境をどーにかせねば。
ところでこのブログがサバイバルゲームのブログであることを
ご認識の上でROMっている同志の皆様方、新しい武器仕入れてますか?
我輩はここんところさっぱりですねぇ。
まずカネがないし、何よりも他に必要なものが多くて武器まで手が届かない。
でも趣味って趣味のものがある程度、必要以上に揃ったら、
次に欲するものはエアガンや装備品じゃなくて予備マガジンとか、
弾速計とか、予備バッテリーとか、メカボ内部の部品とかになっちまうんです。
だから「新しい武器、何買おうかなー」と思案する人達が実に羨ましい。
ていうかパーツとか仕入れてもそんなに気分盛り上がらない。
我輩ピーマン職人とかヅイマー氏みたいに精神まで泥沼に浸かってないから、
エアガンの部品買ってもソコまでワクワクしないんですよねぇ。
マルイのハイスピードモーター(AK用)欲しいんだけど、
手に入れたとしても多分淡々とした気分で組み込むと思う。
でも新しい武器で必要に迫られて欲しいものがあるかって言われても、
それ程「欲しいぃぃぃぃぃ!」って物があるわけでもないんですねコレが。
いや勢いで欲しいものは少々ある(アローダイナミックのBARとか)けど、
冷静に考えて欲しいと思うものはそんなに無いのよね。
でもサバゲー歴はそこそこ長いものの、
現在に至るまで迷走を繰り返していた同志ガーナ殿は
一応AKが好きだけど一歩踏み出せなかった模様。
そこでクリス・コスッタ氏が「吉六会の夜会に呼んで洗脳しましょう」と
提案してきたので彼を呼び出して夜中の12時まで海外製電動ガンの魅力について
吉六会同志で交互に熱く語り合ったところ洗脳成功。

最終的に「木と鉄で出来たAK、欲しいです!」と叫ばせた後、
我輩に2丁のβスペツナズと今まで愛用していたAK74(前回の記事で参照)を
託してきたのでそれらを売り払ってE&LのAKS74Uを購入。
ヤフオクで中古を仕入れたので、購入価格は送料込みで24000円、約1/2パットン。
新品のコンプリートモデルは流通価格は35000円前後、
外装だけのモデル(メカボとバレルとチャンバーが必要)なら25000円弱ぐらいが相場だから、
セコハンとは言え外装に傷も殆ど無い新古レベルのブツを
このお値段で仕入れたのは結構得した気分。
E&Lをというメーカーは以前外装パーツ類を販売していた
“LANDARMS”というメーカーがコンプリート電動ガンを販売するに辺り
立ち上げてしまったメーカーのことらしいです。
現在では先達のLCT程ではないもののロシア系のAKは大抵網羅している模様。
余談ですが大分昔、LANDARMSのAKのルーマニアンストック仕入れたら、
物凄く歪んでいるストックが来てマジ泣きしたことがある我輩。
でもLCT製のAKの素晴らしさはG2所有のAKMとかで既に認識済みなので、
まだ未体験の世界であるE&Lをこの目で見たかったという理由で購入しました。
我輩が買う前に人柱になってもらおうという魂胆も込めて。
そして「調整する」という大義名分を付けて我輩がバラバラにするwww
バラバラにしていたる所まで調べた挙げ句ブログのネタにするwww

箱から出した外観に対する所見は「冷ややかだな」。
良く言えば「AKらしい悪さ」、悪く言えば「綺麗に仕上がっていない」。
まあ正直、LCT製品見た時の「ハァ~」と何とも言えぬ溜息が出る感じではなく、
「ホォ~」と言った感じの何処か引っかかるものがある気分。
色々な部分が荒っぽくて、素直に良いものとは言い難い気がしなくもない。
RSの56式見た時のような実銃感はあまり感じられず、
どちらかと言うとデニックスのモデルガンが小奇麗になった感じ。
でもこの大半が鉄で出来ているが故の重量感、たまらん。
樹脂でできているのはマガジンだけ、金属部分は全て鉄。磁石引っ付く。
重さは2.8kg程度なんで馬鹿みたいに重たくはないけれど、
丁度よい重みが戦いたい気分を掻き立ててくれそう(小並感)。

余談ですが「クリンコフ」とはロシア語で「短いもの」という意味があると
ネット上では言われているようですが確かな情報ではない模様。
ただ、AKS74Uという名称の中にある“U(У)“には
Ukorochennyj (укороченный=短小化)の意味があるとのこと。
はいココ試験に出まーす(大嘘)。
ま、この名称が定着しているという点ではその意味がどうであっても、
それを使うことに問題はなかろうと思うのは我輩だけでしょうか?
マルイの次世代クリンコフはヤフオクで中古が
20000円前後ぐらいのお値段で取引されているようですが、
メカボックスとかを弄る能力があるならLCTやE&Lを買うのが良い選択肢だと思ふ。
マルイの次世代クリンコフにはブローバックとリコイルがありますが、
LCTやE&Lのクリンコフには壊れにくいボディとサイドマウントがありますから。
但し、サイドマウントを使用するとストックが折り畳めないのは仕方ないね。

削り出して作ったと思われるフラッシュハイダーの仕上がりは美しいの一言。
しかし鋳物で作ったと思われるフロントサイト部分はマルイと大差なし。
ハイダー内部を覗くと、インナーバレルがハイダーの手前まで来ております。

LCTとE&LのAKは何処がどのように違うのか、
それを一番理解できる部分が木製ハンドガードやストックの仕上がりでしょう。
明らかすぎるぐらいに厚ぼったく塗られたニス、コレがある意味E&Lの特徴。
LCTの木製ストックはもう少し控えめな塗りです。
どちらが良いのかと言われると好みの問題でしょうね。
実銃がどうなのかはよく解りませんが、もう少し控えめでも良かったんじゃね?

そしてフロントサイトポストの根本に脂っこいカスが付いているのはどうなんでしょ?
前オーナーはそこら辺気が付かなかったのか、それともどーでも良かったのか?

黒染のフレームとレシーバーカバーの仕上がりは鉄感溢れるシャープさ。
塗り仕上げのマルイやCYMAとは雲泥の差です。
もうね、これだけでご飯3杯はイケるよ我輩。
しかしそれと対極的なのがチャージングハンドル。
もう少し綺麗にしろとは言わんが、何か雑。
ただ、ハンドル後付のLCTと比べると全てが一体成型で硬そう。
コレならどっかにぶつけてもハンドルが折れることはないでしょう。
グリップは何処の中華メーカーでも見られる仕上がりのプラ感溢れるシロモノ。
ていうか中華電動ガン用のAK用グリップって
どっかの樹脂加工メーカーが一括して作ってんじゃないのか?
レシーバーカバーと一体化したリアサイトポストは鋳造。
リアサイトはカシメられているので取り外すにはドリルでぶっ壊すしかありません。

マルイのクリンコフは純正マウントが取り付けられないので、
フレームサイドにマウントが付属していないのですが、
中華メーカーの場合は「合うやつ探して付けりゃいいだろ?」と思っているのか、
どのメーカーのクリンコフにも構わずマウントが付属しております。
フレーム各部のリベットの頭がでかいよーな気がせんでもないですが、
ここら辺は実銃知らなければ気にならないところでしょう。
ストック固定用のフックとストック折りたたみ用のボタンのテンションは緩め。
だからストックの開閉はスムースに行なえます。
ストックをロックする部品も頑丈そうなので
マルイの次世代みたいにぶっ壊れる可能性は低そうです。

我輩が感服したのがストックの取り付け。
過去に購入した中華製品やマルイのものよりガッチリしています。
ストック自体も頑丈だし、根元部分も殆どカタカタしません。
ただ、スリングスイベルは片方にしか折り畳めない模様。
スリングの掛け方に少し気を使いそうな予感。

最近のロットのE&L製AKは少しお高く売られているやつを買うと
マグウェル部分にマガジン誤挿入防止のスペーサーが付いているらしいですが、
コイツは初期ロットだったのか、それとも廉価版だったのか、
スペーサーが付属していないので別途購入の必要性があります。
いや別になくても使えんこたぁ無いみたいだけどね、
慌てている時にマガジンが変な刺さり方するんだなコレが。

付属のマガジンはスプリング給弾式の70連のやつ(写真左)。
色はG&PやMAG製のマガジンに似ていてベークライト感ゼロ。
マルイのAK47(次世代じゃないよ)のマガジンはすんなり装着可能でしたが、
写真右にあるCYMA製500連マガジンは少々取り付けに難があります。
でもしっかり撃てたので他社製マガジンもそれなりに使えなくはないでしょう。

さて、我輩は中華の技術は全く信用していないので、
E&L製AKS74U、クリンコフに関しても試射することもなく速攻で分解に入ります。
セコハン物なんで前オーナーがいくらか発射してはいるんでしょうが、
我輩が試射した時点でメカボ破壊したら目も当てられんですからね。
レシーバーカバーを開けると勝手にアッパーハンドガードが外れます。
なお、バッテリーはこのカバーの下に細いやつ(通称ウナギバッテリー)をブチ込みます。

次はロアハンドガードを外すために、根本にあるレバーを起こすのですが、
コイツがなかなか固くて動かないので、ココ外すのに20分ぐらいかかる羽目に。
取り付け位置から180度回転させればハンドガードが外れます。

正ネジで固定されているフラッシュハイダーは外す必要はないのですが、
外してみたところこの様になっておりました。
実銃準拠の22mmのネジ山は別パーツのようですが、
相当固くねじ込まれているようで工具使わないと緩まないようです。

我輩的常識では中華AKはこの部分のピンを抜けば
前回りがズルっと外れるという思考の元、
ピンを叩き抜いてみたんですが全然動きませんでした。

「これもうわかんねぇな」と呟きながら別のところから攻めてみます。
チャージングハンドルからバラしていきましょうという事で、
まずはカバーを固するブロックの根本のイモネジを緩めます。

その後チャージングハンドルを固定&可動させるためのロッドを取り外すと、
チャージングハンドルがフリーになって取り外せます。

その後リアサイトベース内側にある2本のイモネジを緩めるのですが、
あまりにも狭いのでレンチのストロークが稼げず、なかなか緩めるのに難航します。

どうにかして2本のイモネジを緩めたら
チャンバーを固定する2本のネジを緩めます。

一般的に中華メーカーのチャンバーはチャンバー前方にバネが入っており、
そのテンションでメカボックスと密着するようになっているのですが、
E&L製AKのチャンバーはメカボックスに固定する仕様みたいです。
確か社外品のジュラルミンチャンバーがコーいう作りだったはず。
なのでメカボックス前方のネジを緩めてチャンバーが外せるようにします。
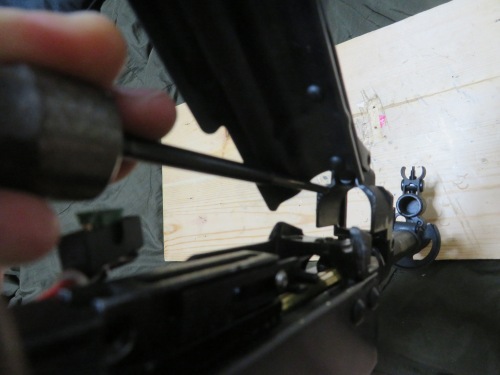
インナーバレルとチャンバーがフリーになったので
アウターバレル部分を引っこ抜こうとしたのですが、
どんだけ固く圧入されているのかハンドパワーでは全く抜ける気配なし。
手でヌケないってどうやってヌケばいいんだよ(声だけ迫真)!
結局、リアサイトブロック内側からポンチとかの固くて長いものを突っ込んで当て、
ハンマーでガンガン叩いたらようやく抜けてきやがりました。

いやしかし、AKのメカボックスにアクセスするのに、
フロント周りバラすのはそんなに苦じゃなかったけどコイツは相当苦難だな。
ここで我輩確信。「素人はE&LのAKに手を出すな!」

無事アウターバレルを分離できたらやっとインナーバレルが取り出せます。
チャンバーのある方向から後ろ斜めに引き抜きましょう。
いやーしかし、マルイのAK47系列の場合は、
フロント周りが全て一体で分離できたから分解超楽だったけど、
VFCを基礎とする中華AK系列の分解方法は意外と手間がかかる事が判明。
とはいえ、他社の中華AKは分解のためのピンやネジや部品がすぐに外せるから、
分解するにもそこまで手間がかかる印象ではなかったんですが、
E&LのAKはピン抜けても部品が外れなくて閉口する仕様なんですね。

兎に角、コレでやっとメカボックスを取り出せるようになります。
グリップ底部のネジを緩めてグリップを取り外し、
セレクターを止めるネジをプライヤー等で緩めてセレクターを外し、
フレーム上部にメカボックスをずらして取り出します。
その際、モーターに繋がっている部分の被膜が破れそうになるので注意。

他の人のブログを見たらメカボックスがシルバーの人がいましたが、
ガーナ氏のAKS74Uのメカボックスは黒ですね。
シリンダーがハマる部分の四隅に割れ防止用の凹みや盛り上がりがあります。
軸受は全部メタルで、ベベルとセクターがベアリングになっています。
ヒューズは小さくて平べったいのが付いています。
メカボ弄るのが好きな人の中にはヒューズ不要論を唱える方も居られるようですが、
我輩的にヒューズ付けないのって風俗でゴム付けないのと同じぐらい不安。
基本的にマルイと同じタイプのヴァージョン3メカボックスなので、
手持ちがあるならマルイ製のメカボックスに換装してしまえば信頼性が上がり、
再びメカボックスに手を付けるために苦難の分解行為を実施する必要が少なくなります。

モーターは“HIGH TORQUE ELM170”とか言うのが付いています。
多分中華モーターの例に漏れず、強いスプリング対応のトルク重視モーターでしょうね。
発射速度はあまり早い感じではなかったです。
ま、我輩的には弾さえ出てくれればサバゲーには使えるんで(適当)。

中華メカボックスの良いところは止めネジがトルクスじゃないところ。
クロスのドライバーで開けられるって便利だよなぁ(小並感)。
余談ですが我輩はマルイメカボックス分解したら
トルクスネジは速攻で捨ててクロスネジに交換します。
シリンダーはAKS74Uのバレル長(300mm弱ぐらい)に合わせた加速シリンダー。
ノズルやタペットプレートは特に問題なさそうなんでそのまま使います。

スプリングはマルイノーマルよりも線径は細いけど少し長め。
両端が削っていない適当仕様なので同じ長さで少し太めなSHSののM90と交換。
ピストンヘッドはサイレントピストンヘッド?なんでしょうかねコレ?
面白いんでそのまま使いますがピストンに突っ込んで先っちょ押さえて
ピストン運動を繰り返したところスッカスカだったんで、
ヘッドのOリングをマルイノーマルのものと交換すると気密アップ。
ピストンの本体は後ろの歯が2枚無い仕様、ピスクラ防止策か?
メカボの溝にハマる部分が一部短いのは多分摩擦抵抗を減らす為?
これもそのまま使って支障はないでしょう。
スプリングガイドはベアリング付きで出来も悪くない、そのまま使える。
うーむ、パーツそれぞれの出来は悪くないみたいですな。

メカボックス開けたら中華お約束の緑色のグリスかと思いきや、
うーん、最近の中華は茶色系グリスが多いみたいなのね。
でもあまり気持ちがいいもんじゃないんでパーツクリーナーで洗浄。
他の人のブログでは青いグリスが付いているのがあった模様。
我輩のエアガン人生で中華ギアが不具合を起こすという事案が
過去に全く存在しないのでギアはそのまま使用します。
ていうか我輩の近辺には中華電動ガンのメカボックスよりも、
マルイの電動ガンぶっ壊す人の方が多いような気がするんですが?
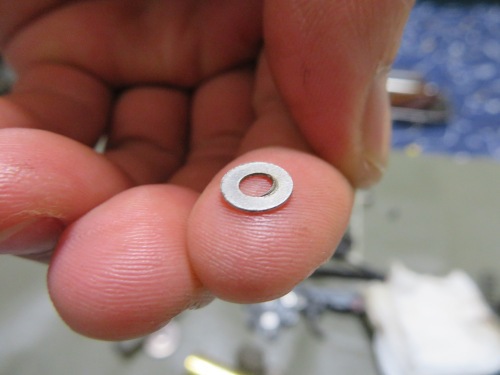
さっきパーツの出来は悪くないと言ったな、アレは嘘だ。
シムの出来は内側が何か捲れていて最悪です。
しかもコレ分厚いやつ以外は全部こんな感じ。交換じゃ!
シムはベベル両側が分厚いの1枚、他は全て中ぐらいの1枚。
そんでもってその状態で仮組みしてシムの具合を確認したところ、
どのギアもガッタガタなんですねコレが。
なので全てのギアに中ぐらいのシム1枚カマしてセットアップ。

しかしメカボックス以上に難航したのはチャンバー。
E&LのAKは金属部分が全て鉄と言った気がしますが、チャンバーは亜鉛のようです。
そしてこのチャンバー、かなり作りがよろしくない模様。
全体的に汚いんですが、ソレ以上にホップレバーがユルユル。
多分コレ、射撃中に振動で緩むなってぐらい酷い。
レバーの裏側に段差があるんでスライド部分の設置が悪く、
いくらネジを締めても埒が明かんので段差部分をプラリペアで埋めて整形し直しました。

写真上のやつはマルイAK47のチャンバー。
ご覧の通り形状的には完全に互換はありますので、
いっそ交換してしまう方が幸せになれるかもしれません。
インナーバレルは外装が少々汚かったんで交換したかったんですが。
手持ちのマルイノーマルバレルが枯渇してしまったんでピカールで磨いて再取り付け。
チャンバーパッキンはホップの出っ張りが切れ込みのあるタイプだったし、
破損も特に無かったんでそのまま使用してみることにしました。

組み立ての際、またアウターバレルをハンマーで叩き込むのは嫌なので、
指差している部分を重点的にヤスリで削り、
バレルがハマる方の穴もサンドペーパーでバリを取ったら
ま、多少はね、すんなりハマるようになりました。
今後の整備性の向上のためにもこの部分、必ず削るべきです。

バッテリーを繋いでS2Sの0.2g弾詰めて射撃してみたところ、
初速の平均は大体86m/sぐらいと少々足りない感じ。
うーん、スプリングは思い切ってM100ブチ込んでも良かったな。
でもパワーが全てじゃないんで良しとしましょう。発射速度はやっぱり遅いが。
E&L製AKはパッと見の印象は悪くありませんが、
細かい部分にアラが見られ、極上の出来栄えとは言い難いです。
でも言い換えればソレがAKらしい雰囲気と言えなくもありません。
厚塗りの赤っぽい木製ハンドガード、我輩的には好きです。
そして中身は相当なもんなのでCYMAやDBOYぐらい手を入れる必要があります。
主要な部品の出来自体は悪くないんでしょうが、細かい部分が微妙。
でも何より、分解するのに手間取るというのはかなり辛いですね。
電動ガンをバラすのが大好きな人だったらオススメしないこともないですが、
多少金額が高くても我輩はLCT製AKの方をオススメしますね。
LCT製なら箱出し状態で使えないこともありませんが、
E&L製は箱出しで使うにはリスクがありそうな気がしますし、
何度もくどいようですが手軽にバラせない鉄砲ってマジ大変。
2018年03月09日
安物買いの何とやら?
今回の記事とは何の関係もないんですが当ブログを御覧の皆様、
ビリー・ヘリントンという方をご存知でしょうか?
大分前に“ガチムチパンツレスリング”という動画で一世を風靡した
アメリカのゲイポルノ俳優の名前なんですがね、
その人が3月2日に交通事故でお亡くなりになったそうです。
注釈:“ガチムチパンツレスリング”とは筋肉質の野郎2人がパンツ一丁で戦い合い、
先にパンツを脱がした方が勝ちというシンプルな漢(おとこ)の戦い。
肉薄する野郎同志の熱気と漢(おとこ)気が伝わる動画です。
実は我輩がニコニコ動画にハマったきっかけはガチムチパンツレスリング。
それ以来ニコニコ動画、いや、パンツレスリングの虜になってしまったというか、
ビリー・ヘリントン関連の動画を探す&鑑賞するのが楽しかったあの頃。
全裸でハーレー洗車している動画とか、ハーネス装着して悦に入る動画とか、
ノンケなのに野郎の裸が面白い&興味深いと思わされる動画が跳梁跋扈しており、
どの動画でもビリー・ヘリントンさんは男の魅力を輝かせていた。
今思えばあの頃が一番ニコニコ動画が輝いていた頃かもしれない。
でもビリー・ヘリントンさんの何が凄いってネタにされて笑われているというのに、
ニコニコのイベントに本人降臨して更に笑いを提供してくれたところですね。
その様はまさに「Mr.エンターテイナー」そしてMr.漢(おとこ)気。兄貴流石だぜ。
そんなビリー・ヘリントンさんが48歳でお亡くなりになったと言うのは
我輩的に実に惜しく、悲しい事態でございます。
この場を借りてご冥福を祈りたいと思います。
さて、本題に戻ってサバゲーの話、武器の話をしましょう。
今回紹介するのは中華製電動ガン、CYMAのAK74。
CYMAのAKシリーズはCM0◯◯(◯の中に数字が入る)で表されますが、
今回レビューするモデルはCM031という名称のブツで、
所謂“スポーツライン”と呼ばれている廉価版モデルでございます。

このブツの持ち主は我輩ではなく、宮崎では数少ないAK同志のガーナ氏。
具体的な購入金額は聞いていないのですが相場は18000円ぐらいの模様。
マルイの次世代じゃない電動ガンと同程度か、
ソレより少々安いぐらいの価格のようですが、
我輩ココ10年ぐらいマルイの新品電動ガン買ったこと無いからよく解らん。
CYMAといえば中華電動ガンの中では比較的安価で、
フルメタル&ウッドストックの外装を持つAK系列の電動ガンが有名ですが、
プラスチックのボディ&ストックの安い電動ガンも生産しており、
今回紹介するAK74、CM031もその安く手に入る電動ガンの一つ。
安価で入手可能ということで我輩も幾度となく購入を検討しておりましたが、
メタルボディのAKから先に手を出してしまったので
「いくら安くても樹脂製フレームはねぇ・・・」と思い購入には至らなかったが故に、
スポーツラインのAKに触れるのは今回が初体験でございます。
付属品は本体、マガジン、微妙に役に立たない説明書、クリーニングロッド、
そして性能的に微妙なニッスイミニバッテリーとノーマル充電器。
ペラペラのスリングが付属していたかどうかは不明ですが、要らんよなあんなの。

安いスポーツラインとは言え、パッと見た印象は案外悪くないんですよ。
シルエットは特にツッコミどころもなく、結構よく出来ております。
何処らへんがどう可笑しいみたいな部分は特に見られません。
フレームの仕上がりなんかもマルイAK47みたいな
テカテカした樹脂感漂うやつじゃなくてAKのHCみたいなマット調。
我輩も一見騙されましたもんね、メタルじゃないかって。

でも反対側を見ると瞬時にメタルフレームじゃないって解るんです。
だって最近のAKに必ず付属しているサイドマウントが無いんだもん。
そう、フレームが樹脂だからマウント付けると破損するんですね。仕方ないね。
だからCYMAの樹脂製ストックのAK74でも
メタルフレームのCM040とかになるとサイドマウントが付属しております。
但し、メタルフレームじゃなくてもAKの構成自体は
比較的頑丈なので想像するほどボディは軋みません。
マルイのAK47と同程度の剛性感は確保されております。

AK74の特徴である大げさなフラッシュハイダーは鉄製。
マルイAK47同様逆ネジで取り付けられております。
フロントサイトがやガスバイパスは亜鉛合金、
アウターバレルとクリーニングロッドは鉄製。
ボディが樹脂なのにアウターバレルが鉄なので結構フロントヘビーです。
因みに、フロントサイトを下から固定しているネジは緩みやすいので、
ネジロックを塗ってガッチリ固定しておかないと確実に紛失します。

ハンドガードは次世代AK74MNと同形状の樹脂製。
プラの質感は安っぽいですが、形は悪くない。
リアサイト周りはサイトも含めて亜鉛合金、
ハンドガードを固定するパーツは前が亜鉛で後ろが鉄。
ココらへんの構成、ていうか全てにおいてマルイAK47と同様の構成です。
だからマルイAK47対応の社外品ハンドガードなら取り付け可能です。

フレームは前述のように樹脂製、トップカバーは鉄製。
よく見ると金属フレームよりは見劣りしますね。だらしねぇな。
微妙にAK47と形状が違うトリガーガードとセレクターは鉄製です。
セレクターの固定はマルイAK47同様、
ネジで取り付けた上に蓋をかぶせるようになっているので、
この部分がAK74っぽくなくて残念な感じです。
そして何故かこのセレクター、カチッとしたクリック感がない。
フルに入れてもセミにしてもグラグラする。
グリップは当然樹脂製。
この部分に関してはLCTやハイエンドモデルのAKのものが使用可能。
フレーム形状がAK47とは異なるのでマルイAK47対応グリップは
付きませんというか、フレームとグリップの間に隙間が出来ます。

樹脂製ストックのモデルなので、ストックも当然樹脂。
そしてストックの蓋の部分も樹脂製です。
バッテリーの交換はマルイAK47同様、ストックの蓋をずらして蓋を開け、
ストック内にバッテリーを突っ込みます。
このストックの蓋が結構保持力が弱く、すぐに外れそうになります。
なおこの蓋の部分、マルイAK47のものは取り付けられません。
ストック内部は広いのでラージバッテリーも入りますが、
コネクタがミニ用なのでラージ用コネクタを別途購入する必要あり。
まあウナギバッテリー以外なら大抵収まるでしょう。

標準装備のマガジンは500連の多弾数マガジン。
AK系列のマガジンのお約束に漏れず、
1回の巻き上げで全てを撃ちつくすことは不可能。
300発ぐらい撃ったら再度巻き上げ必須です。
ただ、マガジンそのものの弾上がりに特に不具合はない模様。
CYMA製のマガジンは安い割には案外使えます。

トップカバーの中身もご覧のとおり、マルイAK47で見慣れた風景です。
チャージングハンドルが黒であること以外はマルイ製と完全互換。

この写真を見てマルイのAK47に精通しておられる方は気が付くでしょう。
マガジン突っ込む部分とその前に部分にフロント部分を固定するネジの存在に。
そう、全体の構成は完全にマルイAK47のパクリなんですね。
だから分解方法はマルイAK47と同様です。
だからCYMA製AK74の分解方法を敢えて載せる必要もないでしょう?

嫁を抱いた回数よりマルイのAK47をバラした回数の方が多いと豪語する我輩ですが、
実は嫁を抱いた回数の方が多いような気がしなくもありません。
そういうわけでマルイAK47に準じたCYMA製AK74(CM031)を分解するのも速攻です。
なお、メタルフレームのCYMA製AK74(CM040)やAK104は、
木製ストックのCM048とかと同じく分解方法になるのでココを見ても参考にはなりません。
ガーナ氏は箱出し状態で使用して不調になったと言うので、
(我輩的に中華エアガンを箱出しで使うなんて自殺行為に等しいのだがw)
メカボックス内部の点検清掃、部品交換、
そしてついでにチャンバーパッキンの交換を実施します。

しかしこのメカボックスがとんでもないシロモノでした。
色々と弄くり回すのに必死で写真を撮る余裕もない有様。
(メカボックス内を弄ると手がグリスまみれになるので、
精神的に余裕がある時じゃないと撮影は出来ない)
まず、セレクタープレートがガタガタ。道理でセレクターが落ち着かないわけだ。
原因はセレクタープレートの後ろの黒いやつがガバガバだった事。
手持ちのマルイAK47のものと交換したらカチッと動くようになりました。
メカボックスを開くと更に地獄を見ます。
とりあえず中華電動ガンお約束の緑グリスがべっとりは予想の範疇。
全てのパーツを取り出してブレーキパーツクリーナーで洗浄します。
モーターは無印ですがCYMAだから多分机モーター。
手持ちにAK用のモーターがないのでそのまま使いましょう。
サイクルは遅いけど必要にして充分です。
パワーダウンの為メインスプリングがぶった切られていたので、
ピーマン職人から貰ったSHSのM90スプリングと交換。
ピストンの気密がスカスカだったのでピストンのOリングはマルイ純正と交換。
透明樹脂のノズルは気に入らないけどそのまま使用。
ピストンヘッドはまあ普通だったんでそのまま使用。
ギア類も特に不具合なさそうだったのでそのまま使用。
スプリングガイドは何の変哲もないやつだったけど、マルイ純正と交換。
白い樹脂製のタペットプレートは削れていたんでマルイ純正と交換。
その後各ギアに付属していたシムをそのままセッティングし、
メカボックスを閉じてネジを締めてシムの具合を確認と・・・
何か中ですっごいカタカタするんですが?
よく見てみるとシムが足りなくて全てのギアが遊んでいる状態。
確かに、シムはどのポジションも薄いのが1枚しか入っていなかったな。
というわけで全てのギアにシムを追加し、セクターは両側に厚みのあるやつ入れたら、
どーにかいい塩梅になったんでグリスアップして組み込み。

CYMA製AK74(CM031)の分解方法がマルイAK47と同様ということは、
組み立て方の手順もマルイAK47と同様ということ。
マルイAK47同様、ドライバーで挿している部分の配線が上手く収まるように、
そして後方への配線がストック取り付け部分に収まるように注意しながら
丁寧にメカボックスをフレーム内に収めます。

フレーム内にメカボックスを突っ込んだらグリップを取り付けて固定し、
セレクタープレートを取り付けます。

その後ストック配線を取り付け、ストックをネジで固定します。
ココのネジも緩みやすいのでネジロックを塗ってねじ込みます。

フロント部分を取り付ける前に、バレルとチャンバーを確認。
案の定、チャンバーパッキンは質感が悪いのでマルイ製と交換。
インナーバレルも見た目が汚すぎるので、マルイAK47のと交換。
中古のバレルですがこのだらしねぇバレルよりはマシでしょう。
欲を言えばチャンバーも交換したいところですが、余剰のパーツがない。
元々の命中精度がどんだけのものであるかは不明ですが、
ココを交換するだけで大分マルイ製品に近い性能になるのは
過去の経験から実証済なので迷わず交換してしまいます。

バレルとチャンバーパッキンを交換したら速やかに元に戻し、
写真で示している部分のバネを紛失しないように気をつけながら、
フロント周りとフレームを合体させます。

そしてフレーム下側から4本のネジで固定。
デフォルトではアレンレンチで締め込むネジだったようですが、
紛失していたので手元にあるステンレスネジと交換。
勿論、ココも紛失しやすいのでネジロック必須。

その後チャージングハンドル部分をはめ込み固定と言いたいところですが
マルイAK47同様この部分が脆いのは仕方ないね。
ま、トップカバー被せれば少しは気にならなくなるんですが、
こういう適当なところが我輩がマルイ製品から遠ざかった理由の一つではあります。
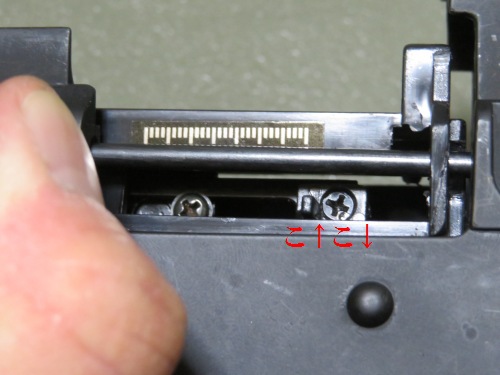
最後でもいいんですが忘れてはならない重要箇所。
ホップレバーを取り付けないと戦場でホップ調整が出来なくて泣きを見ます。

仕上げにトップカバーを取り付けて完成!
射撃してみたところ、初速はホップ最弱で88m/s、適正ホップで84m/sぐらい。
命中精度は15m程度なら直径10cm程度の木に当たるので上々でしょう。
発射サイクルは少しナマクラですが、弾は出てるから問題ない。
いやーしかし、18000円弱で買える電動ガンとは言ったものの
交換したインナーバレル2000円ぐらい、チャンバーパッキン360円、
タペットプレート500円、ピストンOリングやシムの金額や手間も考慮すると、
安い電動ガンとはいい難いシロモノですな。
コレがメタルフレームやマルイにはないモデルのCYMA製AKならば
マルイ製品よりも多少のアドヴァンテェジがあるんですが
素人は素直に次世代AK74買った方が性能的に無難です。
だってヤフオク見ていたら次世代AK74の中古、25000円ぐらいで買えるのね。
というわけでマルイのパーツが使えるという利点がありはしますが、
CYMA製プラフレームのAKはあまり手を出さないほうがよろしいかと。
カスタムベースに買うとしても既にカスタムされたモデル買う方が幸せになれそうです。
安物買いの銭失いとは昔の人は上手い事を言ったもんです。
大分手を入れたんで強気の10000円でヤフオクに出品してみたところ、
樹脂フレームの中華AKだからか予想通り全く盛り上がらずに
10000円で落札されてしまいましたがまあそんなもんでしょうね。
資産的価値にも乏しいという意味でもコイツは正直、買いじゃないですが、
落札者様の手元で無事に動き続けてくれることを切に願うばかりです。

余談ですがガーナ氏が認めたくない若さ故の過ちで購入したという
カスタムされたβスペツナズはコレまたノリで購入してしまった
マルイAK47 HCの外装と組み合わせてトンデモカスタムにしてしまいました。
長いサプレッサーが付いた外観は少しVSSっぽい気がしなくもない?

βスペツナズなのにAK74と同じぐらいの長さがあるというのは
タクティコウアドヴァンテェジ全く皆無ですが悪くはないでしょ?
でもやっぱり、中華電動ガンで数多くの魅力的なAKが出ているのを見ると、
お値段安く買えるとは言えどもβスペツナズはねぇなって思ふ。
ガーナ氏はあまりお気に召さなかったようなのでヤフオクに出したところ、
コイツは14500円で無事引き取られて逝きましたので、
両方の購入代金で新たに歪みねぇなAKを購入してあげましたが、
(実は本人の了解も得ずに勝手に商品を落札し、
その後に本人に連絡したという不届き者な我輩w)
そのAKに関しましてはまだ調整していないのでアップするのは後程。
ビリー・ヘリントンという方をご存知でしょうか?
大分前に“ガチムチパンツレスリング”という動画で一世を風靡した
アメリカのゲイポルノ俳優の名前なんですがね、
その人が3月2日に交通事故でお亡くなりになったそうです。
注釈:“ガチムチパンツレスリング”とは筋肉質の野郎2人がパンツ一丁で戦い合い、
先にパンツを脱がした方が勝ちというシンプルな漢(おとこ)の戦い。
肉薄する野郎同志の熱気と漢(おとこ)気が伝わる動画です。
実は我輩がニコニコ動画にハマったきっかけはガチムチパンツレスリング。
それ以来ニコニコ動画、いや、パンツレスリングの虜になってしまったというか、
ビリー・ヘリントン関連の動画を探す&鑑賞するのが楽しかったあの頃。
全裸でハーレー洗車している動画とか、ハーネス装着して悦に入る動画とか、
ノンケなのに野郎の裸が面白い&興味深いと思わされる動画が跳梁跋扈しており、
どの動画でもビリー・ヘリントンさんは男の魅力を輝かせていた。
今思えばあの頃が一番ニコニコ動画が輝いていた頃かもしれない。
でもビリー・ヘリントンさんの何が凄いってネタにされて笑われているというのに、
ニコニコのイベントに本人降臨して更に笑いを提供してくれたところですね。
その様はまさに「Mr.エンターテイナー」そしてMr.漢(おとこ)気。兄貴流石だぜ。
そんなビリー・ヘリントンさんが48歳でお亡くなりになったと言うのは
我輩的に実に惜しく、悲しい事態でございます。
この場を借りてご冥福を祈りたいと思います。
さて、本題に戻ってサバゲーの話、武器の話をしましょう。
今回紹介するのは中華製電動ガン、CYMAのAK74。
CYMAのAKシリーズはCM0◯◯(◯の中に数字が入る)で表されますが、
今回レビューするモデルはCM031という名称のブツで、
所謂“スポーツライン”と呼ばれている廉価版モデルでございます。

このブツの持ち主は我輩ではなく、宮崎では数少ないAK同志のガーナ氏。
具体的な購入金額は聞いていないのですが相場は18000円ぐらいの模様。
マルイの次世代じゃない電動ガンと同程度か、
ソレより少々安いぐらいの価格のようですが、
我輩ココ10年ぐらいマルイの新品電動ガン買ったこと無いからよく解らん。
CYMAといえば中華電動ガンの中では比較的安価で、
フルメタル&ウッドストックの外装を持つAK系列の電動ガンが有名ですが、
プラスチックのボディ&ストックの安い電動ガンも生産しており、
今回紹介するAK74、CM031もその安く手に入る電動ガンの一つ。
安価で入手可能ということで我輩も幾度となく購入を検討しておりましたが、
メタルボディのAKから先に手を出してしまったので
「いくら安くても樹脂製フレームはねぇ・・・」と思い購入には至らなかったが故に、
スポーツラインのAKに触れるのは今回が初体験でございます。
付属品は本体、マガジン、微妙に役に立たない説明書、クリーニングロッド、
そして性能的に微妙なニッスイミニバッテリーとノーマル充電器。
ペラペラのスリングが付属していたかどうかは不明ですが、要らんよなあんなの。

安いスポーツラインとは言え、パッと見た印象は案外悪くないんですよ。
シルエットは特にツッコミどころもなく、結構よく出来ております。
何処らへんがどう可笑しいみたいな部分は特に見られません。
フレームの仕上がりなんかもマルイAK47みたいな
テカテカした樹脂感漂うやつじゃなくてAKのHCみたいなマット調。
我輩も一見騙されましたもんね、メタルじゃないかって。

でも反対側を見ると瞬時にメタルフレームじゃないって解るんです。
だって最近のAKに必ず付属しているサイドマウントが無いんだもん。
そう、フレームが樹脂だからマウント付けると破損するんですね。仕方ないね。
だからCYMAの樹脂製ストックのAK74でも
メタルフレームのCM040とかになるとサイドマウントが付属しております。
但し、メタルフレームじゃなくてもAKの構成自体は
比較的頑丈なので想像するほどボディは軋みません。
マルイのAK47と同程度の剛性感は確保されております。

AK74の特徴である大げさなフラッシュハイダーは鉄製。
マルイAK47同様逆ネジで取り付けられております。
フロントサイトがやガスバイパスは亜鉛合金、
アウターバレルとクリーニングロッドは鉄製。
ボディが樹脂なのにアウターバレルが鉄なので結構フロントヘビーです。
因みに、フロントサイトを下から固定しているネジは緩みやすいので、
ネジロックを塗ってガッチリ固定しておかないと確実に紛失します。

ハンドガードは次世代AK74MNと同形状の樹脂製。
プラの質感は安っぽいですが、形は悪くない。
リアサイト周りはサイトも含めて亜鉛合金、
ハンドガードを固定するパーツは前が亜鉛で後ろが鉄。
ココらへんの構成、ていうか全てにおいてマルイAK47と同様の構成です。
だからマルイAK47対応の社外品ハンドガードなら取り付け可能です。

フレームは前述のように樹脂製、トップカバーは鉄製。
よく見ると金属フレームよりは見劣りしますね。だらしねぇな。
微妙にAK47と形状が違うトリガーガードとセレクターは鉄製です。
セレクターの固定はマルイAK47同様、
ネジで取り付けた上に蓋をかぶせるようになっているので、
この部分がAK74っぽくなくて残念な感じです。
そして何故かこのセレクター、カチッとしたクリック感がない。
フルに入れてもセミにしてもグラグラする。
グリップは当然樹脂製。
この部分に関してはLCTやハイエンドモデルのAKのものが使用可能。
フレーム形状がAK47とは異なるのでマルイAK47対応グリップは
付きませんというか、フレームとグリップの間に隙間が出来ます。

樹脂製ストックのモデルなので、ストックも当然樹脂。
そしてストックの蓋の部分も樹脂製です。
バッテリーの交換はマルイAK47同様、ストックの蓋をずらして蓋を開け、
ストック内にバッテリーを突っ込みます。
このストックの蓋が結構保持力が弱く、すぐに外れそうになります。
なおこの蓋の部分、マルイAK47のものは取り付けられません。
ストック内部は広いのでラージバッテリーも入りますが、
コネクタがミニ用なのでラージ用コネクタを別途購入する必要あり。
まあウナギバッテリー以外なら大抵収まるでしょう。

標準装備のマガジンは500連の多弾数マガジン。
AK系列のマガジンのお約束に漏れず、
1回の巻き上げで全てを撃ちつくすことは不可能。
300発ぐらい撃ったら再度巻き上げ必須です。
ただ、マガジンそのものの弾上がりに特に不具合はない模様。
CYMA製のマガジンは安い割には案外使えます。

トップカバーの中身もご覧のとおり、マルイAK47で見慣れた風景です。
チャージングハンドルが黒であること以外はマルイ製と完全互換。

この写真を見てマルイのAK47に精通しておられる方は気が付くでしょう。
マガジン突っ込む部分とその前に部分にフロント部分を固定するネジの存在に。
そう、全体の構成は完全にマルイAK47のパクリなんですね。
だから分解方法はマルイAK47と同様です。
だからCYMA製AK74の分解方法を敢えて載せる必要もないでしょう?

嫁を抱いた回数よりマルイのAK47をバラした回数の方が多いと豪語する我輩ですが、
実は嫁を抱いた回数の方が多いような気がしなくもありません。
そういうわけでマルイAK47に準じたCYMA製AK74(CM031)を分解するのも速攻です。
なお、メタルフレームのCYMA製AK74(CM040)やAK104は、
木製ストックのCM048とかと同じく分解方法になるのでココを見ても参考にはなりません。
ガーナ氏は箱出し状態で使用して不調になったと言うので、
(我輩的に中華エアガンを箱出しで使うなんて自殺行為に等しいのだがw)
メカボックス内部の点検清掃、部品交換、
そしてついでにチャンバーパッキンの交換を実施します。

しかしこのメカボックスがとんでもないシロモノでした。
色々と弄くり回すのに必死で写真を撮る余裕もない有様。
(メカボックス内を弄ると手がグリスまみれになるので、
精神的に余裕がある時じゃないと撮影は出来ない)
まず、セレクタープレートがガタガタ。道理でセレクターが落ち着かないわけだ。
原因はセレクタープレートの後ろの黒いやつがガバガバだった事。
手持ちのマルイAK47のものと交換したらカチッと動くようになりました。
メカボックスを開くと更に地獄を見ます。
とりあえず中華電動ガンお約束の緑グリスがべっとりは予想の範疇。
全てのパーツを取り出してブレーキパーツクリーナーで洗浄します。
モーターは無印ですがCYMAだから多分机モーター。
手持ちにAK用のモーターがないのでそのまま使いましょう。
サイクルは遅いけど必要にして充分です。
パワーダウンの為メインスプリングがぶった切られていたので、
ピーマン職人から貰ったSHSのM90スプリングと交換。
ピストンの気密がスカスカだったのでピストンのOリングはマルイ純正と交換。
透明樹脂のノズルは気に入らないけどそのまま使用。
ピストンヘッドはまあ普通だったんでそのまま使用。
ギア類も特に不具合なさそうだったのでそのまま使用。
スプリングガイドは何の変哲もないやつだったけど、マルイ純正と交換。
白い樹脂製のタペットプレートは削れていたんでマルイ純正と交換。
その後各ギアに付属していたシムをそのままセッティングし、
メカボックスを閉じてネジを締めてシムの具合を確認と・・・
何か中ですっごいカタカタするんですが?
よく見てみるとシムが足りなくて全てのギアが遊んでいる状態。
確かに、シムはどのポジションも薄いのが1枚しか入っていなかったな。
というわけで全てのギアにシムを追加し、セクターは両側に厚みのあるやつ入れたら、
どーにかいい塩梅になったんでグリスアップして組み込み。

CYMA製AK74(CM031)の分解方法がマルイAK47と同様ということは、
組み立て方の手順もマルイAK47と同様ということ。
マルイAK47同様、ドライバーで挿している部分の配線が上手く収まるように、
そして後方への配線がストック取り付け部分に収まるように注意しながら
丁寧にメカボックスをフレーム内に収めます。

フレーム内にメカボックスを突っ込んだらグリップを取り付けて固定し、
セレクタープレートを取り付けます。

その後ストック配線を取り付け、ストックをネジで固定します。
ココのネジも緩みやすいのでネジロックを塗ってねじ込みます。

フロント部分を取り付ける前に、バレルとチャンバーを確認。
案の定、チャンバーパッキンは質感が悪いのでマルイ製と交換。
インナーバレルも見た目が汚すぎるので、マルイAK47のと交換。
中古のバレルですがこのだらしねぇバレルよりはマシでしょう。
欲を言えばチャンバーも交換したいところですが、余剰のパーツがない。
元々の命中精度がどんだけのものであるかは不明ですが、
ココを交換するだけで大分マルイ製品に近い性能になるのは
過去の経験から実証済なので迷わず交換してしまいます。

バレルとチャンバーパッキンを交換したら速やかに元に戻し、
写真で示している部分のバネを紛失しないように気をつけながら、
フロント周りとフレームを合体させます。

そしてフレーム下側から4本のネジで固定。
デフォルトではアレンレンチで締め込むネジだったようですが、
紛失していたので手元にあるステンレスネジと交換。
勿論、ココも紛失しやすいのでネジロック必須。

その後チャージングハンドル部分をはめ込み固定と言いたいところですが
マルイAK47同様この部分が脆いのは仕方ないね。
ま、トップカバー被せれば少しは気にならなくなるんですが、
こういう適当なところが我輩がマルイ製品から遠ざかった理由の一つではあります。
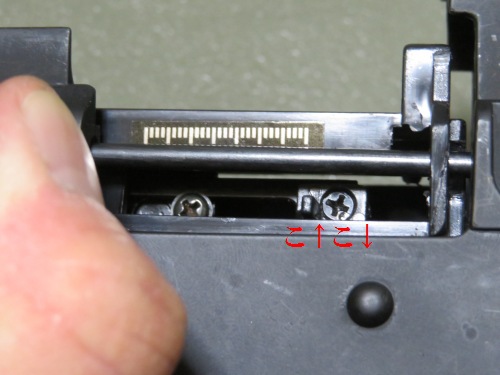
最後でもいいんですが忘れてはならない重要箇所。
ホップレバーを取り付けないと戦場でホップ調整が出来なくて泣きを見ます。

仕上げにトップカバーを取り付けて完成!
射撃してみたところ、初速はホップ最弱で88m/s、適正ホップで84m/sぐらい。
命中精度は15m程度なら直径10cm程度の木に当たるので上々でしょう。
発射サイクルは少しナマクラですが、弾は出てるから問題ない。
いやーしかし、18000円弱で買える電動ガンとは言ったものの
交換したインナーバレル2000円ぐらい、チャンバーパッキン360円、
タペットプレート500円、ピストンOリングやシムの金額や手間も考慮すると、
安い電動ガンとはいい難いシロモノですな。
コレがメタルフレームやマルイにはないモデルのCYMA製AKならば
マルイ製品よりも多少のアドヴァンテェジがあるんですが
素人は素直に次世代AK74買った方が性能的に無難です。
だってヤフオク見ていたら次世代AK74の中古、25000円ぐらいで買えるのね。
というわけでマルイのパーツが使えるという利点がありはしますが、
CYMA製プラフレームのAKはあまり手を出さないほうがよろしいかと。
カスタムベースに買うとしても既にカスタムされたモデル買う方が幸せになれそうです。
安物買いの銭失いとは昔の人は上手い事を言ったもんです。
大分手を入れたんで強気の10000円でヤフオクに出品してみたところ、
樹脂フレームの中華AKだからか予想通り全く盛り上がらずに
10000円で落札されてしまいましたがまあそんなもんでしょうね。
資産的価値にも乏しいという意味でもコイツは正直、買いじゃないですが、
落札者様の手元で無事に動き続けてくれることを切に願うばかりです。

余談ですがガーナ氏が認めたくない若さ故の過ちで購入したという
カスタムされたβスペツナズはコレまたノリで購入してしまった
マルイAK47 HCの外装と組み合わせてトンデモカスタムにしてしまいました。
長いサプレッサーが付いた外観は少しVSSっぽい気がしなくもない?

βスペツナズなのにAK74と同じぐらいの長さがあるというのは
タクティコウアドヴァンテェジ全く皆無ですが悪くはないでしょ?
でもやっぱり、中華電動ガンで数多くの魅力的なAKが出ているのを見ると、
お値段安く買えるとは言えどもβスペツナズはねぇなって思ふ。
ガーナ氏はあまりお気に召さなかったようなのでヤフオクに出したところ、
コイツは14500円で無事引き取られて逝きましたので、
両方の購入代金で新たに歪みねぇなAKを購入してあげましたが、
(実は本人の了解も得ずに勝手に商品を落札し、
その後に本人に連絡したという不届き者な我輩w)
そのAKに関しましてはまだ調整していないのでアップするのは後程。
2017年11月18日
日本の漢(おとこ)の魂、三八式歩兵銃
こないだ、3週間程度の研修期間を終えて宮崎に戻ってきた砥部良軍曹です。
そこで本来ならば研修時の行動とかをココに綴るべきなのでしょうが、
帰還後直ぐ様それどころではない代物が手元に届いたので、
そいつの紹介を実施しなければ(使命感)!ということになりました。
ま、ここは本来サバゲーのブログなんだから、
エアガンのレビューを優先することに何ら不具合はなかろう。
というわけで興味のある方だけ入って、どうぞ。

ずっと欲しくて仕方がなかった、日本男児の魂。
S&Tのエアコキ三八式歩兵銃!
気になるお値段はショップ割引価格で大体税込み38000円ぐらい。
我輩はフォースター初期ロット予約特価で購入したので少し安く仕入れました。
マニアックな代物を世に送り出す事で定評がある
(但し、外観や性能が良いわけではない)中華エアガンメーカーS&Tが
三八式歩兵銃発売のアナウンスを出してから半年経った今、
(その間、2回ぐらい発売延期のメールが来てデカ枕を涙で濡らしたのは言うまでもなかろう)
ようやく我輩の手元に届きやがりましたよ全く。
S&Tの三八式歩兵銃のレビューにどんだけ需要があるか不明ですが、
旧日本軍の出で立ちでサバゲーするわけじゃなくても、
この存在感や佇まいに惚れたとか言う理由で購入した方も居られることでしょう。

三八式歩兵銃が何物であるかを今更説明する必要は無いでしょうが
最近のサバゲーフィールドではM4カービンやMP5ぐらいしか
知らねぇよーな軟弱なプレイヤーが多数散見されるので
一応記載しておきますと旧日本軍が日露戦争後から太平洋戦争終結まで
歩兵の主力武器として使っていたボルトアクションライフルです。
よく戦争を知らない無知な連中が「日本軍は旧式の鉄砲でアメリカと戦争していた」
とのたまうのを耳にすることがありますがそれはとんだ勘違い。
第二時世界大戦当時でも自動小銃を正式化していたのは工業大国のアメリカだけ。
アメリカ以外の歩兵は三八式のような連発不可能なボルトアクションで戦っていたんです。
三八式という名称(明治38年、西暦1905年)から古い鉄砲と言う誤解があるのでしょうが、
ナチス・ドイツが使用していたモーゼルKar98kは
基本はGewehr 98という1898年採用のライフルですし、
ソビエト赤軍が使用していたモシン・ナガンなんかは1891年。
イギリスのリー・エンフィールドも初期型は1895年の採用だから
38式歩兵銃が特別古い銃でないことはお解りでしょうかね?
尚、アメリカが第一次世界大戦で使っていたボルトアクションライフルは
スプリングフィールド1903、つまり三八式よりも2年古い。

まあ旧日本軍の場合、連発でばら撒ける量の弾を作る施設と設備と資源に乏しいという時点で
明らかすぎるぐらいにアメリカとの間に越えられない壁があったが故に
連発可能なライフルやサブマシンガンを大量に持てなかったと亡き父上が言っておりました。
三八式歩兵銃と言えばだいぶん前からKTWが販売しているのですが、
高級感溢れる造りでコレクション的価値を有するKTW製とは違い、
S&T製はあくまでもゲームユースに重点を置いた作りとなっております。
まあ要するに全体的な作りは明らかに安っぽいということ。
ま、KTW製三八式はお値段2パットン以上なのに対し、
(注:パットンとは吉六会内でのエアガンの価格を表す単位で、1パットン=50000円である)
0.7パットン程度で購入可能なS&T製三八式に過度なクオリティを求めるのも酷な話です。
(2期ロット以降からは値上がりして1パットン近い価格で販売されている)
とは言え、昔の「弾が出る程度の能力」のエアガンと比べると出来はよろしいですし、
ホンモノを見たことがないので何処がどういう風に駄目なのかはよく判らんのですよ。

しっかしねぇ、解っちゃいたけど改めて見ると長いですねぇ、三八式。
我輩所有のエアガンで一番長いSVDよりも10cmぐらい長いんじゃねぇかい?
でもこの「銃剣突撃を考慮した」長さこそが三八式。
とはいえ、120cm以上のライフルを収めるライフルケースってなかなか手に入らない。
着剣してロマンに馳せる為に三十年式銃剣も一緒に欲しくなりますが、
安全性の点から考えて着剣突撃はサバゲーではご法度ですし、
大抵のフィールドでは銃剣ぶら下げての参戦も不可みたいなので叶わぬ思いに終わる事です。

基本的にS&T製三八式歩兵銃の材質はストックが木製、
それ以外は全て金属製となっております。
なのでマズル部分も金属製です。ダイキャストですが。
照星(フロントサイト)部分に少々残念なバリも残っています。
でもね、バリぐらいならヤスリで削ってど~にか出来ん事もないですが、
この特徴的な照星のガード部分、木とか石にぶつけたら折れそうで怖い。

アウターバレルは黒塗りのアルミ製のようで、仕上がりはまぁまぁキレイ。
しかもこのアウターバレル内径、インナーバレル外形とほぼ同じ。
だからインナーバレルがカタカタしないのは中華製にしては驚き。
但しアウターバレル自体はガタガタしやがるので、
ストックとバレルの間に何やら詰め物をする必要はありそうですな。
余談ですが銃身下の洗い矢(クリーニングロッド)はダミーです。(しかも仕上げが汚い)

ストックの塗りは全体で見ると一見キレイですが、
よく見ると各部にこんな感じの塗料がだららんとした残念ポイントが。
そして何故かこのストックに塗られている塗料、
不自然なぐらいに感触がツルツルスベスベなんですね。
我輩的にツルンツルンが嬉しいのはおなごの肌だけです。
そしてストックの木か、塗料のせいか知らんけど「くさそう」ではなく「くさい」。

旧日本軍の小銃らしい特徴的な作りの照門(リアサイト)もダイキャスト製。
V字ノッチの整形にシャープさが足りないのか、AKのリアサイト程狙いやすくない。
勿論、照門を立てて対空サイトとして使用することも可能です。
サバゲーではまず使わない機能ですがコレがあるだけでメーカーのやる気は感じます。
こう言う弾の発射やエアガンの性能に直結しない機能を蔑ろにしない姿勢は
喩えるならばおなごが後々脱がされるの解っている、或いは見せもしないだろうに、
デェトにセクスィな下着を着用する行為のよ~なもんですな?
リアサイトの後ろにあるイモネジはホップ調整用。
このネジがまぁ、随分グラグラするんですねぇ。
明らかに射撃の衝撃でホップが緩みそうなぐらいグラグラです。
コレは戦闘中に紛失する恐れも微レ存?

S&Tの三八式は遊底覆(ダストカバー)が標準装備。
実銃ではコイツの存在について賛否両論ですが、
エアガンの場合は・・・別に必要性を感じないよ~な気がする。
当然ですが遊底覆はココらへん周りを分解しないと外せません。
槓桿(ボルト)のコッキング時のストロークは短く、70mmぐらい。
我輩はボルトハンドルを真上に立ててコッキングするボルトアクションライフルを
所有するのが人生初なので少し戸惑いましたが慣れると素早い装填が出来る模様。

安全子(セイフティ)は写真の状態が発射状態。
コイツをダイレクトに押し込んで時計回りに45度回し、
尖った部分が上を向くと安全状態。
尚、コッキングしないとセイフティは動きません。
コレが結構動きが軽く、使いやすいんだな。
余談ですがコッキングの後ボルトハンドルがうまく倒れてくれない時、
ここを押し込むとボルトが“パタン!”と倒れてくれます。

銃把、床尾部分に関しては「まあ、こんなもんでしょ」。
でも実銃のようにストックの上下貼り合わせを再現しているのは良し。
たださっきも言ったように、何か臭うし、ツルツル感が不自然。
あと、床尾板は材質はともかく作りは結構キレイなんですがね、
立て銃を繰り返していると次第に傷だらけになるんだろうな。

S&T製三八式歩兵銃の最大の利点であり、
難点なのがこの弾倉システム。
着脱型マガジン方式はゲームユースには有利だけど、
外観のリアルさという点において「ふざけんな!(声だけ迫真)」。
だがしかし、我輩的にはサバゲーでバンバン撃ちまくりたいのでこのデフォルメは大歓迎。
弾倉交換が出来るからマガジン内蔵式のKTW製三八式より
戦闘中の素早いリロードが出来はしますがこの弾倉結構取り出しにくい。
尚、マガジンリップがある方が後ろ(ボルト側)になります。
箱型マガジンの装弾数は26発。長さは8.5cmぐらい。
9mmパラハンドガンのマガジンポーチには収まりそうだけど、
サバゲーで三八式を使う輩がナイロン装備を使うのかと小一時間問い詰めたい。
ま、我輩は陸自迷彩でこいつを使うつもりなのでハンドガンマグポーチに入れるんですがね。
三八式用の箱みたいな弾納、アレの中の仕切りがなければ、
弾納1つに2マガジンは収まりそうな予感だけど、ね。
尚、この弾倉、銃装着状態で少し飛び出ているのがイラッとする。
でもこの弾倉装着部分が丁度左手を添える部分になるので、
丁度隠れてしまっていい感じになるから気にしないことにします。

本来の弾倉がある部分は一体成型になっており、可動しません。
そして誇らしげに「メイドインチャイナ」と書かれているのが癪ですが、
三八式をコレだけリーズナブルに出してくれるエアガンメーカーなんて、
中国ぐらいしか無いんだろうから仕方ないね。
尚、弾倉の蓋が開かないので、用心鉄(トリガーガード)前方のアレもダミー。

三八式の刻印と菊のご紋もしっかり再現されておりますが、
我輩の個体は菊の御紋に傷が入っているのが悲しい。
中華エアガンは新品の時点で結構傷が入っているもんなんですが、
菊の御紋に傷がついているのは天皇陛下に申し訳がない。
とまあ、所々出来栄えに首を傾げたくなる部分はあるものの、
比較的入手しやすい価格帯でサバゲーで使える三八式歩兵銃としては
なかなか良く出来たもんじゃなかろうかというのが我輩の感想です。
しかし、いざ弾を詰めて撃ってみると、
性能的に少々難があることが判明したのです。
まず着脱可能な箱型弾倉、コレ案外弾詰めるのに手間取る。
マルイのBBローダーで入れられないことはないですが、
リップを指でしっかり押さえとかないとなかなか弾がマガジンに収まりません。
ボルトのテンションは少々重めですが、後退距離は短いので、
素早く引きにくいと言うほどでもなく、まあ許せる範囲かな。
トリガープルは少々重めですが、遊びが少なくストロークが短くて素直に落ちます。
初速はG&Gの0.2gバイオ弾使用時、
ノンホップで90~95m/sぐらい、適正ホップで88~80m/sぐらい、
弾が浮き上がるぐらいだと75~68m/sとかなりバラツキがあります。
命中精度は15m先の直径5cmの柱に当たるか当たらないかというレベル。
そして時々、明らかに着弾がズレております。
一回の発射で2〜3億を放出可能な股間の鉄砲と違って
連射が出来ない分1発必中が必須のボルトアクションにおいて、
このバラツキのある発射性能はある意味致命傷です。

まあ中華エアガンが箱出しで使えるなんて幻想は抱いておりませんでしたので、
S&T製三八式歩兵銃、分解してみることにしたのですが、
こないだ販売したばかりのエアガンの分解方法なんてググっても出てきやしません。
仕方がないので先っちょから手当たり次第にバラしてみることにしました。
まずはフロント周りから分解。
ダミーのクリーニングロッド先端にマイナスドライバーを差し込み、
捻ってグリグリして外すと前回りが外れます。

実は分解をするに辺り、この作業を先にヤるべきなのですが、
フロントサイトを横からポンチとかで軽く叩いて外し、
その下に隠れているイモネジを緩めてフロントサイトを
ハンマーでコツコツ叩けばマズル部分が外れます。
コレを先にヤラないと前回り部分が完全に外れません。

次は被筒部分を固定しているバンドを外すため、
写真のようにしてスプリングを押さえて前に抜きます。
ココで雑にリングを外そうとするとストックに傷が入るのでご注意。
外れたバンドは速やかに前に抜いてしまいましょう。

トリガーガードの前後のボルトを緩めると、機関部がストックから分離します。
ココらへんの作りは一般的なボルトアクションと同じですね。

機関部を取り出すのに必要はありませんが、
ストックの塗り直しをするために他の付属品もボルトを緩めて外します。

フロント部のダミークリーニングロッド固定部分は
ストックにしっかりと食い込んでくっついており、
ドライバーの先でこじってようやく外れました。
ま、機関部整備のための分解なら外さなくてもおk。

ストック前方部分はちっこい木ネジで固定されております。
コレが多少グラグラするのが気になるので、
ネジを交換するか、後から接着剤で固定することを検討しましょう。
我輩はネジを3mm程長いものと交換して固定をガッチリさせました。

ストック塗り直しのため、バットプレートも取り外してしまいます。
余談ですが各部のネジはマイナスで見た目にはリアルなのですが、
ネジの頭にバリが多くて少しイラッとします。
後々服に引っかからないように、ネジの頭のバリをヤスリで削っておきます。

ココからが機関部へのアクセスとなります。
マガジンハウジングは2本の6角ネジで固定されているので、緩めて外します。
ココを外さないとチャンバーにアクセス出来ません。
でもマガジンハウジング後方の銀色のプレート部分は、
別に外さなくてもシリンダーやチャンバーに影響はないのでございます。

引き金室部(トリガー部分)は2本のネジで固定されているので、
緩めたら直ぐ外れますが、「アレ?シリンダーの固定ピンは何処にあるの?」
我輩的常識だと、トリガーASSY外せばシリンダーが抜けるはずなんだけど・・・

もしかしてと思ってシリンダーのサイドにある
実銃ならシリンダー開放ラッチと思しき部分の蓋を緩め、
中の2本のクロスネジを緩めたらピン状の物体が外れてシリンダーが抜けました。
ダストカバー(遊底覆)を外す場合はココまでバラせば外せます。

チャンバーへのアクセスにはリアサイトを分解する必要があります。
リアサイト前方のマイナスネジを緩めて、リーフスプリングとリアサイトASSYを外します。

その後リアサイトに隠れていた小さい4本のネジを緩めると、
半分だけパカっと割れてチャンバーがお目見えになります。
この時にアウターバレルも一緒に外れます。
ていうかS&Tの三八式、チャンバーASSY的なものが無くて、
本体がそのままチャンバーになっているのに驚き。
しかし三八式の細い銃身にチャンバーを収めるとなると、こうなってしまうんでしょうね、

尚、チャンバーの構成はこのようになっております。
リアサイトから露出しているイモネジがチャンバーパッキンの上にある
小さい四角いゴム板を押さえながらホップを掛けるという仕組み。
ホップパッキンはVSR-10のものとほぼ変わらない形状ではあるものの、
パッキンのゴムの厚みが微妙に厚みがあり、
尚且つホップの突起がVSRのものより出っ張っています。
インナーバレルは600mmとかなりの長さです。
それでもインナーバレルの先端はマズルより大分奥にあるので、
インナーをギリギリまで伸ばそうと思えば650mmぐらいまでイケるはずです。
(因みにSVDやRPKのインナーバレルが650mmサイズ)
インナーバレルはVSRやL96等マルイボルトアクションのものが流用可能ですが、
オリジナルやカスタムパーツで同サイズのインナーバレルは存在しない模様。
しかしながらS&T製三八式はアウターバレル内部に段差がないので、
短いインナーバレルを突っ込んで組み上げることも可能です。

シリンダーの構成はこんな感じです。
パッと見た時点でマルイ製ボルトアクションとの互換性、ナシですな。
シリンダー長173mm、直径25.4mm、内径23.5mmで真鍮製、
しかも黒く塗っているだけで所々色剥げてる。
なるほど、この真鍮のシリンダーを隠すために遊底覆が付属しているのか?
そしてこのシリンダー、今まで見たこと無いぐらい肉厚。
ノズルは明らかにVSRより長スギィ!互換性のあるパーツなさそう。
アルミ製の黒いピストンもVSRのものより短く(長さ73mm)、
スプリングガイドも見たことない形状で短い(長さ68mm)。
スプリングはVSRと電動ガンの間ぐらいの直径(外形12mm)。
シリンダー周りは特に交換すべきものが見当たらなかったし、
Oリングの気密も取れていたのでそのまま使用することにします。
ていうかピストンのOリング、メッチャキツキツなんですけど大丈夫なんかコレ?
試しに手元にあったVSR用のOリングブチ込んだら
何ということでしょう、Oリング自体が細すぎてスカスカでした。
追記:ピストンのOリングがキツイために油が切れるとシリンダーにピストンが引っかかって
初速が40m/sぐらいに低下するので小まめにシリンダーにシリコンオイルを注油が必須です。
更に追記:2ロット以降の製品ではOリングは丁度いいサイズに変更されていました。
我輩的に気に入らないのはシリンダー内部の塗装。
剥げた塗料が後々、作動や精度に影響を及ぼしそうですからね。
というわけでシリンダー内側の色落としのために全バラ実施。
エンドボスを固定している割りピンをポンチで叩いてみたところ、
何ということでしょう、この割りピン貫通式じゃなくてはめ殺し式だ。
よーするに長い割りピン1本で固定しているんじゃなくて、
シリンダーの両サイドから短い割りピンで固定しているんで、
いくらポンチで叩いても抜けないわ奥に押し込まれて袋小路。

結局、ステンレス用ドリルの刃を購入してきて、
ピンごとガリガリぶち抜いてエンドボスのピンがハマる穴を削りましたよ。
そして手元にあった適当な長さと太さのピンを打ち込み直して修復。
というわけで、S&T製三八式のエンドボスには手を出すな!
ま、この部分は外す必然性も特に無いんで触らぬ神に祟りなし。
とりあえずシリンダーの後ろからアルミパイプに巻き付けたサンドペーパー突っ込んで、
シリンダー内部を磨いた後にピカールでしごきましたが作動性はそこまで変わらず。

トリガーASSYはどう見ても独自設計で明らか過ぎるほどに従来の既製品が使えない模様。
トリガープルの調整とかいった機能は全くございません。

蓋を開けてみると驚くほどシンプルな設計に驚き。
そしてトリガープルは全てがトリガースプリングに依存していることも判明。
この分だとシアとかのパーツを磨いたところで
トリガータッチの改善は望めそうにありませんので終了。

とりあえず、難がある部分を探しながら機関部を色々舐め回すように見たところ、
チャンバーパッキンのホップの出っ張り部分が削れていました。
なのでパッキンはVSR純正のものと交換。やっぱゴムは日本製が一番ですよ。
しかしVSRのチャンバーパッキン、ノズルが入る部分の内径が太い。
(右がS&Tの、左がVSRのチャンバーパッキン)
要するにガバマン状態で気密もへったくれもあったもんじゃないのです。
とりあえずそのまま組みこんでパワーを測ってみたところ、55m/sぐらいに激減。

やはり、ノズルとチャンバーの気密って重要なんですねということで、
ノズルの直径をアップするいい方法がなかろうかと思案した挙句、
直径6mmの収縮チューブを被せることにしました。
ただ、そのまま被せてもパッキンにハマって抜けてしまうので、
ノズル表面をある程度サンドペーパーでザラザラにして、
アロンアルファを塗って収縮チューブを先端から2mm程はみ出るぐらい被せ、
その後ライターで軽く炙って密着させて仕上げました。
この加工によってパワーは元通りになったのですが、
給弾する度にノズルのチューブが弾と当たってダメージを受けるのが気になるところ。
絶対コレ、後々チューブがズルムケになるよ。
追記:仕入れ先のフォースターにVSRパッキン対応のシリンダーノズルが売っていたので
迷う事なく購入して組み込んだら、精度もパワーも上がって幸せです。
なお、2ロット以降は既にこのパーツが組み込まれている模様なので、
マルイVSR用パッキンが安心して使えます。

インナーバレルは内部に謎の汚れがあったので、
サンドペーパーで落としてピカールで磨いて処置。
金があればPDIとかのロングインナーバレルを組みたいところですが、
我輩の手持ちの予算は本体と予備マガジン買うので精一杯なので保留。
ホップ調整用のイモネジはM3の頭付きのネジと交換。
ネジ山には緩み止めを塗り、容易にネジが回らないようにしました。
尚、組みたてる時は写真のようにして合わせてから組み上げると、
内部でパッキンが捩れることも少ないですし、キレイに収まります。

ストックは軍用銃に似つかわしくない安物家具のような
スベスベ感が気に入らないのでワトコオイルで再塗装することを決意。
120番のサンドペーパーで1時間掛けて色を剥がし、
「すっげぇ白くなってる、はっきりわかんだね」状態にしてしまいました。
そしたら何ということでしょう、ストックの材質がよろしくないのか、
色んな所にひび割れみたいなのが入っていて泣きそうになります。

晴天の空のもとでワトコオイルのマホガニーを塗り、
1~2時間ぐらい乾かしたら染み込まなかった分をウエスで拭き取ってまた色塗り、
コレを4回ほど繰り返して色濃く仕上げてみましたが、
もう少し黒っぽい、ウォールナットの色で仕上げた方が良かったかな?
しかし少なくとも以前のような変な臭い匂いは消えましたし、
色合い的にも我輩好みの良い感じに仕上がって気分がいいです。
そして何より、ストックの細かいひび割れが埋まっていい感じ。
ワトコオイルに含まれている亜麻仁油は木部に浸透して
繊維をつぶして硬化するらしいのでそれが功を奏しているのでしょう。

こうして、気になる部分を予算の範囲内で弄くり回し、
ボルト操作時にカチャカチャ五月蝿い遊底覆を外して再度組み直した結果、
フライヤーはなくなり、それなりに素直な弾道で弾が飛ぶようになりました。
コレならサバゲーで敵の指先は狙えなくても、顔面ぐらいは狙えそうです。
でもやはり、VSRとかL96といったようなマルイ製ボルトアクションと比べると、
インパクト以外では勝負にならないというのが正直なところでしょう。
まあ我輩的には命中精度なんて二の次三の次、
この木の温もりと金属の冷たさの融合がたまらんのですがね。
そしてこの三八式歩兵銃が醸し出す独特の世界観、コレがたまらん。
正確には三八式歩兵銃に合う軍装は旧日本軍一択なんでしょうが、
我輩的にはブラックパジャマで三八式というのも悪くないと思いますし、
(ていうか元々ベトコン装備時のエアコキ限定戦の武器として購入した)
ポリシーもアイデンティティも考慮せずに自衛隊装備でこれもアリかなと?
今更旧軍装備揃えるのも銭と労力がかかるでしょうしなぁ。
マルイ製ボルトアクションと比べると造りが大雑把で、
パーツの互換も全くと行っていいほど存在せず、
各部の改修の余地も少ないS&T製三八式歩兵銃。
当たりの個体を手にすればそのままでも充分使えるかもしれませんが、
我輩みたくパッキンがバカになったものを手にした場合は多少の改修は必要ですし、
もっと性能を高めるには結構な創作意欲と知識と技術を要するので、
万人向けとは言い難いですし、そうそうお勧めできるものではありません。
しかしながら電動ガン買うぐらいのお値段で旧日本軍の魂的存在が
手に入るというのは嬉しい事態であることもまた事実。
そしてそういうエアガンを中国が販売してしまったというのもおかしな話ですが、
ソコは中国人の(いい意味での)厚かましさ、商魂逞しさというべきなんでしょう。
この勢いでS&Tには次回作として九九式小銃か、四四式騎銃を出していただきたい!

追記:四四式は出してくれませんでしたが、三八式機銃が出たので三八式を売り払って購入。
コレで長めのガンケースに収めてサバゲーに持っていけるようになりましたし、
何より短くて使いやすい(個人の感想)。
なお余談ではなく重要事項なので言っておきますが、三八式騎兵銃ではなく「三八式機銃」です。
とりあえずバラして中を確認(分解方法は三八式も三八式騎銃も全く同じ)。
そしたらびっくり、インナーバレルがアルミになっちょっど!
道理で箱出し精度がイマイチなはずだ。
仕方がないのでヤフオクでVSR10のノーマルインナーバレルを2000円ぐらいで仕入れ、
行きつけのショップでチャンバーパッキンも買って来て組み込みました。
ピストンのOリングは三八式程キツキツではなく、気密もバッチリなんですが、
スプリングそのままだと初速が85m/sぐらいと少し物足りないかったので、
PDIのVSR10用の不等ピッチスプリング(太径) 430mmバレル専用を組み込み。
コレで0.2g弾での初速は88m/s、命中精度もだいぶん良くなったんでヨシとします。
そこで本来ならば研修時の行動とかをココに綴るべきなのでしょうが、
帰還後直ぐ様それどころではない代物が手元に届いたので、
そいつの紹介を実施しなければ(使命感)!ということになりました。
ま、ここは本来サバゲーのブログなんだから、
エアガンのレビューを優先することに何ら不具合はなかろう。
というわけで興味のある方だけ入って、どうぞ。

ずっと欲しくて仕方がなかった、日本男児の魂。
S&Tのエアコキ三八式歩兵銃!
気になるお値段はショップ割引価格で大体税込み38000円ぐらい。
我輩はフォースター初期ロット予約特価で購入したので少し安く仕入れました。
マニアックな代物を世に送り出す事で定評がある
(但し、外観や性能が良いわけではない)中華エアガンメーカーS&Tが
三八式歩兵銃発売のアナウンスを出してから半年経った今、
(その間、2回ぐらい発売延期のメールが来てデカ枕を涙で濡らしたのは言うまでもなかろう)
ようやく我輩の手元に届きやがりましたよ全く。
S&Tの三八式歩兵銃のレビューにどんだけ需要があるか不明ですが、
旧日本軍の出で立ちでサバゲーするわけじゃなくても、
この存在感や佇まいに惚れたとか言う理由で購入した方も居られることでしょう。

三八式歩兵銃が何物であるかを今更説明する必要は無いでしょうが
最近のサバゲーフィールドではM4カービンやMP5ぐらいしか
知らねぇよーな軟弱なプレイヤーが多数散見されるので
一応記載しておきますと旧日本軍が日露戦争後から太平洋戦争終結まで
歩兵の主力武器として使っていたボルトアクションライフルです。
よく戦争を知らない無知な連中が「日本軍は旧式の鉄砲でアメリカと戦争していた」
とのたまうのを耳にすることがありますがそれはとんだ勘違い。
第二時世界大戦当時でも自動小銃を正式化していたのは工業大国のアメリカだけ。
アメリカ以外の歩兵は三八式のような連発不可能なボルトアクションで戦っていたんです。
三八式という名称(明治38年、西暦1905年)から古い鉄砲と言う誤解があるのでしょうが、
ナチス・ドイツが使用していたモーゼルKar98kは
基本はGewehr 98という1898年採用のライフルですし、
ソビエト赤軍が使用していたモシン・ナガンなんかは1891年。
イギリスのリー・エンフィールドも初期型は1895年の採用だから
38式歩兵銃が特別古い銃でないことはお解りでしょうかね?
尚、アメリカが第一次世界大戦で使っていたボルトアクションライフルは
スプリングフィールド1903、つまり三八式よりも2年古い。

まあ旧日本軍の場合、連発でばら撒ける量の弾を作る施設と設備と資源に乏しいという時点で
明らかすぎるぐらいにアメリカとの間に越えられない壁があったが故に
連発可能なライフルやサブマシンガンを大量に持てなかったと亡き父上が言っておりました。
三八式歩兵銃と言えばだいぶん前からKTWが販売しているのですが、
高級感溢れる造りでコレクション的価値を有するKTW製とは違い、
S&T製はあくまでもゲームユースに重点を置いた作りとなっております。
まあ要するに全体的な作りは明らかに安っぽいということ。
ま、KTW製三八式はお値段2パットン以上なのに対し、
(注:パットンとは吉六会内でのエアガンの価格を表す単位で、1パットン=50000円である)
0.7パットン程度で購入可能なS&T製三八式に過度なクオリティを求めるのも酷な話です。
(2期ロット以降からは値上がりして1パットン近い価格で販売されている)
とは言え、昔の「弾が出る程度の能力」のエアガンと比べると出来はよろしいですし、
ホンモノを見たことがないので何処がどういう風に駄目なのかはよく判らんのですよ。

しっかしねぇ、解っちゃいたけど改めて見ると長いですねぇ、三八式。
我輩所有のエアガンで一番長いSVDよりも10cmぐらい長いんじゃねぇかい?
でもこの「銃剣突撃を考慮した」長さこそが三八式。
とはいえ、120cm以上のライフルを収めるライフルケースってなかなか手に入らない。
着剣してロマンに馳せる為に三十年式銃剣も一緒に欲しくなりますが、
安全性の点から考えて着剣突撃はサバゲーではご法度ですし、
大抵のフィールドでは銃剣ぶら下げての参戦も不可みたいなので叶わぬ思いに終わる事です。

基本的にS&T製三八式歩兵銃の材質はストックが木製、
それ以外は全て金属製となっております。
なのでマズル部分も金属製です。ダイキャストですが。
照星(フロントサイト)部分に少々残念なバリも残っています。
でもね、バリぐらいならヤスリで削ってど~にか出来ん事もないですが、
この特徴的な照星のガード部分、木とか石にぶつけたら折れそうで怖い。

アウターバレルは黒塗りのアルミ製のようで、仕上がりはまぁまぁキレイ。
しかもこのアウターバレル内径、インナーバレル外形とほぼ同じ。
だからインナーバレルがカタカタしないのは中華製にしては驚き。
但しアウターバレル自体はガタガタしやがるので、
ストックとバレルの間に何やら詰め物をする必要はありそうですな。
余談ですが銃身下の洗い矢(クリーニングロッド)はダミーです。(しかも仕上げが汚い)

ストックの塗りは全体で見ると一見キレイですが、
よく見ると各部にこんな感じの塗料がだららんとした残念ポイントが。
そして何故かこのストックに塗られている塗料、
不自然なぐらいに感触がツルツルスベスベなんですね。
我輩的にツルンツルンが嬉しいのはおなごの肌だけです。
そしてストックの木か、塗料のせいか知らんけど「くさそう」ではなく「くさい」。

旧日本軍の小銃らしい特徴的な作りの照門(リアサイト)もダイキャスト製。
V字ノッチの整形にシャープさが足りないのか、AKのリアサイト程狙いやすくない。
勿論、照門を立てて対空サイトとして使用することも可能です。
サバゲーではまず使わない機能ですがコレがあるだけでメーカーのやる気は感じます。
こう言う弾の発射やエアガンの性能に直結しない機能を蔑ろにしない姿勢は
喩えるならばおなごが後々脱がされるの解っている、或いは見せもしないだろうに、
デェトにセクスィな下着を着用する行為のよ~なもんですな?
リアサイトの後ろにあるイモネジはホップ調整用。
このネジがまぁ、随分グラグラするんですねぇ。
明らかに射撃の衝撃でホップが緩みそうなぐらいグラグラです。
コレは戦闘中に紛失する恐れも微レ存?

S&Tの三八式は遊底覆(ダストカバー)が標準装備。
実銃ではコイツの存在について賛否両論ですが、
エアガンの場合は・・・別に必要性を感じないよ~な気がする。
当然ですが遊底覆はココらへん周りを分解しないと外せません。
槓桿(ボルト)のコッキング時のストロークは短く、70mmぐらい。
我輩はボルトハンドルを真上に立ててコッキングするボルトアクションライフルを
所有するのが人生初なので少し戸惑いましたが慣れると素早い装填が出来る模様。

安全子(セイフティ)は写真の状態が発射状態。
コイツをダイレクトに押し込んで時計回りに45度回し、
尖った部分が上を向くと安全状態。
尚、コッキングしないとセイフティは動きません。
コレが結構動きが軽く、使いやすいんだな。
余談ですがコッキングの後ボルトハンドルがうまく倒れてくれない時、
ここを押し込むとボルトが“パタン!”と倒れてくれます。

銃把、床尾部分に関しては「まあ、こんなもんでしょ」。
でも実銃のようにストックの上下貼り合わせを再現しているのは良し。
たださっきも言ったように、何か臭うし、ツルツル感が不自然。
あと、床尾板は材質はともかく作りは結構キレイなんですがね、
立て銃を繰り返していると次第に傷だらけになるんだろうな。

S&T製三八式歩兵銃の最大の利点であり、
難点なのがこの弾倉システム。
着脱型マガジン方式はゲームユースには有利だけど、
外観のリアルさという点において「ふざけんな!(声だけ迫真)」。
だがしかし、我輩的にはサバゲーでバンバン撃ちまくりたいのでこのデフォルメは大歓迎。
弾倉交換が出来るからマガジン内蔵式のKTW製三八式より
戦闘中の素早いリロードが出来はしますがこの弾倉結構取り出しにくい。
尚、マガジンリップがある方が後ろ(ボルト側)になります。
箱型マガジンの装弾数は26発。長さは8.5cmぐらい。
9mmパラハンドガンのマガジンポーチには収まりそうだけど、
サバゲーで三八式を使う輩がナイロン装備を使うのかと小一時間問い詰めたい。
ま、我輩は陸自迷彩でこいつを使うつもりなのでハンドガンマグポーチに入れるんですがね。
三八式用の箱みたいな弾納、アレの中の仕切りがなければ、
弾納1つに2マガジンは収まりそうな予感だけど、ね。
尚、この弾倉、銃装着状態で少し飛び出ているのがイラッとする。
でもこの弾倉装着部分が丁度左手を添える部分になるので、
丁度隠れてしまっていい感じになるから気にしないことにします。

本来の弾倉がある部分は一体成型になっており、可動しません。
そして誇らしげに「メイドインチャイナ」と書かれているのが癪ですが、
三八式をコレだけリーズナブルに出してくれるエアガンメーカーなんて、
中国ぐらいしか無いんだろうから仕方ないね。
尚、弾倉の蓋が開かないので、用心鉄(トリガーガード)前方のアレもダミー。

三八式の刻印と菊のご紋もしっかり再現されておりますが、
我輩の個体は菊の御紋に傷が入っているのが悲しい。
中華エアガンは新品の時点で結構傷が入っているもんなんですが、
菊の御紋に傷がついているのは天皇陛下に申し訳がない。
とまあ、所々出来栄えに首を傾げたくなる部分はあるものの、
比較的入手しやすい価格帯でサバゲーで使える三八式歩兵銃としては
なかなか良く出来たもんじゃなかろうかというのが我輩の感想です。
しかし、いざ弾を詰めて撃ってみると、
性能的に少々難があることが判明したのです。
まず着脱可能な箱型弾倉、コレ案外弾詰めるのに手間取る。
マルイのBBローダーで入れられないことはないですが、
リップを指でしっかり押さえとかないとなかなか弾がマガジンに収まりません。
ボルトのテンションは少々重めですが、後退距離は短いので、
素早く引きにくいと言うほどでもなく、まあ許せる範囲かな。
トリガープルは少々重めですが、遊びが少なくストロークが短くて素直に落ちます。
初速はG&Gの0.2gバイオ弾使用時、
ノンホップで90~95m/sぐらい、適正ホップで88~80m/sぐらい、
弾が浮き上がるぐらいだと75~68m/sとかなりバラツキがあります。
命中精度は15m先の直径5cmの柱に当たるか当たらないかというレベル。
そして時々、明らかに着弾がズレております。
一回の発射で2〜3億を放出可能な股間の鉄砲と違って
連射が出来ない分1発必中が必須のボルトアクションにおいて、
このバラツキのある発射性能はある意味致命傷です。

まあ中華エアガンが箱出しで使えるなんて幻想は抱いておりませんでしたので、
S&T製三八式歩兵銃、分解してみることにしたのですが、
こないだ販売したばかりのエアガンの分解方法なんてググっても出てきやしません。
仕方がないので先っちょから手当たり次第にバラしてみることにしました。
まずはフロント周りから分解。
ダミーのクリーニングロッド先端にマイナスドライバーを差し込み、
捻ってグリグリして外すと前回りが外れます。

実は分解をするに辺り、この作業を先にヤるべきなのですが、
フロントサイトを横からポンチとかで軽く叩いて外し、
その下に隠れているイモネジを緩めてフロントサイトを
ハンマーでコツコツ叩けばマズル部分が外れます。
コレを先にヤラないと前回り部分が完全に外れません。

次は被筒部分を固定しているバンドを外すため、
写真のようにしてスプリングを押さえて前に抜きます。
ココで雑にリングを外そうとするとストックに傷が入るのでご注意。
外れたバンドは速やかに前に抜いてしまいましょう。

トリガーガードの前後のボルトを緩めると、機関部がストックから分離します。
ココらへんの作りは一般的なボルトアクションと同じですね。

機関部を取り出すのに必要はありませんが、
ストックの塗り直しをするために他の付属品もボルトを緩めて外します。

フロント部のダミークリーニングロッド固定部分は
ストックにしっかりと食い込んでくっついており、
ドライバーの先でこじってようやく外れました。
ま、機関部整備のための分解なら外さなくてもおk。

ストック前方部分はちっこい木ネジで固定されております。
コレが多少グラグラするのが気になるので、
ネジを交換するか、後から接着剤で固定することを検討しましょう。
我輩はネジを3mm程長いものと交換して固定をガッチリさせました。

ストック塗り直しのため、バットプレートも取り外してしまいます。
余談ですが各部のネジはマイナスで見た目にはリアルなのですが、
ネジの頭にバリが多くて少しイラッとします。
後々服に引っかからないように、ネジの頭のバリをヤスリで削っておきます。

ココからが機関部へのアクセスとなります。
マガジンハウジングは2本の6角ネジで固定されているので、緩めて外します。
ココを外さないとチャンバーにアクセス出来ません。
でもマガジンハウジング後方の銀色のプレート部分は、
別に外さなくてもシリンダーやチャンバーに影響はないのでございます。

引き金室部(トリガー部分)は2本のネジで固定されているので、
緩めたら直ぐ外れますが、「アレ?シリンダーの固定ピンは何処にあるの?」
我輩的常識だと、トリガーASSY外せばシリンダーが抜けるはずなんだけど・・・

もしかしてと思ってシリンダーのサイドにある
実銃ならシリンダー開放ラッチと思しき部分の蓋を緩め、
中の2本のクロスネジを緩めたらピン状の物体が外れてシリンダーが抜けました。
ダストカバー(遊底覆)を外す場合はココまでバラせば外せます。

チャンバーへのアクセスにはリアサイトを分解する必要があります。
リアサイト前方のマイナスネジを緩めて、リーフスプリングとリアサイトASSYを外します。

その後リアサイトに隠れていた小さい4本のネジを緩めると、
半分だけパカっと割れてチャンバーがお目見えになります。
この時にアウターバレルも一緒に外れます。
ていうかS&Tの三八式、チャンバーASSY的なものが無くて、
本体がそのままチャンバーになっているのに驚き。
しかし三八式の細い銃身にチャンバーを収めるとなると、こうなってしまうんでしょうね、

尚、チャンバーの構成はこのようになっております。
リアサイトから露出しているイモネジがチャンバーパッキンの上にある
小さい四角いゴム板を押さえながらホップを掛けるという仕組み。
ホップパッキンはVSR-10のものとほぼ変わらない形状ではあるものの、
パッキンのゴムの厚みが微妙に厚みがあり、
尚且つホップの突起がVSRのものより出っ張っています。
インナーバレルは600mmとかなりの長さです。
それでもインナーバレルの先端はマズルより大分奥にあるので、
インナーをギリギリまで伸ばそうと思えば650mmぐらいまでイケるはずです。
(因みにSVDやRPKのインナーバレルが650mmサイズ)
インナーバレルはVSRやL96等マルイボルトアクションのものが流用可能ですが、
オリジナルやカスタムパーツで同サイズのインナーバレルは存在しない模様。
しかしながらS&T製三八式はアウターバレル内部に段差がないので、
短いインナーバレルを突っ込んで組み上げることも可能です。

シリンダーの構成はこんな感じです。
パッと見た時点でマルイ製ボルトアクションとの互換性、ナシですな。
シリンダー長173mm、直径25.4mm、内径23.5mmで真鍮製、
しかも黒く塗っているだけで所々色剥げてる。
なるほど、この真鍮のシリンダーを隠すために遊底覆が付属しているのか?
そしてこのシリンダー、今まで見たこと無いぐらい肉厚。
ノズルは明らかにVSRより長スギィ!互換性のあるパーツなさそう。
アルミ製の黒いピストンもVSRのものより短く(長さ73mm)、
スプリングガイドも見たことない形状で短い(長さ68mm)。
スプリングはVSRと電動ガンの間ぐらいの直径(外形12mm)。
シリンダー周りは特に交換すべきものが見当たらなかったし、
Oリングの気密も取れていたのでそのまま使用することにします。
ていうかピストンのOリング、メッチャキツキツなんですけど大丈夫なんかコレ?
試しに手元にあったVSR用のOリングブチ込んだら
何ということでしょう、Oリング自体が細すぎてスカスカでした。
追記:ピストンのOリングがキツイために油が切れるとシリンダーにピストンが引っかかって
初速が40m/sぐらいに低下するので小まめにシリンダーにシリコンオイルを注油が必須です。
更に追記:2ロット以降の製品ではOリングは丁度いいサイズに変更されていました。
我輩的に気に入らないのはシリンダー内部の塗装。
剥げた塗料が後々、作動や精度に影響を及ぼしそうですからね。
というわけでシリンダー内側の色落としのために全バラ実施。
エンドボスを固定している割りピンをポンチで叩いてみたところ、
何ということでしょう、この割りピン貫通式じゃなくてはめ殺し式だ。
よーするに長い割りピン1本で固定しているんじゃなくて、
シリンダーの両サイドから短い割りピンで固定しているんで、
いくらポンチで叩いても抜けないわ奥に押し込まれて袋小路。

結局、ステンレス用ドリルの刃を購入してきて、
ピンごとガリガリぶち抜いてエンドボスのピンがハマる穴を削りましたよ。
そして手元にあった適当な長さと太さのピンを打ち込み直して修復。
というわけで、S&T製三八式のエンドボスには手を出すな!
ま、この部分は外す必然性も特に無いんで触らぬ神に祟りなし。
とりあえずシリンダーの後ろからアルミパイプに巻き付けたサンドペーパー突っ込んで、
シリンダー内部を磨いた後にピカールでしごきましたが作動性はそこまで変わらず。

トリガーASSYはどう見ても独自設計で明らか過ぎるほどに従来の既製品が使えない模様。
トリガープルの調整とかいった機能は全くございません。

蓋を開けてみると驚くほどシンプルな設計に驚き。
そしてトリガープルは全てがトリガースプリングに依存していることも判明。
この分だとシアとかのパーツを磨いたところで
トリガータッチの改善は望めそうにありませんので終了。

とりあえず、難がある部分を探しながら機関部を色々舐め回すように見たところ、
チャンバーパッキンのホップの出っ張り部分が削れていました。
なのでパッキンはVSR純正のものと交換。やっぱゴムは日本製が一番ですよ。
しかしVSRのチャンバーパッキン、ノズルが入る部分の内径が太い。
(右がS&Tの、左がVSRのチャンバーパッキン)
要するにガバマン状態で気密もへったくれもあったもんじゃないのです。
とりあえずそのまま組みこんでパワーを測ってみたところ、55m/sぐらいに激減。

やはり、ノズルとチャンバーの気密って重要なんですねということで、
ノズルの直径をアップするいい方法がなかろうかと思案した挙句、
直径6mmの収縮チューブを被せることにしました。
ただ、そのまま被せてもパッキンにハマって抜けてしまうので、
ノズル表面をある程度サンドペーパーでザラザラにして、
アロンアルファを塗って収縮チューブを先端から2mm程はみ出るぐらい被せ、
その後ライターで軽く炙って密着させて仕上げました。
この加工によってパワーは元通りになったのですが、
給弾する度にノズルのチューブが弾と当たってダメージを受けるのが気になるところ。
絶対コレ、後々チューブがズルムケになるよ。
追記:仕入れ先のフォースターにVSRパッキン対応のシリンダーノズルが売っていたので
迷う事なく購入して組み込んだら、精度もパワーも上がって幸せです。
なお、2ロット以降は既にこのパーツが組み込まれている模様なので、
マルイVSR用パッキンが安心して使えます。

インナーバレルは内部に謎の汚れがあったので、
サンドペーパーで落としてピカールで磨いて処置。
金があればPDIとかのロングインナーバレルを組みたいところですが、
我輩の手持ちの予算は本体と予備マガジン買うので精一杯なので保留。
ホップ調整用のイモネジはM3の頭付きのネジと交換。
ネジ山には緩み止めを塗り、容易にネジが回らないようにしました。
尚、組みたてる時は写真のようにして合わせてから組み上げると、
内部でパッキンが捩れることも少ないですし、キレイに収まります。

ストックは軍用銃に似つかわしくない安物家具のような
スベスベ感が気に入らないのでワトコオイルで再塗装することを決意。
120番のサンドペーパーで1時間掛けて色を剥がし、
「すっげぇ白くなってる、はっきりわかんだね」状態にしてしまいました。
そしたら何ということでしょう、ストックの材質がよろしくないのか、
色んな所にひび割れみたいなのが入っていて泣きそうになります。

晴天の空のもとでワトコオイルのマホガニーを塗り、
1~2時間ぐらい乾かしたら染み込まなかった分をウエスで拭き取ってまた色塗り、
コレを4回ほど繰り返して色濃く仕上げてみましたが、
もう少し黒っぽい、ウォールナットの色で仕上げた方が良かったかな?
しかし少なくとも以前のような変な臭い匂いは消えましたし、
色合い的にも我輩好みの良い感じに仕上がって気分がいいです。
そして何より、ストックの細かいひび割れが埋まっていい感じ。
ワトコオイルに含まれている亜麻仁油は木部に浸透して
繊維をつぶして硬化するらしいのでそれが功を奏しているのでしょう。

こうして、気になる部分を予算の範囲内で弄くり回し、
ボルト操作時にカチャカチャ五月蝿い遊底覆を外して再度組み直した結果、
フライヤーはなくなり、それなりに素直な弾道で弾が飛ぶようになりました。
コレならサバゲーで敵の指先は狙えなくても、顔面ぐらいは狙えそうです。
でもやはり、VSRとかL96といったようなマルイ製ボルトアクションと比べると、
インパクト以外では勝負にならないというのが正直なところでしょう。
まあ我輩的には命中精度なんて二の次三の次、
この木の温もりと金属の冷たさの融合がたまらんのですがね。
そしてこの三八式歩兵銃が醸し出す独特の世界観、コレがたまらん。
正確には三八式歩兵銃に合う軍装は旧日本軍一択なんでしょうが、
我輩的にはブラックパジャマで三八式というのも悪くないと思いますし、
(ていうか元々ベトコン装備時のエアコキ限定戦の武器として購入した)
ポリシーもアイデンティティも考慮せずに自衛隊装備でこれもアリかなと?
今更旧軍装備揃えるのも銭と労力がかかるでしょうしなぁ。
マルイ製ボルトアクションと比べると造りが大雑把で、
パーツの互換も全くと行っていいほど存在せず、
各部の改修の余地も少ないS&T製三八式歩兵銃。
当たりの個体を手にすればそのままでも充分使えるかもしれませんが、
我輩みたくパッキンがバカになったものを手にした場合は多少の改修は必要ですし、
もっと性能を高めるには結構な創作意欲と知識と技術を要するので、
万人向けとは言い難いですし、そうそうお勧めできるものではありません。
しかしながら電動ガン買うぐらいのお値段で旧日本軍の魂的存在が
手に入るというのは嬉しい事態であることもまた事実。
そしてそういうエアガンを中国が販売してしまったというのもおかしな話ですが、
ソコは中国人の(いい意味での)厚かましさ、商魂逞しさというべきなんでしょう。
この勢いでS&Tには次回作として九九式小銃か、四四式騎銃を出していただきたい!

追記:四四式は出してくれませんでしたが、三八式機銃が出たので三八式を売り払って購入。
コレで長めのガンケースに収めてサバゲーに持っていけるようになりましたし、
何より短くて使いやすい(個人の感想)。
なお余談ではなく重要事項なので言っておきますが、三八式騎兵銃ではなく「三八式機銃」です。
とりあえずバラして中を確認(分解方法は三八式も三八式騎銃も全く同じ)。
そしたらびっくり、インナーバレルがアルミになっちょっど!
道理で箱出し精度がイマイチなはずだ。
仕方がないのでヤフオクでVSR10のノーマルインナーバレルを2000円ぐらいで仕入れ、
行きつけのショップでチャンバーパッキンも買って来て組み込みました。
ピストンのOリングは三八式程キツキツではなく、気密もバッチリなんですが、
スプリングそのままだと初速が85m/sぐらいと少し物足りないかったので、
PDIのVSR10用の不等ピッチスプリング(太径) 430mmバレル専用を組み込み。
コレで0.2g弾での初速は88m/s、命中精度もだいぶん良くなったんでヨシとします。
2017年10月16日
ARES VZ-58Sを分解
コンパクトな東側陣営の武器である、
知名度が低くて所有者が殆ど存在しないと、
我輩好みのファクターを兼ね揃えたARES VZ-58S。
しかし、バッテリーを中に入れられない!
いや別に外でもイイやって思わなくはないけど、
コンパクトなリポバッテリー主流のご時世、外出しっていうのはねぇ。
やっぱ中に入れた方が気持ちが良いもんじゃないですかねぇ(ゲス顔)?
というわけでバッテリーを中に収納する策を考察すべく、
ARES VZ-58Sを分解してみることにしました。
しかし今回、最終的にどうにかなったから良かったものの、
どうにもならなかったら「ふざけんじゃねぇよお前これどうしてくれんだよ!」と
号泣しながら嫁にしまむらで買ってもらったデカい枕を涙で濡らすんですよ。
そして「やっぱりアローダイナミックのAKS74U買えばよかった!」と叫ぶんですよ。
ま、周囲に誰も所有している輩が居ないエアガンの分解なんて、
「なんで見る必要なんかあるんですか(正論)」なんでしょうが、
ここは一応サバゲーのブログだから、ハィ、ヨロシクゥ!

まずは上部カバーとボルト部分を外します。
先に言っておきますがVZ58はメカボを取り外すにしても、
バレルを交換するにしても、全部バラバラにする必要があります。
まあLCTやE&L、CYMAのAKとかも大体そうなんですがね。
ただ、AK系列は全バラするにしてもソコまで手間ではないのですが、
コイツは少しだけ神経を使う作業があったのがイラッとしました。

バレルとチャンバーをフリーにしないとメカボが外せないので、
フロント周りを先に分解してしまいます。
リアサイト基部にあるピンを左から押し込み、
ストッパーがかかるところまで下げると上のガスバイパスのカバーが外れます。
少し抵抗がありますが、力任せに持ち上げると外れます。

カバーを外すとでっかいマイナスネジがありますので、
ソイツをドライバーで緩めるとハンドガード、
そしてフロントサイトアッセンブリーが外れます。

その後本体をひっくり返し、4本のネジを緩めると、
フロントサイト達に包まれていたアウターバレルが外れます。
バレルの中にはチャンバーを押さえるバネがあるのでご注意。

メカボにアクセスする為にストックは外す必要はありませんが、
邪魔だと思う場合はこのクソデカいマイナスネジを緩めましょう。

前回りが外れたらグリップに手を付けます。
VZ58はグリップ部分がM4系列みたいな構成になっております。
まずはグリップの底板を2本のネジを緩めて外します。
そしてモーターに繋がる配線を外します。
しかしこの蓋、放熱のためにスリット付けているんでしょうが、
戦闘中に土が詰まりそうで怖いです。
露出度が高いのは可愛いお姉さんだけで充分なんですがねぇ。

モーターをグリップから引き抜いたらバネを外し、
グリップを固定しているホルダーとグリップを外すために
4本のグリップ止めネジを長いドライバーを突っ込んで外します。
あー何かM4バラしているみたいで('A`)マンドクセ。

コレでやっとメカボが抜けるかと思いきや、
メカボックスがマガジンキャッチ部分のピンでも固定されているので、
折角取り付けたこの部分も取り外さなければいけません。
ピンポンチで叩いてピンを抜きますが、
片方がローレット入りなので叩き出す向きに注意しましょう。

尚、マガジンキャッチ(右)のバネは太いもので、
ボルトキャッチ(左)のバネは細いものとなっております。

コレでようやくメカボックスとフレームを分離できるのですが、
配線がチャンバーとタイラップで固定されているのでぶった切ります。
そして配線を傷つけないように慎重に取り外し、メカボックスを抜きます。

最後にチャンバーとインナーバレルを抜いたら分解完了。
ココまでの所要時間、大体20分ぐらい。
正直な話、ソコまで気難しい作業ではありません。

メカボックスは8mmのベアリング付きのやつですね。
ヴァージョン3に似ていますがセレクタプレートが付いていません。
ガワの形状も所々違いが散見されますので、
VZ58のメカボックスを他のAKに移植するのは至難の業でしょう。
ま、クッソ長いノズルが付いている時点で、
他の銃への流用がきくとは到底思えませんがね。

反対側はAKお約束のデカいセレクタープレートが付いていません。
尚、セイフティはトリガー上のセレクタープレートの横移動で制御し、
セミフルの切り替えはプレートに磁石が入っていてソレで制御している模様。
メカボックスは先っちょにパワーダウン用のゴミも付いていないし、
変な異音もしないのでそのまま使ってみることにします。
追記:2年ぐらいは無事に使えたARES製VZ58S、ある日突然弾が出なくなりました。
中のギアが動いているのに弾が出ない・・タペットプレートが破損したかな?

というわけでメカボ開けてみる事にしました。
メカボックスの開け方に大したコツは必要ありません。
QDタイプのスプリングガイドを捻ってメインスプリングと共に抜き、
メカボックスを固定する上のプレートをスライドさせて、ネジを緩めるだけ。

案の定、タペットプレート下部のタペットスプリングが掛かる部分が折れていました。
調べによるとこのノズルとギアを連動させるためのタペットスプリングが
他の電動ガンと比べると硬い為、よく破損するみたいですので
マルイ電動ガンヴァージョン3メカボ用のタペットスプリングと交換します。
その他、メインスプリングを強めのものと交換、ピストンのOリングを交換。
コレにより今まで初速75m/sぐらいだったのが88m/s出るようになりました。

我輩がVZ58Sを欲しかった理由のもう一つ。
基盤が付いているから察しのいい人は解るでしょうが、
ARESのVZ58は電子制御トリガーなんです。
だからトリガータッチがとても軽く、気持ちが良いのです。
あまりにトリガーが軽いので、セイフティをこまめにかけなければ危険です。
ヅイマー氏所有のハニーバジャーを撃たせてもらった時、
そのトリガータッチに感動して以来、電子制御トリガーが気になっていたんです。

チャンバーはホップ調整ダイヤル上のネジを緩めると分解できますが、
クリックボールを飛ばさないように気をつけながらバラしましょう。
バレルは20cmぐらい、クリンコフと同じぐらいか?
ただ、先っちょはキレイなテーパーがかかっているのにホップ窓にバリがありました。
なので手元にあるマルイのインナーバレルをぶった切って交換。
チャンバーパッキンはシリコンっぽい白いの。破れやすそう。
しかもコイツ、ホップの出っ張りがマルイのやつより小さい。
なのでパッキンもマルイ製と交換。
中華電動ガンを頻繁に買う人はマルイのバレルとチャンバーパッキン、必須です。
気になるのがホップの押さえ部分、コレに押しゴム付いていないんですよ。
だから抑え部分を適当に削って押しゴムを接着してみました。

組み立て方はインナーバレルブチ込んだらメカボックスを押し込み、
マガジンキャッチとボルトストップを取り付け、ピンを打ち込みます。
我輩の場合はマガジンキャッチの代わりにマガジンアダプターを取り付け。
後は分解の逆手順で組み立てていけば完成します。
グリップに配線を通すのが少し('A`)マンドクセですが、
グリップ内部はM4よりも余裕がありますので配線の取り回しは楽です。

さて、肝心のバッテリー搭載の件についてですが、
まずアッパーカバーのスプリングを1本抜くことにして、
内部バッテリースペースを広げてみました。

そして配線をチャンバー付近ではなく、もう少し後ろから引き出してみました。
こうすれば短いバッテリーのコードを容易に繋ぐことが可能になります。

そしてETI800mAh細型リポバッテリーを繋いだらボルトを取り付け、
配線をつまみ出して前に引っ張り、バッテリーの配線を逃します。

バッテリーはカバーの裏に上手く収めて、本体に取り付けます。
少しコツが必要ですが、かなりスムースに収納可能です。
この後、ウナギリポの細いのが入手出来たのでスプリングは元に戻してしまいましたが、
バッテリーを選ぶという点においてARES製VZ58はなかなかの曲者です。

コレで我輩のVZ58S、どうにか使える体制が整いました。
M4用マグウェルを取り付けたので予備マガジンも充分にあります。
マルイのバレルとパッキンに交換して精度も上がったようなので、もう何も怖くない(マミさん)。
正直な話、バッテリー突っ込むのが('A`)マンドクセは電動ガンは、
MP5A5以来懲り懲りというのが我輩の思考なんですが、
フェザータッチなトリガープル、持ち運びやすくて使いやすいサイズ、
(但し重量感は結構あってサイズの割にはかなり重たいのだが、それがいい)
そして何より、誰もが所有していないという満足感。
バッテリー問題なんかどーでもいいと思わされる
魅力と個性が多くあるARESのVZ-58Sは
今後我輩の愛銃として活躍してくれそうです。
但し、コイツを皆にオススメするかと言われると答えはNOですね。
でも我輩自身が「いいゾ~これ」と思っていても
コンパクトな電動ガンが欲しければ他にも色々選択肢はありますし、
他の電動ガンそっちのけでコイツを手にする必然性なんて
「他のプレイヤーと被らない」ぐらいしかありませんから。
だが、それがいいんですよね。
知名度が低くて所有者が殆ど存在しないと、
我輩好みのファクターを兼ね揃えたARES VZ-58S。
しかし、バッテリーを中に入れられない!
いや別に外でもイイやって思わなくはないけど、
コンパクトなリポバッテリー主流のご時世、外出しっていうのはねぇ。
やっぱ中に入れた方が気持ちが良いもんじゃないですかねぇ(ゲス顔)?
というわけでバッテリーを中に収納する策を考察すべく、
ARES VZ-58Sを分解してみることにしました。
しかし今回、最終的にどうにかなったから良かったものの、
どうにもならなかったら「ふざけんじゃねぇよお前これどうしてくれんだよ!」と
号泣しながら嫁にしまむらで買ってもらったデカい枕を涙で濡らすんですよ。
そして「やっぱりアローダイナミックのAKS74U買えばよかった!」と叫ぶんですよ。
ま、周囲に誰も所有している輩が居ないエアガンの分解なんて、
「なんで見る必要なんかあるんですか(正論)」なんでしょうが、
ここは一応サバゲーのブログだから、ハィ、ヨロシクゥ!

まずは上部カバーとボルト部分を外します。
先に言っておきますがVZ58はメカボを取り外すにしても、
バレルを交換するにしても、全部バラバラにする必要があります。
まあLCTやE&L、CYMAのAKとかも大体そうなんですがね。
ただ、AK系列は全バラするにしてもソコまで手間ではないのですが、
コイツは少しだけ神経を使う作業があったのがイラッとしました。

バレルとチャンバーをフリーにしないとメカボが外せないので、
フロント周りを先に分解してしまいます。
リアサイト基部にあるピンを左から押し込み、
ストッパーがかかるところまで下げると上のガスバイパスのカバーが外れます。
少し抵抗がありますが、力任せに持ち上げると外れます。

カバーを外すとでっかいマイナスネジがありますので、
ソイツをドライバーで緩めるとハンドガード、
そしてフロントサイトアッセンブリーが外れます。

その後本体をひっくり返し、4本のネジを緩めると、
フロントサイト達に包まれていたアウターバレルが外れます。
バレルの中にはチャンバーを押さえるバネがあるのでご注意。

メカボにアクセスする為にストックは外す必要はありませんが、
邪魔だと思う場合はこのクソデカいマイナスネジを緩めましょう。

前回りが外れたらグリップに手を付けます。
VZ58はグリップ部分がM4系列みたいな構成になっております。
まずはグリップの底板を2本のネジを緩めて外します。
そしてモーターに繋がる配線を外します。
しかしこの蓋、放熱のためにスリット付けているんでしょうが、
戦闘中に土が詰まりそうで怖いです。
露出度が高いのは可愛いお姉さんだけで充分なんですがねぇ。

モーターをグリップから引き抜いたらバネを外し、
グリップを固定しているホルダーとグリップを外すために
4本のグリップ止めネジを長いドライバーを突っ込んで外します。
あー何かM4バラしているみたいで('A`)マンドクセ。

コレでやっとメカボが抜けるかと思いきや、
メカボックスがマガジンキャッチ部分のピンでも固定されているので、
折角取り付けたこの部分も取り外さなければいけません。
ピンポンチで叩いてピンを抜きますが、
片方がローレット入りなので叩き出す向きに注意しましょう。

尚、マガジンキャッチ(右)のバネは太いもので、
ボルトキャッチ(左)のバネは細いものとなっております。

コレでようやくメカボックスとフレームを分離できるのですが、
配線がチャンバーとタイラップで固定されているのでぶった切ります。
そして配線を傷つけないように慎重に取り外し、メカボックスを抜きます。

最後にチャンバーとインナーバレルを抜いたら分解完了。
ココまでの所要時間、大体20分ぐらい。
正直な話、ソコまで気難しい作業ではありません。

メカボックスは8mmのベアリング付きのやつですね。
ヴァージョン3に似ていますがセレクタプレートが付いていません。
ガワの形状も所々違いが散見されますので、
VZ58のメカボックスを他のAKに移植するのは至難の業でしょう。
ま、クッソ長いノズルが付いている時点で、
他の銃への流用がきくとは到底思えませんがね。

反対側はAKお約束のデカいセレクタープレートが付いていません。
尚、セイフティはトリガー上のセレクタープレートの横移動で制御し、
セミフルの切り替えはプレートに磁石が入っていてソレで制御している模様。
メカボックスは先っちょにパワーダウン用のゴミも付いていないし、
変な異音もしないのでそのまま使ってみることにします。
追記:2年ぐらいは無事に使えたARES製VZ58S、ある日突然弾が出なくなりました。
中のギアが動いているのに弾が出ない・・タペットプレートが破損したかな?

というわけでメカボ開けてみる事にしました。
メカボックスの開け方に大したコツは必要ありません。
QDタイプのスプリングガイドを捻ってメインスプリングと共に抜き、
メカボックスを固定する上のプレートをスライドさせて、ネジを緩めるだけ。

案の定、タペットプレート下部のタペットスプリングが掛かる部分が折れていました。
調べによるとこのノズルとギアを連動させるためのタペットスプリングが
他の電動ガンと比べると硬い為、よく破損するみたいですので
マルイ電動ガンヴァージョン3メカボ用のタペットスプリングと交換します。
その他、メインスプリングを強めのものと交換、ピストンのOリングを交換。
コレにより今まで初速75m/sぐらいだったのが88m/s出るようになりました。

我輩がVZ58Sを欲しかった理由のもう一つ。
基盤が付いているから察しのいい人は解るでしょうが、
ARESのVZ58は電子制御トリガーなんです。
だからトリガータッチがとても軽く、気持ちが良いのです。
あまりにトリガーが軽いので、セイフティをこまめにかけなければ危険です。
ヅイマー氏所有のハニーバジャーを撃たせてもらった時、
そのトリガータッチに感動して以来、電子制御トリガーが気になっていたんです。

チャンバーはホップ調整ダイヤル上のネジを緩めると分解できますが、
クリックボールを飛ばさないように気をつけながらバラしましょう。
バレルは20cmぐらい、クリンコフと同じぐらいか?
ただ、先っちょはキレイなテーパーがかかっているのにホップ窓にバリがありました。
なので手元にあるマルイのインナーバレルをぶった切って交換。
チャンバーパッキンはシリコンっぽい白いの。破れやすそう。
しかもコイツ、ホップの出っ張りがマルイのやつより小さい。
なのでパッキンもマルイ製と交換。
中華電動ガンを頻繁に買う人はマルイのバレルとチャンバーパッキン、必須です。
気になるのがホップの押さえ部分、コレに押しゴム付いていないんですよ。
だから抑え部分を適当に削って押しゴムを接着してみました。

組み立て方はインナーバレルブチ込んだらメカボックスを押し込み、
マガジンキャッチとボルトストップを取り付け、ピンを打ち込みます。
我輩の場合はマガジンキャッチの代わりにマガジンアダプターを取り付け。
後は分解の逆手順で組み立てていけば完成します。
グリップに配線を通すのが少し('A`)マンドクセですが、
グリップ内部はM4よりも余裕がありますので配線の取り回しは楽です。

さて、肝心のバッテリー搭載の件についてですが、
まずアッパーカバーのスプリングを1本抜くことにして、
内部バッテリースペースを広げてみました。

そして配線をチャンバー付近ではなく、もう少し後ろから引き出してみました。
こうすれば短いバッテリーのコードを容易に繋ぐことが可能になります。

そしてETI800mAh細型リポバッテリーを繋いだらボルトを取り付け、
配線をつまみ出して前に引っ張り、バッテリーの配線を逃します。

バッテリーはカバーの裏に上手く収めて、本体に取り付けます。
少しコツが必要ですが、かなりスムースに収納可能です。
この後、ウナギリポの細いのが入手出来たのでスプリングは元に戻してしまいましたが、
バッテリーを選ぶという点においてARES製VZ58はなかなかの曲者です。

コレで我輩のVZ58S、どうにか使える体制が整いました。
M4用マグウェルを取り付けたので予備マガジンも充分にあります。
マルイのバレルとパッキンに交換して精度も上がったようなので、もう何も怖くない(マミさん)。
正直な話、バッテリー突っ込むのが('A`)マンドクセは電動ガンは、
MP5A5以来懲り懲りというのが我輩の思考なんですが、
フェザータッチなトリガープル、持ち運びやすくて使いやすいサイズ、
(但し重量感は結構あってサイズの割にはかなり重たいのだが、それがいい)
そして何より、誰もが所有していないという満足感。
バッテリー問題なんかどーでもいいと思わされる
魅力と個性が多くあるARESのVZ-58Sは
今後我輩の愛銃として活躍してくれそうです。
但し、コイツを皆にオススメするかと言われると答えはNOですね。
でも我輩自身が「いいゾ~これ」と思っていても
コンパクトな電動ガンが欲しければ他にも色々選択肢はありますし、
他の電動ガンそっちのけでコイツを手にする必然性なんて
「他のプレイヤーと被らない」ぐらいしかありませんから。
だが、それがいいんですよね。