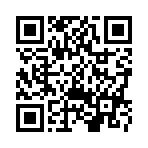2021年05月18日
ロシアのサブマシンガンを手に入れた
何を血迷ったか工業系の高校へ進学してしまったウチの娘、
更に血迷って「弦楽部」というヴァイオリンやらヴィオラやらチェロやらコントラバスで
演奏するという意識よりも敷居の高そうな部活に入っちゃいました。
どの楽器担当になるか決める際、一通り弾いてみたところ、
チビっ子の娘にはクソデカいチェロorコントラバスは物理的に演奏不可能ということで、
無難にヴァイオリンに決まったということです。
んで、最近コロナがまた流行りだしたのでゴォルデンウィィク突入前、
部活が中止になって家で練習しろという事になり、
娘がウチにヴァイオリン持ってきたんですがね、
まさか我が家にリコーダーと鍵盤ハーモニカとはランクが違う
高貴な楽器が来てしまうとは夢にも思いませんでしたよ全くもうw
さて、今まで弦楽器は当然、他の文化的な楽器なるものを触ったことがなかった娘が、
ヴァイオリンというイメージ的には華麗なる一族の子供が習わされるような楽器を
奏でることが出来るのかという一抹の不安はありましたが、
まだ曲を演奏出来ないものの音を出すだけならどうにかなるもんなんですね。
さて、コレが曲を演奏できるようになるまでどれぐらいの時間がかかるのやら?
まあ我輩的にはヴァイオリンが入っていたケースを見ながら
「コイツなら今度仕入れるサブマシンガンをブチ込むケースに出来るな」
としか考えないという相変わらずの人間失格ぶりです。

そのヴァイオリンケースに収まりそうなサブマシンガンが、
今回レビューを上げる「MODIFY製PP2000 CO2」です。
(ロシアの銃器なので、表記するならПП2000と入力するのが正しい?)
モディファイという聞き慣れないメーカーは台湾のトイガンメーカーで、
CARBON8(カーボネイトと読むらしい)というガバメント系の
CO2ハンドガンで一躍有名になった?メーカーみたいです。
そしてこのPP2000もCO2をパワーソースに使用するガスガンです。
CO2ガスガンの利点は「フロンガス程冷えない」。
要するにフロンのガスガンが動かなくなる冬場でも、それなりに作動するんです。
一度吉六会同志所有のCARBON8のガバを撃たせてもらいましたが、
キン★マが縮こまりそうな冬場でもスライドが動いて弾が飛んでいくさまには感動しましたね。
但し、8連射ぐらいしたら我輩のフ★ックのように勢いがなくなりましたがw
とまあ、気温10℃を切ると流石に厳しいものの、
連射するとすぐにマガジンが冷えて作動不良を起こすフロンガスと違い、
パワー、作動性共に(比較的)安定しているのがCO2ガスガンの利点です。
なお、モディファイのPP2000ですが商品名としては
「PP-2K」と言う商品名で販売されているようで、
箱やフレームにもそのように明記されております。
(本名を名乗れないのは大人の事情があるからまあしょうがないね)

製品はハードケース、本体、ショートマガジン、説明書、ボンベ取付用アレンレンチ、
ホップ調整用クソ長アレンレンチ、MODIFYのステッカーやパッチが付属して、
定価は大体1パットンぐらいですかねと結構な高級品です。
まあ近いうちに発売されるであろうマルイ製ガスブロAKMよりは安いですな。
(あっちはフルサイズのライフルなので比べることがお門違いなのだが)
だがしかし、同サイズのマルイ製MP7ガスブローバックが30000円強と考えると、
10000円以上高いコイツがまあ多少割高に思えてしまいがちですが、
出来が良いことで定評のあるVFCやKSCのMP7ガスブローバックは
PP2000と同程度の価格なので別に割高というわけでもないでしょう(確信)。
余談ですがハードケースの中身のスポンジは
ペリカンケースのように細かいブロック状のタイプなので、
PP2000の形状に仕上げていい感じに固定することが可能です。

なお、本体とショートマガジンだけではサバゲーで戦力的に物足りないので、
ロングの予備マガジン(定価10000円超え!)を2本追加して購入しました。
(定価を記入しているが、購入元のBATONでは多少割引価格で販売している)
購入するにあたり「56発しか装填できない弾倉を2000発装填可能な
AKドラムマガジンと同じ金額を出して買うのか・・・」という葛藤がありましたが、
コイツはガスブローバックという動きを楽しめるオトナのオモチャ、
所謂ロマン武器なのでそういうコスパ重視思考をしてはいけないのです。
我輩の父上も生前申しておりました。
「コストパフォーマンスを気にするなら、趣味なんか持っちゃいけない」
「趣味とは、損得を無視した方向にある無駄なものなんだから」とね。
他にもオプションとして専用サプレッサー(7000円ぐらい)、専用ライト(10000円ぐらい)、
カイデックス製のホルスター(7000円ぐらい)がありましたが、
それら全てを揃えてしまうととてつもない価格になってしまい、我輩の手に負えない(落胆)。
ロマンを求めるという行為にはカネがかかるもんですね。
でもロマンを求めないと面白くないのが人生と言うもんなんです。

PP2000という銃はロシアが2001年から開発、2004年に発表、
2008年にロシア警察に採用され、その後ロシア軍に採用されたという、
9mmパラベラム弾を使用する携行性に念頭を置いた小型のサブマシンガンです。
ぱっと味の出来栄えは高額商品に恥じない丁寧な作り。
フレーム部分は樹脂、バレルやアッパーフレーム周りは金属製です。
樹脂部品のバリはありますが(実銃でもある模様)、金属部品の仕上げは比較的丁寧。
こないだ購入したRAPTOR製MP443と比べると実によく出来ております。
ストックを畳んだ長さは35cmぐらい、ストックを展開したら60cm程度。
携行性を重視した作りなので、実銃も重量は1.5kgとかなり軽量。
MODIFY製PP2000も重量はマガジン装填時でも実銃と大差ない(1.3kg)ようで
マルイガスブロMP7の2.2kgと比べるとサブマシンガンとしては軽量な部類なのですが
持って構えてみると数字よりは案外ずっしりしております。

PP2000、現代的な分類ではPDW(パーソナル・ディフェンス・ウェポン)でしょうかね?
しかしサブマシンガンとは拳銃弾を使用する銃器全般のことを指し、
PDWはライフル弾やそれに準ずる威力を有する個人携行武器のことを指すので、
9mmパラベラム弾を使用するコイツに関してはサブマシンガンと呼ぶのが正しいのです。
このPP2000、ロシア軍に採用されていると言われてはいますが、
ロシア連邦軍の武器としてではなく、国防軍や内務省軍が使用している模様。
だから前々回説明したロシア連邦軍の武器に割り当てられるGRAUインデックスは無い模様。
まあ今の御時世このサイズのサブマシンガンは
軍隊よりも法執行機関での運用が主流ですからね。
使用用途が限定されるサブマシンガンは軍隊の武器としては不向きなのです。
だからロシア連邦軍装備しか受け付けない我輩が買う義理はなかったんですがね、
1丁ぐらいガスブロのサブマシンガン、欲しかったからまあしょうがないね。
しかも寒さに比較的強いと言われるCO2ガスガンですから、
10月ぐらいまではフィールドでも充分な戦力となりえそうです。

さて、このPP2000と言うサブマシンガンの外観を一言で表すと
「ロシアの精神が形になったようだ(意味深)!」。
イモネジで下部を固定されたフラッシュハイダーは14mm逆ネジで締められており、
取り外せばマルイ電動ガンに使用可能なハイダー、サプレッサは取付可能。
シュタイアーAUGみたいにグリップと(ていうかフレームと)一体化した
独特スギィ!なフォアグリップはとっつきにくて握りにそうではありますが、
コレが案外フィット感が良くて(個人の意見です)驚きです。
残念なのはこのフォアグリップ周りにレールが付属しないことなんですが、
ロシア的には「レール?そんなのどーせライトぐらいしか付けねぇだろ?」なんでしょうね。

AKみたいな雰囲気のフロントサイトは上下調整が可能です。
まあでもこの手の武器は光学サイト載せての運用が現代の主流でしょう。
それよりもさぁ、フロントサイト根本からピンがとびだせどうぶつの森しているのは何?
注:専用サプレッサーを取り付ける時に引っ掛けるピンでした。
フロントサイト奥のパイプみたいなのがチャージングハンドルになります。
射撃時にはココが豪快に前後しやがるのです。
H&K G36みたいに左右どちらかに折り曲げてコッキングしますが、
G36みたいにバネで真っ直ぐには戻らず、折れ曲がった状態で保持されます。
コレもとっさに使いやすいかと問われると微妙(多分慣れの問題)ですが、
銃を構えて操作しやすいという点では後端部をコッキングするMP7よりも良い感じです。

実銃では9mm弾を詰め込むマガジンが収まる
謎の前傾グリップの握り心地は意外と普通というか、良い。
厚みがなくて握りやすいのが掌が小さい我輩には良きかな。
でもグリップ後端部の穴の意味がさっぱり解りません。
パラコードでも通して、スリングでも引っ掛けろと言いたいのでしょうか?
(しかしスリングスイベルはまた別のところに付いているという)
棒を削って指掛を付けたような細いトリガーのキレは意外と普通&素直で、
RAPTOR製MP443みたいな変な癖はなし。
マガジンキャッチは一般的なハンドガンと同じ場所に設けられており、
使用感もハンドガンとほぼ一緒でマガジンも素直に抜けてくれます。
なお、トリガーガード後部とトリガー後部に空いている穴がホップ調整用の穴。
ココにクソ長アレンレンチを突っ込んで回し、ホップダイヤルを調整します。
ところでさぁ、ロシア人ってデカいセレクターどんだけ好きなんですかねぇ?
親指で操作可能な位置に設置されてはいるものの、このセレクターの存在感よ。
見た目より使いやすい形状ではありますが、動きは渋いです。
なお、セレクターの位置は一番上がセイフティ、真ん中がフルオート、一番下がセミ。
AKと同じポジション設定はAKを使い慣れたロシアの兵士にも優しい設計?
なお、セイフティ状態でコッキングするのはダメみたいですね。
マガジンを抜く前にセレクターをセーフに入れるのもダメらしいです。
ジャムった時にセイフティをかけるのもダメなんですと。
上記事項を守らないと、銃がぶっ壊れるらしいです(迫真)。

リアサイトはレールに侵食され、とりあえず付けときました感半端なし。
まあ前述のようにレールにドットサイト取り付け前提で開発されたんでしょうし、
このサイズのサブマシンガンに過度な命中精度は
期待するなというのが本音なのでしょうか?

サイドスイングで射手の体型に合わせて調整できない
折りたたみストックは前時代的と言うか、武器に身体を合わせろなロシア的。
構えた感触は我輩の体系的には特に問題なし。
銃本体を掴みながらストック本体を持ち上げて握ってロックを解き、ストックを展開します。
折りたたむ時も同様の操作にて実施しますが、正直慣れないと展開しにくい。
MP7みたいなスライドタイプのストックって使いやすくていいですね。
余談ですが折りたたみ状態ではすっげぇガッタガタで
遠慮なしに本体にバシバシ当たりやがるのが困りものです。
そしてこの無愛想で前時代的な折りたたみストックは
レシーバー後端部分のボタンを押すことで取り外しが可能です。
(余談であるがボタンの近所にある出っ張りはスリングスイベル)

何でストックが外れる必要なんかあるんですか(正論)
それはねロングマガジンをストックの代わりにするためなんですね。
発想は面白いと言うか、誰も考えもしなかった的ではありますが、
その機能が果たして必要だったのかと問われると
我輩的には「そんなことしなくていいから(良心)」という思いなんですがね。
どうでもいい話ですがストックを外した状態でも撃てます。
でも当たりにくくなるのでやっぱりストックが欲しくなります。

付属のショートマガジンは22連とマルイガバメントよりも少ない残念な装弾数。
その上「お前さっきグリップにマガジン突っ込んだ時チラチラ見てただろ(因縁)」と
言いたくなる程マガジンからCO2ボンベがチラリズムで存在感を見せつけます。
リアルさという点ではこのCO2マガジンの外観は・・・ダメみたいですね(諦観)。
そしてこのショートマガジン、お値段が定価8000円ぐらいっていうんですから、
マルイのMP7みたいに予備マガジンを大量に揃えるのも金銭的に修羅の道です。
ロングマガジンは装弾数56発とショートマガジンの倍以上のキャパなのに、
お値段の差はショートマガジン+2000円。
前述のようにこの銃にコスパを求めること自体が愚かなのですが、
戦力的or金銭的お得感はロングマガジンのほうが断然高いと我輩は思います(個人の感想です)。
でもロングマガジン、長スギィ!でかなり邪魔なんですがね。
因みに、基本はCO2での運用が主であるMODIFY製PP2000ですが、
フロンガスをチャージするマガジンも販売されております。
(お値段はロング、ショート共にCO2マガジンよりも1000円ぐらい安い)
但し、CO2を使用したときよりも10m/s程パワーが劣る模様ですし、
気温が低くなるとマトモな作動は期待できないとのことです。
実はMODIFY製PP2000がCO2ガスガン初体験の我輩、
ボンベをマガジンに「よし、じゃあブチ込んでやるぜ」に多少戸惑いましたが
ボンベを横から突っ込んでアレンレンチ突っ込んで
下から真っ直ぐねじ込めばとりあえず収まりますが
我輩がブチ込むと3本に2本は入れて直ぐ「シュー!(迫真)」って音がするのが恐怖。

まずは22連ショートマガジンにボンベを挿入、
とりあえず空撃ちでもしてみようかと弾を込めずにマガジンぶっ挿して
チャージングハンドル引いてみたら何ということでしょう、
マガジンフォロアーにノズルが引っかかってハンドルが中途半端な位置で止まります。
なるほど、撃ち終わるとこのようにしてホールドオープンするのか。
ボルトリリースレバー的なものは付いておらず、マガジン抜くとボルトは戻ります。
弾を詰めてセミオートで発射。
夕方でも気温が20℃ぐらいある宮崎の今の季節、作動は快調そのもの。
セミオートでも面白いぐらいに銃が暴れます。
全て弾を撃ち尽くしたら次弾装填、次はフルオート。
22連マガジンはあっという間に空になります。
弾速計で測ってみると秒間16~18発ぐらいだったので、サイクルは若い頃の我輩の腰ぐらい。
次は56連ロングマガジンにボンベ装填、弾を詰めますが56発キレイに入りません。
ボンベをブチ込んで1回目の射撃(セミオート)では初速は平均75m/s位を叩き出しました。
2回目、マガジンの少し冷えた状態での射撃初速は65m/sぐらいに落ちて、
「バッチェ冷えてますよ!」な3回目は半分ぐらい弾を残した状態で閉鎖不良になって弾が出なくなりました。
飛距離に関しては電動ガンより劣るのは仕方ないですが、
デカいハンドガンと考えれば充分な飛びっぷり。
コンパクト電動ガンぐらいの飛距離は出ているので文句なしですね。
但し、銃自体が軽いのとリコイルが災いしているのか命中精度は然程期待できません。
セミオートなら狙って当てられないことはないですが、
フルオートではかなり飛び散って正確に当てるのは難しいです。
まあガスブロのフルオートに命中精度を期待しちゃいけないんですがね。
気になる燃費は1ボンベでセミオートならロングマガジンで2.5マガジン、
フルだと2マガジン撃つとガス欠でスライドが動かなくなります。
まあ大体100発は撃てると考えて差し支えないでしょう。
なお、ガス欠前の最後の方の弾速&リコイルはジジィのファ★クの方が気合が入っています。
途中でガスを追加or交換できないのがCO2ガスガンの欠点ですね。

今後起こることが予測されるであろうジャムのトラブルシューティングに必要なので、
取説を見ながらMODIFY製PP2000を分解してみます。
グリップ内部の分解レバーを銃先端側に倒すことで
アッパーレシーバー(アウターバレル?)が分離できます。

見たところボルトの立て付けや滑り具合に特に問題はないので、
すり合わせを良くする等、特に手を加える要素はないみたいですし、
明日も仕事で忙しいのでコレ以上分解はしません。

アッパーレシーバーはバレルASSY、リコイルスプリング、ボルトASSYに分離できます。
一通り内部を見てみましたが、コレと言った不具合はない感じです。

インナーバレルやパッキンを交換するのであれば、バレル周りを分解する必要がありますが、
他の部分は分解調整しなくてもどうにかなりそうですし、
多分社外品のスプリングとかブリーチとかは出なさそうな予感。

ロアフレーム内部もわざわざバラして中身を取り出し、
パーツ類を耐水ペーパーで滑らかにする必要はないのでこれ以上手はつけません。
MODIFY製PP2000、残念ながら分解してもバラバラにする必要性は皆無の模様。

というわけで元に戻しましょうかね。
リコイルスプリングをロアフレーム内部の凹み部分に押し当てて、
アッパーレシーバーを組み込みます。

その後、バレル部分を上から押さえて、
ロック部分を結合すればちゃんと組み上がるはずです。

携行性の高い軽量サブマシンガンということで、
その性格をスポイルしない小型のドットサイトを搭載し、
スリングを取り付けて持ち運びしやすくしてみました。
ロングマガジンはP90用のマガジンポーチに収まったので、
(但し、太いP90のマガジンが入る入れ物に細いマガジンをブチ込むからガバガバ)
予備マガジンの携行をご検討の方はぜひとも購入すべし。
以前スカルガンナー氏に撃たせてもらったKWC製MINI UZIと比べると
作動は安定している感がありますし、扱いやすいし、リコイルも抜群ではありますが、
他の21世紀前後に登場したサブマシンガンと比べると利便性は恐らく微妙です。
我輩的にはMODIFY製PP2000、実に気に入りました。
ロシアの銃器、独特なのに構えやすい外観、CO2ならではの激しい撃ち味、
そして海外製品とは思えない作動の良さは我輩を虜にしてくれました。
但し、MP7じゃ面白くない、人とは違うガスブロが欲しいというような、
浮ついた気持ちで手を出してはいけない気がするMODIFY製PP2000。
コレはロシアの大地のように壮大で大雑把な気持ちで
購入して運用しなければいけない銃でしょうね。
但し、現時点でCO2を使用するサブマシンガンは選択肢が少ないですし、
モノによってはパワー的にそのまま使えない物もあるようなので、
安心して使えるCO2サブマシンガンが欲しいという層には良い選択肢なのかも?
更に血迷って「弦楽部」というヴァイオリンやらヴィオラやらチェロやらコントラバスで
演奏するという意識よりも敷居の高そうな部活に入っちゃいました。
どの楽器担当になるか決める際、一通り弾いてみたところ、
チビっ子の娘にはクソデカいチェロorコントラバスは物理的に演奏不可能ということで、
無難にヴァイオリンに決まったということです。
んで、最近コロナがまた流行りだしたのでゴォルデンウィィク突入前、
部活が中止になって家で練習しろという事になり、
娘がウチにヴァイオリン持ってきたんですがね、
まさか我が家にリコーダーと鍵盤ハーモニカとはランクが違う
高貴な楽器が来てしまうとは夢にも思いませんでしたよ全くもうw
さて、今まで弦楽器は当然、他の文化的な楽器なるものを触ったことがなかった娘が、
ヴァイオリンというイメージ的には華麗なる一族の子供が習わされるような楽器を
奏でることが出来るのかという一抹の不安はありましたが、
まだ曲を演奏出来ないものの音を出すだけならどうにかなるもんなんですね。
さて、コレが曲を演奏できるようになるまでどれぐらいの時間がかかるのやら?
まあ我輩的にはヴァイオリンが入っていたケースを見ながら
「コイツなら今度仕入れるサブマシンガンをブチ込むケースに出来るな」
としか考えないという相変わらずの人間失格ぶりです。

そのヴァイオリンケースに収まりそうなサブマシンガンが、
今回レビューを上げる「MODIFY製PP2000 CO2」です。
(ロシアの銃器なので、表記するならПП2000と入力するのが正しい?)
モディファイという聞き慣れないメーカーは台湾のトイガンメーカーで、
CARBON8(カーボネイトと読むらしい)というガバメント系の
CO2ハンドガンで一躍有名になった?メーカーみたいです。
そしてこのPP2000もCO2をパワーソースに使用するガスガンです。
CO2ガスガンの利点は「フロンガス程冷えない」。
要するにフロンのガスガンが動かなくなる冬場でも、それなりに作動するんです。
一度吉六会同志所有のCARBON8のガバを撃たせてもらいましたが、
キン★マが縮こまりそうな冬場でもスライドが動いて弾が飛んでいくさまには感動しましたね。
但し、8連射ぐらいしたら我輩のフ★ックのように勢いがなくなりましたがw
とまあ、気温10℃を切ると流石に厳しいものの、
連射するとすぐにマガジンが冷えて作動不良を起こすフロンガスと違い、
パワー、作動性共に(比較的)安定しているのがCO2ガスガンの利点です。
なお、モディファイのPP2000ですが商品名としては
「PP-2K」と言う商品名で販売されているようで、
箱やフレームにもそのように明記されております。
(本名を名乗れないのは大人の事情があるからまあしょうがないね)

製品はハードケース、本体、ショートマガジン、説明書、ボンベ取付用アレンレンチ、
ホップ調整用クソ長アレンレンチ、MODIFYのステッカーやパッチが付属して、
定価は大体1パットンぐらいですかねと結構な高級品です。
まあ近いうちに発売されるであろうマルイ製ガスブロAKMよりは安いですな。
(あっちはフルサイズのライフルなので比べることがお門違いなのだが)
だがしかし、同サイズのマルイ製MP7ガスブローバックが30000円強と考えると、
10000円以上高いコイツがまあ多少割高に思えてしまいがちですが、
出来が良いことで定評のあるVFCやKSCのMP7ガスブローバックは
PP2000と同程度の価格なので別に割高というわけでもないでしょう(確信)。
余談ですがハードケースの中身のスポンジは
ペリカンケースのように細かいブロック状のタイプなので、
PP2000の形状に仕上げていい感じに固定することが可能です。

なお、本体とショートマガジンだけではサバゲーで戦力的に物足りないので、
ロングの予備マガジン(定価10000円超え!)を2本追加して購入しました。
(定価を記入しているが、購入元のBATONでは多少割引価格で販売している)
購入するにあたり「56発しか装填できない弾倉を2000発装填可能な
AKドラムマガジンと同じ金額を出して買うのか・・・」という葛藤がありましたが、
コイツはガスブローバックという動きを楽しめるオトナのオモチャ、
所謂ロマン武器なのでそういうコスパ重視思考をしてはいけないのです。
我輩の父上も生前申しておりました。
「コストパフォーマンスを気にするなら、趣味なんか持っちゃいけない」
「趣味とは、損得を無視した方向にある無駄なものなんだから」とね。
他にもオプションとして専用サプレッサー(7000円ぐらい)、専用ライト(10000円ぐらい)、
カイデックス製のホルスター(7000円ぐらい)がありましたが、
それら全てを揃えてしまうととてつもない価格になってしまい、我輩の手に負えない(落胆)。
ロマンを求めるという行為にはカネがかかるもんですね。
でもロマンを求めないと面白くないのが人生と言うもんなんです。

PP2000という銃はロシアが2001年から開発、2004年に発表、
2008年にロシア警察に採用され、その後ロシア軍に採用されたという、
9mmパラベラム弾を使用する携行性に念頭を置いた小型のサブマシンガンです。
ぱっと味の出来栄えは高額商品に恥じない丁寧な作り。
フレーム部分は樹脂、バレルやアッパーフレーム周りは金属製です。
樹脂部品のバリはありますが(実銃でもある模様)、金属部品の仕上げは比較的丁寧。
こないだ購入したRAPTOR製MP443と比べると実によく出来ております。
ストックを畳んだ長さは35cmぐらい、ストックを展開したら60cm程度。
携行性を重視した作りなので、実銃も重量は1.5kgとかなり軽量。
MODIFY製PP2000も重量はマガジン装填時でも実銃と大差ない(1.3kg)ようで
マルイガスブロMP7の2.2kgと比べるとサブマシンガンとしては軽量な部類なのですが
持って構えてみると数字よりは案外ずっしりしております。

PP2000、現代的な分類ではPDW(パーソナル・ディフェンス・ウェポン)でしょうかね?
しかしサブマシンガンとは拳銃弾を使用する銃器全般のことを指し、
PDWはライフル弾やそれに準ずる威力を有する個人携行武器のことを指すので、
9mmパラベラム弾を使用するコイツに関してはサブマシンガンと呼ぶのが正しいのです。
このPP2000、ロシア軍に採用されていると言われてはいますが、
ロシア連邦軍の武器としてではなく、国防軍や内務省軍が使用している模様。
だから前々回説明したロシア連邦軍の武器に割り当てられるGRAUインデックスは無い模様。
まあ今の御時世このサイズのサブマシンガンは
軍隊よりも法執行機関での運用が主流ですからね。
使用用途が限定されるサブマシンガンは軍隊の武器としては不向きなのです。
だからロシア連邦軍装備しか受け付けない我輩が買う義理はなかったんですがね、
1丁ぐらいガスブロのサブマシンガン、欲しかったからまあしょうがないね。
しかも寒さに比較的強いと言われるCO2ガスガンですから、
10月ぐらいまではフィールドでも充分な戦力となりえそうです。

さて、このPP2000と言うサブマシンガンの外観を一言で表すと
「ロシアの精神が形になったようだ(意味深)!」。
イモネジで下部を固定されたフラッシュハイダーは14mm逆ネジで締められており、
取り外せばマルイ電動ガンに使用可能なハイダー、サプレッサは取付可能。
シュタイアーAUGみたいにグリップと(ていうかフレームと)一体化した
独特スギィ!なフォアグリップはとっつきにくて握りにそうではありますが、
コレが案外フィット感が良くて(個人の意見です)驚きです。
残念なのはこのフォアグリップ周りにレールが付属しないことなんですが、
ロシア的には「レール?そんなのどーせライトぐらいしか付けねぇだろ?」なんでしょうね。

AKみたいな雰囲気のフロントサイトは上下調整が可能です。
まあでもこの手の武器は光学サイト載せての運用が現代の主流でしょう。
それよりもさぁ、フロントサイト根本からピンがとびだせどうぶつの森しているのは何?
注:専用サプレッサーを取り付ける時に引っ掛けるピンでした。
フロントサイト奥のパイプみたいなのがチャージングハンドルになります。
射撃時にはココが豪快に前後しやがるのです。
H&K G36みたいに左右どちらかに折り曲げてコッキングしますが、
G36みたいにバネで真っ直ぐには戻らず、折れ曲がった状態で保持されます。
コレもとっさに使いやすいかと問われると微妙(多分慣れの問題)ですが、
銃を構えて操作しやすいという点では後端部をコッキングするMP7よりも良い感じです。

実銃では9mm弾を詰め込むマガジンが収まる
謎の前傾グリップの握り心地は意外と普通というか、良い。
厚みがなくて握りやすいのが掌が小さい我輩には良きかな。
でもグリップ後端部の穴の意味がさっぱり解りません。
パラコードでも通して、スリングでも引っ掛けろと言いたいのでしょうか?
(しかしスリングスイベルはまた別のところに付いているという)
棒を削って指掛を付けたような細いトリガーのキレは意外と普通&素直で、
RAPTOR製MP443みたいな変な癖はなし。
マガジンキャッチは一般的なハンドガンと同じ場所に設けられており、
使用感もハンドガンとほぼ一緒でマガジンも素直に抜けてくれます。
なお、トリガーガード後部とトリガー後部に空いている穴がホップ調整用の穴。
ココにクソ長アレンレンチを突っ込んで回し、ホップダイヤルを調整します。
ところでさぁ、ロシア人ってデカいセレクターどんだけ好きなんですかねぇ?
親指で操作可能な位置に設置されてはいるものの、このセレクターの存在感よ。
見た目より使いやすい形状ではありますが、動きは渋いです。
なお、セレクターの位置は一番上がセイフティ、真ん中がフルオート、一番下がセミ。
AKと同じポジション設定はAKを使い慣れたロシアの兵士にも優しい設計?
なお、セイフティ状態でコッキングするのはダメみたいですね。
マガジンを抜く前にセレクターをセーフに入れるのもダメらしいです。
ジャムった時にセイフティをかけるのもダメなんですと。
上記事項を守らないと、銃がぶっ壊れるらしいです(迫真)。

リアサイトはレールに侵食され、とりあえず付けときました感半端なし。
まあ前述のようにレールにドットサイト取り付け前提で開発されたんでしょうし、
このサイズのサブマシンガンに過度な命中精度は
期待するなというのが本音なのでしょうか?

サイドスイングで射手の体型に合わせて調整できない
折りたたみストックは前時代的と言うか、武器に身体を合わせろなロシア的。
構えた感触は我輩の体系的には特に問題なし。
銃本体を掴みながらストック本体を持ち上げて握ってロックを解き、ストックを展開します。
折りたたむ時も同様の操作にて実施しますが、正直慣れないと展開しにくい。
MP7みたいなスライドタイプのストックって使いやすくていいですね。
余談ですが折りたたみ状態ではすっげぇガッタガタで
遠慮なしに本体にバシバシ当たりやがるのが困りものです。
そしてこの無愛想で前時代的な折りたたみストックは
レシーバー後端部分のボタンを押すことで取り外しが可能です。
(余談であるがボタンの近所にある出っ張りはスリングスイベル)

何でストックが外れる必要なんかあるんですか(正論)
それはねロングマガジンをストックの代わりにするためなんですね。
発想は面白いと言うか、誰も考えもしなかった的ではありますが、
その機能が果たして必要だったのかと問われると
我輩的には「そんなことしなくていいから(良心)」という思いなんですがね。
どうでもいい話ですがストックを外した状態でも撃てます。
でも当たりにくくなるのでやっぱりストックが欲しくなります。

付属のショートマガジンは22連とマルイガバメントよりも少ない残念な装弾数。
その上「お前さっきグリップにマガジン突っ込んだ時チラチラ見てただろ(因縁)」と
言いたくなる程マガジンからCO2ボンベがチラリズムで存在感を見せつけます。
リアルさという点ではこのCO2マガジンの外観は・・・ダメみたいですね(諦観)。
そしてこのショートマガジン、お値段が定価8000円ぐらいっていうんですから、
マルイのMP7みたいに予備マガジンを大量に揃えるのも金銭的に修羅の道です。
ロングマガジンは装弾数56発とショートマガジンの倍以上のキャパなのに、
お値段の差はショートマガジン+2000円。
前述のようにこの銃にコスパを求めること自体が愚かなのですが、
戦力的or金銭的お得感はロングマガジンのほうが断然高いと我輩は思います(個人の感想です)。
でもロングマガジン、長スギィ!でかなり邪魔なんですがね。
因みに、基本はCO2での運用が主であるMODIFY製PP2000ですが、
フロンガスをチャージするマガジンも販売されております。
(お値段はロング、ショート共にCO2マガジンよりも1000円ぐらい安い)
但し、CO2を使用したときよりも10m/s程パワーが劣る模様ですし、
気温が低くなるとマトモな作動は期待できないとのことです。
実はMODIFY製PP2000がCO2ガスガン初体験の我輩、
ボンベをマガジンに「よし、じゃあブチ込んでやるぜ」に多少戸惑いましたが
ボンベを横から突っ込んでアレンレンチ突っ込んで
下から真っ直ぐねじ込めばとりあえず収まりますが
我輩がブチ込むと3本に2本は入れて直ぐ「シュー!(迫真)」って音がするのが恐怖。

まずは22連ショートマガジンにボンベを挿入、
とりあえず空撃ちでもしてみようかと弾を込めずにマガジンぶっ挿して
チャージングハンドル引いてみたら何ということでしょう、
マガジンフォロアーにノズルが引っかかってハンドルが中途半端な位置で止まります。
なるほど、撃ち終わるとこのようにしてホールドオープンするのか。
ボルトリリースレバー的なものは付いておらず、マガジン抜くとボルトは戻ります。
弾を詰めてセミオートで発射。
夕方でも気温が20℃ぐらいある宮崎の今の季節、作動は快調そのもの。
セミオートでも面白いぐらいに銃が暴れます。
全て弾を撃ち尽くしたら次弾装填、次はフルオート。
22連マガジンはあっという間に空になります。
弾速計で測ってみると秒間16~18発ぐらいだったので、サイクルは若い頃の我輩の腰ぐらい。
次は56連ロングマガジンにボンベ装填、弾を詰めますが56発キレイに入りません。
ボンベをブチ込んで1回目の射撃(セミオート)では初速は平均75m/s位を叩き出しました。
2回目、マガジンの少し冷えた状態での射撃初速は65m/sぐらいに落ちて、
「バッチェ冷えてますよ!」な3回目は半分ぐらい弾を残した状態で閉鎖不良になって弾が出なくなりました。
飛距離に関しては電動ガンより劣るのは仕方ないですが、
デカいハンドガンと考えれば充分な飛びっぷり。
コンパクト電動ガンぐらいの飛距離は出ているので文句なしですね。
但し、銃自体が軽いのとリコイルが災いしているのか命中精度は然程期待できません。
セミオートなら狙って当てられないことはないですが、
フルオートではかなり飛び散って正確に当てるのは難しいです。
まあガスブロのフルオートに命中精度を期待しちゃいけないんですがね。
気になる燃費は1ボンベでセミオートならロングマガジンで2.5マガジン、
フルだと2マガジン撃つとガス欠でスライドが動かなくなります。
まあ大体100発は撃てると考えて差し支えないでしょう。
なお、ガス欠前の最後の方の弾速&リコイルはジジィのファ★クの方が気合が入っています。
途中でガスを追加or交換できないのがCO2ガスガンの欠点ですね。

今後起こることが予測されるであろうジャムのトラブルシューティングに必要なので、
取説を見ながらMODIFY製PP2000を分解してみます。
グリップ内部の分解レバーを銃先端側に倒すことで
アッパーレシーバー(アウターバレル?)が分離できます。

見たところボルトの立て付けや滑り具合に特に問題はないので、
すり合わせを良くする等、特に手を加える要素はないみたいですし、
明日も仕事で忙しいのでコレ以上分解はしません。

アッパーレシーバーはバレルASSY、リコイルスプリング、ボルトASSYに分離できます。
一通り内部を見てみましたが、コレと言った不具合はない感じです。

インナーバレルやパッキンを交換するのであれば、バレル周りを分解する必要がありますが、
他の部分は分解調整しなくてもどうにかなりそうですし、
多分社外品のスプリングとかブリーチとかは出なさそうな予感。

ロアフレーム内部もわざわざバラして中身を取り出し、
パーツ類を耐水ペーパーで滑らかにする必要はないのでこれ以上手はつけません。
MODIFY製PP2000、残念ながら分解してもバラバラにする必要性は皆無の模様。

というわけで元に戻しましょうかね。
リコイルスプリングをロアフレーム内部の凹み部分に押し当てて、
アッパーレシーバーを組み込みます。

その後、バレル部分を上から押さえて、
ロック部分を結合すればちゃんと組み上がるはずです。

携行性の高い軽量サブマシンガンということで、
その性格をスポイルしない小型のドットサイトを搭載し、
スリングを取り付けて持ち運びしやすくしてみました。
ロングマガジンはP90用のマガジンポーチに収まったので、
(但し、太いP90のマガジンが入る入れ物に細いマガジンをブチ込むからガバガバ)
予備マガジンの携行をご検討の方はぜひとも購入すべし。
以前スカルガンナー氏に撃たせてもらったKWC製MINI UZIと比べると
作動は安定している感がありますし、扱いやすいし、リコイルも抜群ではありますが、
他の21世紀前後に登場したサブマシンガンと比べると利便性は恐らく微妙です。
我輩的にはMODIFY製PP2000、実に気に入りました。
ロシアの銃器、独特なのに構えやすい外観、CO2ならではの激しい撃ち味、
そして海外製品とは思えない作動の良さは我輩を虜にしてくれました。
但し、MP7じゃ面白くない、人とは違うガスブロが欲しいというような、
浮ついた気持ちで手を出してはいけない気がするMODIFY製PP2000。
コレはロシアの大地のように壮大で大雑把な気持ちで
購入して運用しなければいけない銃でしょうね。
但し、現時点でCO2を使用するサブマシンガンは選択肢が少ないですし、
モノによってはパワー的にそのまま使えない物もあるようなので、
安心して使えるCO2サブマシンガンが欲しいという層には良い選択肢なのかも?
2021年03月07日
E&L製AKMをフリマで安く買えた
どーも、去年の11月初め頃にエイトドラゴンに行って以来、
全然サバゲーしていないけど特に何とも感じない砥部良軍曹です。
何なんだろう、この倦怠感と言うかやる気の無さは?
まあいいや、やる気というものは勝手に湧き上がるものではなく、
「何かをしなければ」と言う状況の中から生まれるものらしいので、
「今は何もしなくて良い時なんだ」と思うことにしときましょう。
話が横道にそれますが最近インスタ始めました。
でもアレの何が面白いのかさっぱり理解できません。
アレだけのために面白い写真とか旨そうな食い物をアップしたがる輩の気がしれんです。
多分我輩、4月ぐらいにはインスタ止めているでしょう。
まあ、前述のように「何もしなくていい」と思っているから面白くないんでしょうがね。
自分表現って何かしら必然性があるからやることなんですよ。
我輩の場合は「宮崎でもっとサバゲーを流行らせたい」とか、
「新富町にはロシア連邦軍親父が居るよアピール」いう必然性のもとで
このブログをチマチマとアップしているのでありますが、
最近ではそんなアピールしなくてもいいような気がしてきましたからね。
でも少しはアピールしたいので月イチで更新だけしときます。

さて、今回のネタは昨年末に開催されたホークウッドでのフリマ「ホーク売っど!」で
同志スカルガンナー師がE&L製AKMを0.4パットンで出していたので、
40秒も考えずに持ってきていた諭吉2枚で速攻お買い上げしましたという話です。
箱なし説明書付属品なし、本体とマガジンのみの販売ですがこのお値段は破格。
いやーやっぱり我輩的に木製ストックが付いているライフルは最高ですな。
旧車のウッドステアリングとか、一枚板のテーブルとかいった木製製品は我輩の大好物ですよ。
ていうか昔、父上から貰った日産ラルゴに乗っていた時は、
ナルディのウッドステアリングに交換して乗っていましたからね。
(でも1年後にひび割れしたのでMOMOのステアリングに交換したけどね)
ていうか我輩、過去に色んなメーカーのAKMとAKMSとを交互に仕入れては、
「やっぱ要らないか」と思って手放すという行為を幾度となく繰り返している気がする。
コレはやはり、決定版的な満足度の高いブツを手にしなかったが故の愚行ですかね?
という事はやはり、過去に無理してでもLCT製のAKMを買うべきだったか?
さて、我輩的にE&Lというメーカーのエアガンのレビューを
ざっくり一言で書いてしまうと「ジェネリックLCT」です。
(注:ジェネリックと言う言葉は本来「一般的な」と言う意味の言葉で
海外では薬を販売する際、ブランド名でなく一般名を使うことからこう呼ぶそうなのだが
敢えて後発医薬品を意味する「ジェネリック」と言う意味で使わせてもらう)
LCTとは細かいところで違いがあるけれど知らん人が見ればどっちも似たよーな見栄え。
素人が指摘できる違いは精々ストックの色合いの違いぐらいでしょう。
でもメカボックスの中身の精度や構成部品の工作精度とか、
LCT製品を所有していれば「ああ、コイツは違う」と解る部分も多々あります。
実銃のAKファミリーの中でAKMがどういう位置づけのライフルであるか
今更説明する必要はないでしょうが軽く適当に説明すると
「試作品的要素が残っていたAK47の完全版」であると我輩は断言します。
解りやすく言うとAK47が旧ザクならAKMがザク。
つー事はAK74はザク高機動型?それとも後継が違うから「ザクとは違うのだよ」グフ?
余談ですがAK47は日本のサバゲー界隈的には
マルイがAKMの電動ガンを出してくれなかったせいで一番知名度が高いですが、
(ていうかマルイさん、AKMのガスブロ販売あくしろよ)
ソビエト連邦的には1940年代後半~1960年代前半までしか使われなかったAK47に対し
1960年代~2000年代まで永きに渡って使われた7.62mm×39のAKの代表です。

過去に我輩、CYMA、DBOY、VFC、LCT、E&Lと色んなメーカーのAKを仕入れましたが、
E&L製AKMは中華AKの中ではCYMAやDBOYの1ランク上の出来栄えですね。
但しお値段も少々お高め、VFCやLCTと同じぐらいではありますがw
(E&L製AKの新品相場は42000~48000円ぐらい、うわー高いな)
AKが万人に受け入れられない理由はセレクターがグリップ付近でなく
フレーム右側の使いにくい位置にあるが故に指で素早く切り替えることが
出来ないということで使いにくいという難点があるからでしょう。
正直な話、我輩的にもタクトレやシューティングマッチで使うなら、
操作が容易なM4系列のライフルを勧めるところですが、
スタートの合図前にセレクターを切り替えればいいサバゲーでは
AK系列のライフルを使うことに特に不具合を感じたことはありません。
そしてまだ光学照準器が一般的ではなかった時代に出たAKMには
サイドマウントがないのでドットサイト等を取り付けることが出来ないというのも
AKMが一般的なサバゲープレイヤーの購入対象にならない理由でしょう。

相場がお高めなだけあってフロントサイトやフラッシュハイダー、アウターバレル、
ガスバイパス部分の作りは実によく出来ておりますし、素材はFe(鉄)。
但し、フロントサイトとガスチューブ周りはダッチオーブンと同じキャストアイアンでしょう。
そういえばこないだツイッタ見ていたらLCT製AKのフロントサイトやガスチューブ部分が
亜鉛合金のようにばっくりクラックが入っている写真がアップされていたんですが、
キャストアイアンが削り出しやプレスの鉄と比べるとまあ多少は衝撃に弱いとはいえ、
割れるぐらいまでダメージを与える状況ってどれだけの衝撃なんでしょうかね?
まあ木のバリケードにぶつかった程度では割れることはないでしょうが、
ブロックとか石にぶつければダメージはまあ多少はあると思われます。

青森に居た頃、後輩のG2所有のLCT製AKMと砂井さんのE&L製AK74を比べたところ、
E&L製の方がストックやハンドガードが少し赤っぽい塗りだったイメージが有りましたが、
こないだ我輩が仕入れたLCT製RPKS74と比べたところ
E&L製のAKのハンドガードは色がどうこうと言うよりは塗りが濃いみたいです。

リアサイトはしっかりホワイトが入って字が大きめ。
リアサイトブロックはLCT製と比べると少しザラザラ感。
そしてブロックのあちこちに錆があるというwww

LCT製AKも鉄で出来ているんで水分含むとサビは出るんですが、
E&L製AKの方が錆びやすいとAK界隈ではよく言われているようです。

フレームの仕上がりは単体で見ると綺麗なんですが、
LCT製AKと比べてみたら少々粗さがありますね。
レシーバーカバーは閉まりが悪かったんで後部を少し削る必要がありました。
チャージングハンドルはLCT製と比べると後退量が1cm程少ないです。
セレクターの動きが渋いのはLCT製、E&L製も同じぐらい。
尚、E&L製AKは全てバッテリーをレシーバーカバー内に収める仕様になっているようです。
収納可能なサイズはリポバッテリーorリフェの細長いタイプになります。

ニス塗りのストックはうっとりする出来栄えと言いたいところですが、
この部分の塗りは悪くてB品になっていたものを
同志スカルガンナー師は安価にて購入したそうです。
でもやはり、木製ストックってゴシックロリィタ的な奥ゆかしさと華やかさを感じますね。
露出がないのにエロスを感じる的な何と言うか、男心を擽るものであります。
下向きに取り付けられたスリングスイベルはタクティコゥな使用には向きませんが、
どーせ我輩は古典的なコットン製2点スリング使うから無問題。
余談ですが我輩は女性の下着はコットンが好みです。
ストックはバッテリーを入れられない(入れない)構造なので、
ストック後部の蓋の中にはクリーニングキットが入れられます。
そしてこのストックがまた、いい感じにガッチリ固定されているんですね。
相当ぶん殴らないとガタガタになら無さそうなぐらいガッチガチ。

AKMには本来サイドレールがないので光学照準器は諦めましょう。
ていうかそういうタクティコゥ思考ならAKM買うな、AK105とか買えよって話です。
あと、E&L製AKはトリガーガードがリベットで固定されているので、
LCT製AKに取り付けるよーなマグウェルが付けられませんと言うか、
どーしても付けたいならリベットをドリルでぶち抜く&穴にねじ切る加工が必要です。
だから、タクティコゥ思考ならLCTのZENITパーツが付いたの買いなさい。

デフォルトで付属するマガジンは120連マガジン。
フレーム同様の染め加工で結構キレイなのが好みですが、多分錆びるw
マルイやCYMAのノーマルor多弾数600連マガジンも使用可能です。

バッテリー繋いで撃ってみたところ、予想通りスカルガンナー師が手を入れていたようで、
モーターは信頼性の高いマルイEG1000に換装済みでしたし、
メカボックスの動きや音に特に不満はなくパワーも85m/s以上出ていたので
バラす必要はなかったのですがストック塗り直したくてバラしました。
E&L製AKMの分解方法は以前紹介したLCT製AKMとほぼ同じですが、
とある理由で少しだけ違う部分があるので取り合えず分解方法を上げときます。
まずはお約束のハンドガード周りの分解。
リアサイト横のレバーを上に回してガスチューブ部分を外します。

その後(ていうか一番初めでもいいけど)クリーニングロッドを引き抜き、
ハンドガード前方を固定している部分の内側にあるレバーを上に回して
ハンドガード固定しているパーツを前方にずらしてハンドガードを外します。

そしてチャージングハンドルを外すためにデッキロックボタンの根元のイモネジを緩め、
バネが飛んでいかないように注意しながらチャージングハンドルを外します。

LCT製AKの場合はリアサイトブロックをアウターバレルに固定している
ピンを叩いて抜けばリアサイトブロックがずれて分解可能なんですが、
E&L製AKの場合はこの部分のピンがガッチガチで抜けません。
相当ぶっ叩きまくってどーにかははピンを抜いてみたのですが、
リアサイトブロックをいくら殴っても1mmたりとも動く気配すらありません。

仕方がないのでリアサイトを外そうとしたら何ということでしょう、
リアサイトを固定している板バネが硬くてリアサイトが外れません。
仕方がないのでリアサイトブロック内部にアレンレンチ(L字部分が短いの)をツッコみ、
チマチマとイモネジを緩めてフレームからアウターバレルを外すしか無いという悲劇に襲われます。
この部分が容易に分解できないという時点で我輩的にE&L製AKはオススメしません。
E&L製AKのジェネリック製品、アローダイナミック製のAKも同様の難所があるので、
多少安いからといってうかつに手を出すのはオススメできません。

イモネジとの仁義なき戦いの後、無事アウターバレルが外れたら、
チャンバーをフレームに固定するネジを緩めましょう。
因みに、E&L製AKはデフォルトではチャンバーは金属製のものが付いておりますが、
コレがあまり出来がよろしくないのでマルイ製AK用チャンバーに交換するのが望ましいです。
ついでにチャンバーパッキンもマルイ製に換えておいたほうが無難かと。
欲を言えばインナーバレルもマルイ製に換えてしまいたいですがね。

アウターバレルを前にずらしたらインナーバレルを後ろに抜き、
バレルをフレームから外せばようやくメカボックスが取り出せるようになります。
ここに至るまでの所要時間、CYMAやLCTなら20分程度で済むんですが、
E&Lの場合はイモネジとの格闘があるので30分以上かかります。もう嫌だ。

セレクターを留めているネジをプライヤーで摘みながら外し、
グリップ底部のネジを外してグリップを外してしまえば
後は配線に注意しながらメカボックスを上に引き抜くだけです。
余談ですがフレームのマガジン挿入口の下にあるパーツは
マガジン挿入口に取り付けてマガジンチェンジを円滑にするスペーサー。
マガジン挿入部がスカスカなLCT製AKにはお約束のパーツですが、
E&L製AKも同様の作りになっているのでコイツは必需品です。

ストックは根元の上下のネジを緩めて外します。
でもこのままスポッと抜けるような代物じゃないんですねコレが。
ネジを緩めてもストックはガッチガチに固定されております。

尚、ストック付け根部分のフレーム内部はこの様になっており、
ストック内にバッテリーを収めるにはストック付け根部分を
相当根性入れて機械でガリガリ削る必要があるので素直に諦めましょう。

結局、ストックの細い部分にウエスを巻き、
プラスチックハンマー(出来ればゴムハンマーが良い)で30分ぐらい殴り続けて、
2mm程ストックとフレームの間に隙間が出来たところにマイナスドライバーをツッコみ、
少しずつグリグリしながらどうにかストックを外すことに成功しました。
この後、ストック内部とフレーム根元を少しヤスリで削り、
ストックが適度に緩くフレームにハマるように加工して以後の取り付けが楽になりました。

E&L製AKのメカボックスはグリスが中華青グリス、
シム調整も適当らしいのでグリス塗り直しとシム調整が必須のようです。
LCT製AKと同じノリで箱出しでそのまま使うと後々不具合発生しそうです。
外装パーツの構成的にはLCT製AKと大差ないので、
LCT用のパーツも少し加工すれば、あらるいは少し無理すれば取り付けられます。
でもぶっちゃけ正直、E&L製AKは外装そのままで使うことをオススメしますね。
カスタム志向ならハナっからLCT製AKを買うべきです。
我輩的にE&L製AKMは中身を多少手を入れる手間はあれど、
外観は良く出来ているので大変満足の逸品です。
ソ連軍装備orベトコン装備でサバゲーする時に使うので外装のカスタムは必要ありませんしね。
コレで今後、我輩がAKMに飽きて手放すことは無さそうですw
猫も杓子もレール付きの銃を欲する昨今、我輩のような木製ストックフェチも少なくなり、
市場が小さく需要が少ないためかAKMの再販予定のアナウンスを聞く事もありません。
なのでここ数年、木製ストックのAKMは品薄でなかなか入手が困難なようです。
だから悪いことは言わん、欲しいなら見つけたら直ぐに買わないと後悔する。
全然サバゲーしていないけど特に何とも感じない砥部良軍曹です。
何なんだろう、この倦怠感と言うかやる気の無さは?
まあいいや、やる気というものは勝手に湧き上がるものではなく、
「何かをしなければ」と言う状況の中から生まれるものらしいので、
「今は何もしなくて良い時なんだ」と思うことにしときましょう。
話が横道にそれますが最近インスタ始めました。
でもアレの何が面白いのかさっぱり理解できません。
アレだけのために面白い写真とか旨そうな食い物をアップしたがる輩の気がしれんです。
多分我輩、4月ぐらいにはインスタ止めているでしょう。
まあ、前述のように「何もしなくていい」と思っているから面白くないんでしょうがね。
自分表現って何かしら必然性があるからやることなんですよ。
我輩の場合は「宮崎でもっとサバゲーを流行らせたい」とか、
「新富町にはロシア連邦軍親父が居るよアピール」いう必然性のもとで
このブログをチマチマとアップしているのでありますが、
最近ではそんなアピールしなくてもいいような気がしてきましたからね。
でも少しはアピールしたいので月イチで更新だけしときます。

さて、今回のネタは昨年末に開催されたホークウッドでのフリマ「ホーク売っど!」で
同志スカルガンナー師がE&L製AKMを0.4パットンで出していたので、
40秒も考えずに持ってきていた諭吉2枚で速攻お買い上げしましたという話です。
箱なし説明書付属品なし、本体とマガジンのみの販売ですがこのお値段は破格。
いやーやっぱり我輩的に木製ストックが付いているライフルは最高ですな。
旧車のウッドステアリングとか、一枚板のテーブルとかいった木製製品は我輩の大好物ですよ。
ていうか昔、父上から貰った日産ラルゴに乗っていた時は、
ナルディのウッドステアリングに交換して乗っていましたからね。
(でも1年後にひび割れしたのでMOMOのステアリングに交換したけどね)
ていうか我輩、過去に色んなメーカーのAKMとAKMSとを交互に仕入れては、
「やっぱ要らないか」と思って手放すという行為を幾度となく繰り返している気がする。
コレはやはり、決定版的な満足度の高いブツを手にしなかったが故の愚行ですかね?
という事はやはり、過去に無理してでもLCT製のAKMを買うべきだったか?
さて、我輩的にE&Lというメーカーのエアガンのレビューを
ざっくり一言で書いてしまうと「ジェネリックLCT」です。
(注:ジェネリックと言う言葉は本来「一般的な」と言う意味の言葉で
海外では薬を販売する際、ブランド名でなく一般名を使うことからこう呼ぶそうなのだが
敢えて後発医薬品を意味する「ジェネリック」と言う意味で使わせてもらう)
LCTとは細かいところで違いがあるけれど知らん人が見ればどっちも似たよーな見栄え。
素人が指摘できる違いは精々ストックの色合いの違いぐらいでしょう。
でもメカボックスの中身の精度や構成部品の工作精度とか、
LCT製品を所有していれば「ああ、コイツは違う」と解る部分も多々あります。
実銃のAKファミリーの中でAKMがどういう位置づけのライフルであるか
今更説明する必要はないでしょうが軽く適当に説明すると
「試作品的要素が残っていたAK47の完全版」であると我輩は断言します。
解りやすく言うとAK47が旧ザクならAKMがザク。
つー事はAK74はザク高機動型?それとも後継が違うから「ザクとは違うのだよ」グフ?
余談ですがAK47は日本のサバゲー界隈的には
マルイがAKMの電動ガンを出してくれなかったせいで一番知名度が高いですが、
(ていうかマルイさん、AKMのガスブロ販売あくしろよ)
ソビエト連邦的には1940年代後半~1960年代前半までしか使われなかったAK47に対し
1960年代~2000年代まで永きに渡って使われた7.62mm×39のAKの代表です。

過去に我輩、CYMA、DBOY、VFC、LCT、E&Lと色んなメーカーのAKを仕入れましたが、
E&L製AKMは中華AKの中ではCYMAやDBOYの1ランク上の出来栄えですね。
但しお値段も少々お高め、VFCやLCTと同じぐらいではありますがw
(E&L製AKの新品相場は42000~48000円ぐらい、うわー高いな)
AKが万人に受け入れられない理由はセレクターがグリップ付近でなく
フレーム右側の使いにくい位置にあるが故に指で素早く切り替えることが
出来ないということで使いにくいという難点があるからでしょう。
正直な話、我輩的にもタクトレやシューティングマッチで使うなら、
操作が容易なM4系列のライフルを勧めるところですが、
スタートの合図前にセレクターを切り替えればいいサバゲーでは
AK系列のライフルを使うことに特に不具合を感じたことはありません。
そしてまだ光学照準器が一般的ではなかった時代に出たAKMには
サイドマウントがないのでドットサイト等を取り付けることが出来ないというのも
AKMが一般的なサバゲープレイヤーの購入対象にならない理由でしょう。

相場がお高めなだけあってフロントサイトやフラッシュハイダー、アウターバレル、
ガスバイパス部分の作りは実によく出来ておりますし、素材はFe(鉄)。
但し、フロントサイトとガスチューブ周りはダッチオーブンと同じキャストアイアンでしょう。
そういえばこないだツイッタ見ていたらLCT製AKのフロントサイトやガスチューブ部分が
亜鉛合金のようにばっくりクラックが入っている写真がアップされていたんですが、
キャストアイアンが削り出しやプレスの鉄と比べるとまあ多少は衝撃に弱いとはいえ、
割れるぐらいまでダメージを与える状況ってどれだけの衝撃なんでしょうかね?
まあ木のバリケードにぶつかった程度では割れることはないでしょうが、
ブロックとか石にぶつければダメージはまあ多少はあると思われます。

青森に居た頃、後輩のG2所有のLCT製AKMと砂井さんのE&L製AK74を比べたところ、
E&L製の方がストックやハンドガードが少し赤っぽい塗りだったイメージが有りましたが、
こないだ我輩が仕入れたLCT製RPKS74と比べたところ
E&L製のAKのハンドガードは色がどうこうと言うよりは塗りが濃いみたいです。

リアサイトはしっかりホワイトが入って字が大きめ。
リアサイトブロックはLCT製と比べると少しザラザラ感。
そしてブロックのあちこちに錆があるというwww

LCT製AKも鉄で出来ているんで水分含むとサビは出るんですが、
E&L製AKの方が錆びやすいとAK界隈ではよく言われているようです。

フレームの仕上がりは単体で見ると綺麗なんですが、
LCT製AKと比べてみたら少々粗さがありますね。
レシーバーカバーは閉まりが悪かったんで後部を少し削る必要がありました。
チャージングハンドルはLCT製と比べると後退量が1cm程少ないです。
セレクターの動きが渋いのはLCT製、E&L製も同じぐらい。
尚、E&L製AKは全てバッテリーをレシーバーカバー内に収める仕様になっているようです。
収納可能なサイズはリポバッテリーorリフェの細長いタイプになります。

ニス塗りのストックはうっとりする出来栄えと言いたいところですが、
この部分の塗りは悪くてB品になっていたものを
同志スカルガンナー師は安価にて購入したそうです。
でもやはり、木製ストックってゴシックロリィタ的な奥ゆかしさと華やかさを感じますね。
露出がないのにエロスを感じる的な何と言うか、男心を擽るものであります。
下向きに取り付けられたスリングスイベルはタクティコゥな使用には向きませんが、
どーせ我輩は古典的なコットン製2点スリング使うから無問題。
余談ですが我輩は女性の下着はコットンが好みです。
ストックはバッテリーを入れられない(入れない)構造なので、
ストック後部の蓋の中にはクリーニングキットが入れられます。
そしてこのストックがまた、いい感じにガッチリ固定されているんですね。
相当ぶん殴らないとガタガタになら無さそうなぐらいガッチガチ。

AKMには本来サイドレールがないので光学照準器は諦めましょう。
ていうかそういうタクティコゥ思考ならAKM買うな、AK105とか買えよって話です。
あと、E&L製AKはトリガーガードがリベットで固定されているので、
LCT製AKに取り付けるよーなマグウェルが付けられませんと言うか、
どーしても付けたいならリベットをドリルでぶち抜く&穴にねじ切る加工が必要です。
だから、タクティコゥ思考ならLCTのZENITパーツが付いたの買いなさい。

デフォルトで付属するマガジンは120連マガジン。
フレーム同様の染め加工で結構キレイなのが好みですが、多分錆びるw
マルイやCYMAのノーマルor多弾数600連マガジンも使用可能です。

バッテリー繋いで撃ってみたところ、予想通りスカルガンナー師が手を入れていたようで、
モーターは信頼性の高いマルイEG1000に換装済みでしたし、
メカボックスの動きや音に特に不満はなくパワーも85m/s以上出ていたので
バラす必要はなかったのですがストック塗り直したくてバラしました。
E&L製AKMの分解方法は以前紹介したLCT製AKMとほぼ同じですが、
とある理由で少しだけ違う部分があるので取り合えず分解方法を上げときます。
まずはお約束のハンドガード周りの分解。
リアサイト横のレバーを上に回してガスチューブ部分を外します。

その後(ていうか一番初めでもいいけど)クリーニングロッドを引き抜き、
ハンドガード前方を固定している部分の内側にあるレバーを上に回して
ハンドガード固定しているパーツを前方にずらしてハンドガードを外します。

そしてチャージングハンドルを外すためにデッキロックボタンの根元のイモネジを緩め、
バネが飛んでいかないように注意しながらチャージングハンドルを外します。

LCT製AKの場合はリアサイトブロックをアウターバレルに固定している
ピンを叩いて抜けばリアサイトブロックがずれて分解可能なんですが、
E&L製AKの場合はこの部分のピンがガッチガチで抜けません。
相当ぶっ叩きまくってどーにかははピンを抜いてみたのですが、
リアサイトブロックをいくら殴っても1mmたりとも動く気配すらありません。

仕方がないのでリアサイトを外そうとしたら何ということでしょう、
リアサイトを固定している板バネが硬くてリアサイトが外れません。
仕方がないのでリアサイトブロック内部にアレンレンチ(L字部分が短いの)をツッコみ、
チマチマとイモネジを緩めてフレームからアウターバレルを外すしか無いという悲劇に襲われます。
この部分が容易に分解できないという時点で我輩的にE&L製AKはオススメしません。
E&L製AKのジェネリック製品、アローダイナミック製のAKも同様の難所があるので、
多少安いからといってうかつに手を出すのはオススメできません。

イモネジとの仁義なき戦いの後、無事アウターバレルが外れたら、
チャンバーをフレームに固定するネジを緩めましょう。
因みに、E&L製AKはデフォルトではチャンバーは金属製のものが付いておりますが、
コレがあまり出来がよろしくないのでマルイ製AK用チャンバーに交換するのが望ましいです。
ついでにチャンバーパッキンもマルイ製に換えておいたほうが無難かと。
欲を言えばインナーバレルもマルイ製に換えてしまいたいですがね。

アウターバレルを前にずらしたらインナーバレルを後ろに抜き、
バレルをフレームから外せばようやくメカボックスが取り出せるようになります。
ここに至るまでの所要時間、CYMAやLCTなら20分程度で済むんですが、
E&Lの場合はイモネジとの格闘があるので30分以上かかります。もう嫌だ。

セレクターを留めているネジをプライヤーで摘みながら外し、
グリップ底部のネジを外してグリップを外してしまえば
後は配線に注意しながらメカボックスを上に引き抜くだけです。
余談ですがフレームのマガジン挿入口の下にあるパーツは
マガジン挿入口に取り付けてマガジンチェンジを円滑にするスペーサー。
マガジン挿入部がスカスカなLCT製AKにはお約束のパーツですが、
E&L製AKも同様の作りになっているのでコイツは必需品です。

ストックは根元の上下のネジを緩めて外します。
でもこのままスポッと抜けるような代物じゃないんですねコレが。
ネジを緩めてもストックはガッチガチに固定されております。

尚、ストック付け根部分のフレーム内部はこの様になっており、
ストック内にバッテリーを収めるにはストック付け根部分を
相当根性入れて機械でガリガリ削る必要があるので素直に諦めましょう。

結局、ストックの細い部分にウエスを巻き、
プラスチックハンマー(出来ればゴムハンマーが良い)で30分ぐらい殴り続けて、
2mm程ストックとフレームの間に隙間が出来たところにマイナスドライバーをツッコみ、
少しずつグリグリしながらどうにかストックを外すことに成功しました。
この後、ストック内部とフレーム根元を少しヤスリで削り、
ストックが適度に緩くフレームにハマるように加工して以後の取り付けが楽になりました。

E&L製AKのメカボックスはグリスが中華青グリス、
シム調整も適当らしいのでグリス塗り直しとシム調整が必須のようです。
LCT製AKと同じノリで箱出しでそのまま使うと後々不具合発生しそうです。
外装パーツの構成的にはLCT製AKと大差ないので、
LCT用のパーツも少し加工すれば、あらるいは少し無理すれば取り付けられます。
でもぶっちゃけ正直、E&L製AKは外装そのままで使うことをオススメしますね。
カスタム志向ならハナっからLCT製AKを買うべきです。
我輩的にE&L製AKMは中身を多少手を入れる手間はあれど、
外観は良く出来ているので大変満足の逸品です。
ソ連軍装備orベトコン装備でサバゲーする時に使うので外装のカスタムは必要ありませんしね。
コレで今後、我輩がAKMに飽きて手放すことは無さそうですw
猫も杓子もレール付きの銃を欲する昨今、我輩のような木製ストックフェチも少なくなり、
市場が小さく需要が少ないためかAKMの再販予定のアナウンスを聞く事もありません。
なのでここ数年、木製ストックのAKMは品薄でなかなか入手が困難なようです。
だから悪いことは言わん、欲しいなら見つけたら直ぐに買わないと後悔する。
2021年02月04日
性懲りもなくまた買ってしまった長いヤツ
こないだの記事で我輩は「ブルマーは既に絶滅した」と綴りましたが、
実は絶滅しているどころか、我輩の知らないところで進化を遂げておりました。
なんと女子陸上の世界では「レーシングブルマ」という勇ましい名称を名乗り、
大会出場を許された選ばれしアスリートのみが着用できる
勇者の鎧的な存在として君臨しているのだそうです。
ていうか、最近メチャクチャ早そうな女子陸上の選手が履いている、
アシックスとかミズノの海パンみたいなのってそういう名称だったんか・・・
確かにレーシングブルマはブルマの最も機能的だった部分、
脚の付け根の部分を更に露わにすることで可動域を高めることによりスタイリッシュになり
申し訳ない劣情を催すレベルのエロスを醸し出した
紛うことなきブルマの進化系と言っても差し支えないものではありますが、
アレをブルマと呼ぶのには些か違和感を感じるのは我輩だけでしょうか?
スタイリッシュすぎるモノってどうも我輩の性癖には合致しないんですよね。
我輩もサバゲーの装備を決める際、特殊部隊の装備を検討はしましたが、
癖(へき)と言うもんなんでしょうかねぇ、一般兵の装備の方に惹かれるんですね。
というわけなので我輩は選ばれしアスリート(特殊部隊)のレーシングブルマよりは、
普通の女の子(一般兵)が着用する普通のブルマが好きです。
でも皆さん知ってますか?
ブルマってまだ女子が体育を嗜むのが相応しくないと言われていた明治時代に
「運動する女子が居てもいいじゃないか!」という女性の自由を叫ぶ声のもと、
女性向けの体操着として考案された言わば「女性の自由」の象徴なんですよ。
発足当時はもんぺ状の楽な履物という形状だったんですが、
さらなる機能性を追求した結果ちょうちんブルマに進化した後、
最終的に我々の知る太ももを露わにする形状のブルマに変化したそうです。
余談ですが我輩はローカットブルマの控えめなエロスが好きです。
さて、ブルマの話は置いといて今回もタイトル通り性懲りなくエアガンのレビューです。
レーシングブルマみたいに進化を遂げてスタイリッシュになった銃ではなく、
昔の体育の授業で見かけたブルマみたいに古臭さ、野暮ったさを感じるヤツです。

ソレがこのLCT製RPKS74軽機関銃。
この銃の正確な名前を直ぐに答えられた人はかなりの通です。
RPKまでは出てくるかもしれませんが「74」が出てくる人はその中でも30%程度、
「S」まで分かる人は10%ぐらいだと思われます。
よく「RPKとRPK74はどう違うのか?」という質問を受けることがありますが
(大嘘、宮崎のサバゲープレイヤーにそこまでAKについて
詳しく知識を得ようと掘り下げる人間はめったに存在しないw)
外観の大きな違いはRPKはハイダーがAK47同様のものであるのに対し、
RPK74では鳥かご型の発射炎を散らすタイプのものへと変化。
実はソレ以外、特に大きな外観の違いはないという。
でも一番の違いは口径でRPKはAKMと同じ7.62mm×39弾を使用するのに対し、
RPK74ではAK74と同じ5.45mm弾を使用するという違いがあります
ソ連軍装備orロシア軍初期装備用の電動ガンで使えそうなもの、
そして我輩の物欲を満足させてくれるものを検討していた時、
エアガン.JPという通販サイトで中古が0.7パットンで売っていたのを買いました。
新品を買うと1パットン以上するので大変お買い得でした。
こういうなかなか市場に出回らなくて尚且高額な武器を買う場合は、
長期に渡って中古銃取扱店やヤフオクをこまめにチェックしながら
じっくりと探し続ける根気が必要とされますが、
コロナ禍で外出自粛を迫られている現時点、物色の暇は結構あるから、
外に出られなくて辛いと愚痴をいうよりは物欲を煮詰める時間に費やすというのもありかと。

「ところでRPK74とRPKS74、何処が違うのよ?」
ストックが折り畳める、ソレだけです。
RPK74が出た後、装甲車に乗り降りする際に銃身の長いRPKでは、
不便が生じたという現場の意見からストックを折り畳めるRPKSに変化したのでしょう。
以後、ソ連軍及びロシア連邦軍の小火器はストック折りたたみ式が主流になり、
固定ストックのライフルは国境警備隊とか基地防衛隊とかが使用するものとなります。
でもこのストックが折り畳める機能って我輩的には重要なんですよ。
一般的に売られているガンケースの長さは大抵80cmサイズ。
一般的なサバゲープレイヤーが使用している
M4ライフルに適したサイズのものが主流です。
しかしRPK74の全長は1m以上。
そうなると別口で100cmのガンケースを買う必要があります。
でもRPKS74だとストックを折りたたむと80cmぐらいになるので、
AKS74と同じガンケースに入れて持ち運べちゃうんですね。
ぶっちゃけ、ソレ以上の利点はありません。
ストック折りたたんだ状態でサバゲーで使う事はないですからね。
時々この手の折りたたみストックのライフルに対して
「狭い場所ではストックを折りたたんでコンパクトに出来る」と説明している
小火器や戦闘の何たるかを全く理解していない輩が居るようですが、
ストックの折りたたみ機構は運搬時や車載のための機能です。
M14みたいな長いライフルをサバゲーで愛用している人には解るかもしれませんが、
長いライフルを使う時はソレに対応した立ち回りの方法というものがあるので、
(但し、ソレを習得するにはかなりの練習が必要とされるが)
サバゲーでライフルの長さってそれ程障害にはならないんですよね。
寧ろ、長さからくる重さの方が苦になるんですねコレがwww

RPKをRPK足らしめるもの、ソレはこのバイポッド(二脚)。
RPKは軽機関銃という役回りなので遠くに安定した弾丸を撃ち込むために
地面及び遮蔽物に据え付けるためのコレが必要なんですね。
LCTのRPKのバイポットは脚部分は鉄板加工で良く出来てはいますが、
付け根部分がダッチオーブンのような鋳鉄みたいなので
調子に乗ってあまりガチャガチャ動かしていると破損しそうで怖い。
まあ、亜鉛合金のCYMA製RPK74よりは頑丈でしょうけどね。
後もう一つ苦言を述べるとすると、
RPKは長時間の連射に耐えるようにAKよりもバレルが太いのですが、
CYMA製RPK74ではしっかり再現されていたその部分が
LCT製RPK74では再現されていないのも残念ポイントです。
ついでにもう一つ、クリーニングロッドは同社AKの使い回し。
だからノーマルサイズのAKではリアルサイズですが、
RPKではハンドガード先端までしかありません。

RPKのバイポッドを展開すると脚フェチにはたまらない光景がそこにあります。
余談ですがハイレグ好きは大抵、脚の長い女性がお好みのようです(偏見)。
レーシングブルマが良いって言う人種もそこの派生なんでしょうね。
陸上女子のスラッとした脚はRPKのバイポッドと通じるものがある?
但し、昔のフィールドのように敵からの距離が遠いフィールドなら、
銃をバリケードに据え付けての射撃に有効だったんでしょうが、
現在のバリケード多めの戦闘の展開が早いフィールドでは邪魔なだけでしょう。
しかもRPKのバイポッドは展開がかなり面倒ですからね。
そして昔の宮崎ローカルルールでは「全長1m、バイポッド付きのライフルは
機関銃として扱うので弾数無制限(或いは1000発)」というのがあったので、
(昔の宮崎のサバゲーでは1ゲームの持ち弾が300発制限だった)
トリガーハッピー的な意味でRPKの存在意義がある程度有りはしたのですが
何処のフィールドでも弾数無制限となってしまった現在では
敢えてRPKを選択する意味がないのでこいつは完全に漢(おとこ)のロマン武器です。
「じゃあバイポッド外せばいいじゃん?」とツッコみたい方もいるかも知れませんが、
RPKってバイポッドが無くなるとコレジャナイ感半端ないんですよね。

7.62mm口径のRPKと特に変わりのないハンドガードは
LCTお得意の質の良い合板製&美しい仕上がりで
木製ストックフェチの我輩の興奮ポイントです。
木製ストックとブルマは雰囲気が醸し出す温かみが似ていると思うのは多分我輩だけでしょう。
RPKのハンドガードがAKMやAK74みたいなコブ付きでない理由は
(AKM、AK74のハンドガードのコブは握りやすくするためのもの)
RPKがAK47からAKMに変わる時点に開発されたのが理由とされております。
尚、ハンドガードがAKMやAK74と規格が違う(全体的に太い)ので
ガスチューブ部分はAKMorAK74のパーツと交換可能ですが、
ハンドガード部分はRPK専用のものでないとポン付け不可能です。

そしてRPKといえばこの「横調整が可能なリアサイト」。
実はこのリアサイトだけでも0.1パットンします。
しかもこのリアサイト、案外外れやすいんですね。
ガンケースから雑に引っこ抜いただけで外れます。
戦闘中に脱落したらマジ泣きしちゃいますねコレは。

鉄製のフレームは心地よいため息が出るほどの出来栄えです。
フレームの強化リブも入っていてRPKであることを主張。
レシーバーカバーはAKMやAK74と違い、強化リブ無しなのもRPKの特徴。
でもね、何故かLCT製RPKでは樹脂グリップなのが、
RPKS74ではAK47と同じ木製グリップなんですねコレが。
RPKならばAK47のグリップが付いていても可笑しくはないのですが、
Ak47が一線を退いた時代に登場したRPK74でこのグリップは少々可笑しい。
ま、AK74グリップはいくつか持っているんでソレと交換しました。
木製グリップは綺麗なんですが、太くて握りにくいんです。

バイポッド使用時に左手を添えるために膨らみをもたせた
RPK独特の形状の木製ストックも美しいの一言です。
スリングスイベルがこちら側についているのは他の折りたたみストックAK同様、
ストック折りたたみ時にスリングが左に位置するため。
ストック後部には稼働する蓋がついていて、
クリーニングキットを突っ込めるようにもなっています。
余談ですがこのストック、AK74Mのものよりも2cm程短いです。
そのせいかRPKS74、AK74Mと5cmぐらいしか長さに違いがありません。

フレーム左側にはサイドレールマウントは付属しません。
AKMもAK74もRPKもココにマウントが付くようになったのは
ソ連崩壊少し前の80年代中半ぐらいからだったらしいです。

フレームとストックの結合部分にはストック折りたたみレバーがあります。
コレが見た目以上に小さい上に固くて使い難いんだな。
この世で一番使い難い折りたたみストックだと言って過言ではありません。

写真のように親指でグッとレバーを押し込み、ストックを折り曲げます。
当初この部分がなかなか硬くて動かなくて愕然。
でも某国産AK74みたいにレバーが破損する心配は少なさそうです。

そしてストックを伸ばす時はフレーム内部のレバーを押し込んで
ストックを展開しますがこれが折り曲げレバーよりも硬くて指と心が折れそうです。
まあ折りたたみレバーが使いにくい事から、
RPKSの折りたたみストックは戦闘中に使うことは全く想定されておらず、
車載時にコンパクトにするためだけのものであることが伺えます。
それと同時にサバゲーの折りたたみストック武器のレビューに
「狭い場所ではストックを折りたたんで~」とか言っている輩の
知能指数の低さとア*ルの弱さが露見するはずです。

マガジンは茶色の樹脂製550連マガジンが付属します。
このマガジンの色がリアルではないのがLCT製AKの本当に残念部分ですね。
リアルなスリムモーター&グリップなんて作る暇があるなら、
1000円増しになっても構わないからリアルな色合いのマガジン作って欲しい。
実銃では40連マガジンを模した800連マガジンは
CYMA製のものが3000円弱程度で販売されていますが、
全弾撃ち切るのに3回ぐらいゼンマイを巻かなければならないし、
クソ長いマガジンはソレを打ち込むマガジンポーチを探す必要性があるし、
何よりも戦闘中に邪魔なので別に要らないかな?
尚、実銃ではドラムマガジンはRPKもRPK74もロシア製では存在しない模様。
LCTとかBATTLEAXEが販売しているドラムマガジンはノリンコ製のコピーらしいです。
軍隊ではドラムマガジンは弾薬装填に手間がかかるのと、
携行に難がある、確実性に欠けるということであまり使われないそうです。
PPsh41が大戦後期にはバナナマガジンになった理由もそうらしいです。

バッテリーはレシーバーカバー内にスティックバッテリーを収めます。
メカボックスは発射時に特に雑音もなく、ある程度の調整はされているようです。
初速も90m/s前後と必要にして充分な威力で、
常に安定したパワーと作動なので分解調整は必要ないようです。
但し650mmのロングバレルが命中精度に恩恵を与えているかどうかは不明。
発射速度は秒間13~14発程度と可もなく不可もない速度ですので、
無理してモーターを交換しなくてもそのままでも十分美味しくいただけます。

我輩的には見て良し撃って良しのLCT製RPKS74。
木製ストックが醸し出す雰囲気はソ連時代のノスタルジーな香りを感じるような気がすると共に、
体操服ブルマの野暮ったさの中にある奥なるエロス的な魅力を秘めているような気がするのです。
でも正直な話、長くて振り回しにくい(でもAK74Mとの差は数cm程度)、
バイポッドが余計に重い、M4ライフルユーザーには無視されると、
サバゲーでのタクティカルアドヴァンテージは皆無です。
このロングバレルには漢(おとこ)のロマン以外、後は何もありません。
つまり、敢えてRPKをサバゲーの武器としてフィールドに持ち込むプレイヤー、
ソイツらは真のロマンチストであると言っても過言ではないでしょう。
ていうかM60とかM240とか三八式とかM14とかSVDとか長い武器を使いたがるプレイヤーは
我輩みたいにサバゲーに勝利以外、勝利以上のロマンしか求めていないんです。
ソレがなにか他人に説明するのが非常に難しいのは、
漢(おとこ)のロマンは漢(おとこ)達一人ひとりの
心の内に秘めてじっくり温めるものであって
他人に理解してもらうものではないからなんですよね。
実は絶滅しているどころか、我輩の知らないところで進化を遂げておりました。
なんと女子陸上の世界では「レーシングブルマ」という勇ましい名称を名乗り、
大会出場を許された選ばれしアスリートのみが着用できる
勇者の鎧的な存在として君臨しているのだそうです。
ていうか、最近メチャクチャ早そうな女子陸上の選手が履いている、
アシックスとかミズノの海パンみたいなのってそういう名称だったんか・・・
確かにレーシングブルマはブルマの最も機能的だった部分、
脚の付け根の部分を更に露わにすることで可動域を高めることによりスタイリッシュになり
申し訳ない劣情を催すレベルのエロスを醸し出した
紛うことなきブルマの進化系と言っても差し支えないものではありますが、
アレをブルマと呼ぶのには些か違和感を感じるのは我輩だけでしょうか?
スタイリッシュすぎるモノってどうも我輩の性癖には合致しないんですよね。
我輩もサバゲーの装備を決める際、特殊部隊の装備を検討はしましたが、
癖(へき)と言うもんなんでしょうかねぇ、一般兵の装備の方に惹かれるんですね。
というわけなので我輩は選ばれしアスリート(特殊部隊)のレーシングブルマよりは、
普通の女の子(一般兵)が着用する普通のブルマが好きです。
でも皆さん知ってますか?
ブルマってまだ女子が体育を嗜むのが相応しくないと言われていた明治時代に
「運動する女子が居てもいいじゃないか!」という女性の自由を叫ぶ声のもと、
女性向けの体操着として考案された言わば「女性の自由」の象徴なんですよ。
発足当時はもんぺ状の楽な履物という形状だったんですが、
さらなる機能性を追求した結果ちょうちんブルマに進化した後、
最終的に我々の知る太ももを露わにする形状のブルマに変化したそうです。
余談ですが我輩はローカットブルマの控えめなエロスが好きです。
さて、ブルマの話は置いといて今回もタイトル通り性懲りなくエアガンのレビューです。
レーシングブルマみたいに進化を遂げてスタイリッシュになった銃ではなく、
昔の体育の授業で見かけたブルマみたいに古臭さ、野暮ったさを感じるヤツです。

ソレがこのLCT製RPKS74軽機関銃。
この銃の正確な名前を直ぐに答えられた人はかなりの通です。
RPKまでは出てくるかもしれませんが「74」が出てくる人はその中でも30%程度、
「S」まで分かる人は10%ぐらいだと思われます。
よく「RPKとRPK74はどう違うのか?」という質問を受けることがありますが
(大嘘、宮崎のサバゲープレイヤーにそこまでAKについて
詳しく知識を得ようと掘り下げる人間はめったに存在しないw)
外観の大きな違いはRPKはハイダーがAK47同様のものであるのに対し、
RPK74では鳥かご型の発射炎を散らすタイプのものへと変化。
実はソレ以外、特に大きな外観の違いはないという。
でも一番の違いは口径でRPKはAKMと同じ7.62mm×39弾を使用するのに対し、
RPK74ではAK74と同じ5.45mm弾を使用するという違いがあります
ソ連軍装備orロシア軍初期装備用の電動ガンで使えそうなもの、
そして我輩の物欲を満足させてくれるものを検討していた時、
エアガン.JPという通販サイトで中古が0.7パットンで売っていたのを買いました。
新品を買うと1パットン以上するので大変お買い得でした。
こういうなかなか市場に出回らなくて尚且高額な武器を買う場合は、
長期に渡って中古銃取扱店やヤフオクをこまめにチェックしながら
じっくりと探し続ける根気が必要とされますが、
コロナ禍で外出自粛を迫られている現時点、物色の暇は結構あるから、
外に出られなくて辛いと愚痴をいうよりは物欲を煮詰める時間に費やすというのもありかと。

「ところでRPK74とRPKS74、何処が違うのよ?」
ストックが折り畳める、ソレだけです。
RPK74が出た後、装甲車に乗り降りする際に銃身の長いRPKでは、
不便が生じたという現場の意見からストックを折り畳めるRPKSに変化したのでしょう。
以後、ソ連軍及びロシア連邦軍の小火器はストック折りたたみ式が主流になり、
固定ストックのライフルは国境警備隊とか基地防衛隊とかが使用するものとなります。
でもこのストックが折り畳める機能って我輩的には重要なんですよ。
一般的に売られているガンケースの長さは大抵80cmサイズ。
一般的なサバゲープレイヤーが使用している
M4ライフルに適したサイズのものが主流です。
しかしRPK74の全長は1m以上。
そうなると別口で100cmのガンケースを買う必要があります。
でもRPKS74だとストックを折りたたむと80cmぐらいになるので、
AKS74と同じガンケースに入れて持ち運べちゃうんですね。
ぶっちゃけ、ソレ以上の利点はありません。
ストック折りたたんだ状態でサバゲーで使う事はないですからね。
時々この手の折りたたみストックのライフルに対して
「狭い場所ではストックを折りたたんでコンパクトに出来る」と説明している
小火器や戦闘の何たるかを全く理解していない輩が居るようですが、
ストックの折りたたみ機構は運搬時や車載のための機能です。
M14みたいな長いライフルをサバゲーで愛用している人には解るかもしれませんが、
長いライフルを使う時はソレに対応した立ち回りの方法というものがあるので、
(但し、ソレを習得するにはかなりの練習が必要とされるが)
サバゲーでライフルの長さってそれ程障害にはならないんですよね。
寧ろ、長さからくる重さの方が苦になるんですねコレがwww

RPKをRPK足らしめるもの、ソレはこのバイポッド(二脚)。
RPKは軽機関銃という役回りなので遠くに安定した弾丸を撃ち込むために
地面及び遮蔽物に据え付けるためのコレが必要なんですね。
LCTのRPKのバイポットは脚部分は鉄板加工で良く出来てはいますが、
付け根部分がダッチオーブンのような鋳鉄みたいなので
調子に乗ってあまりガチャガチャ動かしていると破損しそうで怖い。
まあ、亜鉛合金のCYMA製RPK74よりは頑丈でしょうけどね。
後もう一つ苦言を述べるとすると、
RPKは長時間の連射に耐えるようにAKよりもバレルが太いのですが、
CYMA製RPK74ではしっかり再現されていたその部分が
LCT製RPK74では再現されていないのも残念ポイントです。
ついでにもう一つ、クリーニングロッドは同社AKの使い回し。
だからノーマルサイズのAKではリアルサイズですが、
RPKではハンドガード先端までしかありません。

RPKのバイポッドを展開すると脚フェチにはたまらない光景がそこにあります。
余談ですがハイレグ好きは大抵、脚の長い女性がお好みのようです(偏見)。
レーシングブルマが良いって言う人種もそこの派生なんでしょうね。
陸上女子のスラッとした脚はRPKのバイポッドと通じるものがある?
但し、昔のフィールドのように敵からの距離が遠いフィールドなら、
銃をバリケードに据え付けての射撃に有効だったんでしょうが、
現在のバリケード多めの戦闘の展開が早いフィールドでは邪魔なだけでしょう。
しかもRPKのバイポッドは展開がかなり面倒ですからね。
そして昔の宮崎ローカルルールでは「全長1m、バイポッド付きのライフルは
機関銃として扱うので弾数無制限(或いは1000発)」というのがあったので、
(昔の宮崎のサバゲーでは1ゲームの持ち弾が300発制限だった)
トリガーハッピー的な意味でRPKの存在意義がある程度有りはしたのですが
何処のフィールドでも弾数無制限となってしまった現在では
敢えてRPKを選択する意味がないのでこいつは完全に漢(おとこ)のロマン武器です。
「じゃあバイポッド外せばいいじゃん?」とツッコみたい方もいるかも知れませんが、
RPKってバイポッドが無くなるとコレジャナイ感半端ないんですよね。

7.62mm口径のRPKと特に変わりのないハンドガードは
LCTお得意の質の良い合板製&美しい仕上がりで
木製ストックフェチの我輩の興奮ポイントです。
木製ストックとブルマは雰囲気が醸し出す温かみが似ていると思うのは多分我輩だけでしょう。
RPKのハンドガードがAKMやAK74みたいなコブ付きでない理由は
(AKM、AK74のハンドガードのコブは握りやすくするためのもの)
RPKがAK47からAKMに変わる時点に開発されたのが理由とされております。
尚、ハンドガードがAKMやAK74と規格が違う(全体的に太い)ので
ガスチューブ部分はAKMorAK74のパーツと交換可能ですが、
ハンドガード部分はRPK専用のものでないとポン付け不可能です。

そしてRPKといえばこの「横調整が可能なリアサイト」。
実はこのリアサイトだけでも0.1パットンします。
しかもこのリアサイト、案外外れやすいんですね。
ガンケースから雑に引っこ抜いただけで外れます。
戦闘中に脱落したらマジ泣きしちゃいますねコレは。

鉄製のフレームは心地よいため息が出るほどの出来栄えです。
フレームの強化リブも入っていてRPKであることを主張。
レシーバーカバーはAKMやAK74と違い、強化リブ無しなのもRPKの特徴。
でもね、何故かLCT製RPKでは樹脂グリップなのが、
RPKS74ではAK47と同じ木製グリップなんですねコレが。
RPKならばAK47のグリップが付いていても可笑しくはないのですが、
Ak47が一線を退いた時代に登場したRPK74でこのグリップは少々可笑しい。
ま、AK74グリップはいくつか持っているんでソレと交換しました。
木製グリップは綺麗なんですが、太くて握りにくいんです。

バイポッド使用時に左手を添えるために膨らみをもたせた
RPK独特の形状の木製ストックも美しいの一言です。
スリングスイベルがこちら側についているのは他の折りたたみストックAK同様、
ストック折りたたみ時にスリングが左に位置するため。
ストック後部には稼働する蓋がついていて、
クリーニングキットを突っ込めるようにもなっています。
余談ですがこのストック、AK74Mのものよりも2cm程短いです。
そのせいかRPKS74、AK74Mと5cmぐらいしか長さに違いがありません。

フレーム左側にはサイドレールマウントは付属しません。
AKMもAK74もRPKもココにマウントが付くようになったのは
ソ連崩壊少し前の80年代中半ぐらいからだったらしいです。

フレームとストックの結合部分にはストック折りたたみレバーがあります。
コレが見た目以上に小さい上に固くて使い難いんだな。
この世で一番使い難い折りたたみストックだと言って過言ではありません。

写真のように親指でグッとレバーを押し込み、ストックを折り曲げます。
当初この部分がなかなか硬くて動かなくて愕然。
でも某国産AK74みたいにレバーが破損する心配は少なさそうです。

そしてストックを伸ばす時はフレーム内部のレバーを押し込んで
ストックを展開しますがこれが折り曲げレバーよりも硬くて指と心が折れそうです。
まあ折りたたみレバーが使いにくい事から、
RPKSの折りたたみストックは戦闘中に使うことは全く想定されておらず、
車載時にコンパクトにするためだけのものであることが伺えます。
それと同時にサバゲーの折りたたみストック武器のレビューに
「狭い場所ではストックを折りたたんで~」とか言っている輩の
知能指数の低さとア*ルの弱さが露見するはずです。

マガジンは茶色の樹脂製550連マガジンが付属します。
このマガジンの色がリアルではないのがLCT製AKの本当に残念部分ですね。
リアルなスリムモーター&グリップなんて作る暇があるなら、
1000円増しになっても構わないからリアルな色合いのマガジン作って欲しい。
実銃では40連マガジンを模した800連マガジンは
CYMA製のものが3000円弱程度で販売されていますが、
全弾撃ち切るのに3回ぐらいゼンマイを巻かなければならないし、
クソ長いマガジンはソレを打ち込むマガジンポーチを探す必要性があるし、
何よりも戦闘中に邪魔なので別に要らないかな?
尚、実銃ではドラムマガジンはRPKもRPK74もロシア製では存在しない模様。
LCTとかBATTLEAXEが販売しているドラムマガジンはノリンコ製のコピーらしいです。
軍隊ではドラムマガジンは弾薬装填に手間がかかるのと、
携行に難がある、確実性に欠けるということであまり使われないそうです。
PPsh41が大戦後期にはバナナマガジンになった理由もそうらしいです。

バッテリーはレシーバーカバー内にスティックバッテリーを収めます。
メカボックスは発射時に特に雑音もなく、ある程度の調整はされているようです。
初速も90m/s前後と必要にして充分な威力で、
常に安定したパワーと作動なので分解調整は必要ないようです。
但し650mmのロングバレルが命中精度に恩恵を与えているかどうかは不明。
発射速度は秒間13~14発程度と可もなく不可もない速度ですので、
無理してモーターを交換しなくてもそのままでも十分美味しくいただけます。

我輩的には見て良し撃って良しのLCT製RPKS74。
木製ストックが醸し出す雰囲気はソ連時代のノスタルジーな香りを感じるような気がすると共に、
体操服ブルマの野暮ったさの中にある奥なるエロス的な魅力を秘めているような気がするのです。
でも正直な話、長くて振り回しにくい(でもAK74Mとの差は数cm程度)、
バイポッドが余計に重い、M4ライフルユーザーには無視されると、
サバゲーでのタクティカルアドヴァンテージは皆無です。
このロングバレルには漢(おとこ)のロマン以外、後は何もありません。
つまり、敢えてRPKをサバゲーの武器としてフィールドに持ち込むプレイヤー、
ソイツらは真のロマンチストであると言っても過言ではないでしょう。
ていうかM60とかM240とか三八式とかM14とかSVDとか長い武器を使いたがるプレイヤーは
我輩みたいにサバゲーに勝利以外、勝利以上のロマンしか求めていないんです。
ソレがなにか他人に説明するのが非常に難しいのは、
漢(おとこ)のロマンは漢(おとこ)達一人ひとりの
心の内に秘めてじっくり温めるものであって
他人に理解してもらうものではないからなんですよね。
2021年01月29日
(大分前の話だけど)LCT製AK、ついに入手
どーも、最近嫁がパートで帰るのが遅いこともあって、
夕飯は我輩が作ることもしばしばなのですが、
我輩も精神的によろしくないと飯が作れない性分なので、
最近はうめこうじ西都店で税抜250円という破格で売られて種類も多い
「逆ギレ弁当」を買うことが多い砥部良軍曹です。
さて我輩、ロシア連邦軍装備をある程度整えてふと気がついたんですよ。
「アレ?ウチってひょっとしてロシア連邦軍のライフル無いんじゃね?」
そう、ロシア連邦軍の兵士は皆んなAK74Mを使っているんですよ。
でも我輩の手元にあるのはマルイ次世代AKS74と謎仕様βスペツナズ、
ピーマン職人から頂いたジャンクのマルイAK102をレストアしたタクティコゥ仕様AK、
そしてG&G製RK74EというKEYMOD付きAK。これもうわかんねえな。
ロシア連邦軍装備がフルコンプしたのに、
我輩の手元にロシア連邦軍のライフルは無い。
つまりソレはブルマーの下に何も履いてないのと同じぐらいありえねぇ事態。
ブルマーが絶滅した昨今ではブルマーの着こなしを知らん人が居るのか、
(多分ブルマーは下着のようなもんだと勘違いしている)
それとも「どーせ脱がすからパンツは要らんやろうもん」と思っているのか、
AVではブルマーの下はノーパンであることが多いんですが、
我輩世代がリアルで見ていたブルマー着用同級生女子は絶対にパンツを履いていた!
時々、白いパンツが太股の付け根からはみ出している女子がいて、
ソレをチラチラ見ながら瞼にじっくり焼き付けた遠い日の思ひではこの際置いといて、
肝心のライフルが揃わなければコスプレフルコンプしたと公言できない!
というわけで急遽ジャンクから蘇らせたタクティコウAKをwakanax様に売りつけ、
ヤフオクにマルイのAK74MNがいちまんえんぐらいで出てくるのをじっと待っていたら
LCT製AK74Mが0.5パットンで出ているではありませんか?
ええ勿論、即入札しましたよ。
最近はレール付きとかカービンモデルのAKが売れ筋なのか、
ノーマルハンドガードのAK74Mは誰も見向きもしなかったんで
出品時の価格そのままですんなり落札してしまってウハウハ。
だってLCTのAKって樹脂ハンドガードのでも定価0.8パットンぐらいですからね。
(まあソレ以前に最近LCTはAK74Mを生産してない模様)

そしてコイツが去年の夏に仕入れたLCT製AK74M。
こいつを手に入れた時、謎の感動が我輩の脳内を駆け巡り、
感慨深いものを感じたことは言うまでもありません。
「ああ、ついに我輩もトイガンAKの頂点?であるLCT製AKを手に入れたぞ・・・」とね。
というわけで今更ですがLCT製AK74Mのレビューを上げることにします。
ていうかホント、何で今までLCTのAKを買わなかったんだろうって気分でしたね。
まあコイツを買う金がなかったと言うか、迷走していたと言うか、
金がある時に限って欲しい型のLCT製AKが売り切れだったとか、
キャンプ用品買うのに精一杯でてっぽーに気が行かなかったとか、
理由はいくらでもあるんですがコレでやっと我輩も己をAKマニアであると自負できます。
尚、AK74には数種類の形状があります。
受験には出ないから別に覚えなくてもいいけど説明しますから見ろよ見ろよ〜。
まずは素の状態の初期のAK74。
木製ストック&ハンドガードでサイドマウントのレールが無いものです。
そして折りたたみストックのAKS74。
ストック部分が折り畳める空挺部隊、戦車兵用のAK74ですが、
装甲車とかの車両に乗り込む際、全長を縮められるこちらの方が便利であるということで、
国外へ展開する部隊(連邦軍)は大半がAKS74を支給されました。
少し遅れて現れたのが短い派生型、AKS74U。
そして分隊支援用に長い派生型のRPK74というのもあります。
その後AK74の木製ストックは樹脂製のストック&ハンドガードに改められました。
ソ連時代に生産されたものはストック&ハンドガードがプラム色らしいです。
そして1980年代ぐらいにAK独特のサイドレールマウントが付けられ、
光学照準器が取り付けられるようにはなりましたが、肝心の光学照準器は部隊へ支給されなかったというw
そしてソ連崩壊後、最終形態としてAK74Mが作られて今に至るわけです。

本来AK74Mのハンドガードにレールは付属していないのですが、
いつかこういう日がいつか来るだろうと思って同志スカルガンナー氏から
事前にLCT製TK104用の樹脂製レール付きハンドガードを頂いていたので早速交換しました。
ロシア連邦軍の歩兵はレールハンドガードなんて付けていないんですが、
レールがあれば夜戦でも使いやすいからまあ多少はね、勘弁してくれ。
よく「AK47とAK74ってどう違うんですか?」という質問を受けるのですが
(大嘘、そもそも宮崎にはAKを愛用するプレイヤーは我輩とスカルガンナー氏ぐらいしか居ないし
AK持ってきているプレイヤーが居たとしてもとりあえず1丁持っている程度であるが故、
M4ライフルVSカラシニコフの大会を開催するとAKチームは2人プラスα程度しか
居ないという事態になるぐらい宮崎にはAKに興味のあるプレイヤーが存在しない)
ぶっちゃけて言うと口径と弾倉と先っちょ(消炎制退器)が違うだけです。多分。

AK74Mの「M」とはマゾヒストという意味ではなく、
AKMの「M」同様「Модернизированный(改良型)」という意味です。
余談ですがマルイのAK74MNの「N」はナガノヤのNです(大嘘)。
そしてその改良とは歩兵(自動車化狙撃兵)、空挺部隊、戦車兵全てに支給できるように、
ストックを樹脂製の折りたたみ式に改修したことをいいます。
ストックを折り畳めるようにしたことで全長が20cmぐらい短縮できるので
狭い車内に搭載するにも邪魔になりにくいですし、
空挺降下の際も荷物を短縮化出来るというメリットがあります。
国軍正式の小銃のストックを折りたたみ式にすることで全部隊に対応させる手法は
スイスのSTG90(SIG550)、ドイツのG36、ベルギーのFNCと同様です。
ストック以外にも機関部にも地味な改修が加えられており、
射撃時の反動が軽減されて扱いやすくなっているそうです。
尚、折りたたみストックなのに固定ストックみたいな形状である理由は不明。

LCT製AK74Mは先端からケツまで何処を見てもその造形に惚れ惚れします。
ハイダーも削り出しなので亜鉛合金鋳造の他社メーカー品に比べるとシャープな出来栄え。
なお、この逆ネジで固定されているハイダーを外すと、
下には22mmのネジが出てきますがLCT製AK74の全ての機種は
このネジ部分も外して14mm逆ネジのオプションを取付可能です。

ハンドガードはLCT製TK104(AK104にM4ストックが付いたやつ)の
樹脂製TDIレールハンドガードに交換しております。
(元のハンドガードはその後、我輩の汚部屋の中で行方不明)
ところでこの中華製の「タクティカルAK」と呼ばれている機種に
よく搭載されているこのTDIレールハンドガードって、
ロシア軍が使っているの見たこと無いんですが何処が発祥なんですかね?
デザイン的には野暮ったいものですが4面にレールがあるので最低限、
ライトやグリップ等の付けたいものを付けることは出来ます。
LCTのAKは樹脂パーツもよく出来ていると言いたいところですが、
ブッチャケた話、樹脂クオリティはCYMAと大差ないです。

LCT製AKお約束の黒染めフレームの美しい出来栄えは
「実銃のAK74は黒塗装なんだよなー」という文句すら封印します。
LCT製品って実は細部までガッチガチにリアルってわけじゃないんですけどね、
造形や仕上げの良さで実銃らしいリアルさというか、説得力を生み出しているのが見事です。
AK74Mではレシーバーカバーも強化されてAK47と同じ形状の
リブ無しのつんつるてんなカバーになっているのですが、
実はコレ、LCTの箱出し状態では他のAK74と同じリブ付きカバーらしいんですね。
このAK74Mの前オーナーが拘ってリブ無しのカバーに交換した模様。

我輩がAK74Mを好きになれなくて、今まで買うに至らなかったのは、
ストック後部の肩を当てる部分にあるポコっと飛び出した
ストック展開用ボタンが邪魔そうな気がしたからなんですが、
実際肩付けしてみるとボタンのテンション弱めだから然程気にならないんですねコレが。
後部スリングフックは全部スリングフックとは反対の位置にあるのですが、
コレはストックを畳んだ時にスリングが適正位置に来るようにするためです。

ストックはフレーム左側の根本のボタンを押し込むと折れ曲がり、
フレーム全部にあるフックに引っかかって固定されますが、
コレが意外とスパッと収まらなくて少し残念な気分。
まあでも、戦闘中にストック開いたり畳んだりするわけではないんで、
(折りたたみストックは基本、銃をコンパクトに持ち運ぶための機能であって、
戦闘中に狭い場所に入る時に折りたたむものではない)
展開がスムーズじゃないというのは然程難点でもないですがね。

AK74Mの難点はサイドマウントレール。
ココにマウント付けて光学照準器付けてしまうと、
ストックを折り畳めなくなってしまうんですね。
AKのこういう不器用な部分が好きになれないという人も居るようですが、
光学照準器を多用しない性格の我輩的には然程気にならないんだなコレが。
AKにドットサイトを付けようと企んでいる人は最新型のAK12を買いましょう。

LCT製AKはマガジン挿入部分に隙間がアリスギィ!なので、
別売のスペーサーをブチ込まないとスムーズにマグチェンジ出来ないのが難点です。
我輩の落札した個体はそのスペーサーも込みだったのがありがたかったです。
余談ですがLCT製AKはトリガーガードがネジでガッチリ固定されているので、
マガジンキャッチ部分に取り付けるマグウェルを取り付けることが可能ですが、
実はこのマグウェルを付けられるという機能、
フレームが頑丈なLCTの真骨頂であることを知るものは少ない。
コレがE&L製AKだとこの部分がリベット留めだから
リベットをステンレスドリルでぶち抜いてタップでねじ切りしないといけないとか、
マルイのAKだとネジとフレームがガッチリしていないので
マグウェルを取り付けるとガタガタするんですねコレが。

バッテリーはスティックタイプの1200mAぐらいのを使います。
M4のストックパイプに収めるタイプのものは然程太くなければ使用可能です。
レシーバーカーバーを外しメカボックス上部に収める方式は
初めはまあ多少はね挿入に手こずりますが、慣れればそうでもなし。
我輩は手持ちの武器の大半がこの部分にバッテリーを詰め込こむAKなので、
色々な形状のバッテリーを買わなくて済むのが便利なんですねコレが。

LCT製AK74系列に付属のマガジンは大抵多弾式の樹脂製550連マガジンです。
LCT製と銘打って販売している予備マガジンはあまり市場に出ておりませんが、
CYMA製のマガジンと中身はほぼほぼ一緒なので予備はそちらを買いましょう。
お値段も550連が3000円弱程度、ノーマル80連も2500円弱程度で、
弾の巻き上がりもだいたい確実で比較的リーズナブル。
ただ、難点を述べるとすればAKの樹脂製マガジンは
マガジン前方先端のフレームに引っ掛ける部分、
この部分も樹脂なんで非常に破損しやすいんですね。

現在では多種多様な面白いスリングが販売しているようですが、
AK74といえば2点式スリング、異論は認めん。
最近では写真のようなODのスリングも使われているようですが、
やはりミリフォトでよく見かける主流は茶色のスリングですね。
写真のような状態でスリングを調整して取り付けると、
ストックを折りたたんだ状態で銃を携行しやすい状態になり、
ストックを伸ばすとスリングが適度に緊張して邪魔になりません。
LCT製電動ガンは余程変な機種を買わない限り、
メカボックスの品質が悪いとか、構成が適当だという事は無いようなので、
分解もせずにそのまま使用しておりますが故、AK74Mの分解時のレビューは割愛します。
LCT製AKは箱出しでそのまま使える数少ない海外製品です。
モーターはマルイEG1000に交換したほうが良いかもしれませんがね。
レールハンドガード、M4タイプストックが主流の最近のサバゲー界隈では
カスタム要素がハンドガードぐらいしか無いAK74Mをわざわざ買う理由or必要性は
「ロシア連邦軍コスプレのため」しかないので敢えてコレを買う必要性は皆無です。
でもマルイAK74MNを定価で買うよりは、
中古でもLCT製AK74Mを買った方が幸せになれるのは事実。
ストック基部のレバーも折れにくいし、予備マガジンは安いし、
バッテリーも入れやすいし、何より全体的に頑丈で美しい。
美しくて丈夫な女性は世の中になかなか存在しませんが、
LCT製AKはその両方を兼ね揃えております。
そのままでも充分楽しめる、充分な満足感を得られる、
ソレがLCT製AKの最大の特徴であり利点です(断言)。
そしてカスタムパーツの幅はマルイ製品よりLCT製品の方が広いです。
まあカスタムするなら既にカスタム済みのLCT製AK買うのが得策ですがね。
(但し、パーツの金額もピンキリで天井知らず、深い沼が待っているw)
夕飯は我輩が作ることもしばしばなのですが、
我輩も精神的によろしくないと飯が作れない性分なので、
最近はうめこうじ西都店で税抜250円という破格で売られて種類も多い
「逆ギレ弁当」を買うことが多い砥部良軍曹です。
さて我輩、ロシア連邦軍装備をある程度整えてふと気がついたんですよ。
「アレ?ウチってひょっとしてロシア連邦軍のライフル無いんじゃね?」
そう、ロシア連邦軍の兵士は皆んなAK74Mを使っているんですよ。
でも我輩の手元にあるのはマルイ次世代AKS74と謎仕様βスペツナズ、
ピーマン職人から頂いたジャンクのマルイAK102をレストアしたタクティコゥ仕様AK、
そしてG&G製RK74EというKEYMOD付きAK。これもうわかんねえな。
ロシア連邦軍装備がフルコンプしたのに、
我輩の手元にロシア連邦軍のライフルは無い。
つまりソレはブルマーの下に何も履いてないのと同じぐらいありえねぇ事態。
ブルマーが絶滅した昨今ではブルマーの着こなしを知らん人が居るのか、
(多分ブルマーは下着のようなもんだと勘違いしている)
それとも「どーせ脱がすからパンツは要らんやろうもん」と思っているのか、
AVではブルマーの下はノーパンであることが多いんですが、
我輩世代がリアルで見ていたブルマー着用同級生女子は絶対にパンツを履いていた!
時々、白いパンツが太股の付け根からはみ出している女子がいて、
ソレをチラチラ見ながら瞼にじっくり焼き付けた遠い日の思ひではこの際置いといて、
肝心のライフルが揃わなければコスプレフルコンプしたと公言できない!
というわけで急遽ジャンクから蘇らせたタクティコウAKをwakanax様に売りつけ、
ヤフオクにマルイのAK74MNがいちまんえんぐらいで出てくるのをじっと待っていたら
LCT製AK74Mが0.5パットンで出ているではありませんか?
ええ勿論、即入札しましたよ。
最近はレール付きとかカービンモデルのAKが売れ筋なのか、
ノーマルハンドガードのAK74Mは誰も見向きもしなかったんで
出品時の価格そのままですんなり落札してしまってウハウハ。
だってLCTのAKって樹脂ハンドガードのでも定価0.8パットンぐらいですからね。
(まあソレ以前に最近LCTはAK74Mを生産してない模様)

そしてコイツが去年の夏に仕入れたLCT製AK74M。
こいつを手に入れた時、謎の感動が我輩の脳内を駆け巡り、
感慨深いものを感じたことは言うまでもありません。
「ああ、ついに我輩もトイガンAKの頂点?であるLCT製AKを手に入れたぞ・・・」とね。
というわけで今更ですがLCT製AK74Mのレビューを上げることにします。
ていうかホント、何で今までLCTのAKを買わなかったんだろうって気分でしたね。
まあコイツを買う金がなかったと言うか、迷走していたと言うか、
金がある時に限って欲しい型のLCT製AKが売り切れだったとか、
キャンプ用品買うのに精一杯でてっぽーに気が行かなかったとか、
理由はいくらでもあるんですがコレでやっと我輩も己をAKマニアであると自負できます。
尚、AK74には数種類の形状があります。
受験には出ないから別に覚えなくてもいいけど説明しますから見ろよ見ろよ〜。
まずは素の状態の初期のAK74。
木製ストック&ハンドガードでサイドマウントのレールが無いものです。
そして折りたたみストックのAKS74。
ストック部分が折り畳める空挺部隊、戦車兵用のAK74ですが、
装甲車とかの車両に乗り込む際、全長を縮められるこちらの方が便利であるということで、
国外へ展開する部隊(連邦軍)は大半がAKS74を支給されました。
少し遅れて現れたのが短い派生型、AKS74U。
そして分隊支援用に長い派生型のRPK74というのもあります。
その後AK74の木製ストックは樹脂製のストック&ハンドガードに改められました。
ソ連時代に生産されたものはストック&ハンドガードがプラム色らしいです。
そして1980年代ぐらいにAK独特のサイドレールマウントが付けられ、
光学照準器が取り付けられるようにはなりましたが、肝心の光学照準器は部隊へ支給されなかったというw
そしてソ連崩壊後、最終形態としてAK74Mが作られて今に至るわけです。

本来AK74Mのハンドガードにレールは付属していないのですが、
いつかこういう日がいつか来るだろうと思って同志スカルガンナー氏から
事前にLCT製TK104用の樹脂製レール付きハンドガードを頂いていたので早速交換しました。
ロシア連邦軍の歩兵はレールハンドガードなんて付けていないんですが、
レールがあれば夜戦でも使いやすいからまあ多少はね、勘弁してくれ。
よく「AK47とAK74ってどう違うんですか?」という質問を受けるのですが
(大嘘、そもそも宮崎にはAKを愛用するプレイヤーは我輩とスカルガンナー氏ぐらいしか居ないし
AK持ってきているプレイヤーが居たとしてもとりあえず1丁持っている程度であるが故、
M4ライフルVSカラシニコフの大会を開催するとAKチームは2人プラスα程度しか
居ないという事態になるぐらい宮崎にはAKに興味のあるプレイヤーが存在しない)
ぶっちゃけて言うと口径と弾倉と先っちょ(消炎制退器)が違うだけです。多分。

AK74Mの「M」とはマゾヒストという意味ではなく、
AKMの「M」同様「Модернизированный(改良型)」という意味です。
余談ですがマルイのAK74MNの「N」はナガノヤのNです(大嘘)。
そしてその改良とは歩兵(自動車化狙撃兵)、空挺部隊、戦車兵全てに支給できるように、
ストックを樹脂製の折りたたみ式に改修したことをいいます。
ストックを折り畳めるようにしたことで全長が20cmぐらい短縮できるので
狭い車内に搭載するにも邪魔になりにくいですし、
空挺降下の際も荷物を短縮化出来るというメリットがあります。
国軍正式の小銃のストックを折りたたみ式にすることで全部隊に対応させる手法は
スイスのSTG90(SIG550)、ドイツのG36、ベルギーのFNCと同様です。
ストック以外にも機関部にも地味な改修が加えられており、
射撃時の反動が軽減されて扱いやすくなっているそうです。
尚、折りたたみストックなのに固定ストックみたいな形状である理由は不明。

LCT製AK74Mは先端からケツまで何処を見てもその造形に惚れ惚れします。
ハイダーも削り出しなので亜鉛合金鋳造の他社メーカー品に比べるとシャープな出来栄え。
なお、この逆ネジで固定されているハイダーを外すと、
下には22mmのネジが出てきますがLCT製AK74の全ての機種は
このネジ部分も外して14mm逆ネジのオプションを取付可能です。

ハンドガードはLCT製TK104(AK104にM4ストックが付いたやつ)の
樹脂製TDIレールハンドガードに交換しております。
(元のハンドガードはその後、我輩の汚部屋の中で行方不明)
ところでこの中華製の「タクティカルAK」と呼ばれている機種に
よく搭載されているこのTDIレールハンドガードって、
ロシア軍が使っているの見たこと無いんですが何処が発祥なんですかね?
デザイン的には野暮ったいものですが4面にレールがあるので最低限、
ライトやグリップ等の付けたいものを付けることは出来ます。
LCTのAKは樹脂パーツもよく出来ていると言いたいところですが、
ブッチャケた話、樹脂クオリティはCYMAと大差ないです。

LCT製AKお約束の黒染めフレームの美しい出来栄えは
「実銃のAK74は黒塗装なんだよなー」という文句すら封印します。
LCT製品って実は細部までガッチガチにリアルってわけじゃないんですけどね、
造形や仕上げの良さで実銃らしいリアルさというか、説得力を生み出しているのが見事です。
AK74Mではレシーバーカバーも強化されてAK47と同じ形状の
リブ無しのつんつるてんなカバーになっているのですが、
実はコレ、LCTの箱出し状態では他のAK74と同じリブ付きカバーらしいんですね。
このAK74Mの前オーナーが拘ってリブ無しのカバーに交換した模様。

我輩がAK74Mを好きになれなくて、今まで買うに至らなかったのは、
ストック後部の肩を当てる部分にあるポコっと飛び出した
ストック展開用ボタンが邪魔そうな気がしたからなんですが、
実際肩付けしてみるとボタンのテンション弱めだから然程気にならないんですねコレが。
後部スリングフックは全部スリングフックとは反対の位置にあるのですが、
コレはストックを畳んだ時にスリングが適正位置に来るようにするためです。

ストックはフレーム左側の根本のボタンを押し込むと折れ曲がり、
フレーム全部にあるフックに引っかかって固定されますが、
コレが意外とスパッと収まらなくて少し残念な気分。
まあでも、戦闘中にストック開いたり畳んだりするわけではないんで、
(折りたたみストックは基本、銃をコンパクトに持ち運ぶための機能であって、
戦闘中に狭い場所に入る時に折りたたむものではない)
展開がスムーズじゃないというのは然程難点でもないですがね。

AK74Mの難点はサイドマウントレール。
ココにマウント付けて光学照準器付けてしまうと、
ストックを折り畳めなくなってしまうんですね。
AKのこういう不器用な部分が好きになれないという人も居るようですが、
光学照準器を多用しない性格の我輩的には然程気にならないんだなコレが。
AKにドットサイトを付けようと企んでいる人は最新型のAK12を買いましょう。

LCT製AKはマガジン挿入部分に隙間がアリスギィ!なので、
別売のスペーサーをブチ込まないとスムーズにマグチェンジ出来ないのが難点です。
我輩の落札した個体はそのスペーサーも込みだったのがありがたかったです。
余談ですがLCT製AKはトリガーガードがネジでガッチリ固定されているので、
マガジンキャッチ部分に取り付けるマグウェルを取り付けることが可能ですが、
実はこのマグウェルを付けられるという機能、
フレームが頑丈なLCTの真骨頂であることを知るものは少ない。
コレがE&L製AKだとこの部分がリベット留めだから
リベットをステンレスドリルでぶち抜いてタップでねじ切りしないといけないとか、
マルイのAKだとネジとフレームがガッチリしていないので
マグウェルを取り付けるとガタガタするんですねコレが。

バッテリーはスティックタイプの1200mAぐらいのを使います。
M4のストックパイプに収めるタイプのものは然程太くなければ使用可能です。
レシーバーカーバーを外しメカボックス上部に収める方式は
初めはまあ多少はね挿入に手こずりますが、慣れればそうでもなし。
我輩は手持ちの武器の大半がこの部分にバッテリーを詰め込こむAKなので、
色々な形状のバッテリーを買わなくて済むのが便利なんですねコレが。

LCT製AK74系列に付属のマガジンは大抵多弾式の樹脂製550連マガジンです。
LCT製と銘打って販売している予備マガジンはあまり市場に出ておりませんが、
CYMA製のマガジンと中身はほぼほぼ一緒なので予備はそちらを買いましょう。
お値段も550連が3000円弱程度、ノーマル80連も2500円弱程度で、
弾の巻き上がりもだいたい確実で比較的リーズナブル。
ただ、難点を述べるとすればAKの樹脂製マガジンは
マガジン前方先端のフレームに引っ掛ける部分、
この部分も樹脂なんで非常に破損しやすいんですね。

現在では多種多様な面白いスリングが販売しているようですが、
AK74といえば2点式スリング、異論は認めん。
最近では写真のようなODのスリングも使われているようですが、
やはりミリフォトでよく見かける主流は茶色のスリングですね。
写真のような状態でスリングを調整して取り付けると、
ストックを折りたたんだ状態で銃を携行しやすい状態になり、
ストックを伸ばすとスリングが適度に緊張して邪魔になりません。
LCT製電動ガンは余程変な機種を買わない限り、
メカボックスの品質が悪いとか、構成が適当だという事は無いようなので、
分解もせずにそのまま使用しておりますが故、AK74Mの分解時のレビューは割愛します。
LCT製AKは箱出しでそのまま使える数少ない海外製品です。
モーターはマルイEG1000に交換したほうが良いかもしれませんがね。
レールハンドガード、M4タイプストックが主流の最近のサバゲー界隈では
カスタム要素がハンドガードぐらいしか無いAK74Mをわざわざ買う理由or必要性は
「ロシア連邦軍コスプレのため」しかないので敢えてコレを買う必要性は皆無です。
でもマルイAK74MNを定価で買うよりは、
中古でもLCT製AK74Mを買った方が幸せになれるのは事実。
ストック基部のレバーも折れにくいし、予備マガジンは安いし、
バッテリーも入れやすいし、何より全体的に頑丈で美しい。
美しくて丈夫な女性は世の中になかなか存在しませんが、
LCT製AKはその両方を兼ね揃えております。
そのままでも充分楽しめる、充分な満足感を得られる、
ソレがLCT製AKの最大の特徴であり利点です(断言)。
そしてカスタムパーツの幅はマルイ製品よりLCT製品の方が広いです。
まあカスタムするなら既にカスタム済みのLCT製AK買うのが得策ですがね。
(但し、パーツの金額もピンキリで天井知らず、深い沼が待っているw)
2020年12月25日
念願のロシア軍装備用ハンドガン、ついに入手!
せっかくの冬休みだというのにコロナが再び蔓延したせいで、
陽気に福岡に帰ることすらままならない砥部良軍曹です。
娘が来年高校受験なんで福岡帰って太宰府天満宮にお参りに行きたいところなんですが、
正月三が日の大宰府は前方に居るおなごのケツを触っても気が付かないぐらい
すし詰めギュウギュウの人多スギィ!状態なので
何処からウィルスが飛んで来て憂き目に遭うか解りませんからね。
受験前に変なウィルスにやられて人生パーになるのだけは勘弁です。
ところで娘といえば昨晩のクリスマスイブの夜、
我輩が渾身のチキン丸焼きを作ったにもかかわらず、
「ウチのクリスマスといえば、父さんのボルシチだよね!」と言いやがるんですよ。
(2週間前に生ビーツが手に入ったのでボルシチも作っていた)
我輩、もう2度とクリスマスにチキン丸焼きは作るまいと心に誓うと同時に、
娘は我輩を無意識のうちにロシア的男子と認識しているのでは?という疑念が。
さて、少々減りはしたものの今年も無事にボーナスを頂きました。
それに伴い嫁から小遣いを頂いたので軍拡しちゃいました。
「お前は毎回冬のボーナス時に軍拡してんじゃねぇのか?」という
至極もっともなツッコミは逐次受け付けておりますのでご遠慮無くどーぞ。
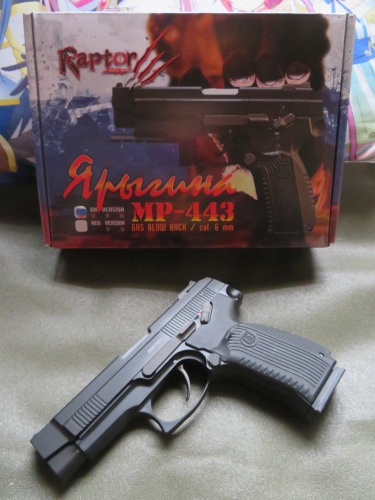
今回我輩が小遣い叩いて仕入れたのは
台湾のRAPTORなるメーカーの
MP443というロシアの拳銃です。
ハンドガンなので、当然ながらガスを使って動く銃(パットン氏曰く)です。
余談ですがこのロシアンピストルのMP443と言う名称は
この拳銃を生産しているイジェフスク工場の商品名的なもので、
ロシア軍では6П35(Пは「ぺー」と読む)と呼ばれているようです。
まあアレだ、H&K USPがドイツ連邦軍ではP8、
ベレッタM92FSが米軍ではM9と呼ばれているのと同様。
またこのMP443と言う拳銃はソ連、ロシアの銃器が一般的に、
「カラシニコフ」や「ドラグノフ」というような設計者の名前で呼ばれる例に漏れず
「ヤリギン」「グラッチ」と言う名称でも呼ばれております。
ヤリギンとはこの拳銃の設計者の名前で、
トカレフとかマカロフと同じニュアンスですね。
グラッチというのはこの拳銃の開発プロジェクトの名称らしく、
ロシア語で「ミヤマガラス」と言う意味なのだとか。
ロシア軍装備をするにあたり、一番のネックとなっていたのがハンドガン。
ソ連、ロシアの拳銃自体がそもそも少ない(PMとAPSとコレぐらい)というのに、
モデルアップされているのがKSC製マカロフぐらいしかないという状況。
そしてそのマカロフは小型が故にマルイ製ハンドガンと渡り合うには不向き。
そんなシベリアの永久凍土的なお寒いロシアンハンドガン事情を
打ち破ってくれたのがこのRAPTOR製MP443なのでございます。
こういうマニアックなモデルを出してくれるという点において、
海外メーカーの存在は「ユーザーとしてとても嬉しい」

しかしながらこの台湾ラプター製MP443、
取扱店がAKの品揃えに定評のあるNOOBARMSぐらいしかなく、
ツイッタで予約受付開始した次の日(w8月下旬ぐらい)に予約を申し込み、
手持ちの武器を売り払って必死且つ迅速に資金集めをしたにもかかわらず、
初回生産分は予約開始当日に予約した方々に全て奪われしまったようで、
予約から4ヶ月経った12月中旬になってようやく手に届くという有様なのでした。
なので今から買おうとしても手元に届くのは何時になるか解りませんですし、
そもそもこのラプターのMP443は本来フルメタルで生産しているものを
規制の喧しい日本向けにフレームを樹脂製に作り変えたもので、
生産数が限定されているが故に今後入手可能であるかも定かではありません。
我輩が購入したのは予備マガジンとマウントのセットであるデラックスバージョン。
お値段は0.5パットンぐらいとハンドガンにしては結構お高めではありますが、
(注:1パットン=50000円ぐらいですかね?)
後から予備マガジンを買うことを考慮するとお買い得な選択肢とも言えます。
海外製品はオプションや予備マガジンの流通が不安定なので、
出来ることなら予備マガジンも一緒に手に入れたいですからね。
ていうかハンドガンなのに本体だけでも20000円ぐらいするというお値段は
マルイ製ハンドガンしか買わない方々から見るとお高く感じるでしょうが、
タナカやKSCのハンドガンもだいたいそんぐらいのお値段なので特別高いわけでも無し(錯乱)。

尚、付属の取扱説明書に日本語記載がないのは仕方ないね(ビリー兄貴)としても、
フィールドストリッピングの方法ぐらい載せてくれよというツッコミは入れたくなります。
取扱説明書の情報量が少ないのは大抵の海外製エアソフトガンの難点です。

初速は平均83.4m/sとマルイ製ガスハンドガンと同等な数字が書かれておりますが、
我輩の個体は桐灰マグマカイロでマガジンを適度に温めても70m/s超えるぐらいでした。
夏場の暑い時期ならコレぐらい出て欲しいなと期待したいところです。

ラプター製MP443の外装レビューの前に軽く実銃の説明。
MP443はかつてのソ連、ロシア軍の拳銃とは異なり、
(永きに渡りソ連及びロシアは独自の企画の弾薬を使う拳銃しか作らなかった)
世界的に一般的な9mmパラベラムを使用する拳銃です。
実銃の装弾数は17+1発、その後改良されて18+1発になったのは、
MP443開発以前からFSB(旧KGB)やロシア連邦軍以外の部隊で使われている
グロック17(装弾数17+1発)に対抗するためですかね?
トリガーメカは実銃ではダブルアクションらしいですが
RAPTORのMP443は何故かシングルアクション。意味不明。
全体的なシルエット的には最近のポリマーフレーム拳銃よりは
一昔前のベレッタM9やスタームルガーP85に似た感じのものですね。
21世紀に採用された拳銃なのにアンダーマウントレールがないのも1世代前感。
そして余計な刻印や印字がないのが実にロシア。
でも、フィンガーレストが設けられたグリップや、
フレームに配置されたセイフティレバーと言うデザインは
昨今の流行に則ったものとなっております。

反対側に余計なものが飛び出していないのもある意味ロシア的。
でも此方側にもセイフティレバーがあるのは現代風。
サイズ的にはグロックやP226といった9mm口径の
中型オートマチックピストルと大差ない大きさですが
スライドはグロックより細く、グリップはグロックよりも太いです。
MP443は1990年代に開発され、2003年にロシア軍に採用され、
2010年ぐらいからロシア軍に配備された拳銃であるにも関わらず、
フレームはポリマーフレームではなく鉄製という変な拘り。
「プラスチックが我が祖国の極寒の環境に耐えられるのか?」と、
ロシア軍上層部は考えたから手堅く鉄製フレームを選択したのでしょうかね?
民生モデルのMP446は樹脂製フレームを採用しているらしいです。
そういえば大分昔、アカ嫌いの父上が元気ビンビンだった頃に、
「ソ連のライフルが木製ストックなのは、寒くても割れにくいから」
という露助を半分バカにしたよーな、でも真意っぽい話をしてましたが、
今ではあながちジョークとも思えない心境です。

トリガーは電動ガンのAKみたいに細く、我輩的には引きやすい形状です。
但しシングルアクションであるにも関わらずトリガーストロークは
異様に遊びが多くハンマーの落ちる感覚は掴みにくいという。
強いて言うならタナカ製ブローニング・ハイパワーのような感触。
スライドリリースレバーはセイフティレバーが少し邪魔で使い難い。
セイフティレバーは丁度いい位置でまあ使いやすいのですが
箱出し状態ではセイフティレバーが馬鹿みたいに固くて動かなくて唖然。
尚、このセイフティはハンマーがどの状態でもかけられます。

一体型のグリップパネルは太めで、嫁よりも掌が小さい我輩には握り辛いです。
グリップ後部の妙な角張った形状が手に馴染まないんですね。
まあロシアの武器は「武器に身体を合わせる」もんなんで、
軟弱な思考のプレイヤーにはロシア軍装備なんて無理なんですがw
マガジンリリースは形状的には可もなく不可もないボタン式ですが、
内部がキツイのかマガジンが中で引っかかってスルッと落下しない。
そしてマガジン装填時も途中で引っかかるので少し戸惑いを感じます。

21世紀の拳銃であるにも関わらず、古めかしさを感じるハンマー式。
ストライカー式にすればハンマーが引っかかる心配もないのにねぇと思うんですが、
どうやらロシア人はストライカー式の拳銃に親でも殺されたようです。
トカレフみたいにフレーム後部がハンマーを包み込む形状は
厚着の状態でハンマーが引っかかって暴発する可能性を防ぐロシアの伝統的デザイン。
ちなみに、この起こしにくいハンマーを手動でダウンさせると、
マガジンのガス放出バルブを強制的に叩いてガス全部出ます。

マガジンは25発装填可能。必要にして充分なキャパシティ。
但し取説のように上から弾を詰めるのは結構無理です。
まあそこら辺はマルイのガスガンのマガジンと同じように
フォロアーを下げて下の広がったスリットから装填すれば無問題。

不便なのはガスを充填する際、マガジンボトムをずらす必要がある事。
マガジンフォロワーの下のやつをずらせばマガジンボトムは動きますが、
毎回ガス注入の度にコレするのマンドクセ。
そして注入バルブが海外製高圧ガス対応型で
ジャパニーズフロン134や152はなかなか充填されないので、
WEガスガン用の日本バージョン注入バルブに交換したら何ということでしょう、
パッキン形状が合わなくて貴重なガスがダダ漏れしやがったんで、
パッキンは元のバルブに付いているものと入れ替える必要があります。

我輩が購入したMP443デラべっぴん、もといデラックスバージョンに付いているマウント、
取り付けるにはまずマウントのトリガーガードに引っ掛かる部分の蓋?を外して引っ掛けます。

その後、蓋を閉めてトリガーガード前側とレール部分に付いている固定用の芋ネジを締めます。
あまり締めすぎるとフレームに傷が入るのが嫌。

マウントレールを取り付ける事によりウェポンライトを取り付けられるという利点の代わりに
サイズ的に嵩張り、コイツを納めるホルスターはどうすればいいんじゃという難点が生まれます。
ぶっちゃけ、夜戦用にグロック17買った方が幸せになれそうです。
MP443、一つの拳銃として見るとロシア製消火器らしい大雑把で取っ付きにくさのある
何時ものロシアンクオリティといった感じのブツです。
正直、グロックやUSPといったような西側製拳銃と比較すると洗練が足りない。


そしてラプター製のMP443という点から見ると正直、雑な作り。
アルミ製のスライドはホコリが付いた上から塗装していたり、塗装が雑だったり、
スライド自体も出来がよろしくなくて至るところにボコボコが見られます。
中身にしても割り箸を割るようなトリガーのキレの悪さ、
ご機嫌斜めな時の嫁の股以上に動かないセイフティレバー、
築40年の中古物件の引き戸かと思うぐらい動きの渋いスライドの動き、
ケツ★ン開発されてないホ★ガキのようなマガジン出し入れのキツさ、
どれをとってもマルイ製ハンドガンには到底及ばない作りに泣きそうです。
撃ってみると弾は確かに飛びますが、精度がいいかと問われると微妙。
アルミスライドが重いのか、スライドの動きもかったるくて時々ジャムります。
多分、本来はパワーのあるガスでAV男優の腰のように激しくバシバシ動かして、
使っている間に各所が削れてだんだん滑らかになるという仕様なんでしょう。
コレ、マルイ製エアソフトガンしか知らない人種からすると完全に不良品です。
ラプター製MP443、初期状態のレビューを上げるのは躊躇われるシロモノ。

というわけでバラして調整するかと目論んだのですが、
前述のようにスライドをフレームから外す方法すら説明書に記載してないという体たらく、
初見殺しとはまさにコイツのためにある言葉です。
ま、ネットで検索したらすぐにスライドストップを外す方法が見つかって事なきを得ましたが、
その外し方が他の拳銃とは随分異なる方法なのに戸惑った我輩。
まずマガジンを抜いて(常識ですね)スライドを引き、スライドストップをかけます。
謎形状のリコイルスプリングガイドを露出させます。
その後リコイルスプリングガイドを少し引っ張り出すと、何処かで引っかかります。
そしてスライドを戻し、スライドストップをガバメントみたいにフレームの反対側から押し出すと、
スライドストップが抜けてフレームとスライドが分離します。これもうわかんねぇな。

リコイルスプリングガイドをずらして90度ひねり、持ち上げて外したら、
リコイルスプリングガイドが抜けてアウターバレルが外れるようになります。
コレがなかなか外れなくて少しイラッとするんだな。
尚、組み込みの際は更に面倒なのですがそれを解消する方法は後述にて。

スライドを何度か動かすor何度か撃っていると、
アウターバレルのチャンバー部分上部に傷が入っているのが確認できるでしょう。
その部分はスライドと干渉して作動不良の原因になっているので、
ヤスリである程度削って作動を滑らかにすることをオススメします。
目安はスライドを動かしても傷が入らなくなるまで。
ドライバーの先で示している部分がホップ調整ダイヤルです。
ストロークは少ない上に、調整は結構シビアです。
しかも指では動かないというオマケ付き。ドライバー必須。

チャンバーは小さなクロスネジで固定されています。
外部、内部共に仕上げが悪く引っかかるので
目の細かいヤスリやサンドペーパーでバリを取ります。
インナーバレルとチャンバーはマルイハンドガンと同規格です。
マルイのと交換してみたところ、チャンバーのゴムが気持ち柔らかいためか、
作動が少し滑らかになり、フライヤーがなくなりました。
どうやらゴム製品は日本製が性能がよろしいようです(意味深)。
インナーバレルの長さは95mmぐらいなので、グロックやP226のものが丁度いいでしょう。
インナーバレルが全体的に仕上げが良くなかったので、
マルイ製に交換すれば性能向上が期待できそうです。

ブリーチ部分は2つの6角ネジで固定されているので、緩めて取り外しますが、
初期段階では愛し合う2人の棒と穴よりもスライド内部にガッチリハマっているので
プラスチックハンマーでスライドをぶん殴らないと外れません。

勢いよく外そうとしてブリーチ上部のスプリング2本が無くならないように注意してください。
ブリーチブロックの外側サイド部分をサンドペーパーでキレイにすると、
取り外しor組み込みの時に引っかかりにくくなって楽になります。

ノズルの先端部分と弾のローディング部分にバリがあるので、
この部分もしっかりキレイに仕上げますが
削りすぎると作動不良の原因になるので丁寧に作業しましょう。
アレだ、指1本入れて大丈夫そうだから3本入れようみたいなのは止めとけという。

ノズルはブリーチ上部のスプリングを外せば前方に引き抜くだけで外れます。
(ていうかスプリングはすぐに外れるていうか、無くしそうになる)
あと、ドライバーで指している部分に半月状の金属パーツがあるので、
コイツもなくさないようにすぐに外しておきましょう。
この後、ブリーチ内部のピストン部分が外せるか試みたのですが、
結構キツキツにハマっているようで外せませんでした。

ノズル内部も分解してバリを取ります。
ノズルの右側に小さいクロスねじがあるので、それを緩めます。

ノズル内部はこのようなパーツ構成になっております。
左から順にノズル、スプリング、センサーバルブ、ストッパー。
センサーバルブとストッパーもバリがあるのでキレイにします。

さて、このストッパーですが我輩の個体(2期ロット以降生産品?)では、
ハの字部分が下を向くこの状態で付いておりました。

初期ロットでは写真のように上が広がっている状態(上下反対)で組まれていたらしく、
コレを反対に入れ替えて組み上げた方が動きが良くなるという情報がありました。
試しに入れ替えて組み上げてみたところ初速が70m/s強⇒70弱ぐらいになったたので、
ココの組付け次第でガスの流量が変化していると思われます。
初期ロットをお持ちの方は上下入れ替えて組んだほうがよろしいでしょう。

でもガスの流量が増えてマズルエナジーが上がっても
根本的にスライドの動きの渋さが作動の妨げになっているみたいなので、
スライドのレール部分、フレームのレールが噛み合う部分をサンドペーパーで均し、
引っかかりがないように仕上げればスライドの動きが大分改善され、動きが良くなります。
ついでにスライド内部もアウターバレルが干渉する部分は軽く磨きました。
更にスライドの表側のボコボコした部分や塗装の汚い部分も磨いて塗り直しました。
ここまですれば大分、作動がまあ多少は良くなりジャムの可能性が下がります。
結構大変な作業ですが、ここまでしてもアルミスライドが思いのほか重いのか、
リコイルはよいものの数発撃つと動きは悪くなります

さて、我輩が全国のMP443ユーザーにオススメしたい加工が、
リコイルスプリングガイドのスライドストップレバーのハマる部分の加工。
写真のこ↑こ↓が示している「くの字」の部分を
目の細かい細いヤスリで軽く削って丸めると
あら不思議、組立時にリコイルスプリングガイドをガチャガチャ弄らなくても、
スライドストップレバーを押し込んだ勢いで経験豊富な女子のように
棒の部分がカシャッとハマって直ぐに組み立てられます。

削る目安はリコイルスプリングガイドを組んだ状態で、
写真のようにスライドストップレバーを押し込んでハマるようになるまで
少しずつ調整しながら削るという完全に現物合わせなんですが、
(然程削らなくてもスルッと入るようにはなる)
この加工によってイチイチ組立時に反対側の穴から
ドライバーを突っ込んでスライドストップレバーを押し込む手間が省けます。

ここまで手を加えないと使うのが難しいであろうRAPTOR製MP443、
正直、ロシア軍装備に拘る人以外は全く手を出す必要性のない代物です。
ロシア軍装備でもスペツナズとかFSBとかやっている人は
余計な思考に陥ることなくマルイのグロック17を使いなさい。
かなり珍しいハンドガンが欲しい的な軽い気分で手を出すと地獄を見ます。
ただ、ロシア連邦軍装備をシメる一品としては
銃剣やスコップ以上に必要不可欠な品でしょう。
だってハンドガンだから、銃剣やスコップよりはサバゲーに使える。
装弾数的には普通のプレイヤーが使用しているハンドガンと大差なく、
パワーも然程変わらないので互角に渡り合えなくはないのですが、
信頼性ではやはり、マルイ製ハンドガンには敵わないなというのが正直な感想です。
我輩的にはロシア軍装備のサイドアームとしてMP443を手にしたことで、
ようやくロシア軍装備という名のパズルの完成に終わりが見えたという気分です。
まあ要するに、それなりには満足しているということだ。
でも我輩って実はロシア軍装備の時は案外、ハンドガン使わない人なんで、
コイツの存在がどれぐらいのタクティカルアドバンテージが有るかは未知のエリアーッ!
尚、一緒に撮影した「おいしいロシア」というマンガ、
著者がロシア人の旦那と一緒にロシアに1年間滞在し、
そこで生活してどのような経験をしたかというエピソードを交えて
ロシアの主な料理をマンガで面白く説明するというマンガなので、
ロシア軍を極める活動の一環でロシア料理にハマりたい人(居るのか?)は是非とも買うべし。
2022.12.8追記
アルミスライドの重量感よりも確実な作動と発射を求めて、
RAPTOR製MP443用樹脂スライドの購入に踏み切った我輩。
しかし、最近は大分マシになったとは聞くものの3Dプリンター製というのが
無加工で使えるのか否かどーも不安で仕方がなかったんです。

現物を手にして不安が絶望にランクアップ。
「我輩はこんな物に0.2パットンを費やしてしまったのか」という自己嫌悪に陥りました。
余りにも酷くて当初の写真を撮影する心の余裕もなかったのですが、
この内側のシワシワガタガタ質感が購入時の質感です。
恐る恐るプリーチを組み込んでみたところ、まあ多少はねきつかったですが、
サンドペーパーでスライド内側を均したらブリーチは収まりました。
でもリアサイトがキツくて溝をヤスリで削る羽目に。
嬉しい誤算だったのは取り付け後の作動。普通にブローバックして弾も出ました。

しかしこの汚い見た目だけは見ていて悲しくなるレベルだったので、
何日かかけてサンドペーパーでかなり磨きまくり、表面を平らにしました。

しかし塗装が綺麗に乗らないのでプラモデルマスターの我が愛しの同期、
学長に託して更に磨きをかけてもらい、下地をしっかりと塗ってもらい、
艶消しブラックで塗って貰ったお陰で何とか鑑賞に耐える風合いになりました。
因みにセレーション部分、一晩かけて細いヤスリで磨きまくりましたがこの体たらくです。

スライドを樹脂製に替えた事によって冬以外はある程度撃てるシロモノになりました。
でも学長から受け取った時はスライドストップは作動していたのですが、
暫くパコパコ撃っていたらスライドストップの掛かる部分が適度に摩耗、
ホールドオープンしなくなってしまいましたが作動はするからオッケー・・・なのか?
2024.8.10追記
RAPTOR製MP443のバリエーションにMP446ヴァイキングが加わったので
ヤフオクで0.76パットンで購入しました。

ハンドガンに電動ガン並の金を払うのは酔狂かとも思いはしましたが、
MP446の生産数はかなり少なく、240ドルぐらいするみたいなので、
「WAのハンドガンも同じぐらいの価格だし、まあしょうがないね」という気持ちで購入。
セット内容は本体、マガジン、マウントレール、そして内容が薄い説明書。
MP443に付属していたサプレッサー用アダプターは付いてませんでした。

MP446ヴァイキングとはMP443を樹脂フレームに変更したモデルで、輸出用なんだとか。
Wikipediaにはロシア軍でも使用されているような記載がありましたが、どうだか?

ヴィジュアル的にはスライドの刻印が増えただけで、
フレームはMP443と全く変わらないのですが、
このスライドの刻印が入っただけでも大分雰囲気が違います。
しかも、スライドの仕上がりが我輩所有の2期ロット品よりも綺麗で「何だこれは、たまげたなあ」。

我輩所有のMP443同様、トリガー&ハンマーは相変わらずシングルアクションです。
セイフティレバーは箱出しでもそれなりに動いてくれましたが、作動はイマイチです。

このスライドの仕上げに時間を掛けた分、価格が上がったのかなぁ?と
野暮な事を考えながら見ていたら、MP446はスライドの形状が違うんですね。
イジェクションポート周辺が肉厚になっております。

ガスと弾を入れて発射してみたら、気温が高いからか結構快調に作動しました。
よく見たら我輩所有のMP443で作動を良くするために削った
アウターバレルのチャンバー部分(指差している所)に削り跡が見られます。
まさか、RAPTORの中の人は我輩のブログを参考にして加工したのかな?

もう一つ「何だこれは、たまげたなあ」だったのは、
リコリスリコイルスプリングガイドを引っ張り出さなくても
スライドリリースレバーを右側から押し出せば外せるんですね。
やっぱりRAPTORの中の人、我輩のブログ見てるわ(確信)。

上がMP446、下がMP443のスライドです。
とりあえずフィールドストリッピングしてみたところ
アウターバレルが外れないので何故かと思いきや、
多分作動を良くするためのアウターバレルを固定するパーツがスライド先端に追加されていました。
コイツはスライド先端を軽くプラスチックハンマーとかで叩くと外れます。

右がMP446、左がMP443です。
アウターバレル固定パーツが追加された以外、その他各パーツに変化はありません。
そして各パーツのバリも案外少ないというか、あまり気になりません。
更に、フレームのレールも滑らかで作動向上の為に磨く必要もなさそうです。

でもやっぱり、相変わらずホールドオープンはしてくれないので調べてみたら、
スライドストップがリコイルスプリングガイドに引っかかって動きが悪いんですね。
なので前回同様、リコイルスプリングガイドの根元の「く」の字部分と
スライドストップの軸部分のリコイルスプリングガイドに干渉する部分をヤスリで磨きました。

尚、組み立ての際はアウターバレル固定パーツがズレて、
スライドが入らない事があるので注意しましょう。

この上記の加工だけで難なくホールドオープンするようになりました。
スライドが重いので涼しく過ごしやすい季節になると動きが悪くなるでしょうが、
少なくとも夏場はバンバン弾を出して活躍してくれそうです。
RAPTOR製MP446は以前生産されたMP443と比べると大分クオリティが上がったので、
今後生産されるMP443(生産するのか、おい?)は箱出しでもそこそこ使えるモノになりそうです。
他のメーカーはMP446はおろか、MP443すら出してくれる気配がないので、
唯一の生産元であるラプターにはまだまだ頑張って欲しいですね(上から目線)。
陽気に福岡に帰ることすらままならない砥部良軍曹です。
娘が来年高校受験なんで福岡帰って太宰府天満宮にお参りに行きたいところなんですが、
正月三が日の大宰府は前方に居るおなごのケツを触っても気が付かないぐらい
すし詰めギュウギュウの人多スギィ!状態なので
何処からウィルスが飛んで来て憂き目に遭うか解りませんからね。
受験前に変なウィルスにやられて人生パーになるのだけは勘弁です。
ところで娘といえば昨晩のクリスマスイブの夜、
我輩が渾身のチキン丸焼きを作ったにもかかわらず、
「ウチのクリスマスといえば、父さんのボルシチだよね!」と言いやがるんですよ。
(2週間前に生ビーツが手に入ったのでボルシチも作っていた)
我輩、もう2度とクリスマスにチキン丸焼きは作るまいと心に誓うと同時に、
娘は我輩を無意識のうちにロシア的男子と認識しているのでは?という疑念が。
さて、少々減りはしたものの今年も無事にボーナスを頂きました。
それに伴い嫁から小遣いを頂いたので軍拡しちゃいました。
「お前は毎回冬のボーナス時に軍拡してんじゃねぇのか?」という
至極もっともなツッコミは逐次受け付けておりますのでご遠慮無くどーぞ。
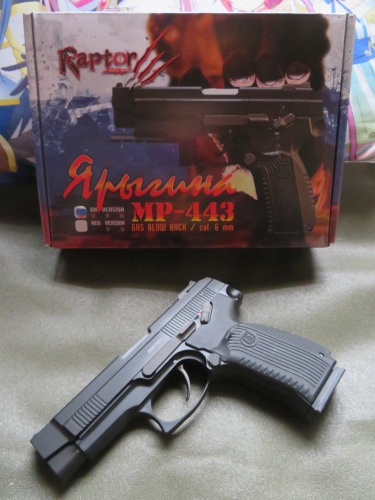
今回我輩が小遣い叩いて仕入れたのは
台湾のRAPTORなるメーカーの
MP443というロシアの拳銃です。
ハンドガンなので、当然ながらガスを使って動く銃(パットン氏曰く)です。
余談ですがこのロシアンピストルのMP443と言う名称は
この拳銃を生産しているイジェフスク工場の商品名的なもので、
ロシア軍では6П35(Пは「ぺー」と読む)と呼ばれているようです。
まあアレだ、H&K USPがドイツ連邦軍ではP8、
ベレッタM92FSが米軍ではM9と呼ばれているのと同様。
またこのMP443と言う拳銃はソ連、ロシアの銃器が一般的に、
「カラシニコフ」や「ドラグノフ」というような設計者の名前で呼ばれる例に漏れず
「ヤリギン」「グラッチ」と言う名称でも呼ばれております。
ヤリギンとはこの拳銃の設計者の名前で、
トカレフとかマカロフと同じニュアンスですね。
グラッチというのはこの拳銃の開発プロジェクトの名称らしく、
ロシア語で「ミヤマガラス」と言う意味なのだとか。
ロシア軍装備をするにあたり、一番のネックとなっていたのがハンドガン。
ソ連、ロシアの拳銃自体がそもそも少ない(PMとAPSとコレぐらい)というのに、
モデルアップされているのがKSC製マカロフぐらいしかないという状況。
そしてそのマカロフは小型が故にマルイ製ハンドガンと渡り合うには不向き。
そんなシベリアの永久凍土的なお寒いロシアンハンドガン事情を
打ち破ってくれたのがこのRAPTOR製MP443なのでございます。
こういうマニアックなモデルを出してくれるという点において、
海外メーカーの存在は「ユーザーとしてとても嬉しい」

しかしながらこの台湾ラプター製MP443、
取扱店がAKの品揃えに定評のあるNOOBARMSぐらいしかなく、
ツイッタで予約受付開始した次の日(w8月下旬ぐらい)に予約を申し込み、
手持ちの武器を売り払って必死且つ迅速に資金集めをしたにもかかわらず、
初回生産分は予約開始当日に予約した方々に全て奪われしまったようで、
予約から4ヶ月経った12月中旬になってようやく手に届くという有様なのでした。
なので今から買おうとしても手元に届くのは何時になるか解りませんですし、
そもそもこのラプターのMP443は本来フルメタルで生産しているものを
規制の喧しい日本向けにフレームを樹脂製に作り変えたもので、
生産数が限定されているが故に今後入手可能であるかも定かではありません。
我輩が購入したのは予備マガジンとマウントのセットであるデラックスバージョン。
お値段は0.5パットンぐらいとハンドガンにしては結構お高めではありますが、
(注:1パットン=50000円ぐらいですかね?)
後から予備マガジンを買うことを考慮するとお買い得な選択肢とも言えます。
海外製品はオプションや予備マガジンの流通が不安定なので、
出来ることなら予備マガジンも一緒に手に入れたいですからね。
ていうかハンドガンなのに本体だけでも20000円ぐらいするというお値段は
マルイ製ハンドガンしか買わない方々から見るとお高く感じるでしょうが、
タナカやKSCのハンドガンもだいたいそんぐらいのお値段なので特別高いわけでも無し(錯乱)。

尚、付属の取扱説明書に日本語記載がないのは仕方ないね(ビリー兄貴)としても、
フィールドストリッピングの方法ぐらい載せてくれよというツッコミは入れたくなります。
取扱説明書の情報量が少ないのは大抵の海外製エアソフトガンの難点です。

初速は平均83.4m/sとマルイ製ガスハンドガンと同等な数字が書かれておりますが、
我輩の個体は桐灰マグマカイロでマガジンを適度に温めても70m/s超えるぐらいでした。
夏場の暑い時期ならコレぐらい出て欲しいなと期待したいところです。

ラプター製MP443の外装レビューの前に軽く実銃の説明。
MP443はかつてのソ連、ロシア軍の拳銃とは異なり、
(永きに渡りソ連及びロシアは独自の企画の弾薬を使う拳銃しか作らなかった)
世界的に一般的な9mmパラベラムを使用する拳銃です。
実銃の装弾数は17+1発、その後改良されて18+1発になったのは、
MP443開発以前からFSB(旧KGB)やロシア連邦軍以外の部隊で使われている
グロック17(装弾数17+1発)に対抗するためですかね?
トリガーメカは実銃ではダブルアクションらしいですが
RAPTORのMP443は何故かシングルアクション。意味不明。
全体的なシルエット的には最近のポリマーフレーム拳銃よりは
一昔前のベレッタM9やスタームルガーP85に似た感じのものですね。
21世紀に採用された拳銃なのにアンダーマウントレールがないのも1世代前感。
そして余計な刻印や印字がないのが実にロシア。
でも、フィンガーレストが設けられたグリップや、
フレームに配置されたセイフティレバーと言うデザインは
昨今の流行に則ったものとなっております。

反対側に余計なものが飛び出していないのもある意味ロシア的。
でも此方側にもセイフティレバーがあるのは現代風。
サイズ的にはグロックやP226といった9mm口径の
中型オートマチックピストルと大差ない大きさですが
スライドはグロックより細く、グリップはグロックよりも太いです。
MP443は1990年代に開発され、2003年にロシア軍に採用され、
2010年ぐらいからロシア軍に配備された拳銃であるにも関わらず、
フレームはポリマーフレームではなく鉄製という変な拘り。
「プラスチックが我が祖国の極寒の環境に耐えられるのか?」と、
ロシア軍上層部は考えたから手堅く鉄製フレームを選択したのでしょうかね?
民生モデルのMP446は樹脂製フレームを採用しているらしいです。
そういえば大分昔、アカ嫌いの父上が元気ビンビンだった頃に、
「ソ連のライフルが木製ストックなのは、寒くても割れにくいから」
という露助を半分バカにしたよーな、でも真意っぽい話をしてましたが、
今ではあながちジョークとも思えない心境です。

トリガーは電動ガンのAKみたいに細く、我輩的には引きやすい形状です。
但しシングルアクションであるにも関わらずトリガーストロークは
異様に遊びが多くハンマーの落ちる感覚は掴みにくいという。
強いて言うならタナカ製ブローニング・ハイパワーのような感触。
スライドリリースレバーはセイフティレバーが少し邪魔で使い難い。
セイフティレバーは丁度いい位置でまあ使いやすいのですが
箱出し状態ではセイフティレバーが馬鹿みたいに固くて動かなくて唖然。
尚、このセイフティはハンマーがどの状態でもかけられます。

一体型のグリップパネルは太めで、嫁よりも掌が小さい我輩には握り辛いです。
グリップ後部の妙な角張った形状が手に馴染まないんですね。
まあロシアの武器は「武器に身体を合わせる」もんなんで、
軟弱な思考のプレイヤーにはロシア軍装備なんて無理なんですがw
マガジンリリースは形状的には可もなく不可もないボタン式ですが、
内部がキツイのかマガジンが中で引っかかってスルッと落下しない。
そしてマガジン装填時も途中で引っかかるので少し戸惑いを感じます。

21世紀の拳銃であるにも関わらず、古めかしさを感じるハンマー式。
ストライカー式にすればハンマーが引っかかる心配もないのにねぇと思うんですが、
どうやらロシア人はストライカー式の拳銃に親でも殺されたようです。
トカレフみたいにフレーム後部がハンマーを包み込む形状は
厚着の状態でハンマーが引っかかって暴発する可能性を防ぐロシアの伝統的デザイン。
ちなみに、この起こしにくいハンマーを手動でダウンさせると、
マガジンのガス放出バルブを強制的に叩いてガス全部出ます。

マガジンは25発装填可能。必要にして充分なキャパシティ。
但し取説のように上から弾を詰めるのは結構無理です。
まあそこら辺はマルイのガスガンのマガジンと同じように
フォロアーを下げて下の広がったスリットから装填すれば無問題。

不便なのはガスを充填する際、マガジンボトムをずらす必要がある事。
マガジンフォロワーの下のやつをずらせばマガジンボトムは動きますが、
毎回ガス注入の度にコレするのマンドクセ。
そして注入バルブが海外製高圧ガス対応型で
ジャパニーズフロン134や152はなかなか充填されないので、
WEガスガン用の日本バージョン注入バルブに交換したら何ということでしょう、
パッキン形状が合わなくて貴重なガスがダダ漏れしやがったんで、
パッキンは元のバルブに付いているものと入れ替える必要があります。

我輩が購入したMP443デラべっぴん、もといデラックスバージョンに付いているマウント、
取り付けるにはまずマウントのトリガーガードに引っ掛かる部分の蓋?を外して引っ掛けます。

その後、蓋を閉めてトリガーガード前側とレール部分に付いている固定用の芋ネジを締めます。
あまり締めすぎるとフレームに傷が入るのが嫌。

マウントレールを取り付ける事によりウェポンライトを取り付けられるという利点の代わりに
サイズ的に嵩張り、コイツを納めるホルスターはどうすればいいんじゃという難点が生まれます。
ぶっちゃけ、夜戦用にグロック17買った方が幸せになれそうです。
MP443、一つの拳銃として見るとロシア製消火器らしい大雑把で取っ付きにくさのある
何時ものロシアンクオリティといった感じのブツです。
正直、グロックやUSPといったような西側製拳銃と比較すると洗練が足りない。


そしてラプター製のMP443という点から見ると正直、雑な作り。
アルミ製のスライドはホコリが付いた上から塗装していたり、塗装が雑だったり、
スライド自体も出来がよろしくなくて至るところにボコボコが見られます。
中身にしても割り箸を割るようなトリガーのキレの悪さ、
ご機嫌斜めな時の嫁の股以上に動かないセイフティレバー、
築40年の中古物件の引き戸かと思うぐらい動きの渋いスライドの動き、
ケツ★ン開発されてないホ★ガキのようなマガジン出し入れのキツさ、
どれをとってもマルイ製ハンドガンには到底及ばない作りに泣きそうです。
撃ってみると弾は確かに飛びますが、精度がいいかと問われると微妙。
アルミスライドが重いのか、スライドの動きもかったるくて時々ジャムります。
多分、本来はパワーのあるガスでAV男優の腰のように激しくバシバシ動かして、
使っている間に各所が削れてだんだん滑らかになるという仕様なんでしょう。
コレ、マルイ製エアソフトガンしか知らない人種からすると完全に不良品です。
ラプター製MP443、初期状態のレビューを上げるのは躊躇われるシロモノ。

というわけでバラして調整するかと目論んだのですが、
前述のようにスライドをフレームから外す方法すら説明書に記載してないという体たらく、
初見殺しとはまさにコイツのためにある言葉です。
ま、ネットで検索したらすぐにスライドストップを外す方法が見つかって事なきを得ましたが、
その外し方が他の拳銃とは随分異なる方法なのに戸惑った我輩。
まずマガジンを抜いて(常識ですね)スライドを引き、スライドストップをかけます。
謎形状のリコイルスプリングガイドを露出させます。
その後リコイルスプリングガイドを少し引っ張り出すと、何処かで引っかかります。
そしてスライドを戻し、スライドストップをガバメントみたいにフレームの反対側から押し出すと、
スライドストップが抜けてフレームとスライドが分離します。これもうわかんねぇな。

リコイルスプリングガイドをずらして90度ひねり、持ち上げて外したら、
リコイルスプリングガイドが抜けてアウターバレルが外れるようになります。
コレがなかなか外れなくて少しイラッとするんだな。
尚、組み込みの際は更に面倒なのですがそれを解消する方法は後述にて。

スライドを何度か動かすor何度か撃っていると、
アウターバレルのチャンバー部分上部に傷が入っているのが確認できるでしょう。
その部分はスライドと干渉して作動不良の原因になっているので、
ヤスリである程度削って作動を滑らかにすることをオススメします。
目安はスライドを動かしても傷が入らなくなるまで。
ドライバーの先で示している部分がホップ調整ダイヤルです。
ストロークは少ない上に、調整は結構シビアです。
しかも指では動かないというオマケ付き。ドライバー必須。

チャンバーは小さなクロスネジで固定されています。
外部、内部共に仕上げが悪く引っかかるので
目の細かいヤスリやサンドペーパーでバリを取ります。
インナーバレルとチャンバーはマルイハンドガンと同規格です。
マルイのと交換してみたところ、チャンバーのゴムが気持ち柔らかいためか、
作動が少し滑らかになり、フライヤーがなくなりました。
どうやらゴム製品は日本製が性能がよろしいようです(意味深)。
インナーバレルの長さは95mmぐらいなので、グロックやP226のものが丁度いいでしょう。
インナーバレルが全体的に仕上げが良くなかったので、
マルイ製に交換すれば性能向上が期待できそうです。

ブリーチ部分は2つの6角ネジで固定されているので、緩めて取り外しますが、
初期段階では愛し合う2人の棒と穴よりもスライド内部にガッチリハマっているので
プラスチックハンマーでスライドをぶん殴らないと外れません。

勢いよく外そうとしてブリーチ上部のスプリング2本が無くならないように注意してください。
ブリーチブロックの外側サイド部分をサンドペーパーでキレイにすると、
取り外しor組み込みの時に引っかかりにくくなって楽になります。

ノズルの先端部分と弾のローディング部分にバリがあるので、
この部分もしっかりキレイに仕上げますが
削りすぎると作動不良の原因になるので丁寧に作業しましょう。
アレだ、指1本入れて大丈夫そうだから3本入れようみたいなのは止めとけという。

ノズルはブリーチ上部のスプリングを外せば前方に引き抜くだけで外れます。
(ていうかスプリングはすぐに外れるていうか、無くしそうになる)
あと、ドライバーで指している部分に半月状の金属パーツがあるので、
コイツもなくさないようにすぐに外しておきましょう。
この後、ブリーチ内部のピストン部分が外せるか試みたのですが、
結構キツキツにハマっているようで外せませんでした。

ノズル内部も分解してバリを取ります。
ノズルの右側に小さいクロスねじがあるので、それを緩めます。

ノズル内部はこのようなパーツ構成になっております。
左から順にノズル、スプリング、センサーバルブ、ストッパー。
センサーバルブとストッパーもバリがあるのでキレイにします。

さて、このストッパーですが我輩の個体(2期ロット以降生産品?)では、
ハの字部分が下を向くこの状態で付いておりました。

初期ロットでは写真のように上が広がっている状態(上下反対)で組まれていたらしく、
コレを反対に入れ替えて組み上げた方が動きが良くなるという情報がありました。
試しに入れ替えて組み上げてみたところ初速が70m/s強⇒70弱ぐらいになったたので、
ココの組付け次第でガスの流量が変化していると思われます。
初期ロットをお持ちの方は上下入れ替えて組んだほうがよろしいでしょう。

でもガスの流量が増えてマズルエナジーが上がっても
根本的にスライドの動きの渋さが作動の妨げになっているみたいなので、
スライドのレール部分、フレームのレールが噛み合う部分をサンドペーパーで均し、
引っかかりがないように仕上げればスライドの動きが大分改善され、動きが良くなります。
ついでにスライド内部もアウターバレルが干渉する部分は軽く磨きました。
更にスライドの表側のボコボコした部分や塗装の汚い部分も磨いて塗り直しました。
ここまですれば大分、作動がまあ多少は良くなりジャムの可能性が下がります。
結構大変な作業ですが、ここまでしてもアルミスライドが思いのほか重いのか、
リコイルはよいものの数発撃つと動きは悪くなります

さて、我輩が全国のMP443ユーザーにオススメしたい加工が、
リコイルスプリングガイドのスライドストップレバーのハマる部分の加工。
写真のこ↑こ↓が示している「くの字」の部分を
目の細かい細いヤスリで軽く削って丸めると
あら不思議、組立時にリコイルスプリングガイドをガチャガチャ弄らなくても、
スライドストップレバーを押し込んだ勢いで経験豊富な女子のように
棒の部分がカシャッとハマって直ぐに組み立てられます。

削る目安はリコイルスプリングガイドを組んだ状態で、
写真のようにスライドストップレバーを押し込んでハマるようになるまで
少しずつ調整しながら削るという完全に現物合わせなんですが、
(然程削らなくてもスルッと入るようにはなる)
この加工によってイチイチ組立時に反対側の穴から
ドライバーを突っ込んでスライドストップレバーを押し込む手間が省けます。

ここまで手を加えないと使うのが難しいであろうRAPTOR製MP443、
正直、ロシア軍装備に拘る人以外は全く手を出す必要性のない代物です。
ロシア軍装備でもスペツナズとかFSBとかやっている人は
余計な思考に陥ることなくマルイのグロック17を使いなさい。
かなり珍しいハンドガンが欲しい的な軽い気分で手を出すと地獄を見ます。
ただ、ロシア連邦軍装備をシメる一品としては
銃剣やスコップ以上に必要不可欠な品でしょう。
だってハンドガンだから、銃剣やスコップよりはサバゲーに使える。
装弾数的には普通のプレイヤーが使用しているハンドガンと大差なく、
パワーも然程変わらないので互角に渡り合えなくはないのですが、
信頼性ではやはり、マルイ製ハンドガンには敵わないなというのが正直な感想です。
我輩的にはロシア軍装備のサイドアームとしてMP443を手にしたことで、
ようやくロシア軍装備という名のパズルの完成に終わりが見えたという気分です。
まあ要するに、それなりには満足しているということだ。
でも我輩って実はロシア軍装備の時は案外、ハンドガン使わない人なんで、
コイツの存在がどれぐらいのタクティカルアドバンテージが有るかは未知のエリアーッ!
尚、一緒に撮影した「おいしいロシア」というマンガ、
著者がロシア人の旦那と一緒にロシアに1年間滞在し、
そこで生活してどのような経験をしたかというエピソードを交えて
ロシアの主な料理をマンガで面白く説明するというマンガなので、
ロシア軍を極める活動の一環でロシア料理にハマりたい人(居るのか?)は是非とも買うべし。
2022.12.8追記
アルミスライドの重量感よりも確実な作動と発射を求めて、
RAPTOR製MP443用樹脂スライドの購入に踏み切った我輩。
しかし、最近は大分マシになったとは聞くものの3Dプリンター製というのが
無加工で使えるのか否かどーも不安で仕方がなかったんです。

現物を手にして不安が絶望にランクアップ。
「我輩はこんな物に0.2パットンを費やしてしまったのか」という自己嫌悪に陥りました。
余りにも酷くて当初の写真を撮影する心の余裕もなかったのですが、
この内側のシワシワガタガタ質感が購入時の質感です。
恐る恐るプリーチを組み込んでみたところ、まあ多少はねきつかったですが、
サンドペーパーでスライド内側を均したらブリーチは収まりました。
でもリアサイトがキツくて溝をヤスリで削る羽目に。
嬉しい誤算だったのは取り付け後の作動。普通にブローバックして弾も出ました。

しかしこの汚い見た目だけは見ていて悲しくなるレベルだったので、
何日かかけてサンドペーパーでかなり磨きまくり、表面を平らにしました。

しかし塗装が綺麗に乗らないのでプラモデルマスターの我が愛しの同期、
学長に託して更に磨きをかけてもらい、下地をしっかりと塗ってもらい、
艶消しブラックで塗って貰ったお陰で何とか鑑賞に耐える風合いになりました。
因みにセレーション部分、一晩かけて細いヤスリで磨きまくりましたがこの体たらくです。

スライドを樹脂製に替えた事によって冬以外はある程度撃てるシロモノになりました。
でも学長から受け取った時はスライドストップは作動していたのですが、
暫くパコパコ撃っていたらスライドストップの掛かる部分が適度に摩耗、
ホールドオープンしなくなってしまいましたが作動はするからオッケー・・・なのか?
2024.8.10追記
RAPTOR製MP443のバリエーションにMP446ヴァイキングが加わったので
ヤフオクで0.76パットンで購入しました。

ハンドガンに電動ガン並の金を払うのは酔狂かとも思いはしましたが、
MP446の生産数はかなり少なく、240ドルぐらいするみたいなので、
「WAのハンドガンも同じぐらいの価格だし、まあしょうがないね」という気持ちで購入。
セット内容は本体、マガジン、マウントレール、そして内容が薄い説明書。
MP443に付属していたサプレッサー用アダプターは付いてませんでした。

MP446ヴァイキングとはMP443を樹脂フレームに変更したモデルで、輸出用なんだとか。
Wikipediaにはロシア軍でも使用されているような記載がありましたが、どうだか?

ヴィジュアル的にはスライドの刻印が増えただけで、
フレームはMP443と全く変わらないのですが、
このスライドの刻印が入っただけでも大分雰囲気が違います。
しかも、スライドの仕上がりが我輩所有の2期ロット品よりも綺麗で「何だこれは、たまげたなあ」。

我輩所有のMP443同様、トリガー&ハンマーは相変わらずシングルアクションです。
セイフティレバーは箱出しでもそれなりに動いてくれましたが、作動はイマイチです。

このスライドの仕上げに時間を掛けた分、価格が上がったのかなぁ?と
野暮な事を考えながら見ていたら、MP446はスライドの形状が違うんですね。
イジェクションポート周辺が肉厚になっております。

ガスと弾を入れて発射してみたら、気温が高いからか結構快調に作動しました。
よく見たら我輩所有のMP443で作動を良くするために削った
アウターバレルのチャンバー部分(指差している所)に削り跡が見られます。
まさか、RAPTORの中の人は我輩のブログを参考にして加工したのかな?

もう一つ「何だこれは、たまげたなあ」だったのは、
リコリスリコイルスプリングガイドを引っ張り出さなくても
スライドリリースレバーを右側から押し出せば外せるんですね。
やっぱりRAPTORの中の人、我輩のブログ見てるわ(確信)。

上がMP446、下がMP443のスライドです。
とりあえずフィールドストリッピングしてみたところ
アウターバレルが外れないので何故かと思いきや、
多分作動を良くするためのアウターバレルを固定するパーツがスライド先端に追加されていました。
コイツはスライド先端を軽くプラスチックハンマーとかで叩くと外れます。

右がMP446、左がMP443です。
アウターバレル固定パーツが追加された以外、その他各パーツに変化はありません。
そして各パーツのバリも案外少ないというか、あまり気になりません。
更に、フレームのレールも滑らかで作動向上の為に磨く必要もなさそうです。

でもやっぱり、相変わらずホールドオープンはしてくれないので調べてみたら、
スライドストップがリコイルスプリングガイドに引っかかって動きが悪いんですね。
なので前回同様、リコイルスプリングガイドの根元の「く」の字部分と
スライドストップの軸部分のリコイルスプリングガイドに干渉する部分をヤスリで磨きました。

尚、組み立ての際はアウターバレル固定パーツがズレて、
スライドが入らない事があるので注意しましょう。

この上記の加工だけで難なくホールドオープンするようになりました。
スライドが重いので涼しく過ごしやすい季節になると動きが悪くなるでしょうが、
少なくとも夏場はバンバン弾を出して活躍してくれそうです。
RAPTOR製MP446は以前生産されたMP443と比べると大分クオリティが上がったので、
今後生産されるMP443(生産するのか、おい?)は箱出しでもそこそこ使えるモノになりそうです。
他のメーカーはMP446はおろか、MP443すら出してくれる気配がないので、
唯一の生産元であるラプターにはまだまだ頑張って欲しいですね(上から目線)。
2020年05月23日
中華安物電動ガンは道具としては悪くない
ツイッターを見ていると「中国製電動ガン使っているやつは売国奴!」とか、
「あんな不良品でよくサバゲー出来るな!」みたいな戯言を見かけるんですが、
そういうツイートしちゃう人って中国がアレだけ勢い付いている今の御時世、
中国製品を使わずに人生過ごすことはほぼほぼ不可能だってこと解ってんのかねぇ?
それに、エアガンに関して言えば魅力的な商品を展開しているメーカーは
どちらかと言うと中国のメーカーが多数を占めているんですよね。
中国人は厚かましさや傲慢さがある反面、冒険心とか探究心もあるみたいだから、
こんなの誰得なんだよな色んなエアガンを販売してみたり、
ソレを色んな国で売って金稼ごうみたいな行動力に繋がるんでしょうね。
さて、現在我輩がサバゲーの沼に沈めようととしている後輩のイチロク、
名前からするとアーマーライトを買わせるべきだったんでしょうが、
我輩はねぇ、アーマーライトはキャリハン付きじゃねぇと好きじゃないんだよ!
M4ライフルも欲しい?オゥ考えといてやるよ(買わせるとは言ってない)。
そんな我輩が後輩に買わせるてっぽーはAKだよ!木製ストックのAK!
というわけで本来ならばLCTの高級品を買わせたいところではありましたが、
彼はサバゲーにそれ程銭をつぎ込めない家庭の理由があるということで、
内部の手入れの必要はあるけど比較的安価で購入可能である
中華CYMA製AKS74Uを買わせることにしました。
我輩の初めてのサバゲーの武器、
それはAK47で我輩は20歳でした。
ソレはとても頑丈で信頼性が高く、
こんな素晴らしい武器を使っている我輩は
きっと特別な存在なのだと感じました。
今では我輩の武器がAK74。
後輩に買わせるのは勿論AK74。
なぜなら彼も特別な存在だからです。
余談ですが日本では一般的にAKS74Uを「クリンコフ」と呼びますが、
コレは開発者の名前ではなくロシア語で「短いもの」を指す言葉らしい(詳しくは不明)ので、
我輩的にはあまりそういう適当な名称で呼びたくはないんですねぇ。
尚、「お前のち★ちん、クリンコフなんだろ?」と言うツッコミは真摯に受け止めます。

CYMAのAKS74Uはマルイ旧世代AKと構成が同じの「CM035」と
LCTやE&Lに構成が似た「CM045」という2つのモデルが有り、
我輩が気になっていたのはマルイ準拠のCM035だったのでそっちを買わせました。
(ハンドガードが木製のモデルはCM035Aという)
お値段はフォースターで0.4パットン程度。
マ●ガ倉庫でマルイ製中古銃買うよりも安いのに、ハンドガードは木製です。

全体的パーツ構成は見慣れたもので構成されているし、
我輩自身も過去にAKS74Uは3丁ほど弄ったんで正直な話、新鮮さは皆無ですね。
ただ、コレぐらいのサブマシンガンぐらいなサイズの電動ガンは
初心者に買わせるには丁度良く扱いやすいサイズなんです。
長い武器って正直な話、どんな戦場でも使いにくいですからね。
実銃ではライフル弾を撃ち出す短い鉄砲は反動が強くて撃ちにくいらしいですが、
電動ガンなら反動がないので短さが優位性を確保します。
まあコイツを始めに買わせて戦場での戦いに慣れされた上で、
もう少し長いほうが好みだというのならフルサイズAKを買わせればいいし、
コレぐらいが丁度良いというのであればこの系列を買い足すようにすればよろしいかと。

いやしかし、正直な話、パッと見はよく出来てんなと思ったんですが、
つぶさに見ていくと結構突っ込みどころあるなコレ。
CYMAのAK74系列のハイダーは外側に22mmのインナーにかぶさり、
インナーを外すと14mm逆ネジ山が出てくるので、
このハイダーをマルイ次世代AK74に流用することが可能ですし、
インナー外して14mm逆ネジの全く違うハイダーを取り付けることも出来ます。

フロントサイトが前方に傾いているような気がするのは
少し削って調整すればどうにかなりそうなんですが、
ハンドガードが合板じゃないのはAK原理主義者的に認められません。
しかも結構柔らかそうな木材、だから安いのね。
とにかく、AKのハンドガードと女の子のパンツはしましまじゃねぇと萌えねぇんだよ。
合板ならではのハンドガード下部の縞々がAKらしさを醸し出すんですよ。

CYMAのラインナップにはフレームが樹脂製の
スポーツラインとかいうのも存在しておりますが、
このモデルはフレームは金属製(多分材質はアルミ)です。
スポーツラインのAK74とこのAKS74Uは同じぐらいの値段なので、
耐久性を求めるならAKS74Uを買うほうが得策です。
フレーム周りはそれ程不自然でもないですからね。
トリガーガードはクロスネジで止められているので、
見た目は残念ですが社外品のAKマグウェルも取付可能です。
セレクターの止めネジがマルイAK47みたいなカバーが被ったやつなのも残念。
AKM、AK74系列はこ↑こ↓の形状が平べったいネジなんだよなぁ。

折りたたみストックの出来はマルイAKS74と大差ない感じです。
色が剥げやすいのはCYMAもマルイも変わらないですからね。
新品時はガッチリしておりますが、多分使っているうちにガタガタになる?
でも根本のロック部分のパーツはマルイより丈夫かも知れない?

マルイAKS74よりCYMA製AKS74がよろしい部分は
サイドマウントベースが取り付けられていること。
マルイは純正マウントベースのレールがリアサイトに当たるので、
マウントレールを断念せざるを得なかったようですが、
CYMAの別売りマウントベースはレールをひっくり返してつければ
リアサイトと干渉しないので大丈夫なのです。

バッテリーは細いタイプなら大概のものはデッキカバー内に収まります。
少し短め&太めのリポでもどうにかならんことはないです。
因みに、チャンバーはマガジンリップに優しい樹脂製です。
ただ、チャージングハンドルはフルストロークで引けませんがね。
あ、写真を撮り忘れておりましたが純正マガジンは茶色の500連多弾マガジンです。
出来はLCTのと大差ない(予備で購入したのがLCTのやつだった)んで
ひょっとしてAK74のマガジンってパッケージだけ別で中身は同じ製品?

最近の中華電動ガンの中身は大分出来は良くなりましたが、
グリスは相変わらず青いネバッとした変なのを使っているし、
シムやスプリングも適当なのが入っているので、
CYMAのAKS74Uも内部改めのために分解します。
フロント周りがマルイ旧世代AK47のように4本のネジで固定されているだけなので、
ネジを外してフロントをそのまま前に引き出せばメカボックスへのアクセスは容易です。
マルイ旧世代AK47みたいにメカボの上に余計なインナーもないので、
なんの気遣いもなく前回りを外すことが可能です。
という事はスポーツラインのAK74(マルイ旧世代AK47と構成が一緒)の
前回りだけ持っていれば気分に合わせてフルサイズとショートを楽しめる!?
或いは前回りをβスペツナズのものと交換ということも可能です。誰もやらんだろうけどw
チャンバーの固定方法はマルイ旧世代AK47と同じなので、
ネジを外してパッキンのゴムを交換してもよろしいでしょう。
まあ我輩は素の性能を確認したいんで敢えてそのままにしておきましたがねw

その後、デッキロックから伸びているチャージングハンドルを外してしまいましょう。
分解が容易であるという点に置いてもCYMA製AKS74Uはおすすめの一品です。
分解がややこしい電動ガンの修理を依頼された日にゃあ
かかった時間と手間を考慮して2000円ぐらい整備料を頂きたくなりますが、
コイツならそれ程面倒でもないんで500円ぐらいで「オゥ、やってやるよ」。
まあ今回は特別にタダでやっておりますがね。
最近はコスパ厨が多くなって電動ガンだけでなくクルマとかでも
「部品交換しない内部調整だけでなんでそんなに金取られるんだ」
「部品入れ替えるだけの作業にカネがかかるのはおかしい」
という戯言をほざく世間知らずで馬鹿なキッズが増えてきました。
エアガンのパーツなんかはそのまま交換したからと言って性能が上がるとは限らないので、
他の部品を調整、交換するとかの作業が発生するのが普通なのです。
それに銃の分解、メカボックス開け締めするだけでもそれなりに時間はかかります。
だから人に改造や調整を頼むということはその人の時間を奪うのと同じことなんです。
だからこそその時間がかかった分、費用が発生するのは当たり前なのです。
どーしてもカネ払いたくないなら自分でメカボぐらい弄れるようになりなさい。
ま、何も出来ないやつに限って文句ばかり言うんですがね。

まあそんな苦言は置いといて、あとは他社メーカーのAKのように、
セレクター止めネジの上の蓋を外し、ネジを緩めてセレクターを外し、
グリップ底のネジを緩めてグリップを抜き、メカボックスを上に持ち上げれば、
メカボックスが完全に外に出て手術をすることが出来ます。

セレクタープレートを外してセレクターのギアをすべて外し、
モーターを固定するネジを外してしまい、トリガー後部のカバーを外し、
メカボ上部の固定プレートを外せばあとはメカボのネジを緩めるだけ。

案の定というか、期待通りというか、グリスは最近のCYMAお約束の青グリス。
この青グリスも過去の緑グリス同様、粘性が高く電動ガン向きではないと思われるので、
ブレーキパーツクリーナーで洗浄してマルイのグリスを塗り直します。
シムはそれほど酷くなかったのですが、スパーとベベルギアがガタついていたので1枚増やして調整。
スイッチ周りは過去の製品と比べると大分綺麗ですね。

ピストンはOリングがガバガバだったのでマルイ純正と交換。
スプリングはとりあえずそのままブチ込んでみましたがパワーは規制値内。
最近のCYMA製品は大体どれも日本の法規制に沿ったスプリングが入っているようです。

シリンダー、ノズル、シリンダーヘッド、タペットプレート、スプリングガイドに
特に酷い箇所は見られなかったのでタペットプレートだけ少しサンドペーパーで均して使用。

ギアも特に悪い点は見られなかったのでそのまま使用。
過去にAKM、AIMS、RPK74、SVD、SVU、AK74MとCYMA製品を扱ってきましたが、
メカボックス内はそれ程酷いパーツに当たったことはなかった・・・かな?
多分ココ数年のCYMAの電動ガンは中身入れ替えなくても案外使えます。
でも中華電動ガンの大半に言えることなんですが、
モーターは強いバネを引けるようにトルク型のもっさり回転なので、
マルイの電動ガン並みの連射速度(秒間14~16発)を求めるとなると、
モーターだけはEG1000を別途準備して交換したほうがよろしいでしょうね。

CYMA製AKS74Uのいいところもう一つ。
ハンドガードの取り付けは他社製品と同様、レバーによる固定。
だからまあ多少はね、すり合わせが必要かもしれませんが、
LCTのハンドガードを取り寄せて組み込むことも出来ます。
マルイは実銃パーツ組み込み防止のために敢えて独特の構成にしているそうですが、
ソレが仇となって最近の機種はどれも分解がややこしくなっているようですし、
リアルさを求めると限界を感じる部分が多々見られる気がします。
中華電動みたいなユーザーに優しい設計をもう少し見習ってほしいですね。

中身の調整だけでG&G0.2g弾で初速平均80m/s強ぐらい。
という事はピストンスカスカだったからノーマルはもう少しパワー低いのか?
SHSのM90スプリングに入れ替えれば初速90近くにはなると思いますが、
我輩的に電動ガンのパワーなんて80ちょいあれば充分です。
なお、連射速度は秒間12発程度なので火力的には物足りませんね。
命中精度はオリジナルパッキンのせいか、それともバレルがいかんのか結構散るようです。

イチロク本人はコレが初の電動ガンといううことでブツには満足している模様。
コレで彼は今のところかなり戦果を上げてはいるんで、
そこそこの性能が出ていれば電動ガンなんて
バカみたく性能を突き詰めなくてもいいのかなって思いました。
電動ガンをサバイバルゲーム用の弾を撃ち出す道具と考えれば
外観のリアルさとか質感の良さなんてのはそれ程重要でもないのですが、
今後サバゲーの世界にのめり込むと武器としての性能を突き詰める方向に進むか、
それとも外観への拘り&満足感を求める方向に進むはずです。
その時にこの武器に対してどう考えるか、ソレは自身が決めること。
そうなるとCYMAのAKS74Uはかなり物足りない一品だとは思うのですが、
LCTやE&Lといった上位互換品が品薄である事実を考慮すると
現時点でかなり入手しやすい(しかも安い)AKS74Uであり、
メカボックスの改造も容易であるのでまあ悪くはない選択肢ではあると思います。
追記:イチロクは最近、このAKS74Uが夜戦向きではない事に気がついた模様。
レールハンドガードのAKにしとけばよかったかと只今絶賛後悔中。
「あんな不良品でよくサバゲー出来るな!」みたいな戯言を見かけるんですが、
そういうツイートしちゃう人って中国がアレだけ勢い付いている今の御時世、
中国製品を使わずに人生過ごすことはほぼほぼ不可能だってこと解ってんのかねぇ?
それに、エアガンに関して言えば魅力的な商品を展開しているメーカーは
どちらかと言うと中国のメーカーが多数を占めているんですよね。
中国人は厚かましさや傲慢さがある反面、冒険心とか探究心もあるみたいだから、
こんなの誰得なんだよな色んなエアガンを販売してみたり、
ソレを色んな国で売って金稼ごうみたいな行動力に繋がるんでしょうね。
さて、現在我輩がサバゲーの沼に沈めようととしている後輩のイチロク、
名前からするとアーマーライトを買わせるべきだったんでしょうが、
我輩はねぇ、アーマーライトはキャリハン付きじゃねぇと好きじゃないんだよ!
M4ライフルも欲しい?オゥ考えといてやるよ(買わせるとは言ってない)。
そんな我輩が後輩に買わせるてっぽーはAKだよ!木製ストックのAK!
というわけで本来ならばLCTの高級品を買わせたいところではありましたが、
彼はサバゲーにそれ程銭をつぎ込めない家庭の理由があるということで、
内部の手入れの必要はあるけど比較的安価で購入可能である
中華CYMA製AKS74Uを買わせることにしました。
我輩の初めてのサバゲーの武器、
それはAK47で我輩は20歳でした。
ソレはとても頑丈で信頼性が高く、
こんな素晴らしい武器を使っている我輩は
きっと特別な存在なのだと感じました。
今では我輩の武器がAK74。
後輩に買わせるのは勿論AK74。
なぜなら彼も特別な存在だからです。
余談ですが日本では一般的にAKS74Uを「クリンコフ」と呼びますが、
コレは開発者の名前ではなくロシア語で「短いもの」を指す言葉らしい(詳しくは不明)ので、
我輩的にはあまりそういう適当な名称で呼びたくはないんですねぇ。
尚、「お前のち★ちん、クリンコフなんだろ?」と言うツッコミは真摯に受け止めます。

CYMAのAKS74Uはマルイ旧世代AKと構成が同じの「CM035」と
LCTやE&Lに構成が似た「CM045」という2つのモデルが有り、
我輩が気になっていたのはマルイ準拠のCM035だったのでそっちを買わせました。
(ハンドガードが木製のモデルはCM035Aという)
お値段はフォースターで0.4パットン程度。
マ●ガ倉庫でマルイ製中古銃買うよりも安いのに、ハンドガードは木製です。

全体的パーツ構成は見慣れたもので構成されているし、
我輩自身も過去にAKS74Uは3丁ほど弄ったんで正直な話、新鮮さは皆無ですね。
ただ、コレぐらいのサブマシンガンぐらいなサイズの電動ガンは
初心者に買わせるには丁度良く扱いやすいサイズなんです。
長い武器って正直な話、どんな戦場でも使いにくいですからね。
実銃ではライフル弾を撃ち出す短い鉄砲は反動が強くて撃ちにくいらしいですが、
電動ガンなら反動がないので短さが優位性を確保します。
まあコイツを始めに買わせて戦場での戦いに慣れされた上で、
もう少し長いほうが好みだというのならフルサイズAKを買わせればいいし、
コレぐらいが丁度良いというのであればこの系列を買い足すようにすればよろしいかと。

いやしかし、正直な話、パッと見はよく出来てんなと思ったんですが、
つぶさに見ていくと結構突っ込みどころあるなコレ。
CYMAのAK74系列のハイダーは外側に22mmのインナーにかぶさり、
インナーを外すと14mm逆ネジ山が出てくるので、
このハイダーをマルイ次世代AK74に流用することが可能ですし、
インナー外して14mm逆ネジの全く違うハイダーを取り付けることも出来ます。

フロントサイトが前方に傾いているような気がするのは
少し削って調整すればどうにかなりそうなんですが、
ハンドガードが合板じゃないのはAK原理主義者的に認められません。
しかも結構柔らかそうな木材、だから安いのね。
とにかく、AKのハンドガードと女の子のパンツはしましまじゃねぇと萌えねぇんだよ。
合板ならではのハンドガード下部の縞々がAKらしさを醸し出すんですよ。

CYMAのラインナップにはフレームが樹脂製の
スポーツラインとかいうのも存在しておりますが、
このモデルはフレームは金属製(多分材質はアルミ)です。
スポーツラインのAK74とこのAKS74Uは同じぐらいの値段なので、
耐久性を求めるならAKS74Uを買うほうが得策です。
フレーム周りはそれ程不自然でもないですからね。
トリガーガードはクロスネジで止められているので、
見た目は残念ですが社外品のAKマグウェルも取付可能です。
セレクターの止めネジがマルイAK47みたいなカバーが被ったやつなのも残念。
AKM、AK74系列はこ↑こ↓の形状が平べったいネジなんだよなぁ。

折りたたみストックの出来はマルイAKS74と大差ない感じです。
色が剥げやすいのはCYMAもマルイも変わらないですからね。
新品時はガッチリしておりますが、多分使っているうちにガタガタになる?
でも根本のロック部分のパーツはマルイより丈夫かも知れない?

マルイAKS74よりCYMA製AKS74がよろしい部分は
サイドマウントベースが取り付けられていること。
マルイは純正マウントベースのレールがリアサイトに当たるので、
マウントレールを断念せざるを得なかったようですが、
CYMAの別売りマウントベースはレールをひっくり返してつければ
リアサイトと干渉しないので大丈夫なのです。

バッテリーは細いタイプなら大概のものはデッキカバー内に収まります。
少し短め&太めのリポでもどうにかならんことはないです。
因みに、チャンバーはマガジンリップに優しい樹脂製です。
ただ、チャージングハンドルはフルストロークで引けませんがね。
あ、写真を撮り忘れておりましたが純正マガジンは茶色の500連多弾マガジンです。
出来はLCTのと大差ない(予備で購入したのがLCTのやつだった)んで
ひょっとしてAK74のマガジンってパッケージだけ別で中身は同じ製品?

最近の中華電動ガンの中身は大分出来は良くなりましたが、
グリスは相変わらず青いネバッとした変なのを使っているし、
シムやスプリングも適当なのが入っているので、
CYMAのAKS74Uも内部改めのために分解します。
フロント周りがマルイ旧世代AK47のように4本のネジで固定されているだけなので、
ネジを外してフロントをそのまま前に引き出せばメカボックスへのアクセスは容易です。
マルイ旧世代AK47みたいにメカボの上に余計なインナーもないので、
なんの気遣いもなく前回りを外すことが可能です。
という事はスポーツラインのAK74(マルイ旧世代AK47と構成が一緒)の
前回りだけ持っていれば気分に合わせてフルサイズとショートを楽しめる!?
或いは前回りをβスペツナズのものと交換ということも可能です。誰もやらんだろうけどw
チャンバーの固定方法はマルイ旧世代AK47と同じなので、
ネジを外してパッキンのゴムを交換してもよろしいでしょう。
まあ我輩は素の性能を確認したいんで敢えてそのままにしておきましたがねw

その後、デッキロックから伸びているチャージングハンドルを外してしまいましょう。
分解が容易であるという点に置いてもCYMA製AKS74Uはおすすめの一品です。
分解がややこしい電動ガンの修理を依頼された日にゃあ
かかった時間と手間を考慮して2000円ぐらい整備料を頂きたくなりますが、
コイツならそれ程面倒でもないんで500円ぐらいで「オゥ、やってやるよ」。
まあ今回は特別にタダでやっておりますがね。
最近はコスパ厨が多くなって電動ガンだけでなくクルマとかでも
「部品交換しない内部調整だけでなんでそんなに金取られるんだ」
「部品入れ替えるだけの作業にカネがかかるのはおかしい」
という戯言をほざく世間知らずで馬鹿なキッズが増えてきました。
エアガンのパーツなんかはそのまま交換したからと言って性能が上がるとは限らないので、
他の部品を調整、交換するとかの作業が発生するのが普通なのです。
それに銃の分解、メカボックス開け締めするだけでもそれなりに時間はかかります。
だから人に改造や調整を頼むということはその人の時間を奪うのと同じことなんです。
だからこそその時間がかかった分、費用が発生するのは当たり前なのです。
どーしてもカネ払いたくないなら自分でメカボぐらい弄れるようになりなさい。
ま、何も出来ないやつに限って文句ばかり言うんですがね。

まあそんな苦言は置いといて、あとは他社メーカーのAKのように、
セレクター止めネジの上の蓋を外し、ネジを緩めてセレクターを外し、
グリップ底のネジを緩めてグリップを抜き、メカボックスを上に持ち上げれば、
メカボックスが完全に外に出て手術をすることが出来ます。

セレクタープレートを外してセレクターのギアをすべて外し、
モーターを固定するネジを外してしまい、トリガー後部のカバーを外し、
メカボ上部の固定プレートを外せばあとはメカボのネジを緩めるだけ。

案の定というか、期待通りというか、グリスは最近のCYMAお約束の青グリス。
この青グリスも過去の緑グリス同様、粘性が高く電動ガン向きではないと思われるので、
ブレーキパーツクリーナーで洗浄してマルイのグリスを塗り直します。
シムはそれほど酷くなかったのですが、スパーとベベルギアがガタついていたので1枚増やして調整。
スイッチ周りは過去の製品と比べると大分綺麗ですね。

ピストンはOリングがガバガバだったのでマルイ純正と交換。
スプリングはとりあえずそのままブチ込んでみましたがパワーは規制値内。
最近のCYMA製品は大体どれも日本の法規制に沿ったスプリングが入っているようです。

シリンダー、ノズル、シリンダーヘッド、タペットプレート、スプリングガイドに
特に酷い箇所は見られなかったのでタペットプレートだけ少しサンドペーパーで均して使用。

ギアも特に悪い点は見られなかったのでそのまま使用。
過去にAKM、AIMS、RPK74、SVD、SVU、AK74MとCYMA製品を扱ってきましたが、
メカボックス内はそれ程酷いパーツに当たったことはなかった・・・かな?
多分ココ数年のCYMAの電動ガンは中身入れ替えなくても案外使えます。
でも中華電動ガンの大半に言えることなんですが、
モーターは強いバネを引けるようにトルク型のもっさり回転なので、
マルイの電動ガン並みの連射速度(秒間14~16発)を求めるとなると、
モーターだけはEG1000を別途準備して交換したほうがよろしいでしょうね。

CYMA製AKS74Uのいいところもう一つ。
ハンドガードの取り付けは他社製品と同様、レバーによる固定。
だからまあ多少はね、すり合わせが必要かもしれませんが、
LCTのハンドガードを取り寄せて組み込むことも出来ます。
マルイは実銃パーツ組み込み防止のために敢えて独特の構成にしているそうですが、
ソレが仇となって最近の機種はどれも分解がややこしくなっているようですし、
リアルさを求めると限界を感じる部分が多々見られる気がします。
中華電動みたいなユーザーに優しい設計をもう少し見習ってほしいですね。

中身の調整だけでG&G0.2g弾で初速平均80m/s強ぐらい。
という事はピストンスカスカだったからノーマルはもう少しパワー低いのか?
SHSのM90スプリングに入れ替えれば初速90近くにはなると思いますが、
我輩的に電動ガンのパワーなんて80ちょいあれば充分です。
なお、連射速度は秒間12発程度なので火力的には物足りませんね。
命中精度はオリジナルパッキンのせいか、それともバレルがいかんのか結構散るようです。

イチロク本人はコレが初の電動ガンといううことでブツには満足している模様。
コレで彼は今のところかなり戦果を上げてはいるんで、
そこそこの性能が出ていれば電動ガンなんて
バカみたく性能を突き詰めなくてもいいのかなって思いました。
電動ガンをサバイバルゲーム用の弾を撃ち出す道具と考えれば
外観のリアルさとか質感の良さなんてのはそれ程重要でもないのですが、
今後サバゲーの世界にのめり込むと武器としての性能を突き詰める方向に進むか、
それとも外観への拘り&満足感を求める方向に進むはずです。
その時にこの武器に対してどう考えるか、ソレは自身が決めること。
そうなるとCYMAのAKS74Uはかなり物足りない一品だとは思うのですが、
LCTやE&Lといった上位互換品が品薄である事実を考慮すると
現時点でかなり入手しやすい(しかも安い)AKS74Uであり、
メカボックスの改造も容易であるのでまあ悪くはない選択肢ではあると思います。
追記:イチロクは最近、このAKS74Uが夜戦向きではない事に気がついた模様。
レールハンドガードのAKにしとけばよかったかと只今絶賛後悔中。
2020年05月19日
サバゲー界隈では電子トリガーが流行中?
我輩、台湾という国は素晴らしいと常日頃思っております。
東日本大震災発生後も躊躇なく義援金を沢山贈り、救助隊員も派遣してくれました。
今回のコロナウィルスの対応も迅速で、感染者をむやみに出すこともなく収めております。
そして何より、台湾製の電動ガンは分解しなくても使える!
我輩が一番最初に買った海外製の電動ガンは
台湾のICS製AK74Mだったんですがコレはなかなかいいブツでした。
後発の高級製品には劣るもののしっかりと作られた外観、
バレルやチャンバーパッキンを変えなくても充分な精度、
メカボックス内部はマルイと大差なく、変なグリスも使ってない!
そして一番嬉しいのはデフォルトで多弾数マガジン2本付き!
青森転勤前に後輩のエロ小僧のβスペツナズ&AKS47と交換してしまったので、
現在では手元にございませんが出物がアレばまた欲しいかもしれん。
まあその後もICS製品なら問題なかろうとM3グリースガンを仕入れましたが、
コレも外観は素晴らしい出来栄えで作りもしっかりしており
内部修正に必要なしに充分使える素晴らしい電動ガンでした。
最近の台湾製電動ガンは正規品なら大抵、日本仕様にして生産されているので、
箱出しでも文句なしに充分使える優秀なサバゲーツールです。
ところで我輩は基本、人の銃を見ながら「いいなぁ、コレ」と言いはするのですが、
心の底からいいと思った事はそうそうありません。
マジでコレ欲しいと思ったのはLCTの木製ストック付きAKぐらいでしょうかね。
でもね、ある日の夜戦の時にコマさんが台湾のG&G製AKを持ってきており、
ソレが思いの外ツボにはまるブツだったので、久しぶりに心の底から「いいなぁ、コレ」と思いました。
タクティコウなAKカスタムが欲しいと思っていた矢先、
外観もソソるものがあるし、クオリティもかなり高い。
何より台湾製電動ガンならメカボバラさなくても使える!
我輩その日からヤフオクで使わない武器やコレクションを売り払い、
(父上の遺品を持ち帰ったものが思いの外いい値で売れたので、天国の父上に感謝!)
ヤフオクでG&G製AKが出るのを常にウォッチしておりました。
え?ケチって中古なんか買わずに新品買えよって?
ムリムリ、我輩の小遣いじゃあ一般流通価格1パットン近い電動ガンなんか夢のまた夢。
そしたらある日、G&G製AKが新品よりも1万円安ぐらいで出品されていたので、
「誰も入札しませんよーに!」と願いながら30分前に入札ぶっこんだら0.7パットンですんなり落札。
でもその2週間後、同じ仕様のブツが0.6パットンで落札されてて少し涙目。

G&G製AKは「AK」という名称では販売されておらず、
「RK」という独特の名称をつけて販売しております。
なのでコイツの名称は「G&G RK74E」です。
G&G製RK74は3種のバリエーションが有り、
1つはフルサイズAK74と同サイズのRK74T、
今回レビューを上げるAK104orAK105のような銃身サイズのRK74E
そしてAKS74UぐらいのサイズのRK74 CQBがあります。
(厳密に言うとRK74 CQBはβスペツナズと同サイズ)
我輩がこいつを選んだ理由はコレしかヤフオクに流れていなかったわけでなく、
フルサイズはマルイの次世代があるし、CQBは短すぎて好みでなかったから。
RK74Tはフルサイズで長いですが、ストックが折りたたみ式になっているのが特徴。
RK74 CQBは極限まで短くしたサバゲー特化型のサイズが特徴です。
となるとコイツが一番中途半端なポジション?
いやいや、コレこそが理想のサイズなんですよ(我輩的には)。

G&G製RK74Eの最大の特徴は「AKメカニズムのオリジナル電動ガン」であること。
LCTやE&LにあるAK74またはAK105を母体にハンドガードやストックを
タクティコゥなものに交換したAKのカスタムモデルではなく、
AKを母体としながらAKらしさを拭い去ってしまった銃というべきでしょう。
我輩はそのAKらしくないのにAKであることをひっそりと主張している
その慎ましい佇まいが気に入ってコイツに物欲を突き動かされたのです。
全長は810mm(ストックを縮めた状態)なので、
M4A1の803mm(ストックを縮めた状態)と大差ありません。
重量は3kg弱なので、コレもマルイ次世代M4A1と同じぐらいです。
外観の最大の特徴はKEYMODというレールシステムを組み込んでいる事。
従来のレールシステムと違い、MLOK同様個人の必要に応じたポジションに、
レールを付けてアイテムを搭載したり、専用のアイテムを装着できるのが特徴です。
KEYMODハンドガードの利点はレールが付いていない分、軽く仕上がる事でしょう。

ハイダーはAK105独特のラッパ付きのアレではなく、
NOVESKE KFH風の太いハイダーが付いております。
ハイダーは下からイモネジで固定されており、
14mm逆ネジで取り付けられているので交換することも可能です。
ええ、勿論交換しますよAKのハイダーにね!

ち★こみたいな穴が特徴的なKEYMODハンドガード。
コレが素晴らしいぐらいにスマートで実に握りやすいのです。
でもハンドガード下部のフレーム寄りにレールが付いているんで、
ココに短いフォアグリップを取り付けます。
なお、写真では見えにくいのですが、
下部ハンドガード内にはダミークリーニングロッドも付いているのですが
これが下部ハンドガードにアクセサリーを付ける際、物凄く邪魔なので撤去。
ハイダーを外し、そのまま強引に持ち上げて引っ張れば外せます。

フロントサイトはAK105っぽいのが付いておりますが、
ガスチューブ部分はオリジナル設計になっており、妙なダイヤルが付いています。
このダイヤル部分を緩めると上部ハンドガードが外れます。
リアサイトブロックにあるリリーズレバーだけ動かしても開きません。

マルイ次世代AKのようにバッテリーは上部ハンドガード内に収めます。
入るサイズはM4のストックに入るぐらいのやつ。
長さ10cm、厚み1.5cmぐらいのものを上部に収めるか、
セパレートタイプのバッテリーを下部に収めることが出来ます。
下部ハンドガードの内側には妙な樹脂製スペーサー(写真下)が入っておりますが、
コレの有無が性能に差をつけるわけでもないので外してしまって結構です。

AKのリアサイトといえばタンジェントサイトですが、
AKであることを払拭したいのか、それとも光学照準器をつけるのが前提なのか、
レシーバーカバーと一体化した簡易リアサイトが付属しております。
使えない事はないですが、使い易くはないですね。

フレームだけはどうにも出来なかったのか、AKそのままですが、
チャージングハンドルはマグプルAKっぽい形状で左右にレバーがあるものです。
レシーバーカバーはリアサイトベースにヒンジで固定、トップレール付き。
マガジンキャッチはガリルみたいな形状で人差し指を伸ばして操作可能、
トリガーガードはワイドタイプで暑い手袋しても使いやすい、
グリップが妙に角ばっているけどそこそこ握りやすい形状と全てオリジナルです。
セレクターはタクティコゥAKお約束のチャージングハンドル引っかける
&人差し指で操作する部分が追加されたものですが、
オリジナルと比べると幅広でコレジャナイ感があります。

レシーバーカバーを開けると内側には細長いリポバッテリーを収めるぐらいの
スペースがあるので配線を引き直してコチラ側にバッテリーを入れる改修もありでしょう。
本来我輩はそうするつもりだったんですが、
太めの光学照準器を乗せるとレシーバーカバーが意外と重くなってしまい
開け閉めした時に下手すると破損の恐れがあると思ったので止めました。

ストックはマグプルのCTRストックを模したものが付いております。
ストックの長さは6段階調整可能です。
内側を握ってレバーをリリースしてスライド、外側を握って固定するこのストックは、
オーソドックスな形状で使いやすく構えやすく、
我輩は結構気にいったのでそのまま使用します。

ところでさぁ、このストック後ろ上部の穴ぽこは、
QDスイベル付ける穴ってのはわかったんだけどさぁ、
下部のボタンを押したらストックの中がにゅーんってなるのは誰得なのかね?
とりあえずCR123電池が入りそうだったんで突っ込んでみましたが、
M1ガーランドのストック内部にメントスを入れたまま8年以上放置した我輩、
ココになにか入れていると間違いなく忘却の彼方になってしまいそうです。

スリングスイベルは何も考えずに取ってつけたような形状。
フックタイプのスリングならどれでも使えるんで、
最近流行りのタクティコウなスリングをつけるなら特に不具合はないでしょうが
我輩的にはもう少しワイドなスリングスイベルに交換したい。
でもこのリング部分、交換するには加工が必要みたいです。

フレーム左側に近代化AKお約束のサイドマウントは付いていませんが、
サイドマウントを付ける穴にねじ山はあるので、
マルイ次世代以外のAK用マウントレールは取り付けられるかもしれません。
(マルイ次世代用のサイドレールは穴の位置が違って付けられなかった)
我輩的には反対側のチャージングハンドルが邪魔なので
ぶった切ってやりたいんですが結構硬そうな素材なのでサンダーがないと無理そう。
レシーバーカバーにチャージングハンドルが動く分のスリットがあり、
そこからメカボックスがチラ見えするのは嬉しくないですね。

シースルーで星マークが入ってファンキーな外装の
付属のマガジンは115発と中途半端な装弾数。
内側から弾丸の意匠のシールを貼り付けてそれっぽくっできるというおまけ付き。
でもこのマガジン、油断するとマガジンフォロアーが折れそうですね。
なお、別売りで430連のマガジンもあるようです。

ま、手元にあるAK74用マガジンはLCT、CYMA、ICS、どれでも使用可能だったので、
AK原理主義者の我輩としてはコチラを使用していくことにします。

G&G製RK74Eって恐らく、AKは好みじゃないけど、
M4には飽きたというプレイヤーをターゲットにしているから、
各部のAKらしさを払拭したデザインになっているんですよね。
しかしAK原理主義者(穏健派)の我輩としましてはコイツをAKらしく戻してやりたい!
というわけでハイダーはスカルガンナー氏から頂いたAK105ハイダーに交換、
夜戦でライトを付けられるように下部のみレール取り付け、
左側にQDスイベル追加、G&Pのタンゴダウンタイプフォアグリップを取り付け、
フレームにはガーナ氏から頂いたLCTマグウェル取り付け、
グリップはスカルガンナー氏が余らせていたLCT AK74用のグリップに交換、
(実はこれの方がノーマルのグリップより細身で握りやすい)
光学照準器は鹿児島のマンガ倉庫で0.1パットン以下で購入したACOGレプリカ。
コレでパッと見はAK105のカスタムっぽくなったんで我輩的には満足です。
我輩みたいにAKらしく戻すとか考えないのなら
元がカスタムメイドなので自我カスタムの幅が少なさそうなのが難ですね。
ハンドガードが完全独自設計なので、
他社製のハンドガードをつけるのも難しいみたいです。

分解に関しては申し訳ありませんが今回は実施しておりません。
だって何でG&GのRK74E買ったのかって、分解したくなかったからですよ(断言)!
ところで、我輩がG&G製RK74Eを手に入れたかったもう一つの理由を
説明するのを忘れておりましたが多分大半は知っている事項でしょう。
ココ数年に販売されたG&Gの電動ガンはETUという電子トリガーと
MOSFETを搭載してキレの良いトリガープルがウリだというので、
ARES製VZ58Sで電子トリガーの良さに開眼した我輩としては見逃せなかったのです。
そしてもう一つ、G&G製RK74にはバーストモードも付属しております。
セミオートで1発射撃したらそのままトリガーを引いたまま10秒待てば
フルオートに切り替えると3点バーストでの射撃が可能になるのです。
セミオート限定のフィールドやゲームでも、3点バーストはおkという場合もあるので、
1発でも多く撃ちたい我輩的にはこの機能はすごく魅力的でしたね。
実際、ゲームで使ってみてRK74の電子トリガーがどれぐらい気持ちいいかと問われると、
期待ほどではないと言うか、意外と電子感に乏しいというのが正直な感想。
まあ電気的レスポンスのよさはまあ多少はね感じられますが、
トリガーのキレが感動的かと問われるとそれ程でもない。
多分トリガースプリングナニソレ?な軽トリガーのARES製VZ58と違い、
RK74Eはトリガーのスプリングがある程度効いているから、
トリガーを引く力が少しかかるということでそう感じたのでしょう。
ARESの電子トリガーはまきのうどん、G&Gのは宮崎のうどん、
そして一般的なAKのトリガーは讃岐うどん、例えるならそういう感じ?
これもうわかんねぇな。
コマさんは「モーターを少し回転が高いのに交換するといいかも」と言いましたが、
モーターの回転自体は比較的シャープでスムーズですし、
連射速度は秒間15発は出ているので我輩的には然程問題なしと思います。
命中精度も30mで2リットルペットボトルにバンバン当てられるし、
初速も平均85m/sぐらい出ているので必要にして充分満足の性能です。
クオリティは高いけどオリジナルデザインなのでリアルさは首を傾げるものがあるし、
お値段もリーズナブルとは言い難いから初心者向けとも言い難い、
そんなG&G製RK74を欲する層というのがイマイチ理解できない我輩ですが、
1つの電動ガンとして見た場合、コレは優れた逸品であると言い切れます。
東日本大震災発生後も躊躇なく義援金を沢山贈り、救助隊員も派遣してくれました。
今回のコロナウィルスの対応も迅速で、感染者をむやみに出すこともなく収めております。
そして何より、台湾製の電動ガンは分解しなくても使える!
我輩が一番最初に買った海外製の電動ガンは
台湾のICS製AK74Mだったんですがコレはなかなかいいブツでした。
後発の高級製品には劣るもののしっかりと作られた外観、
バレルやチャンバーパッキンを変えなくても充分な精度、
メカボックス内部はマルイと大差なく、変なグリスも使ってない!
そして一番嬉しいのはデフォルトで多弾数マガジン2本付き!
青森転勤前に後輩のエロ小僧のβスペツナズ&AKS47と交換してしまったので、
現在では手元にございませんが出物がアレばまた欲しいかもしれん。
まあその後もICS製品なら問題なかろうとM3グリースガンを仕入れましたが、
コレも外観は素晴らしい出来栄えで作りもしっかりしており
内部修正に必要なしに充分使える素晴らしい電動ガンでした。
最近の台湾製電動ガンは正規品なら大抵、日本仕様にして生産されているので、
箱出しでも文句なしに充分使える優秀なサバゲーツールです。
ところで我輩は基本、人の銃を見ながら「いいなぁ、コレ」と言いはするのですが、
心の底からいいと思った事はそうそうありません。
マジでコレ欲しいと思ったのはLCTの木製ストック付きAKぐらいでしょうかね。
でもね、ある日の夜戦の時にコマさんが台湾のG&G製AKを持ってきており、
ソレが思いの外ツボにはまるブツだったので、久しぶりに心の底から「いいなぁ、コレ」と思いました。
タクティコウなAKカスタムが欲しいと思っていた矢先、
外観もソソるものがあるし、クオリティもかなり高い。
何より台湾製電動ガンならメカボバラさなくても使える!
我輩その日からヤフオクで使わない武器やコレクションを売り払い、
(父上の遺品を持ち帰ったものが思いの外いい値で売れたので、天国の父上に感謝!)
ヤフオクでG&G製AKが出るのを常にウォッチしておりました。
え?ケチって中古なんか買わずに新品買えよって?
ムリムリ、我輩の小遣いじゃあ一般流通価格1パットン近い電動ガンなんか夢のまた夢。
そしたらある日、G&G製AKが新品よりも1万円安ぐらいで出品されていたので、
「誰も入札しませんよーに!」と願いながら30分前に入札ぶっこんだら0.7パットンですんなり落札。
でもその2週間後、同じ仕様のブツが0.6パットンで落札されてて少し涙目。

G&G製AKは「AK」という名称では販売されておらず、
「RK」という独特の名称をつけて販売しております。
なのでコイツの名称は「G&G RK74E」です。
G&G製RK74は3種のバリエーションが有り、
1つはフルサイズAK74と同サイズのRK74T、
今回レビューを上げるAK104orAK105のような銃身サイズのRK74E
そしてAKS74UぐらいのサイズのRK74 CQBがあります。
(厳密に言うとRK74 CQBはβスペツナズと同サイズ)
我輩がこいつを選んだ理由はコレしかヤフオクに流れていなかったわけでなく、
フルサイズはマルイの次世代があるし、CQBは短すぎて好みでなかったから。
RK74Tはフルサイズで長いですが、ストックが折りたたみ式になっているのが特徴。
RK74 CQBは極限まで短くしたサバゲー特化型のサイズが特徴です。
となるとコイツが一番中途半端なポジション?
いやいや、コレこそが理想のサイズなんですよ(我輩的には)。

G&G製RK74Eの最大の特徴は「AKメカニズムのオリジナル電動ガン」であること。
LCTやE&LにあるAK74またはAK105を母体にハンドガードやストックを
タクティコゥなものに交換したAKのカスタムモデルではなく、
AKを母体としながらAKらしさを拭い去ってしまった銃というべきでしょう。
我輩はそのAKらしくないのにAKであることをひっそりと主張している
その慎ましい佇まいが気に入ってコイツに物欲を突き動かされたのです。
全長は810mm(ストックを縮めた状態)なので、
M4A1の803mm(ストックを縮めた状態)と大差ありません。
重量は3kg弱なので、コレもマルイ次世代M4A1と同じぐらいです。
外観の最大の特徴はKEYMODというレールシステムを組み込んでいる事。
従来のレールシステムと違い、MLOK同様個人の必要に応じたポジションに、
レールを付けてアイテムを搭載したり、専用のアイテムを装着できるのが特徴です。
KEYMODハンドガードの利点はレールが付いていない分、軽く仕上がる事でしょう。

ハイダーはAK105独特のラッパ付きのアレではなく、
NOVESKE KFH風の太いハイダーが付いております。
ハイダーは下からイモネジで固定されており、
14mm逆ネジで取り付けられているので交換することも可能です。
ええ、勿論交換しますよAKのハイダーにね!

ち★こみたいな穴が特徴的なKEYMODハンドガード。
コレが素晴らしいぐらいにスマートで実に握りやすいのです。
でもハンドガード下部のフレーム寄りにレールが付いているんで、
ココに短いフォアグリップを取り付けます。
なお、写真では見えにくいのですが、
下部ハンドガード内にはダミークリーニングロッドも付いているのですが
これが下部ハンドガードにアクセサリーを付ける際、物凄く邪魔なので撤去。
ハイダーを外し、そのまま強引に持ち上げて引っ張れば外せます。

フロントサイトはAK105っぽいのが付いておりますが、
ガスチューブ部分はオリジナル設計になっており、妙なダイヤルが付いています。
このダイヤル部分を緩めると上部ハンドガードが外れます。
リアサイトブロックにあるリリーズレバーだけ動かしても開きません。

マルイ次世代AKのようにバッテリーは上部ハンドガード内に収めます。
入るサイズはM4のストックに入るぐらいのやつ。
長さ10cm、厚み1.5cmぐらいのものを上部に収めるか、
セパレートタイプのバッテリーを下部に収めることが出来ます。
下部ハンドガードの内側には妙な樹脂製スペーサー(写真下)が入っておりますが、
コレの有無が性能に差をつけるわけでもないので外してしまって結構です。

AKのリアサイトといえばタンジェントサイトですが、
AKであることを払拭したいのか、それとも光学照準器をつけるのが前提なのか、
レシーバーカバーと一体化した簡易リアサイトが付属しております。
使えない事はないですが、使い易くはないですね。

フレームだけはどうにも出来なかったのか、AKそのままですが、
チャージングハンドルはマグプルAKっぽい形状で左右にレバーがあるものです。
レシーバーカバーはリアサイトベースにヒンジで固定、トップレール付き。
マガジンキャッチはガリルみたいな形状で人差し指を伸ばして操作可能、
トリガーガードはワイドタイプで暑い手袋しても使いやすい、
グリップが妙に角ばっているけどそこそこ握りやすい形状と全てオリジナルです。
セレクターはタクティコゥAKお約束のチャージングハンドル引っかける
&人差し指で操作する部分が追加されたものですが、
オリジナルと比べると幅広でコレジャナイ感があります。

レシーバーカバーを開けると内側には細長いリポバッテリーを収めるぐらいの
スペースがあるので配線を引き直してコチラ側にバッテリーを入れる改修もありでしょう。
本来我輩はそうするつもりだったんですが、
太めの光学照準器を乗せるとレシーバーカバーが意外と重くなってしまい
開け閉めした時に下手すると破損の恐れがあると思ったので止めました。

ストックはマグプルのCTRストックを模したものが付いております。
ストックの長さは6段階調整可能です。
内側を握ってレバーをリリースしてスライド、外側を握って固定するこのストックは、
オーソドックスな形状で使いやすく構えやすく、
我輩は結構気にいったのでそのまま使用します。

ところでさぁ、このストック後ろ上部の穴ぽこは、
QDスイベル付ける穴ってのはわかったんだけどさぁ、
下部のボタンを押したらストックの中がにゅーんってなるのは誰得なのかね?
とりあえずCR123電池が入りそうだったんで突っ込んでみましたが、
M1ガーランドのストック内部にメントスを入れたまま8年以上放置した我輩、
ココになにか入れていると間違いなく忘却の彼方になってしまいそうです。

スリングスイベルは何も考えずに取ってつけたような形状。
フックタイプのスリングならどれでも使えるんで、
最近流行りのタクティコウなスリングをつけるなら特に不具合はないでしょうが
我輩的にはもう少しワイドなスリングスイベルに交換したい。
でもこのリング部分、交換するには加工が必要みたいです。

フレーム左側に近代化AKお約束のサイドマウントは付いていませんが、
サイドマウントを付ける穴にねじ山はあるので、
マルイ次世代以外のAK用マウントレールは取り付けられるかもしれません。
(マルイ次世代用のサイドレールは穴の位置が違って付けられなかった)
我輩的には反対側のチャージングハンドルが邪魔なので
ぶった切ってやりたいんですが結構硬そうな素材なのでサンダーがないと無理そう。
レシーバーカバーにチャージングハンドルが動く分のスリットがあり、
そこからメカボックスがチラ見えするのは嬉しくないですね。

シースルーで星マークが入ってファンキーな外装の
付属のマガジンは115発と中途半端な装弾数。
内側から弾丸の意匠のシールを貼り付けてそれっぽくっできるというおまけ付き。
でもこのマガジン、油断するとマガジンフォロアーが折れそうですね。
なお、別売りで430連のマガジンもあるようです。

ま、手元にあるAK74用マガジンはLCT、CYMA、ICS、どれでも使用可能だったので、
AK原理主義者の我輩としてはコチラを使用していくことにします。

G&G製RK74Eって恐らく、AKは好みじゃないけど、
M4には飽きたというプレイヤーをターゲットにしているから、
各部のAKらしさを払拭したデザインになっているんですよね。
しかしAK原理主義者(穏健派)の我輩としましてはコイツをAKらしく戻してやりたい!
というわけでハイダーはスカルガンナー氏から頂いたAK105ハイダーに交換、
夜戦でライトを付けられるように下部のみレール取り付け、
左側にQDスイベル追加、G&Pのタンゴダウンタイプフォアグリップを取り付け、
フレームにはガーナ氏から頂いたLCTマグウェル取り付け、
グリップはスカルガンナー氏が余らせていたLCT AK74用のグリップに交換、
(実はこれの方がノーマルのグリップより細身で握りやすい)
光学照準器は鹿児島のマンガ倉庫で0.1パットン以下で購入したACOGレプリカ。
コレでパッと見はAK105のカスタムっぽくなったんで我輩的には満足です。
我輩みたいにAKらしく戻すとか考えないのなら
元がカスタムメイドなので自我カスタムの幅が少なさそうなのが難ですね。
ハンドガードが完全独自設計なので、
他社製のハンドガードをつけるのも難しいみたいです。

分解に関しては申し訳ありませんが今回は実施しておりません。
だって何でG&GのRK74E買ったのかって、分解したくなかったからですよ(断言)!
ところで、我輩がG&G製RK74Eを手に入れたかったもう一つの理由を
説明するのを忘れておりましたが多分大半は知っている事項でしょう。
ココ数年に販売されたG&Gの電動ガンはETUという電子トリガーと
MOSFETを搭載してキレの良いトリガープルがウリだというので、
ARES製VZ58Sで電子トリガーの良さに開眼した我輩としては見逃せなかったのです。
そしてもう一つ、G&G製RK74にはバーストモードも付属しております。
セミオートで1発射撃したらそのままトリガーを引いたまま10秒待てば
フルオートに切り替えると3点バーストでの射撃が可能になるのです。
セミオート限定のフィールドやゲームでも、3点バーストはおkという場合もあるので、
1発でも多く撃ちたい我輩的にはこの機能はすごく魅力的でしたね。
実際、ゲームで使ってみてRK74の電子トリガーがどれぐらい気持ちいいかと問われると、
期待ほどではないと言うか、意外と電子感に乏しいというのが正直な感想。
まあ電気的レスポンスのよさはまあ多少はね感じられますが、
トリガーのキレが感動的かと問われるとそれ程でもない。
多分トリガースプリングナニソレ?な軽トリガーのARES製VZ58と違い、
RK74Eはトリガーのスプリングがある程度効いているから、
トリガーを引く力が少しかかるということでそう感じたのでしょう。
ARESの電子トリガーはまきのうどん、G&Gのは宮崎のうどん、
そして一般的なAKのトリガーは讃岐うどん、例えるならそういう感じ?
これもうわかんねぇな。
コマさんは「モーターを少し回転が高いのに交換するといいかも」と言いましたが、
モーターの回転自体は比較的シャープでスムーズですし、
連射速度は秒間15発は出ているので我輩的には然程問題なしと思います。
命中精度も30mで2リットルペットボトルにバンバン当てられるし、
初速も平均85m/sぐらい出ているので必要にして充分満足の性能です。
クオリティは高いけどオリジナルデザインなのでリアルさは首を傾げるものがあるし、
お値段もリーズナブルとは言い難いから初心者向けとも言い難い、
そんなG&G製RK74を欲する層というのがイマイチ理解できない我輩ですが、
1つの電動ガンとして見た場合、コレは優れた逸品であると言い切れます。
2020年03月08日
アローダイナミックMP18を分解
全世界を巻き込んだ形になった人類史上初の戦争と言われ、
近代の戦争から現代の戦争への転機となったと言われる第一次世界大戦。
一般的には史上初の総力戦(民間人をも巻き込んだという意味)であるとか、
戦車や航空機などが初めて投入された戦争という認識でありますが、
銃器マニアの我輩的には手持ちの機関銃が活躍した戦争である点が見逃せません。
過去の戦争では機関銃といえば台車に載せられたものや
三脚に載せた据え付け型のものしか無かったのでありますが、
(マキシム機関銃とかホチキス機関銃とかね)
第一次世界大戦ではルイス機関銃、ショーシャ機関銃、BAR M1918というような
歩兵が手で担いで運べる機関銃が主流化していった時代でもありました。
とは言っても未だ歩兵の主力武器はボルトアクションの小銃だったのですが、
機関銃の発展によって当時の陣地に多く作られた
塹壕という狭い溝のような場所での戦闘において、
弾が無くなったら着剣して突撃するが為に槍のような長さをもつ小銃は明らかに厳しい。
そもそも着剣突撃って発想は機関銃が無かった頃の発想ですからね。

そこで当時のドイツが「狭い所で使うなら拳銃弾でフルオート出来ればイイんじゃね?」と
塹壕で戦うことを考慮して開発したのがサブマシンガンなのです。
そしてその先駆けとなった銃がこのベルグマンMP18です。
このMP18はZB26やベレッタM1938やBAR M1918といった
クラシックな銃をラインナップに持つアローダイナミックの製品です。
当時のドイツはこのMP18を戦場に投入することによって
目論見通りに塹壕での戦いで多大な戦果を上げたそうなのですが、
MP18が戦場デビューしたのは第一次世界大戦終了1年前だったので、
結局自国の勝利に結びつくほどの効果を上げることは出来ませんでしたとさ。
ドイツって目の付け所はイイんだろうけど、実用化に至るのが遅くて残念なものがあります。
第二次世界大戦末期にデビューしたアサルトライフルの先駆け、
STG44も終戦前だったんでそれ程活躍せずに終わっちゃったし。
そこらへん、1年戦争末期にゲルググというガンダムに匹敵するMSがあったものの、
戦局を大きく変えること無く負けてしまったジオン軍に似ているところがありますね。

我輩が何故にコイツを仕入れてしまったのかといいますと、
三八式とセットになるフルオートが撃てる武器って無いかなと思ったらコレがあった。
MP18は少量が日本にも輸入されて海軍陸戦隊が使用していたそうですからね。
但し、コイツを仕入れはしたものの海軍陸戦隊の服が何処にも売っていない。
サブマシンガンとは言いますがまだ曲銃床の1m以上のライフルが主流だった時代の銃、
ストックはライフルのものを少し短くした程度、本体部分も直径40mmの筒みたいでかなりゴツい。
長さ的にはAK47とかM4と大差ありませんですし、重量も殆ど同じぐらいです。
曲銃床のライフルグリップはピストルグリップに慣れた現代人には使いにくいでしょうが、
普段からPPSh41とかBAR M1918を使っている我輩には特に支障なし。むしろ大好物。
いやしかし、こういう木製ストックの銃ってのはいいもんですなぁ。
夜戦ではレール付きの銃がライトが付けられるから便利ですが、
普通のゲームはこういう雰囲気重視の武器を愛でながら戦うのが好み。

とりあえずいつものように先端から少しずつ舐め回すように見ていきましょう。
マズルフェイスは他に類を見ない独特な形状。まるでA-10みたい。
当然ですが弾が出るのは真ん中の穴です。銃身は回転しません。
マズルの上にある小さい2つの穴はフロントサイトを固定するイモネジの入る穴です。

バレルジャケットは当時の機関銃や機関砲みたいな形状です。
多分射撃によって加熱したバレルを放熱させることを考えてこうなっているのでしょう(適当)。
フロントのスリングスイベルは大分前に付いているんですが
実銃の写真を見たらもう少し後ろなんだよなぁコレ。

バレルジャケットの次にあるのは排莢口、カタカナでエジェクションポート。
チャージングハンドルを引くと奥にホップ調整ダイヤルが出てきます。
ダイヤルが少し奥まっているので調整は少しやり辛いかな?

機関部周りは実にシンプルなのは弾が出るだけの武器だからですかね?
チャージングハンドルの出っ張りが長スギィ!(AKの1.5倍ぐらいの長さ)
そしてチャージングハンドルの溝の後ろは引っ掛けられるような形状ですが、
ココにチャージングハンドルを引っ掛けることは出来ませんのであしからず。
(実銃ではココにハンドルを引っ掛けてセーフ状態にする)
余談ですがこの手のライフルとかによく見られるストックの溝は
この溝の下に手を添えて、指をかけるボジションなんですね。
三八式や九九式、モシンナガンにはありますがKar98k、M1ガーランドには無い。

チャージングハンドルの下にあるレバーはセイフティ(前が安全、後ろが発射)で、
反対側にあるレバーがセミ・フルの切り替えです。
セイフティの操作はチャージングハンドルが邪魔で結構難しいですが、
セレクターの操作は銃を構えた左手で操作可能です。
でも実銃のMP18にはセレクターもセイフティも付いていないんだな。
(実銃のMP18はフルオートオンリー)
でも目立たないところにあるので、気にしなければ問題なし。

リアサイトはシンプルなVノッチで、AKに慣れた我輩はコレでもいいんですが、
ピープサイトに慣れた人はサイティングし難いんじゃないでしょうか?
尚、このリアサイト稼働するんですがどっちに倒しても特に変わりなし。
レシーバーの一番後ろの出っ張りは実銃では分解用のラッチらしいですが、
残念なことにアローダイナミックのMP18ではダミーとなっております。

ストックの塗り具合はまあ悪くはないんですが、
ややムラが見られるところが好きじゃないので暇を見つけて全部剥がし、
ワトコオイルで塗り直そうと目論んでおります。

バットプレートは工具なしでも開けられる親切設計。
上の部分を持ち上げて90°回転させればバッテリーが入れられます。
リポの2200mAh(ミニバッテリーサイズ)なら余裕で入るサイズです。
そしてヒューズは自動車用の平型ヒューズ。
ただ、バットプレートの支点になる部分のネジは緩みやすいので、
時々締めるか、ネジロックを塗ったほうがいいでしょう。

本来ならマガジンぶっ刺す部分の上に「MP18」って刻印があるはずなんですが、何もなし。
刻印がない銃ってユニクロのパンツみたいで色気がなくて駄目だなぁ。
MP18の最大の特徴は「横にマガジンをぶっ刺す」事でしょう。
尚、マグウェルの根元にあるデカいネジのようなブツがマガジンキャッチです。
操作性に関しましては正直な話、使い難い。
伏せ撃ちに有利な形状ではありますが、CQBでは壁にガンガン当たりそう。

マガジンは横に刺すので多弾マガジンが使えません。
なので専用マガジンは180連のバネ式マガジンです。
給弾は思ったよりスムーズで、概ね弾を撃ち切ることができます。
AGMのMP40用マガジンが使えるかなと思ったんですが、
マガジンキャッチの位置や給弾口が違うみたいで使えない模様。
何でMP18はマガジンを横にぶっ刺すのか、
一般的には「伏せ撃ちしやすいように」と思われているようですが、
実際のところは別の理由があったようです。

元々MP18は当時のドイツ軍が使用していた拳銃、
ルガーP08のスネイルマガジン(ドラムマガジンみたいなやつ)を
流用する事で弾数を稼ぐというコンセプトで作られました。
早く戦場に投入したいという焦りと既存のものを使えば早く仕上がるんじゃねって
思考がミックスした結果のもと、MP18は世に送り出されたのです。

こんなゴッツいマガジンが銃の下に刺さっていると邪魔で仕方がないので、
横にマガジンが刺さる形状になったのだと思われます。
(まあ横に刺さっていてもすっげぇ邪魔っぽい、はっきりわかんだね)
んじゃあアローダイナミック製のMP18は何で箱マガジンなんだよって思うでしょ?
実はこのMP18は戦後の改良型なんですね。
ルガーのスネイルマガジンはかさばる上に弾の装填に時間がかかるということで
持ち運びが容易で扱いやすい箱型マガジンに換えたそうなんです。

そして更にMP18の改修型でセミ・フル切り替えがトリガーガードの上についた
MP28という見た目は全く一緒なやつが大戦終了後に出てきたんですね。
写真のブツは実銃のMP28です。なんか少し違うでしょ?
んじゃあアローダイナミック製MP18は本当はMP28なんじゃねぇのかと
思いっきりツッコんでやりたいところなんですが、
MP28はチャージングハンドルの形状も変わり、
リアサイトがAKみたいなタンジェントサイトになり、
尚且ベルグマンじゃなくてハーネルという会社が作るようになったんで
ワーゲンタイプ1とカルマンギアぐらいの違いがあるんですね。
まあそんなわけでMP18、全体的に見るとかなり使いにくい銃です。
M4に飽きた(そんな奴居るのか?)とかゲームに出ていたから(コレが出るゲームってあるのか?)
みたいな軽い気持ちで買ったら確実に嫌になる電動ガンに位置するでしょう。
でも世界初のサブマシンガンなんだから、まあ多少はね。
まあそんな我輩も軽い気持ちで仕入れたアローダイナミック製MP18ですが、
中国製の電動ガンなので箱出しで使うのはどうも躊躇われるのです。
我輩が中華電動ガンを買うようになって10年ぐらい経ち、
中国製品も国産に近い品質を持つものも大分増えてはきましたが、
やっぱり中身を開けてみるとグリスが青かったり、シムがボロかったり、
スプリングがなんじゃこりゃだったりとトンデモ仕様なわけなんですよ。

というわけでアローダイナミック製ベルグマンMP18も例に漏れず、
一通り舐め回すように眺めて写真を撮った後は1発も撃たずに分解します。
しかし何ですな、スマートフォンの普及によって、
今までパソコンを持っていなかった層でも情報を気軽に発信できるはずなのに、
何故かネット界隈は昔より有益な情報が少なくなっている気がするのは我輩だけ?
アローダイナミック製MP18の分解方法も何処にも載っていなかったので、
手探りで銃を隅々まで眺め、今までの教訓を元に分解したところ、
コレがかなり電動ガンの中ではシンプルな構成になっており、
今までバラした電動ガンの中では相当ハードルが低いんじゃないかと思いました。
但し、MP18を買うという行為がかなりハードル高めな気がせんでもないですがw

まずは機関部とストックを分離しなければと考えたので、
ストックと機関部を固定している後ろのスクリューを緩めます。
このスクリューがマイナスネジで見た目にはいいんですが、
やはり中華製品、ネジのクオリティは相変わらず低く、
油断するとネジの頭が舐めて削れてしまいます。
でもねぇ、マイナスネジってホムセンに気軽に売っていないんだよなぁ。
そろそろ我輩もピーマン職人のようにモノタロウを活用せねばと考えております。

後ろのネジを緩めればココからヒンジで折れ曲がるんじゃなかろうかと思いましたが、
全くその気配がなかったのでこの部分のデカいネジも緩めてしまいます。

トリガーガードとその前方にあるデカいネジ合計3本を緩めてみましたが、
トリガーガード後ろ側のネジは緩めなくても分解には支障はなかったようです。
というわけで下部の前2本のネジを外すということにします。

その後アウターバレルとフレームを前に抜くと
チャージングハンドルとリターンスプリングとスプリングガイドが
びよ~んと勢いよく外れて少し面食らってしまいますが、
コレでインナーバレルとバレル&フレームが外れます。
結局、バレル&フレームをストックから分離するのに、
ストック下部のネジを緩める必要はなかったのですが
この後メカボックスを分離するために結局は外さなければいけません。

でもメカボックスを外す前にストック内のコネクタを引き抜きます。
コレをしないとストックのクビレ部分でヒューズが引っかかってしまいます。
ヒューズレスに改造してしまえばこの手順は必要なくなるのでしょうが、
ヒューズレスってパンツ履かないで外に出るのと同じぐらい不安。

3つ前の手順でストックとメカボックスの結合は解かれているので、
後はそのままメカボックスを持ち上げてしまえば取り出せますが、
配線が引っかからないように気をつけるのは言うまでもないでしょう。

MP18はマガジンを横から刺すようになっているので
チャンバーは当然どの電動ガンとも互換性はないでしょう。
つまりココがぶっ壊れるとア ウ ト。
チャンバーパッキンは少し固めだったので、マルイ製と交換。
でもねコレ、ホップの出っ張りが最強にしても適正ホップぐらいなんですね。
なのでホップアームに収縮チューブを被せて少しだけ嵩上げしたんですが、
それでも適正ホップにするには調整を2/3ぐらい回さないとダメみたいですね・・・
径が一回り太い押しゴムみたいなのがあれば問題は解決するのかな?
図体の割にバレルは20cmぐらいと結構短いです。
ホップ窓が少し汚かったんでコレ同じぐらいじゃねって思いながら
マルイβスペツナズのバレルを入れてみたら何ということでしょう、
インナーバレルが1cmぐらい外にはみだし刑事情熱系。
結局、バレルはそのまま使う事に。

メカボックスは多分というか確実に独自設計。
でもよく見ると、ひょっとしたらP90に使われているヴァージョン6かもしれません。
面白いというか、ナンジャコリャなところは、
VER2メカボではトリガーと連動するスイッチの部分から
長いロッドが後ろに伸びてトリガーと連動するという作り。
そのせいかアローダイナミック製MP18、トリガーストロークが恐ろしく長いです。
ピストンの下にあるのはセイフティレバー。
更に下にある謎のブロックはストック内にメカボを固定すると同時に、
アウターバレル&フレームをメカボに固定するためのブロックです。

反対側の中央、ピストンの下にあるのがセレクターで、
ココを移動させることによってカットオフスイッチを制御します。
セイフティレバーもセレクターもメカボックスを分解するのに
外す必要はないのでそっとしといてあげます。

メカボックスの分解はまず、トリガーとスイッチの連動を絶ちます。
トリガー側でロッドを固定しているネジを緩めて、ロッドを外します。

次にメカボからモーターを分離するのですが、
その作業の前にモーターを上から固定しているステイを外します。
メカボックス側の太いの1本、モーター側の小さいの2本外しましょう。

先程のステイを外して、後ろからスプリングガイドを撚ると、
メインスプリングを抜き出せる設計なのは嬉しいですね。
ユーザーがバラすことを前提に考えて設計されているあたり、
中華電動ガンは結構好感度高いなって思うのが我輩の感想。
21世紀以降、日本の製品が海外でウケなくなったのは、
こういうアマチュアリズムに乏しいが故だと我輩は思うのです。

後は配線をモーターから外し、配線を固定している2箇所のステイを外し、
モーターホルダーを左右からネジを緩めて外せばモーターが分離できます。
モーターは無記名の相変わらず磁力が強いやつで
ショートタイプのモーターと互換があるようです。
組み上げ後連射速度を測ってみたところ、秒間10発ぐらいしか出ないんで、
もう少し回転速度のあるモーターに交換したいところです。

メカボックス上部はヴァージョン3メカボのように
ステイで固定されているのでスライドさせて外し、
ピンポンチが刺さっている部分のピンを抜き、外側のネジを4本外します。
メカボックスのネジが普通にクロスネジなのも中華電動ガンをバラすにあたって
面倒くさがり屋の我輩がそれ程苦痛にならない理由の一つであります。

メカボックスを割って一番驚いたのが、グリスの色が青や緑じゃない!
マルイのシリコングリスが少し黄色っぽくなったようなグリスが付着しております。
そしてもう一つ「あっ、おい待てい(江戸っ子)」だったのが、シムの数が多スギィ!
各ギアに表裏合わせて5~6枚入っているじゃねぇか!
しかもそのシムの半分以上は内側の穴にバリがあるという体たらくなので、速攻交換。
しかし少ないシムで良好なセッティングを導き出すのが厳しく、
手元のシムの在庫が尽きるぐらい大量にシムを突っこむ羽目になってしまい
シム調整だけで2時間以上費やす羽目になってしまいました。

中の部品を見てみましょう。
ノズルは他の電動ガンよりも5mmほど長いので互換品がない模様。
ピストンシリンダーとピストンヘッドは接着されていて外せません。
両方とも品質に問題はないようなのでそのまま使用。
ピストンは中にベアリングが付いており、
レールは抵抗の少ないタイプ、ピストン歯は外が1つ無いタイプ。
Oリングがスカスカで気密がなかったので、マルイ純正ピストンのものと交換。
タペットプレートはVER6に似ている気がするけど、現物が手元にないので不明です。

ギアは全て最近のCYMAとかS&Tに使われているのに似ています。
そのまま使用しても特に差し支えはないみたいです。
ベベルギアが少し小さい気がするので、VER6メカボのギアと互換性がある可能性が微レ存。

問題なのはメインスプリング。これもうわかんねぇなってぐらい短い。
一番下が純正、真ん中がマルイ純正、上がSYSTEMAの1Jスプリング。
でも1Jスプリングをブチ込んでみたらどういうわけか初速がノンホップで96~98m/s出てしまいます。
コレじゃあ我輩のホームフィールドであるホークウッドでは使えないという事で、
マルイ純正に換えたところ初速が78~80m/sぐらいになってしまいました。
というわけでSHSのM90をブチ込んでみたらノンホップで80~85m/s
適正ホップで何故か85~90m/sになってしまいましたがコレでキマリという事に。

中身を調整し終わったんで組み立てようとしたところ、
チャージングハンドルのスプリングが付けにくくて閉口します。
そこでスプリングガイド部分後端をフレーム後端とイモネジで連結してしまいました。
フレーム上、左右にステンレスドリルで穴を開けてネジ山を切り(意外と固くて削れない)、
イモネジで固定したらフレームとチャージングハンドルが一体になって組み立てやすくなりました。

バレルが短いのか、精度良くないのか判りませんが20m以上だと結構着弾が散ります。
トリガーの遊びが大きく、発射速度が遅いせいかセミオートのキレがあまり良くありませんが、
そこんところはEG30000あたりを突っ込んで回転を上げるぐらいしか手がつけられません。
ギアは社外品が使えそうなので、単純にハイサイクルにするか?
何にしてもセミオート重視のセッティングは難しいみたいです。
ま、元々弾をばらまくために作られたサブマシンガンなんだから、
サイクルを上げるほうがそれらしいかなとは思います。
ところで、我輩的にはこのクラシックなサブマシンガンを、
どのような出で立ちで使うべきかが一番の課題なのですが、
第一次世界大戦のドイツ軍装備なんて何処で買えばいいのか解らないし、
最近のサバイバルゲームの服装は大半のプレイヤーが自由な感じで、
それに影響されてか我輩も軍装に対する拘りがなくなりつつあるので、
まあ普通にというか、適当に使いたいように使うかなと思っています。
最近、古い銃、それもかなり古い銃じゃないと興奮しないこの性癖は、
骨董品が好きだった父上の血を引き継いでいるんじゃないかと思う事がしばしばです。
だからといって最近の鉄砲が嫌いってわけでもないんですよね。
同じ値段ならどっちを買うかと言われると古い鉄砲買うよって事です。
そんなわけでタクティコゥな戦闘にはいささか不向きである
アローダイナミックのベルグマンMP18ではありますが、
誰もが持ってこないような電動ガンを所有しているという
謎な悦びには満ち溢れておりますが故、勢いで手を出しても悪くはないかも?
近代の戦争から現代の戦争への転機となったと言われる第一次世界大戦。
一般的には史上初の総力戦(民間人をも巻き込んだという意味)であるとか、
戦車や航空機などが初めて投入された戦争という認識でありますが、
銃器マニアの我輩的には手持ちの機関銃が活躍した戦争である点が見逃せません。
過去の戦争では機関銃といえば台車に載せられたものや
三脚に載せた据え付け型のものしか無かったのでありますが、
(マキシム機関銃とかホチキス機関銃とかね)
第一次世界大戦ではルイス機関銃、ショーシャ機関銃、BAR M1918というような
歩兵が手で担いで運べる機関銃が主流化していった時代でもありました。
とは言っても未だ歩兵の主力武器はボルトアクションの小銃だったのですが、
機関銃の発展によって当時の陣地に多く作られた
塹壕という狭い溝のような場所での戦闘において、
弾が無くなったら着剣して突撃するが為に槍のような長さをもつ小銃は明らかに厳しい。
そもそも着剣突撃って発想は機関銃が無かった頃の発想ですからね。

そこで当時のドイツが「狭い所で使うなら拳銃弾でフルオート出来ればイイんじゃね?」と
塹壕で戦うことを考慮して開発したのがサブマシンガンなのです。
そしてその先駆けとなった銃がこのベルグマンMP18です。
このMP18はZB26やベレッタM1938やBAR M1918といった
クラシックな銃をラインナップに持つアローダイナミックの製品です。
当時のドイツはこのMP18を戦場に投入することによって
目論見通りに塹壕での戦いで多大な戦果を上げたそうなのですが、
MP18が戦場デビューしたのは第一次世界大戦終了1年前だったので、
結局自国の勝利に結びつくほどの効果を上げることは出来ませんでしたとさ。
ドイツって目の付け所はイイんだろうけど、実用化に至るのが遅くて残念なものがあります。
第二次世界大戦末期にデビューしたアサルトライフルの先駆け、
STG44も終戦前だったんでそれ程活躍せずに終わっちゃったし。
そこらへん、1年戦争末期にゲルググというガンダムに匹敵するMSがあったものの、
戦局を大きく変えること無く負けてしまったジオン軍に似ているところがありますね。

我輩が何故にコイツを仕入れてしまったのかといいますと、
三八式とセットになるフルオートが撃てる武器って無いかなと思ったらコレがあった。
MP18は少量が日本にも輸入されて海軍陸戦隊が使用していたそうですからね。
但し、コイツを仕入れはしたものの海軍陸戦隊の服が何処にも売っていない。
サブマシンガンとは言いますがまだ曲銃床の1m以上のライフルが主流だった時代の銃、
ストックはライフルのものを少し短くした程度、本体部分も直径40mmの筒みたいでかなりゴツい。
長さ的にはAK47とかM4と大差ありませんですし、重量も殆ど同じぐらいです。
曲銃床のライフルグリップはピストルグリップに慣れた現代人には使いにくいでしょうが、
普段からPPSh41とかBAR M1918を使っている我輩には特に支障なし。むしろ大好物。
いやしかし、こういう木製ストックの銃ってのはいいもんですなぁ。
夜戦ではレール付きの銃がライトが付けられるから便利ですが、
普通のゲームはこういう雰囲気重視の武器を愛でながら戦うのが好み。

とりあえずいつものように先端から少しずつ舐め回すように見ていきましょう。
マズルフェイスは他に類を見ない独特な形状。まるでA-10みたい。
当然ですが弾が出るのは真ん中の穴です。銃身は回転しません。
マズルの上にある小さい2つの穴はフロントサイトを固定するイモネジの入る穴です。

バレルジャケットは当時の機関銃や機関砲みたいな形状です。
多分射撃によって加熱したバレルを放熱させることを考えてこうなっているのでしょう(適当)。
フロントのスリングスイベルは大分前に付いているんですが
実銃の写真を見たらもう少し後ろなんだよなぁコレ。

バレルジャケットの次にあるのは排莢口、カタカナでエジェクションポート。
チャージングハンドルを引くと奥にホップ調整ダイヤルが出てきます。
ダイヤルが少し奥まっているので調整は少しやり辛いかな?

機関部周りは実にシンプルなのは弾が出るだけの武器だからですかね?
チャージングハンドルの出っ張りが長スギィ!(AKの1.5倍ぐらいの長さ)
そしてチャージングハンドルの溝の後ろは引っ掛けられるような形状ですが、
ココにチャージングハンドルを引っ掛けることは出来ませんのであしからず。
(実銃ではココにハンドルを引っ掛けてセーフ状態にする)
余談ですがこの手のライフルとかによく見られるストックの溝は
この溝の下に手を添えて、指をかけるボジションなんですね。
三八式や九九式、モシンナガンにはありますがKar98k、M1ガーランドには無い。

チャージングハンドルの下にあるレバーはセイフティ(前が安全、後ろが発射)で、
反対側にあるレバーがセミ・フルの切り替えです。
セイフティの操作はチャージングハンドルが邪魔で結構難しいですが、
セレクターの操作は銃を構えた左手で操作可能です。
でも実銃のMP18にはセレクターもセイフティも付いていないんだな。
(実銃のMP18はフルオートオンリー)
でも目立たないところにあるので、気にしなければ問題なし。

リアサイトはシンプルなVノッチで、AKに慣れた我輩はコレでもいいんですが、
ピープサイトに慣れた人はサイティングし難いんじゃないでしょうか?
尚、このリアサイト稼働するんですがどっちに倒しても特に変わりなし。
レシーバーの一番後ろの出っ張りは実銃では分解用のラッチらしいですが、
残念なことにアローダイナミックのMP18ではダミーとなっております。

ストックの塗り具合はまあ悪くはないんですが、
ややムラが見られるところが好きじゃないので暇を見つけて全部剥がし、
ワトコオイルで塗り直そうと目論んでおります。

バットプレートは工具なしでも開けられる親切設計。
上の部分を持ち上げて90°回転させればバッテリーが入れられます。
リポの2200mAh(ミニバッテリーサイズ)なら余裕で入るサイズです。
そしてヒューズは自動車用の平型ヒューズ。
ただ、バットプレートの支点になる部分のネジは緩みやすいので、
時々締めるか、ネジロックを塗ったほうがいいでしょう。

本来ならマガジンぶっ刺す部分の上に「MP18」って刻印があるはずなんですが、何もなし。
刻印がない銃ってユニクロのパンツみたいで色気がなくて駄目だなぁ。
MP18の最大の特徴は「横にマガジンをぶっ刺す」事でしょう。
尚、マグウェルの根元にあるデカいネジのようなブツがマガジンキャッチです。
操作性に関しましては正直な話、使い難い。
伏せ撃ちに有利な形状ではありますが、CQBでは壁にガンガン当たりそう。

マガジンは横に刺すので多弾マガジンが使えません。
なので専用マガジンは180連のバネ式マガジンです。
給弾は思ったよりスムーズで、概ね弾を撃ち切ることができます。
AGMのMP40用マガジンが使えるかなと思ったんですが、
マガジンキャッチの位置や給弾口が違うみたいで使えない模様。
何でMP18はマガジンを横にぶっ刺すのか、
一般的には「伏せ撃ちしやすいように」と思われているようですが、
実際のところは別の理由があったようです。

元々MP18は当時のドイツ軍が使用していた拳銃、
ルガーP08のスネイルマガジン(ドラムマガジンみたいなやつ)を
流用する事で弾数を稼ぐというコンセプトで作られました。
早く戦場に投入したいという焦りと既存のものを使えば早く仕上がるんじゃねって
思考がミックスした結果のもと、MP18は世に送り出されたのです。

こんなゴッツいマガジンが銃の下に刺さっていると邪魔で仕方がないので、
横にマガジンが刺さる形状になったのだと思われます。
(まあ横に刺さっていてもすっげぇ邪魔っぽい、はっきりわかんだね)
んじゃあアローダイナミック製のMP18は何で箱マガジンなんだよって思うでしょ?
実はこのMP18は戦後の改良型なんですね。
ルガーのスネイルマガジンはかさばる上に弾の装填に時間がかかるということで
持ち運びが容易で扱いやすい箱型マガジンに換えたそうなんです。

そして更にMP18の改修型でセミ・フル切り替えがトリガーガードの上についた
MP28という見た目は全く一緒なやつが大戦終了後に出てきたんですね。
写真のブツは実銃のMP28です。なんか少し違うでしょ?
んじゃあアローダイナミック製MP18は本当はMP28なんじゃねぇのかと
思いっきりツッコんでやりたいところなんですが、
MP28はチャージングハンドルの形状も変わり、
リアサイトがAKみたいなタンジェントサイトになり、
尚且ベルグマンじゃなくてハーネルという会社が作るようになったんで
ワーゲンタイプ1とカルマンギアぐらいの違いがあるんですね。
まあそんなわけでMP18、全体的に見るとかなり使いにくい銃です。
M4に飽きた(そんな奴居るのか?)とかゲームに出ていたから(コレが出るゲームってあるのか?)
みたいな軽い気持ちで買ったら確実に嫌になる電動ガンに位置するでしょう。
でも世界初のサブマシンガンなんだから、まあ多少はね。
まあそんな我輩も軽い気持ちで仕入れたアローダイナミック製MP18ですが、
中国製の電動ガンなので箱出しで使うのはどうも躊躇われるのです。
我輩が中華電動ガンを買うようになって10年ぐらい経ち、
中国製品も国産に近い品質を持つものも大分増えてはきましたが、
やっぱり中身を開けてみるとグリスが青かったり、シムがボロかったり、
スプリングがなんじゃこりゃだったりとトンデモ仕様なわけなんですよ。

というわけでアローダイナミック製ベルグマンMP18も例に漏れず、
一通り舐め回すように眺めて写真を撮った後は1発も撃たずに分解します。
しかし何ですな、スマートフォンの普及によって、
今までパソコンを持っていなかった層でも情報を気軽に発信できるはずなのに、
何故かネット界隈は昔より有益な情報が少なくなっている気がするのは我輩だけ?
アローダイナミック製MP18の分解方法も何処にも載っていなかったので、
手探りで銃を隅々まで眺め、今までの教訓を元に分解したところ、
コレがかなり電動ガンの中ではシンプルな構成になっており、
今までバラした電動ガンの中では相当ハードルが低いんじゃないかと思いました。
但し、MP18を買うという行為がかなりハードル高めな気がせんでもないですがw

まずは機関部とストックを分離しなければと考えたので、
ストックと機関部を固定している後ろのスクリューを緩めます。
このスクリューがマイナスネジで見た目にはいいんですが、
やはり中華製品、ネジのクオリティは相変わらず低く、
油断するとネジの頭が舐めて削れてしまいます。
でもねぇ、マイナスネジってホムセンに気軽に売っていないんだよなぁ。
そろそろ我輩もピーマン職人のようにモノタロウを活用せねばと考えております。

後ろのネジを緩めればココからヒンジで折れ曲がるんじゃなかろうかと思いましたが、
全くその気配がなかったのでこの部分のデカいネジも緩めてしまいます。

トリガーガードとその前方にあるデカいネジ合計3本を緩めてみましたが、
トリガーガード後ろ側のネジは緩めなくても分解には支障はなかったようです。
というわけで下部の前2本のネジを外すということにします。

その後アウターバレルとフレームを前に抜くと
チャージングハンドルとリターンスプリングとスプリングガイドが
びよ~んと勢いよく外れて少し面食らってしまいますが、
コレでインナーバレルとバレル&フレームが外れます。
結局、バレル&フレームをストックから分離するのに、
ストック下部のネジを緩める必要はなかったのですが
この後メカボックスを分離するために結局は外さなければいけません。

でもメカボックスを外す前にストック内のコネクタを引き抜きます。
コレをしないとストックのクビレ部分でヒューズが引っかかってしまいます。
ヒューズレスに改造してしまえばこの手順は必要なくなるのでしょうが、
ヒューズレスってパンツ履かないで外に出るのと同じぐらい不安。

3つ前の手順でストックとメカボックスの結合は解かれているので、
後はそのままメカボックスを持ち上げてしまえば取り出せますが、
配線が引っかからないように気をつけるのは言うまでもないでしょう。

MP18はマガジンを横から刺すようになっているので
チャンバーは当然どの電動ガンとも互換性はないでしょう。
つまりココがぶっ壊れるとア ウ ト。
チャンバーパッキンは少し固めだったので、マルイ製と交換。
でもねコレ、ホップの出っ張りが最強にしても適正ホップぐらいなんですね。
なのでホップアームに収縮チューブを被せて少しだけ嵩上げしたんですが、
それでも適正ホップにするには調整を2/3ぐらい回さないとダメみたいですね・・・
径が一回り太い押しゴムみたいなのがあれば問題は解決するのかな?
図体の割にバレルは20cmぐらいと結構短いです。
ホップ窓が少し汚かったんでコレ同じぐらいじゃねって思いながら
マルイβスペツナズのバレルを入れてみたら何ということでしょう、
インナーバレルが1cmぐらい外にはみだし刑事情熱系。
結局、バレルはそのまま使う事に。

メカボックスは多分というか確実に独自設計。
でもよく見ると、ひょっとしたらP90に使われているヴァージョン6かもしれません。
面白いというか、ナンジャコリャなところは、
VER2メカボではトリガーと連動するスイッチの部分から
長いロッドが後ろに伸びてトリガーと連動するという作り。
そのせいかアローダイナミック製MP18、トリガーストロークが恐ろしく長いです。
ピストンの下にあるのはセイフティレバー。
更に下にある謎のブロックはストック内にメカボを固定すると同時に、
アウターバレル&フレームをメカボに固定するためのブロックです。

反対側の中央、ピストンの下にあるのがセレクターで、
ココを移動させることによってカットオフスイッチを制御します。
セイフティレバーもセレクターもメカボックスを分解するのに
外す必要はないのでそっとしといてあげます。

メカボックスの分解はまず、トリガーとスイッチの連動を絶ちます。
トリガー側でロッドを固定しているネジを緩めて、ロッドを外します。

次にメカボからモーターを分離するのですが、
その作業の前にモーターを上から固定しているステイを外します。
メカボックス側の太いの1本、モーター側の小さいの2本外しましょう。

先程のステイを外して、後ろからスプリングガイドを撚ると、
メインスプリングを抜き出せる設計なのは嬉しいですね。
ユーザーがバラすことを前提に考えて設計されているあたり、
中華電動ガンは結構好感度高いなって思うのが我輩の感想。
21世紀以降、日本の製品が海外でウケなくなったのは、
こういうアマチュアリズムに乏しいが故だと我輩は思うのです。

後は配線をモーターから外し、配線を固定している2箇所のステイを外し、
モーターホルダーを左右からネジを緩めて外せばモーターが分離できます。
モーターは無記名の相変わらず磁力が強いやつで
ショートタイプのモーターと互換があるようです。
組み上げ後連射速度を測ってみたところ、秒間10発ぐらいしか出ないんで、
もう少し回転速度のあるモーターに交換したいところです。

メカボックス上部はヴァージョン3メカボのように
ステイで固定されているのでスライドさせて外し、
ピンポンチが刺さっている部分のピンを抜き、外側のネジを4本外します。
メカボックスのネジが普通にクロスネジなのも中華電動ガンをバラすにあたって
面倒くさがり屋の我輩がそれ程苦痛にならない理由の一つであります。

メカボックスを割って一番驚いたのが、グリスの色が青や緑じゃない!
マルイのシリコングリスが少し黄色っぽくなったようなグリスが付着しております。
そしてもう一つ「あっ、おい待てい(江戸っ子)」だったのが、シムの数が多スギィ!
各ギアに表裏合わせて5~6枚入っているじゃねぇか!
しかもそのシムの半分以上は内側の穴にバリがあるという体たらくなので、速攻交換。
しかし少ないシムで良好なセッティングを導き出すのが厳しく、
手元のシムの在庫が尽きるぐらい大量にシムを突っこむ羽目になってしまい
シム調整だけで2時間以上費やす羽目になってしまいました。

中の部品を見てみましょう。
ノズルは他の電動ガンよりも5mmほど長いので互換品がない模様。
ピストンシリンダーとピストンヘッドは接着されていて外せません。
両方とも品質に問題はないようなのでそのまま使用。
ピストンは中にベアリングが付いており、
レールは抵抗の少ないタイプ、ピストン歯は外が1つ無いタイプ。
Oリングがスカスカで気密がなかったので、マルイ純正ピストンのものと交換。
タペットプレートはVER6に似ている気がするけど、現物が手元にないので不明です。

ギアは全て最近のCYMAとかS&Tに使われているのに似ています。
そのまま使用しても特に差し支えはないみたいです。
ベベルギアが少し小さい気がするので、VER6メカボのギアと互換性がある可能性が微レ存。

問題なのはメインスプリング。これもうわかんねぇなってぐらい短い。
一番下が純正、真ん中がマルイ純正、上がSYSTEMAの1Jスプリング。
でも1Jスプリングをブチ込んでみたらどういうわけか初速がノンホップで96~98m/s出てしまいます。
コレじゃあ我輩のホームフィールドであるホークウッドでは使えないという事で、
マルイ純正に換えたところ初速が78~80m/sぐらいになってしまいました。
というわけでSHSのM90をブチ込んでみたらノンホップで80~85m/s
適正ホップで何故か85~90m/sになってしまいましたがコレでキマリという事に。

中身を調整し終わったんで組み立てようとしたところ、
チャージングハンドルのスプリングが付けにくくて閉口します。
そこでスプリングガイド部分後端をフレーム後端とイモネジで連結してしまいました。
フレーム上、左右にステンレスドリルで穴を開けてネジ山を切り(意外と固くて削れない)、
イモネジで固定したらフレームとチャージングハンドルが一体になって組み立てやすくなりました。

バレルが短いのか、精度良くないのか判りませんが20m以上だと結構着弾が散ります。
トリガーの遊びが大きく、発射速度が遅いせいかセミオートのキレがあまり良くありませんが、
そこんところはEG30000あたりを突っ込んで回転を上げるぐらいしか手がつけられません。
ギアは社外品が使えそうなので、単純にハイサイクルにするか?
何にしてもセミオート重視のセッティングは難しいみたいです。
ま、元々弾をばらまくために作られたサブマシンガンなんだから、
サイクルを上げるほうがそれらしいかなとは思います。
ところで、我輩的にはこのクラシックなサブマシンガンを、
どのような出で立ちで使うべきかが一番の課題なのですが、
第一次世界大戦のドイツ軍装備なんて何処で買えばいいのか解らないし、
最近のサバイバルゲームの服装は大半のプレイヤーが自由な感じで、
それに影響されてか我輩も軍装に対する拘りがなくなりつつあるので、
まあ普通にというか、適当に使いたいように使うかなと思っています。
最近、古い銃、それもかなり古い銃じゃないと興奮しないこの性癖は、
骨董品が好きだった父上の血を引き継いでいるんじゃないかと思う事がしばしばです。
だからといって最近の鉄砲が嫌いってわけでもないんですよね。
同じ値段ならどっちを買うかと言われると古い鉄砲買うよって事です。
そんなわけでタクティコゥな戦闘にはいささか不向きである
アローダイナミックのベルグマンMP18ではありますが、
誰もが持ってこないような電動ガンを所有しているという
謎な悦びには満ち溢れておりますが故、勢いで手を出しても悪くはないかも?
2019年07月10日
SVU!SVU!
ボーナス前になると「次はどんな武器を買おうか」と
エアガンショップのサイトを見ながらニヤニヤするのが
我輩の毎年のルーティンとなっております。
我輩が武器を選定するにあたり、念頭に置いているのは以下の事項。
◎手持ちの予備マガジン、バッテリー、ポーチ等が使用可能であること
◎折鶴が折れない我輩の不器用さでも分解結合がどーにかなりそうであること
◎外装が頑丈であること
◎他のプレイヤーが買わなさそうなブツ
◎我輩の予算で買えること(ここ重要!)
上記事項を踏まえるとマガジン独自規格のPPSH41とかBARとかM3グリースガンを買うのは
可笑しいじゃねぇかのってツッコミはごもっともなので黙殺しますが、
全ての条件を満たした武器が最近日本上陸したんでソレを買いました。

中華のCYMA製SVU M-LOKです。
解る人ならフレーム見れば速攻で解るんでしょうが
SVUとはロシアのSVD(所謂ドラグノフって呼ばれているアレ)を
ブルパップ(銃床部に機関部を設けて短縮化したライフル)にしたものです。
ブツは中華電動ガンの品揃えに定評のあるフォースターで0.7パットンで購入。
(その後レールを探すためにフォースターのサイトを覗いてみたら
プラチナセールとやらで0.6パットンになっているのを見て我輩号泣)
青森に居た頃、砂井さんがAPSというメーカーのSVUを持っていたのを見て、
「あ、コレがあればSVDとマガジンorバッテリー使い回せるな」と思い、
コレは仕入れねば(使命感)!と前々から目論んでいたブツだったのです。
APS製のSVUはずっと品切れ状態で入手困難でしたが、
良いタイミングでCYMAが出してくれたんで我輩的には渡りに船でした。
手元にある我輩のブツを穴が開くほど見つめながら、
砂井さんのブログに掲載されたAPS製SVUと見比べてみたところ、
販売元がCYMAになっただけで、ブツそのものは同じである可能性が大。
ま、APS製SVUの情報はまあ多少はねネットに流れているようですが、
CYMA製SVU、しかもM-LOKのレビューあげてる人は、
まだ居ないみたいなんでまあ多少はね参考になるでしょう。
いやしかし、FA-MASとかAUGというよーな元からブルパップとして作られたライフルって、
普通のライフル以上に銃全体の構成に創意工夫があるのが面白いのですが、
SVUはSVDをそのまま何も考えずにブルパップにしたやっつけ感が凄い。
「いやマジコレ、ドラグノフなんですけどそれは大丈夫なんですかね・・・」

CYMA製SVUはオリジナルに準じたハンドガードに
トリガーガード付近から不自然ににょーんと伸びた
ステイに付けられたバイポッドがあるノーマルモデルと、
我輩が今回購入したM-LOKハンドガードのものがあります。
余談ですがコイツに付けられそうなレールが手元に無かったので、
(数年前に我輩はレール不要論を唱えてレール類は殆ど手放した)
吉六会のLINEにて「親愛なる同志一同よ、MLOK対応のレールが余っておらぬか?」
と問うたところ一部の同志は「あの閣下がMLOKとは、どういうご乱心か?」とか
「まさか・・・閣下がM4に手を出すという暴挙に出たのか・・・」と思ったそうな。
んで、SVUの写真を送ったところ「平常運行」と一同一安心した模様w
いやね、元々SVU仕入れたらあのヘンテコリンなバイポッドは撤去して、
下からレール生やしてフォアグリップ付けようと妄想していたので、
(その上、ヘンテコリンなフロント&リアサイトとサプレッサーも撤去予定だった)
んじゃあ無改造であんなもの飾りですな足がなくて、
レール付ける事が出来るMLOKがいいじゃんってなったんですわ。
ロシアのライフルにアメリカンなレールシステムはどうかと思わなくもなかったんですが、
元々スリムなSVUにスリムなM-LOKハンドガードは意外とお似合いです。
好みに合わせて好きなところにレールを増設可能なのがM-LOKの利点みたいですが、
レール無しのほうがスッキリしていて見栄えがいいかなと?

元々全長120cm位あるSVDがブルパップ化してどれぐらい短くなったのかといいますと、
AK74と同じぐらいの長さになっているんで扱いやすさは大分向上しているはずです(適当)。
苦労して作ったA&K製SVDショートバージョンよりも更に短い。
その上、SVUにはフルオートも付いているんでSVD以上の活躍が期待できます。
ていうかセミオンリーのSVDは今後使用しない可能性も微レ存?

しかし、砂井さんがブログで「発射速度が遅い!」と記載していたとおり、
箱出し状態では実銃のM3グリースガンと同じぐらいの発射速度。
写真はメカボックス調整後、再度モーターを元のやつに戻し、
7.4V 1200mAhリポバッテリー繋いで射撃した時の結果ですが、
やはりそのままでは夏バテ寸前のスカルガンナー氏にも避けられそうな勢いです。

9.9V 900mAhのリフェバッテリーを繋いでもこの体たらく。
高橋名人の16連射まではいかなくても、
せめてマルイのノーマル電動ガンぐらいの発射速度は欲しい。
実銃のSVUではフルオートは緊急時以外使用禁止らしいですが、
我輩はサバゲーでフルオート思いっきりぶっ放したいんでそんなスロー発射は嫌。
ところで、SVUの実弾は7.62mm×54Rだから7.62mm×51のG3とかM14よりも、
まあ多少はね反動が強い程度じゃないのかなって勝手な推測。

実銃ではその反動を押さえるのがこのサプレッサー兼ハイダー的なブツ。
コイツのお陰で反動がかなり軽減され、SVU実用化に至ったそうです。
サプレッサーの中にはスポンジが詰め込まれておりますが、
サプレッサーの先端付近までインナーバレルが伸びているので
発射音が軽減されている気配は全くございません。
サプレッサー自体は14mmの逆ネジで取り付けられているので、
外して別のハイダーを取り付けることも可能です。
そして奥に見える折りたたみのフロントサイト。
デザイン的にもう少しどうにかならんかったんかと思いはしますが、
このやっつけ感がロシアっぽいといえばロシアっぽい。

MLOKハンドガードは20mm幅のトップレール付属。
レールはアルミ製で軽く、塗装も綺麗、ガタツキも無し。
最近の中華パーツはレールのコマも均等で良い出来栄えです。
リアサイトの傍にあるボタンを強く押し込むとトップカバーが外れます。

トップカバー内部にはリポの細長いバッテリーを搭載可能。
少し厚みのある短いバッテリー(M4ストップパイプ用)を
突っ込んでみたんですが隙間が狭いようで無理でした。
MLOKハンドガードがスケスケなんでバッテリーや配線が丸見えなのは興ざめですが、
このハンドガード、結構細身で握りやすくてコレならフォアグリップ要らねぇかな?

樹脂製グリップはSVDのものを切り取ったような形状。
握り難いわけじゃないですが、縦に短い気がせんでもない。
スラブ系のゴツいロシア人には物足りないんじゃないでしょうか?
トリガーの上にある丸いポッチがセイフティ。
M870みたいにトリガーをロックするタイプになっております。
(実銃は従来のポジションにセイフティがある)
銃の右側に出ている状態でセイフティ、左側でファイア。
セーフからファイヤへは人差し指で操作できるので
リアルさはともかく、オリジナルよりは使いやすいです。
問題なのは無理やり増設したようなブサイクな折りたたみリアサイト。
先っちょの小さい穴を覗いて照準を合わせるんですが、
コレがまあ使いにくい見にくいったらありゃしない。
しかも上下左右の調整なんて気が利いた機能もございません。

ブルパップの難点としてマガジン交換がやり辛いことが挙げられますが、
SVUの場合マガジンが短い、そして太いということで、
マガジンとグリップの間隙が短くなっており、更にマグチェンジの難易度が高いです。
多分コレ、同志熊頃氏はグリップとマガジンに手が挟まって抜けんぞ。
正直な話、手がデカい人はSVU買わないほうがよろしいかと。
撃とうと思えば(王者の風格)撃てん事はないでしょうがかなり扱いづらい筈です。
でも手がデカい人ってほぼ例外なく、ち★ちんがデカいんだよなぁ・・・

セレクターは実銃では上から順にセイフティ、セミオート、フルオートらしいですが、
電動ガンの場合はメカボックスの都合でセイフティ状態でセミオート、
その下もセミオート、一番下がフルオートになります。
スリングスイベルはQB、じゃなくてQDスイベルです。
(QBはキュウベェなんだけどさ、QDって何の略だ?)
他社製のQDスイベルが使えるか否かは
我輩の手元にそういう近代的なブツがないので不明。
追記:2種類程試してみたところ、使える模様。
SVDではグリップが付くところにストックが設置されております。
グリップにモーターが入るSVDのメカボックスを使いまわしている都合上、
ストックに謎の傾斜が付いていてリアルさを損ねている&構えにくいのが難点。
しかもバットプレート部分がツルツルなんで、滑るんだコレが。
後でゴム版でも貼り付けましょうかね?
マガジンはCYMA、S&T、RSのマガジンと共通です。
デフォルトでは多弾数マガジンが付属。
ところでこのCYMA(或いはS&T製)ドラグノフ用の多弾数マガジン、
ショップによって120連とか190連とか表記がまちまちでどっちが正しいんじゃ?!
な感じなので弾詰めて数えてみたところ180発ぐらいしか入らなかったので
ドラグノフの多弾数マガジンは今後180連マガジンということにします。
尚、戦闘中のリロードを楽しみたい方は別売りの80連マガジンを買うべし。
でもノーマルマガジンもRSのやつは96連って書いているし、
実際何発入るのかこれもうわかんねぇなですわ。

チークパッドはトップカバーにネジ止めされております。
当然ながら高さ調整なんてぇ気の利いたものはありません。
そしてご覧のとおり、コイツは構成的に完全に右利き用のライフルです。
イギリスのL85同様、左で構えて射撃することは全く想定されておりません。

そしてこのトリガー上部のフレーム部分の樹脂製モッコリカバーに
SVU本来のマウントレールが隠れており、ネジ4本緩めるとカバーが外れます。
我輩がMLOKのSVUを購入したもうひとつの理由がコレ。
ノーマルのSVUだとドラグノフ用のスコープを別途購入しないと
光学照準器が取り付けられないのでその分財政的負担がかかりますが、
MLOKならトップレールに一般的な光学照準器が載せられるので、普遍性が高い。
MLOKの場合は上部ハンドガードにレールが付属しているんで、
この部分が使えなくても特に不具合はないんですが、
「ロシアのライフルにはPSO-1だろ?」的な原理主義者は
ココを外せば手持ちのロシアンスコープが搭載可能です。

当然ながらデフォルトのマウントレールには各社製AK用マウントが取付可能ですが、
AK用のマウントを取り付けると光学サイトの位置が高スギィ!
ロシアのゴツいヘルメット、ALTYN装着時ならコレでもいいんでしょうが、
見た目的にも実用性的にも我輩的にもコレはいただけません。

我輩のCYMA製SVDに絶賛装着中のPSO-1レプリカを取り付けると
これが本来の姿って気がしますし、しっくり来ます。
でもSVD取り付け時と同じく、スコープは左にオフセット。
まあおそロシアの暗黒面に飲み込まれた変態プレイヤー的には
「この左オフセットがいいんじゃねぇか!」なんでしょうがね。

我輩の回答はACOGレプリカ無倍率ドットサイト装着。
ACOGはマウント位置が元から高めなので、丁度いい高さです。
尚、社外品のスコープ類を搭載する場合はハイマウントのものを選ばないと、
装着は可能でもサイティングが出来ないのでご注意。
本体価格はノーマルより5000円ぐらい割高なMLOKですが、
光学サイトを選ばないという点では安上がりとも言えます。

さて、中華電動ガン黎明期にCYMA製AIMSを購入したら、
ノズルにゴミが刺さってディチューンされていたのに戦慄を覚えた我輩、
CYMA製SVU M-LOKも何かしら不安要素は秘められているに違いないということで、
メカボックス調整のために今回も1発も撃たないまま分解しちゃいますよ。
この部分はバラさなくても影響はないんですが、
サプレッサー兼ハイダーはハナっから外すつもりだったので速攻外します。
斜め位置にセットされているイモネジを緩め、逆ネジに回して外します。
フロントサイトは下からイモネジで止められているので、コレも外します。

まずはフレーム後部にあるカバー取り外しレバーをCW方向に回し、
トップカバーを持ち上げて外します。
その後チャージングハンドル上部にあるスプリング&シャフトを
メカボックス後端から外せばチャージングハンドル一式が外れます。
その後写真の位置にセレクターをCCW方向に回すと、
セレクターが外れますがココは後からでもいいでしょう。

バットプレート部分は下部のスクリューを緩めると外せます。
まあココも後から外していいんですがね。
尚、CYMA製SVUは外装の至るところにケツの穴みたいな
トルクスタイプのネジが使われているのが嫌ですね。
何度も分解するとなるとトルクスネジは煩わしいだけです。
我輩は中華電動ガン整備用or交換用に事前にハンズマンやサンワドーで
各種クロスネジや六角ネジを購入してストックしているので、
ア★ルネジを外しては捨て、それらのネジと交換します。
余談だけど八戸のサンワドー、結構ネジとか小物パーツ充実していてたし、
キャンプ用品や業務用食材とかも充実していて結構好きだった。

CYMA製SVUのメカボックスを取り出すためには、
フロント周りやバレル周りを全部分解しないといけません。
そう言うとフレーム割ればメカボックスに到達する
M4系の電動ガンの方が分解が楽な気がせんでもないですが、
手順そのものに神経を使う部分は少ないので我輩的には意外と楽です。
まず初めにチャンバーとアウターバレルを
左右から固定しているこのネジを外してしまいます。
SVDの時はコイツの有無で精度が変わるとか2発給弾が出なくなるという話だったので
面倒とは思いながらも取り付けていましたが付けなくても影響ない模様。

アウターバレルとフレームはリアサイトの下に隠れている
2本のイモネジで固定されているのでリアサイトを起こし、
リアサイト根本のマイナスネジを外し、更に根本のブロックを外して、
写真で示した部分にアレンレンチを突っ込んで緩めます。

SVDの場合はコレだけでアウターバレルが外れるんですが、
前方にトリガーやセイフティがあるSVUはそうは行きません。
トリガーガード前方にある2本のネジを緩め、
更にフレームとバレルの連結を解きます。

するとトリガー上部の中にあるセイフティのクリックが緩むので、
セイフティボタンを抜き出して外せるようになります。
ココを外さないとMLOKのハンドガードを外す時にモロに干渉します。
その後、トリガーを固定しているピンをポンチで叩いて、
トリガーの固定を解かなければアウターバレルが抜けないから困ったもんだ。

MLOKのハンドガードは下部のネジ2本でバレルに固定されているので
コレを緩めればスルッと前方に抜き出せます。
その後アウターバレルをゆっくりと前方へ引き出せば
アウターとインナーバレルが分離するので、
ゆっくりとインナーバレルをメカボックス方向へ引っ張り出して、
チャンバーが引っかからないように外せば前回りの分解は完了。

メカボックス下部のSVDので言うところのトリガーハウジングは
セレクターとカバー取り外しレバーを回して外せば、
マガジンキャッチ上部にあるピンを軸にしてこのように持ち上がるので、
このままクルッと外してしまいましょう。

写真ではトリガーハウジングを外す前に着手しておりますが、
ハウジングを外したらマガジンキャッチがあった場所の上部に
メカボックスとフレームを固定するクロスネジがあるのでソレを外します。

ハンドガード内にあったバッテリーコネクタ&ヒューズボックス部分を
ちぎれないように丁寧に引っ張って外し、
写真で指差している部分の配線の固定を緩めて、配線をフリーにします。

かなり判りづらいでしょうが場所的に写真に撮りづらいんで仕方がないね。
ドライバーで差している部分がメカボックスとトリガーをつなぐリンケージです。
トリガーにかかっているこのバーを上に持ち上げれば外れます。
そしてメカボックスをフレームから上に持ち上げて引っ張り出すと、
多分レバーも一緒に外れてくれるでしょう(適当)。
尚、組立時はメカボックスをフレームに入れると同時に、
このリンケージバーも一緒に組まないといけません。
そしてコレが結構面倒orコツを必要とするんだな。
ブルパップはこういうところが結構手間であります。

メカボックスは同社SVDのものと変わらないようで、少し違う。
SVDでは下部に出っ張っているトリガーが無く、
代わりにフルオートポジションに移動させるためのクリックや
リンケージ用のプレートが付加されております。
赤丸部分がリンケージバーのハマるポイント。

反対側はフルオートにするためのカットオフレバーや
ソレを動かすためのギアが付属しております。
とりあえず、モーターのプラス極にマイナスのコードが繋がっていても、
「ああ、このメカボはギアが4枚だから回転が逆なんだ」と認識した上で
モーターに繋がるコードを外し、モーターハウジングごとネジ緩めて外します。


上の写真がドラグノフのメカボ、下のがSVUのメカボ。
この写真を見比べながら「ひょっとしてSVUのメカボが手に入れば、
CYMA製ドラグノフをフルオートに出来るんじゃね?」って妄想しましたが、
セイフティをどうするかとか、フレームの加工とか、課題が山積みの模様。

変な妄想をする以前に、目の前にある課題を片付けましょう。
メカボックス右側のセレクターがハマるプレートを外し、
その下にあるセレクターと連動するプレートとギアを外します。
この時、◯部分にハマっているバネとポッチを無くさないように注意!
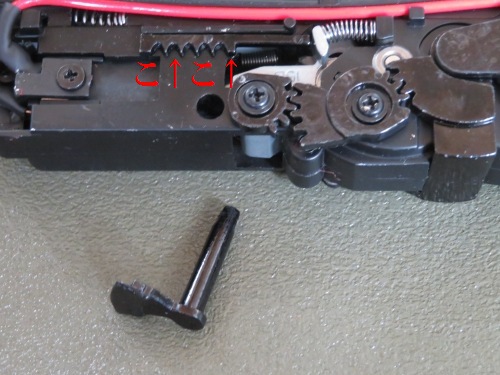
ギアとシャフトが一緒になっているパーツを外すと、
左側にあるフルオート切り替えの小さいパーツがポロッと外れるので注意。
コイツを紛失するとSVUはフルオートで撃てなくなります。

細かいパーツを確保したらギアの配置をカメラで撮影してポジションを把握。
その後外側に付いているギア類をねじを緩めて外していきます。

そしてトリガーパーツを外し、根本のバネを丁寧に外せば、
やっとメカボックスを開けることが出来るようになります。
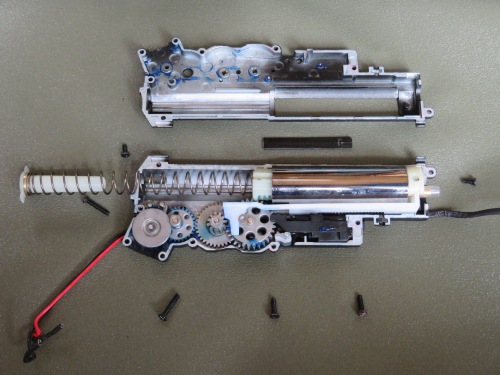
メカボックスの尻にある穴に細いドライバーを突っ込み、
逆転防止ラッチを開放したらメカボックス周囲のネジと
上部にあるプレートを外してメカボックス開放。
デチューンのためのプラの破片とか、変なゴミとかは入っていませんでしたが、
青くて粘度が高くて気持ち悪いグリスがベッタリと塗られております。
ギア類は速攻で外し、ギアもメカボ内部もブレーキパーツクリーナーで洗浄。
シムは上下ともに0.2mmのやつが1枚ずつと適当にぶっ込んでいるのみ。
とりあえず手持ちのキレイなシムと交換してデフォの状態で組んでみました。

メカボックス内パーツはCYMA製ドラグノフと同じです。
謎に短いノズル、オフセットしたシリンダーヘッド、
長いタペットプレートとシリンダーとピストン、スプリング。
一般的なパーツが流用可能なのはスプリングガイドとピストンヘッド、
そしてピストンのOリングぐらいであることを再確認し、
青いグリスを拭き取ってマルイ純正グリスでも塗りましょう。

参考までにスプリングの写真を掲載。
一番上・・・CYMA SVU純正スプリング
2段め・・・SHS M100スプリング
3段目・・・SYSTEMA M110スプリング
一番下・・・旧世代マルイ純正スプリング
同じぐらいの長さのスプリングを入れないと、確実に作動に支障をきたしますので、
ぶっ込むとしたらM100ぐらいの長いスプリングを入れることになるでしょう。

砂井さんのブログによるとハイスピードモーター換装が
発射サイクル上昇の一番手っ取り早い手段ということなので、
ヅイマー氏曰く「強いバネも引けて、サイクルもアップ、いいゾ^~これ」という
「SPARK High Torque Moter INAZUMA」をぶっ込んでみました。
後はスカスカだったピストンのOリングをマルイ純正のものと交換、
650mmのクソ長いインナーバレルは450mmのマルイAK47用と交換、
チャンバーパッキンもマルイ純正と交換して組み直します。

どうでもいい改修ですが、セイフティのポッチがONでもOFFでもどちらかに飛び出していて
パット見解りづらかったのでフレームとほぼツライチになるように3mmほど削りました。
コレによってセイフティのON/OFFが解りやすくなりました。

レールはMLOK用の80mmサイズを同志クリ◯◯ス・コスッタ氏から提案&提供。
フォアグリップだけ付けるならコレでも必要にして充分です。

握り具合に疑問の残るグリップをAKのものと交換したいなと思い、
とりあえず底蓋外してグリップ外してみたんですが、
AKのグリップ内部にパテ盛り加工しないと付けられない模様なので今後の課題に。

組み込み時の注意点は以下のとおり。
◎トリガーとトリガーリンケージの組み込み
◎配線のルーティング
◎セイフティボタン組み込み
◎モーターに配線つなぐ時は黒をプラスに、赤をマイナスに繋ぐ
これらの事項に注意すれば、すんなり組み上がるはずです。

ロシア原理主義者的には外装のカスタムなんてもっての外なんでしょうが、
特徴的なサプレッサーを外してKMのドラグノフハイダーと交換し、
フロント&リアサイトは撤去してコレも同志クリ◯◯ス・コスッタ氏から提供された
マルイM4用のフリップアップサイトをバックアップ用に取り付け、
(余談だがこのフリップアップサイト、フェイスマスク装着状態ではサイティング出来ないw)
ハンドガード下部にマルイのショートグリップ取り付けて一応の完成。
ハイダーが長いので全長はさほど変わりませんが、
全体的なシルエットがスッキリして野暮ったさが無くなったと自負。
欲を言えばもう少しコンパクトでインパクトのあるハイダーを付けたいとか、
ガスチューブの直ぐ先にハイダーを付けたいとか、課題は山盛りです。

初速は適正ホップで88~90m/sぐらいとまあ悪くない数値ですが、
それよりも特筆すべきというか、目を疑うのは発射速度。
INAZUMAモーターを搭載しているのに毎分600発程度の発射速度とは・・・
まあそれでも、ノーマルより多少マシにはなったんでなんとか戦えそう。

9.9Vリフェを使えば大抵の電動ガン並みの発射速度になるんで、
新たにスティックタイプのリフェバッテリー仕入れたい衝動に駆られております。
11.1Vのリポ使えばもっと早くなるんでしょうが、
それをすると確実にメカボ、ぶっ壊れるでしょうねぇ・・・

モーター換装でサイクルがまあ多少はね早くなったお陰か、
ドラグノフで多発していた2発給弾は起こらず、
セミオートでも安定した性能を発揮してくれるのが嬉しいです。
という事はCYMAのドラグノフも、ハイスピード系のモーターに換えれば良くなるかも?
ただ、バレルをAK並みに短くしたのが災いしたか、
命中精度は普通の電動ガンレベルなのが少し不満ですね。
まあ、コレでもサバゲーに使えないことはないのでしょうが、
もう少し突き詰めて性能アップを図りたいところです。
L85に匹敵するぐらい使いにくいブルパップであるとか、
サイズ的にも中途半端で取り回しが良いとも言えないとか、
メカボックス内部が専用パーツてんこ盛りで改修の幅がないとか、
我輩のように運良く専用のチェストリグ持っていないと
予備マガジンの持ち運びさえもままならないとか、
何よりも発射速度に難有りという素人には到底オスス出来ない電動ガンのSVU。
正直「なんで買う必要なんかあるんですか?」と言いたくなるような電動SVU、
コレを買うぐらいならLCTのAK買う方が利口だとは思うんですが、
こんなアホっぽい電動ガンなんて宮崎では我輩ぐらいしか使わないでしょうし、
何よりもロシア装備の武器が一つ増えた悦びの方が大きいので、
少しずつ性能向上を考察しながら、暫く手元で愛でることにします。
エアガンショップのサイトを見ながらニヤニヤするのが
我輩の毎年のルーティンとなっております。
我輩が武器を選定するにあたり、念頭に置いているのは以下の事項。
◎手持ちの予備マガジン、バッテリー、ポーチ等が使用可能であること
◎折鶴が折れない我輩の不器用さでも分解結合がどーにかなりそうであること
◎外装が頑丈であること
◎他のプレイヤーが買わなさそうなブツ
◎我輩の予算で買えること(ここ重要!)
上記事項を踏まえるとマガジン独自規格のPPSH41とかBARとかM3グリースガンを買うのは
可笑しいじゃねぇかのってツッコミはごもっともなので黙殺しますが、
全ての条件を満たした武器が最近日本上陸したんでソレを買いました。

中華のCYMA製SVU M-LOKです。
解る人ならフレーム見れば速攻で解るんでしょうが
SVUとはロシアのSVD(所謂ドラグノフって呼ばれているアレ)を
ブルパップ(銃床部に機関部を設けて短縮化したライフル)にしたものです。
ブツは中華電動ガンの品揃えに定評のあるフォースターで0.7パットンで購入。
(その後レールを探すためにフォースターのサイトを覗いてみたら
プラチナセールとやらで0.6パットンになっているのを見て我輩号泣)
青森に居た頃、砂井さんがAPSというメーカーのSVUを持っていたのを見て、
「あ、コレがあればSVDとマガジンorバッテリー使い回せるな」と思い、
コレは仕入れねば(使命感)!と前々から目論んでいたブツだったのです。
APS製のSVUはずっと品切れ状態で入手困難でしたが、
良いタイミングでCYMAが出してくれたんで我輩的には渡りに船でした。
手元にある我輩のブツを穴が開くほど見つめながら、
砂井さんのブログに掲載されたAPS製SVUと見比べてみたところ、
販売元がCYMAになっただけで、ブツそのものは同じである可能性が大。
ま、APS製SVUの情報はまあ多少はねネットに流れているようですが、
CYMA製SVU、しかもM-LOKのレビューあげてる人は、
まだ居ないみたいなんでまあ多少はね参考になるでしょう。
いやしかし、FA-MASとかAUGというよーな元からブルパップとして作られたライフルって、
普通のライフル以上に銃全体の構成に創意工夫があるのが面白いのですが、
SVUはSVDをそのまま何も考えずにブルパップにしたやっつけ感が凄い。
「いやマジコレ、ドラグノフなんですけどそれは大丈夫なんですかね・・・」

CYMA製SVUはオリジナルに準じたハンドガードに
トリガーガード付近から不自然ににょーんと伸びた
ステイに付けられたバイポッドがあるノーマルモデルと、
我輩が今回購入したM-LOKハンドガードのものがあります。
余談ですがコイツに付けられそうなレールが手元に無かったので、
(数年前に我輩はレール不要論を唱えてレール類は殆ど手放した)
吉六会のLINEにて「親愛なる同志一同よ、MLOK対応のレールが余っておらぬか?」
と問うたところ一部の同志は「あの閣下がMLOKとは、どういうご乱心か?」とか
「まさか・・・閣下がM4に手を出すという暴挙に出たのか・・・」と思ったそうな。
んで、SVUの写真を送ったところ「平常運行」と一同一安心した模様w
いやね、元々SVU仕入れたらあのヘンテコリンなバイポッドは撤去して、
下からレール生やしてフォアグリップ付けようと妄想していたので、
(その上、ヘンテコリンなフロント&リアサイトとサプレッサーも撤去予定だった)
んじゃあ無改造であんなもの飾りですな足がなくて、
レール付ける事が出来るMLOKがいいじゃんってなったんですわ。
ロシアのライフルにアメリカンなレールシステムはどうかと思わなくもなかったんですが、
元々スリムなSVUにスリムなM-LOKハンドガードは意外とお似合いです。
好みに合わせて好きなところにレールを増設可能なのがM-LOKの利点みたいですが、
レール無しのほうがスッキリしていて見栄えがいいかなと?

元々全長120cm位あるSVDがブルパップ化してどれぐらい短くなったのかといいますと、
AK74と同じぐらいの長さになっているんで扱いやすさは大分向上しているはずです(適当)。
苦労して作ったA&K製SVDショートバージョンよりも更に短い。
その上、SVUにはフルオートも付いているんでSVD以上の活躍が期待できます。
ていうかセミオンリーのSVDは今後使用しない可能性も微レ存?

しかし、砂井さんがブログで「発射速度が遅い!」と記載していたとおり、
箱出し状態では実銃のM3グリースガンと同じぐらいの発射速度。
写真はメカボックス調整後、再度モーターを元のやつに戻し、
7.4V 1200mAhリポバッテリー繋いで射撃した時の結果ですが、
やはりそのままでは夏バテ寸前のスカルガンナー氏にも避けられそうな勢いです。

9.9V 900mAhのリフェバッテリーを繋いでもこの体たらく。
高橋名人の16連射まではいかなくても、
せめてマルイのノーマル電動ガンぐらいの発射速度は欲しい。
実銃のSVUではフルオートは緊急時以外使用禁止らしいですが、
我輩はサバゲーでフルオート思いっきりぶっ放したいんでそんなスロー発射は嫌。
ところで、SVUの実弾は7.62mm×54Rだから7.62mm×51のG3とかM14よりも、
まあ多少はね反動が強い程度じゃないのかなって勝手な推測。

実銃ではその反動を押さえるのがこのサプレッサー兼ハイダー的なブツ。
コイツのお陰で反動がかなり軽減され、SVU実用化に至ったそうです。
サプレッサーの中にはスポンジが詰め込まれておりますが、
サプレッサーの先端付近までインナーバレルが伸びているので
発射音が軽減されている気配は全くございません。
サプレッサー自体は14mmの逆ネジで取り付けられているので、
外して別のハイダーを取り付けることも可能です。
そして奥に見える折りたたみのフロントサイト。
デザイン的にもう少しどうにかならんかったんかと思いはしますが、
このやっつけ感がロシアっぽいといえばロシアっぽい。

MLOKハンドガードは20mm幅のトップレール付属。
レールはアルミ製で軽く、塗装も綺麗、ガタツキも無し。
最近の中華パーツはレールのコマも均等で良い出来栄えです。
リアサイトの傍にあるボタンを強く押し込むとトップカバーが外れます。

トップカバー内部にはリポの細長いバッテリーを搭載可能。
少し厚みのある短いバッテリー(M4ストップパイプ用)を
突っ込んでみたんですが隙間が狭いようで無理でした。
MLOKハンドガードがスケスケなんでバッテリーや配線が丸見えなのは興ざめですが、
このハンドガード、結構細身で握りやすくてコレならフォアグリップ要らねぇかな?

樹脂製グリップはSVDのものを切り取ったような形状。
握り難いわけじゃないですが、縦に短い気がせんでもない。
スラブ系のゴツいロシア人には物足りないんじゃないでしょうか?
トリガーの上にある丸いポッチがセイフティ。
M870みたいにトリガーをロックするタイプになっております。
(実銃は従来のポジションにセイフティがある)
銃の右側に出ている状態でセイフティ、左側でファイア。
セーフからファイヤへは人差し指で操作できるので
リアルさはともかく、オリジナルよりは使いやすいです。
問題なのは無理やり増設したようなブサイクな折りたたみリアサイト。
先っちょの小さい穴を覗いて照準を合わせるんですが、
コレがまあ使いにくい見にくいったらありゃしない。
しかも上下左右の調整なんて気が利いた機能もございません。

ブルパップの難点としてマガジン交換がやり辛いことが挙げられますが、
SVUの場合マガジンが短い、そして太いということで、
マガジンとグリップの間隙が短くなっており、更にマグチェンジの難易度が高いです。
多分コレ、同志熊頃氏はグリップとマガジンに手が挟まって抜けんぞ。
正直な話、手がデカい人はSVU買わないほうがよろしいかと。
撃とうと思えば(王者の風格)撃てん事はないでしょうがかなり扱いづらい筈です。
でも手がデカい人ってほぼ例外なく、ち★ちんがデカいんだよなぁ・・・

セレクターは実銃では上から順にセイフティ、セミオート、フルオートらしいですが、
電動ガンの場合はメカボックスの都合でセイフティ状態でセミオート、
その下もセミオート、一番下がフルオートになります。
スリングスイベルはQB、じゃなくてQDスイベルです。
(QBはキュウベェなんだけどさ、QDって何の略だ?)
他社製のQDスイベルが使えるか否かは
我輩の手元にそういう近代的なブツがないので不明。
追記:2種類程試してみたところ、使える模様。
SVDではグリップが付くところにストックが設置されております。
グリップにモーターが入るSVDのメカボックスを使いまわしている都合上、
ストックに謎の傾斜が付いていてリアルさを損ねている&構えにくいのが難点。
しかもバットプレート部分がツルツルなんで、滑るんだコレが。
後でゴム版でも貼り付けましょうかね?
マガジンはCYMA、S&T、RSのマガジンと共通です。
デフォルトでは多弾数マガジンが付属。
ところでこのCYMA(或いはS&T製)ドラグノフ用の多弾数マガジン、
ショップによって120連とか190連とか表記がまちまちでどっちが正しいんじゃ?!
な感じなので弾詰めて数えてみたところ180発ぐらいしか入らなかったので
ドラグノフの多弾数マガジンは今後180連マガジンということにします。
尚、戦闘中のリロードを楽しみたい方は別売りの80連マガジンを買うべし。
でもノーマルマガジンもRSのやつは96連って書いているし、
実際何発入るのかこれもうわかんねぇなですわ。

チークパッドはトップカバーにネジ止めされております。
当然ながら高さ調整なんてぇ気の利いたものはありません。
そしてご覧のとおり、コイツは構成的に完全に右利き用のライフルです。
イギリスのL85同様、左で構えて射撃することは全く想定されておりません。

そしてこのトリガー上部のフレーム部分の樹脂製モッコリカバーに
SVU本来のマウントレールが隠れており、ネジ4本緩めるとカバーが外れます。
我輩がMLOKのSVUを購入したもうひとつの理由がコレ。
ノーマルのSVUだとドラグノフ用のスコープを別途購入しないと
光学照準器が取り付けられないのでその分財政的負担がかかりますが、
MLOKならトップレールに一般的な光学照準器が載せられるので、普遍性が高い。
MLOKの場合は上部ハンドガードにレールが付属しているんで、
この部分が使えなくても特に不具合はないんですが、
「ロシアのライフルにはPSO-1だろ?」的な原理主義者は
ココを外せば手持ちのロシアンスコープが搭載可能です。

当然ながらデフォルトのマウントレールには各社製AK用マウントが取付可能ですが、
AK用のマウントを取り付けると光学サイトの位置が高スギィ!
ロシアのゴツいヘルメット、ALTYN装着時ならコレでもいいんでしょうが、
見た目的にも実用性的にも我輩的にもコレはいただけません。

我輩のCYMA製SVDに絶賛装着中のPSO-1レプリカを取り付けると
これが本来の姿って気がしますし、しっくり来ます。
でもSVD取り付け時と同じく、スコープは左にオフセット。
まあおそロシアの暗黒面に飲み込まれた変態プレイヤー的には
「この左オフセットがいいんじゃねぇか!」なんでしょうがね。

我輩の回答はACOGレプリカ無倍率ドットサイト装着。
ACOGはマウント位置が元から高めなので、丁度いい高さです。
尚、社外品のスコープ類を搭載する場合はハイマウントのものを選ばないと、
装着は可能でもサイティングが出来ないのでご注意。
本体価格はノーマルより5000円ぐらい割高なMLOKですが、
光学サイトを選ばないという点では安上がりとも言えます。

さて、中華電動ガン黎明期にCYMA製AIMSを購入したら、
ノズルにゴミが刺さってディチューンされていたのに戦慄を覚えた我輩、
CYMA製SVU M-LOKも何かしら不安要素は秘められているに違いないということで、
メカボックス調整のために今回も1発も撃たないまま分解しちゃいますよ。
この部分はバラさなくても影響はないんですが、
サプレッサー兼ハイダーはハナっから外すつもりだったので速攻外します。
斜め位置にセットされているイモネジを緩め、逆ネジに回して外します。
フロントサイトは下からイモネジで止められているので、コレも外します。

まずはフレーム後部にあるカバー取り外しレバーをCW方向に回し、
トップカバーを持ち上げて外します。
その後チャージングハンドル上部にあるスプリング&シャフトを
メカボックス後端から外せばチャージングハンドル一式が外れます。
その後写真の位置にセレクターをCCW方向に回すと、
セレクターが外れますがココは後からでもいいでしょう。

バットプレート部分は下部のスクリューを緩めると外せます。
まあココも後から外していいんですがね。
尚、CYMA製SVUは外装の至るところにケツの穴みたいな
トルクスタイプのネジが使われているのが嫌ですね。
何度も分解するとなるとトルクスネジは煩わしいだけです。
我輩は中華電動ガン整備用or交換用に事前にハンズマンやサンワドーで
各種クロスネジや六角ネジを購入してストックしているので、
ア★ルネジを外しては捨て、それらのネジと交換します。
余談だけど八戸のサンワドー、結構ネジとか小物パーツ充実していてたし、
キャンプ用品や業務用食材とかも充実していて結構好きだった。

CYMA製SVUのメカボックスを取り出すためには、
フロント周りやバレル周りを全部分解しないといけません。
そう言うとフレーム割ればメカボックスに到達する
M4系の電動ガンの方が分解が楽な気がせんでもないですが、
手順そのものに神経を使う部分は少ないので我輩的には意外と楽です。
まず初めにチャンバーとアウターバレルを
左右から固定しているこのネジを外してしまいます。
SVDの時はコイツの有無で精度が変わるとか2発給弾が出なくなるという話だったので
面倒とは思いながらも取り付けていましたが付けなくても影響ない模様。

アウターバレルとフレームはリアサイトの下に隠れている
2本のイモネジで固定されているのでリアサイトを起こし、
リアサイト根本のマイナスネジを外し、更に根本のブロックを外して、
写真で示した部分にアレンレンチを突っ込んで緩めます。

SVDの場合はコレだけでアウターバレルが外れるんですが、
前方にトリガーやセイフティがあるSVUはそうは行きません。
トリガーガード前方にある2本のネジを緩め、
更にフレームとバレルの連結を解きます。

するとトリガー上部の中にあるセイフティのクリックが緩むので、
セイフティボタンを抜き出して外せるようになります。
ココを外さないとMLOKのハンドガードを外す時にモロに干渉します。
その後、トリガーを固定しているピンをポンチで叩いて、
トリガーの固定を解かなければアウターバレルが抜けないから困ったもんだ。

MLOKのハンドガードは下部のネジ2本でバレルに固定されているので
コレを緩めればスルッと前方に抜き出せます。
その後アウターバレルをゆっくりと前方へ引き出せば
アウターとインナーバレルが分離するので、
ゆっくりとインナーバレルをメカボックス方向へ引っ張り出して、
チャンバーが引っかからないように外せば前回りの分解は完了。

メカボックス下部のSVDので言うところのトリガーハウジングは
セレクターとカバー取り外しレバーを回して外せば、
マガジンキャッチ上部にあるピンを軸にしてこのように持ち上がるので、
このままクルッと外してしまいましょう。

写真ではトリガーハウジングを外す前に着手しておりますが、
ハウジングを外したらマガジンキャッチがあった場所の上部に
メカボックスとフレームを固定するクロスネジがあるのでソレを外します。

ハンドガード内にあったバッテリーコネクタ&ヒューズボックス部分を
ちぎれないように丁寧に引っ張って外し、
写真で指差している部分の配線の固定を緩めて、配線をフリーにします。

かなり判りづらいでしょうが場所的に写真に撮りづらいんで仕方がないね。
ドライバーで差している部分がメカボックスとトリガーをつなぐリンケージです。
トリガーにかかっているこのバーを上に持ち上げれば外れます。
そしてメカボックスをフレームから上に持ち上げて引っ張り出すと、
多分レバーも一緒に外れてくれるでしょう(適当)。
尚、組立時はメカボックスをフレームに入れると同時に、
このリンケージバーも一緒に組まないといけません。
そしてコレが結構面倒orコツを必要とするんだな。
ブルパップはこういうところが結構手間であります。

メカボックスは同社SVDのものと変わらないようで、少し違う。
SVDでは下部に出っ張っているトリガーが無く、
代わりにフルオートポジションに移動させるためのクリックや
リンケージ用のプレートが付加されております。
赤丸部分がリンケージバーのハマるポイント。

反対側はフルオートにするためのカットオフレバーや
ソレを動かすためのギアが付属しております。
とりあえず、モーターのプラス極にマイナスのコードが繋がっていても、
「ああ、このメカボはギアが4枚だから回転が逆なんだ」と認識した上で
モーターに繋がるコードを外し、モーターハウジングごとネジ緩めて外します。


上の写真がドラグノフのメカボ、下のがSVUのメカボ。
この写真を見比べながら「ひょっとしてSVUのメカボが手に入れば、
CYMA製ドラグノフをフルオートに出来るんじゃね?」って妄想しましたが、
セイフティをどうするかとか、フレームの加工とか、課題が山積みの模様。

変な妄想をする以前に、目の前にある課題を片付けましょう。
メカボックス右側のセレクターがハマるプレートを外し、
その下にあるセレクターと連動するプレートとギアを外します。
この時、◯部分にハマっているバネとポッチを無くさないように注意!
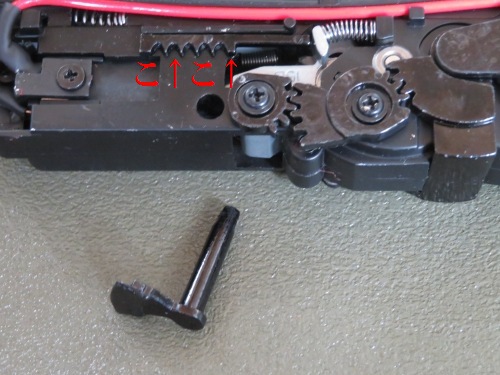
ギアとシャフトが一緒になっているパーツを外すと、
左側にあるフルオート切り替えの小さいパーツがポロッと外れるので注意。
コイツを紛失するとSVUはフルオートで撃てなくなります。

細かいパーツを確保したらギアの配置をカメラで撮影してポジションを把握。
その後外側に付いているギア類をねじを緩めて外していきます。

そしてトリガーパーツを外し、根本のバネを丁寧に外せば、
やっとメカボックスを開けることが出来るようになります。
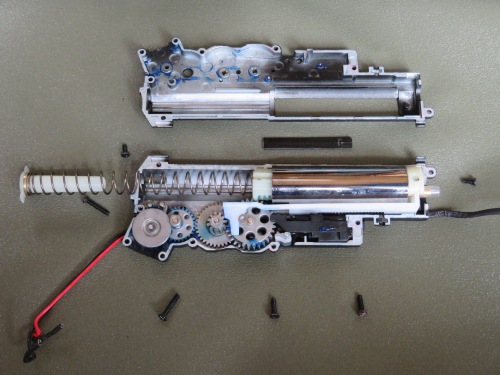
メカボックスの尻にある穴に細いドライバーを突っ込み、
逆転防止ラッチを開放したらメカボックス周囲のネジと
上部にあるプレートを外してメカボックス開放。
デチューンのためのプラの破片とか、変なゴミとかは入っていませんでしたが、
青くて粘度が高くて気持ち悪いグリスがベッタリと塗られております。
ギア類は速攻で外し、ギアもメカボ内部もブレーキパーツクリーナーで洗浄。
シムは上下ともに0.2mmのやつが1枚ずつと適当にぶっ込んでいるのみ。
とりあえず手持ちのキレイなシムと交換してデフォの状態で組んでみました。

メカボックス内パーツはCYMA製ドラグノフと同じです。
謎に短いノズル、オフセットしたシリンダーヘッド、
長いタペットプレートとシリンダーとピストン、スプリング。
一般的なパーツが流用可能なのはスプリングガイドとピストンヘッド、
そしてピストンのOリングぐらいであることを再確認し、
青いグリスを拭き取ってマルイ純正グリスでも塗りましょう。

参考までにスプリングの写真を掲載。
一番上・・・CYMA SVU純正スプリング
2段め・・・SHS M100スプリング
3段目・・・SYSTEMA M110スプリング
一番下・・・旧世代マルイ純正スプリング
同じぐらいの長さのスプリングを入れないと、確実に作動に支障をきたしますので、
ぶっ込むとしたらM100ぐらいの長いスプリングを入れることになるでしょう。

砂井さんのブログによるとハイスピードモーター換装が
発射サイクル上昇の一番手っ取り早い手段ということなので、
ヅイマー氏曰く「強いバネも引けて、サイクルもアップ、いいゾ^~これ」という
「SPARK High Torque Moter INAZUMA」をぶっ込んでみました。
後はスカスカだったピストンのOリングをマルイ純正のものと交換、
650mmのクソ長いインナーバレルは450mmのマルイAK47用と交換、
チャンバーパッキンもマルイ純正と交換して組み直します。

どうでもいい改修ですが、セイフティのポッチがONでもOFFでもどちらかに飛び出していて
パット見解りづらかったのでフレームとほぼツライチになるように3mmほど削りました。
コレによってセイフティのON/OFFが解りやすくなりました。

レールはMLOK用の80mmサイズを同志クリ◯◯ス・コスッタ氏から提案&提供。
フォアグリップだけ付けるならコレでも必要にして充分です。

握り具合に疑問の残るグリップをAKのものと交換したいなと思い、
とりあえず底蓋外してグリップ外してみたんですが、
AKのグリップ内部にパテ盛り加工しないと付けられない模様なので今後の課題に。

組み込み時の注意点は以下のとおり。
◎トリガーとトリガーリンケージの組み込み
◎配線のルーティング
◎セイフティボタン組み込み
◎モーターに配線つなぐ時は黒をプラスに、赤をマイナスに繋ぐ
これらの事項に注意すれば、すんなり組み上がるはずです。

ロシア原理主義者的には外装のカスタムなんてもっての外なんでしょうが、
特徴的なサプレッサーを外してKMのドラグノフハイダーと交換し、
フロント&リアサイトは撤去してコレも同志クリ◯◯ス・コスッタ氏から提供された
マルイM4用のフリップアップサイトをバックアップ用に取り付け、
(余談だがこのフリップアップサイト、フェイスマスク装着状態ではサイティング出来ないw)
ハンドガード下部にマルイのショートグリップ取り付けて一応の完成。
ハイダーが長いので全長はさほど変わりませんが、
全体的なシルエットがスッキリして野暮ったさが無くなったと自負。
欲を言えばもう少しコンパクトでインパクトのあるハイダーを付けたいとか、
ガスチューブの直ぐ先にハイダーを付けたいとか、課題は山盛りです。

初速は適正ホップで88~90m/sぐらいとまあ悪くない数値ですが、
それよりも特筆すべきというか、目を疑うのは発射速度。
INAZUMAモーターを搭載しているのに毎分600発程度の発射速度とは・・・
まあそれでも、ノーマルより多少マシにはなったんでなんとか戦えそう。

9.9Vリフェを使えば大抵の電動ガン並みの発射速度になるんで、
新たにスティックタイプのリフェバッテリー仕入れたい衝動に駆られております。
11.1Vのリポ使えばもっと早くなるんでしょうが、
それをすると確実にメカボ、ぶっ壊れるでしょうねぇ・・・

モーター換装でサイクルがまあ多少はね早くなったお陰か、
ドラグノフで多発していた2発給弾は起こらず、
セミオートでも安定した性能を発揮してくれるのが嬉しいです。
という事はCYMAのドラグノフも、ハイスピード系のモーターに換えれば良くなるかも?
ただ、バレルをAK並みに短くしたのが災いしたか、
命中精度は普通の電動ガンレベルなのが少し不満ですね。
まあ、コレでもサバゲーに使えないことはないのでしょうが、
もう少し突き詰めて性能アップを図りたいところです。
L85に匹敵するぐらい使いにくいブルパップであるとか、
サイズ的にも中途半端で取り回しが良いとも言えないとか、
メカボックス内部が専用パーツてんこ盛りで改修の幅がないとか、
我輩のように運良く専用のチェストリグ持っていないと
予備マガジンの持ち運びさえもままならないとか、
何よりも発射速度に難有りという素人には到底オスス出来ない電動ガンのSVU。
正直「なんで買う必要なんかあるんですか?」と言いたくなるような電動SVU、
コレを買うぐらいならLCTのAK買う方が利口だとは思うんですが、
こんなアホっぽい電動ガンなんて宮崎では我輩ぐらいしか使わないでしょうし、
何よりもロシア装備の武器が一つ増えた悦びの方が大きいので、
少しずつ性能向上を考察しながら、暫く手元で愛でることにします。
2019年06月08日
自衛隊装備用サイドアームの決定版!
「更新するのはいいけど、鉄砲の話題ばっかじゃん」と
お思いの同志も少なくないと思います。
でも何度もしつこく言いますが実はココはサバゲーのブログです。
いやね、なんだかんだ言って我輩、エアガン弄ったり、
銃器に纏わる話をしている時が一番楽しい、元気になれるって理解しました。
只の暇つぶしではない、生きがいとかライフワーク的な趣味があるということは、
人が人らしく生きるために、そして自分を取り戻すために必要であると確信しました。
まあ我輩に関しては嫁の実家でM1ガーランド見つけたことがきっかけで
回復に至る事が出来る程度の小さい心の痛みだったとも言えなくもありませんが、
趣味があることで、そして趣味に関わる友人が居てくれることで、
精神的な傷口を癒せるというのは間違いではないと思います。
さて、去年膝を怪我した時の保険金(0.5パットン程度)が年明けに入ったので、
「我輩的にコレは買わなければイカンだろう」なハンドガンを買いました。
買ったのは大分前の話なんですが、その時はブログアップする気力がなかったんで、
遅ればせながらクスリが効いて元気な今、アップする事にします。

今回レビューするのはタナカのSIG P220IC 9mm拳銃です。
現在、自衛隊が採用しているハンドガンです。ガスを使って動きます(名言)。
初見で「箱がP220モデルガンの色違いだな」って思ったんですが、
調べてみたら実銃(P220)もこんな感じのロゴが入った箱(色は淡い青)の模様。
自衛隊の9mm拳銃はスイスのSIG社とドイツのザウエル&ゾーン社が
共同開発したSIG SAUER P220という名前の拳銃を
日本のミネベア(現ミネベアミツミ)がライセンス生産したものです。
尚、ミネベアミツミという会社はベアリングを主に作っている会社で、
世界最小の1.5mmベアリングを開発したトンデモな会社。
世界一よく回るハンドスピナーの中身はミネベアが作っているんだって。
ところで一時期アレだけ流行ったハンドスピナー、どこに逝ったんだ?
何でベアリングの会社が拳銃を作っているのかといいますと、
新中央工業というニューナンブM60(お巡りさんのリボルバーね)を
作っている会社を吸収合併したからなんですね(はいココ試験に出まーす)。
タナカのSIG P220or9mm拳銃は20年ぐらい前から販売されておりましたが、
それがあまりにも出来が良くないのをようやく理解したのか、
それともついに本気を出してくれたのか真相は不明ですが、
去年「IC(インテグレーテッド・シャーシシステム)」という
名称を引っさげて完全リニューアルしちゃいました。
お値段は税抜き定価24800円と次世代じゃない電動ガンが買えそうな
WA製品と比べたらちったぁマシだけどハンドガンとしては随分法外なお値段なのですが、
(参考までにマルイのハンドガンは大半が15000~18000円ぐらい)
過去の9mm拳銃に比べるとそれだけのカネを払う価値のある逸品です。

(上の写真は20年ぐらい前に購入したマグナブローバックの9mm拳銃)
以前販売していたブツはメカがWAのマグナであるとは思えないほどの
面白みのない緩いブローバックと遠くに飛ばないホップアップシステム、
暫くするとジャムを起こすようになるし、酷い時は生ガス吹き出す。
そしてマガジンからは物凄いガス漏れという産業廃棄物レベルの代物でした。
去年まで自衛隊コスプレサバイバルゲームプレイヤーの大半は
「マルイがP220を出してくれればいいのに(迫真)」と思いながら
仕方なくタナカの9mm拳銃を腰に(装飾品として)ぶら下げていたり、
「昔は自衛隊もガバメント使っていたから」と心で呟きつつも
不本意な気分でマルイのM1911A1を使っていたことでしょう。
或いは我輩のように「自衛隊もP226を採用すればいいのに」と思っていたとか。
だってさぁ、装弾数9発+1の拳銃なんてガチで使うには弾数足りなすぎでしょ?
CQBとか想定するならドズル・ザビ中将の「戦いは数だよ兄貴!」の
言葉通り弾数多い方が明らかに有利でしょう?
まあ9mm拳銃が採用された1970年代後半~80年代という時代は
何処の軍隊でも威力に優れるアサルトライフルこそが戦場では正義、
射程の短い拳銃弾を使うサブマシンガンは警察の武器という扱い、
拳銃はさほど重要視されていなかった時代ではありましたがね。
自衛隊のとある部隊ではP226やUSPが使われているとの噂ですが、
一般的に自衛隊で使われている拳銃はこのP220。
一説によると自衛隊がM1911A1に換わる拳銃を検討していた際、
装弾数も使い勝手も勝るP226があったにもかかわらずP220を採用した理由が
「P220の方がグリップが薄く、日本人に適している」だったという逸話があるとか?

旧作との外観の大きな違いはスライドとフレームの色が同一ではない事。
スライドはパーカーグレー、フレームはブラックです。
実銃ではスライドはスチールプレス、フレームはアルミと素材が違うので、
色分けすることでそれを再現しているとのこと。
尚、全てのパーツをリニューアルして作られたという事で、
全てのパーツは旧作と互換がないそうです。

材質は普通のABS樹脂で、重量は740g。
マルイP226やグロック17、XDM-40と同じぐらい。
実銃は830gらしいので重量にそう大差はありませんね。
多分暫くしたらヘビーウェイトが限定で販売されそうな予感。
各パーツは分解レバー以外、手抜きのない出来栄えで、
(我輩の個体は分解用のラッチだけ表面がボコボコしている)
フレームのパーティングラインもしっかり処理されており、
流石モデルガンメーカーの製品だと唸らされます(感嘆)。
我輩、マルイのP226のフレーム下部のパーティングラインが気に入らなくて、
耐水ペーパーでシコシコ磨いて綺麗にしたんですがね、
作業に掛ける手間を考慮したら3000円ぐらい払ってもらわねぇとやってらんねぇ。
だからパーティングラインの処理がしている⇒その分お値段高いのは当然と思います。

上がタナカ9mm拳銃、下はマルイP226(見れば解るか)。
外観の大きな違いは装弾数の増加によるグリップの太さ、
ハンマーやレバーの形状、グリップの滑り止めの形状、ランヤードリングの位置、
そしてマガジンキャッチの位置(9mmはグリップボトム、P226はグリップサイド)。
実はP220よりもP226の方がグリップ幅が狭いんですね。
元々P220はアメリカ向けに45ACPにも対応したサイズで作られたので、
9mmパラベラムの拳銃としてはグリップが太くなっているそうです。
我輩的にはデザインは9mm拳銃(P220)の方が好み。
グリップがストレートで滑り止めがギザギザしていているのが前時代的でカッコいい。

前作の9mm拳銃がどーいう作りだったかは覚えていませんが、
新型のP220 ICは金属のシャーシレールをフレーム先端まで伸ばすことで
確実なブローバックを実現させているらしいです。
そしてこのシャーシの名称が、インテグレーテッド・シャーシなんだとか。
その上、二次的作用として長いシャーシがフレームに収まることで、
耐久性と重量アップにも貢献しているようです。
スライドを引くとインナーバレルが飛び出してくるのは
モデルガン的観点から見ると興ざめではありますが、
サバイバルゲームのツールであると考えれば些細な問題に過ぎないでしょう。

余談ですが我輩がSIG SAUERの拳銃が好きな理由、
ソレはマガジンリリース、デコッキングレバー、スライドストップといった
拳銃の各操作部が全て親指で操作可能であることです。
でも9mm拳銃はマガジンリリースがここら辺に付いていないんだな。
M1911はスライドストップが遠い、M92Fはセイフティが遠い、
USPはマガジンリリースが使い難い、となると我輩的にはP226が一番!
え?グロック?そーいえばそういう拳銃もあったよね?

マガジンリリースはワルサーP38やSIG210、ベレッタM1934といったよーな、
古い時代の拳銃に見られるグリップ底部に設けられた所謂コンチネンタルタイプなので、
先程も申しました通り、戦闘中の素早いリロードには向いておりません。
但し、戦闘中に不意にマガジンが抜け落ち難いという利点があります(適当)。
一説によると自衛隊とか防衛庁(当時)のお偉いさんはP220を見て
「このマガジンリリースは脱落防止にいい!」と感激してコイツを採用したとか?
薬莢一つ、部品一つ無くしたら大事になる自衛隊らしい噂話です。
マガジンがシングルカーラムなので、グリップは薄く握りやすいです。
グリップの質感もなかなかよろしく、フレームとのフィッティングもキマっています。

他社の色んなハンドガンに比べると、刻印は控えめで薄め。
SIG SAUERのオリジナルはもう少し主張のある刻印なんですが、
ミネベア(現ミネベアミツミ)でライセンス生産された9mm拳銃は
本物もそれ程刻印が主張していないのである意味リアル?

ところで、我輩陸自コスプレサバゲー用に9mm拳銃を買ったはずなのに、
何を血迷ったか航空自衛隊モデルを購入しちゃったんですねwww
陸自のやつとの違いは桜に翼がついていること。
何で陸自のじゃなくて空自の買っちゃったのかといいますと
今後資金難で売却する際、一般的な陸自モデルより、
生産数が少なさそうな航空自衛隊モデルの方が高く売れそうだからです。
んで、ふと思ったんですが空自の刻印ってこんなに小さかったかな?
陸自モデルの桜はもう少しデカかったはずなんですが・・・

リアサイトは別パーツですが、フロントサイトはスライド一体成型です。
サイトにはホワイトが入っていてエイミングもしやすいです。
ダブルアクションのトリガーリーチはP226より気持ち遠いですが、
シングルは可もなく不可もなく、だけど素直なトリガーフィーリングです。
尚、SIG SAUERの拳銃はデコッキングレバーでハンマーを落とした状態にする事を
安全装置としているのでセイフティは付いておりません。
但し、タナカの9mm拳銃は実銃同様マガジンセイフティが組み込まれており、
ガスと弾が入ったマガジンを装填しただけでは発射出来ないようになっております。

実銃では9発のマガジンは20発装填可能。
前作では12発ぐらいしか入らなかったので、コレは大きな進歩。
サイドアームとして充分役に立つキャパシティでしょう。
ガスは満タンで2マガジン半ぐらい射撃可能です。
しかも・・・何処からもガス漏れしない!
(何を言っているんだとお思いの方が居るでしょうが、
前作の9mm拳銃のマガジンは新品でもガス漏れした)

分解はまずマガジンを抜いて(当たり前ですね)、
スライドストップをかけたらトリガーガード上のラッチを反時計回りに90度回転。

その後スライドストップを解除すればスライドとフレームが分かれます。
余談ですが実銃の9mm拳銃は弾が入っていなければ
マガジン入れたままでも分解可能。
昔、MGCのP220のモデルガンで試したら本当に分解できた。

各パーツどれも丁寧に作られており、手を加える必要性は皆無。
インナーバレルは先端1cmぐらいに段差があります。
スライドを引くと時々、ハンマーがスライドのブリーチに引っかかりますが、
射撃してみても特に不具合はないのでハンマーを削る必要はなさそうです。

スライドストップはスライドの切り欠きではなく、
スライド内のブリーチに引っかかって止まる方式なので、
スライドが無慈悲に削れる心配はしなくてもいいです。素晴らしい!

ホップの調整はチャンバー下のダイヤルを左右に動かすことで調整可能。
右回しで弱くなり、左に回すと強くなります。
ホップの性能も前作とは段違いで、0.2g弾で30mぐらい飛んでいきます。

ブローバックはマルイUSPほどハードなキックではありませんが、
マルイのP226と遜色ないぐらい気持ちよくスライドが動きます。
前作と比べると目からウロコが100枚ぐらい落ちそうなキレの良い作動に感動します。
命中精度も確かで、10mぐらいなら幅10cm以内に収まります。
射手の能力次第では20m先の人間に当てることも可能でしょう。
つまり、マルイのハンドガンと撃ち合っても負けることはないでしょう(断言)。
ただ、マガジンが薄いので気温が低い時に連射すると厳しいですね。
そこら辺はガスの入る量が少ないシングルカーラムならではの難点です。
前作の9mm拳銃と比べると見た目、作動、性能、全てにおいて優れる新作9mm拳銃。
自衛隊装備でサバゲーするプレイヤーのお供としては勿論、
コレクションの一つとしても価値ある逸品であると断言できる!
「いいゾ~これ」「ああ^~いいっすね^~」
タナカにはこの勢いでぜひ、ブローニング・ハイパワーもリニューアルして欲しい。
お思いの同志も少なくないと思います。
でも何度もしつこく言いますが実はココはサバゲーのブログです。
いやね、なんだかんだ言って我輩、エアガン弄ったり、
銃器に纏わる話をしている時が一番楽しい、元気になれるって理解しました。
只の暇つぶしではない、生きがいとかライフワーク的な趣味があるということは、
人が人らしく生きるために、そして自分を取り戻すために必要であると確信しました。
まあ我輩に関しては嫁の実家でM1ガーランド見つけたことがきっかけで
回復に至る事が出来る程度の小さい心の痛みだったとも言えなくもありませんが、
趣味があることで、そして趣味に関わる友人が居てくれることで、
精神的な傷口を癒せるというのは間違いではないと思います。
さて、去年膝を怪我した時の保険金(0.5パットン程度)が年明けに入ったので、
「我輩的にコレは買わなければイカンだろう」なハンドガンを買いました。
買ったのは大分前の話なんですが、その時はブログアップする気力がなかったんで、
遅ればせながらクスリが効いて元気な今、アップする事にします。

今回レビューするのはタナカのSIG P220IC 9mm拳銃です。
現在、自衛隊が採用しているハンドガンです。ガスを使って動きます(名言)。
初見で「箱がP220モデルガンの色違いだな」って思ったんですが、
調べてみたら実銃(P220)もこんな感じのロゴが入った箱(色は淡い青)の模様。
自衛隊の9mm拳銃はスイスのSIG社とドイツのザウエル&ゾーン社が
共同開発したSIG SAUER P220という名前の拳銃を
日本のミネベア(現ミネベアミツミ)がライセンス生産したものです。
尚、ミネベアミツミという会社はベアリングを主に作っている会社で、
世界最小の1.5mmベアリングを開発したトンデモな会社。
世界一よく回るハンドスピナーの中身はミネベアが作っているんだって。
ところで一時期アレだけ流行ったハンドスピナー、どこに逝ったんだ?
何でベアリングの会社が拳銃を作っているのかといいますと、
新中央工業というニューナンブM60(お巡りさんのリボルバーね)を
作っている会社を吸収合併したからなんですね(はいココ試験に出まーす)。
タナカのSIG P220or9mm拳銃は20年ぐらい前から販売されておりましたが、
それがあまりにも出来が良くないのをようやく理解したのか、
それともついに本気を出してくれたのか真相は不明ですが、
去年「IC(インテグレーテッド・シャーシシステム)」という
名称を引っさげて完全リニューアルしちゃいました。
お値段は税抜き定価24800円と次世代じゃない電動ガンが買えそうな
WA製品と比べたらちったぁマシだけどハンドガンとしては随分法外なお値段なのですが、
(参考までにマルイのハンドガンは大半が15000~18000円ぐらい)
過去の9mm拳銃に比べるとそれだけのカネを払う価値のある逸品です。

(上の写真は20年ぐらい前に購入したマグナブローバックの9mm拳銃)
以前販売していたブツはメカがWAのマグナであるとは思えないほどの
面白みのない緩いブローバックと遠くに飛ばないホップアップシステム、
暫くするとジャムを起こすようになるし、酷い時は生ガス吹き出す。
そしてマガジンからは物凄いガス漏れという産業廃棄物レベルの代物でした。
去年まで自衛隊コスプレサバイバルゲームプレイヤーの大半は
「マルイがP220を出してくれればいいのに(迫真)」と思いながら
仕方なくタナカの9mm拳銃を腰に(装飾品として)ぶら下げていたり、
「昔は自衛隊もガバメント使っていたから」と心で呟きつつも
不本意な気分でマルイのM1911A1を使っていたことでしょう。
或いは我輩のように「自衛隊もP226を採用すればいいのに」と思っていたとか。
だってさぁ、装弾数9発+1の拳銃なんてガチで使うには弾数足りなすぎでしょ?
CQBとか想定するならドズル・ザビ中将の「戦いは数だよ兄貴!」の
言葉通り弾数多い方が明らかに有利でしょう?
まあ9mm拳銃が採用された1970年代後半~80年代という時代は
何処の軍隊でも威力に優れるアサルトライフルこそが戦場では正義、
射程の短い拳銃弾を使うサブマシンガンは警察の武器という扱い、
拳銃はさほど重要視されていなかった時代ではありましたがね。
自衛隊のとある部隊ではP226やUSPが使われているとの噂ですが、
一般的に自衛隊で使われている拳銃はこのP220。
一説によると自衛隊がM1911A1に換わる拳銃を検討していた際、
装弾数も使い勝手も勝るP226があったにもかかわらずP220を採用した理由が
「P220の方がグリップが薄く、日本人に適している」だったという逸話があるとか?

旧作との外観の大きな違いはスライドとフレームの色が同一ではない事。
スライドはパーカーグレー、フレームはブラックです。
実銃ではスライドはスチールプレス、フレームはアルミと素材が違うので、
色分けすることでそれを再現しているとのこと。
尚、全てのパーツをリニューアルして作られたという事で、
全てのパーツは旧作と互換がないそうです。

材質は普通のABS樹脂で、重量は740g。
マルイP226やグロック17、XDM-40と同じぐらい。
実銃は830gらしいので重量にそう大差はありませんね。
多分暫くしたらヘビーウェイトが限定で販売されそうな予感。
各パーツは分解レバー以外、手抜きのない出来栄えで、
(我輩の個体は分解用のラッチだけ表面がボコボコしている)
フレームのパーティングラインもしっかり処理されており、
流石モデルガンメーカーの製品だと唸らされます(感嘆)。
我輩、マルイのP226のフレーム下部のパーティングラインが気に入らなくて、
耐水ペーパーでシコシコ磨いて綺麗にしたんですがね、
作業に掛ける手間を考慮したら3000円ぐらい払ってもらわねぇとやってらんねぇ。
だからパーティングラインの処理がしている⇒その分お値段高いのは当然と思います。

上がタナカ9mm拳銃、下はマルイP226(見れば解るか)。
外観の大きな違いは装弾数の増加によるグリップの太さ、
ハンマーやレバーの形状、グリップの滑り止めの形状、ランヤードリングの位置、
そしてマガジンキャッチの位置(9mmはグリップボトム、P226はグリップサイド)。
実はP220よりもP226の方がグリップ幅が狭いんですね。
元々P220はアメリカ向けに45ACPにも対応したサイズで作られたので、
9mmパラベラムの拳銃としてはグリップが太くなっているそうです。
我輩的にはデザインは9mm拳銃(P220)の方が好み。
グリップがストレートで滑り止めがギザギザしていているのが前時代的でカッコいい。

前作の9mm拳銃がどーいう作りだったかは覚えていませんが、
新型のP220 ICは金属のシャーシレールをフレーム先端まで伸ばすことで
確実なブローバックを実現させているらしいです。
そしてこのシャーシの名称が、インテグレーテッド・シャーシなんだとか。
その上、二次的作用として長いシャーシがフレームに収まることで、
耐久性と重量アップにも貢献しているようです。
スライドを引くとインナーバレルが飛び出してくるのは
モデルガン的観点から見ると興ざめではありますが、
サバイバルゲームのツールであると考えれば些細な問題に過ぎないでしょう。

余談ですが我輩がSIG SAUERの拳銃が好きな理由、
ソレはマガジンリリース、デコッキングレバー、スライドストップといった
拳銃の各操作部が全て親指で操作可能であることです。
でも9mm拳銃はマガジンリリースがここら辺に付いていないんだな。
M1911はスライドストップが遠い、M92Fはセイフティが遠い、
USPはマガジンリリースが使い難い、となると我輩的にはP226が一番!
え?グロック?そーいえばそういう拳銃もあったよね?

マガジンリリースはワルサーP38やSIG210、ベレッタM1934といったよーな、
古い時代の拳銃に見られるグリップ底部に設けられた所謂コンチネンタルタイプなので、
先程も申しました通り、戦闘中の素早いリロードには向いておりません。
但し、戦闘中に不意にマガジンが抜け落ち難いという利点があります(適当)。
一説によると自衛隊とか防衛庁(当時)のお偉いさんはP220を見て
「このマガジンリリースは脱落防止にいい!」と感激してコイツを採用したとか?
薬莢一つ、部品一つ無くしたら大事になる自衛隊らしい噂話です。
マガジンがシングルカーラムなので、グリップは薄く握りやすいです。
グリップの質感もなかなかよろしく、フレームとのフィッティングもキマっています。

他社の色んなハンドガンに比べると、刻印は控えめで薄め。
SIG SAUERのオリジナルはもう少し主張のある刻印なんですが、
ミネベア(現ミネベアミツミ)でライセンス生産された9mm拳銃は
本物もそれ程刻印が主張していないのである意味リアル?

ところで、我輩陸自コスプレサバゲー用に9mm拳銃を買ったはずなのに、
何を血迷ったか航空自衛隊モデルを購入しちゃったんですねwww
陸自のやつとの違いは桜に翼がついていること。
何で陸自のじゃなくて空自の買っちゃったのかといいますと
今後資金難で売却する際、一般的な陸自モデルより、
生産数が少なさそうな航空自衛隊モデルの方が高く売れそうだからです。
んで、ふと思ったんですが空自の刻印ってこんなに小さかったかな?
陸自モデルの桜はもう少しデカかったはずなんですが・・・

リアサイトは別パーツですが、フロントサイトはスライド一体成型です。
サイトにはホワイトが入っていてエイミングもしやすいです。
ダブルアクションのトリガーリーチはP226より気持ち遠いですが、
シングルは可もなく不可もなく、だけど素直なトリガーフィーリングです。
尚、SIG SAUERの拳銃はデコッキングレバーでハンマーを落とした状態にする事を
安全装置としているのでセイフティは付いておりません。
但し、タナカの9mm拳銃は実銃同様マガジンセイフティが組み込まれており、
ガスと弾が入ったマガジンを装填しただけでは発射出来ないようになっております。

実銃では9発のマガジンは20発装填可能。
前作では12発ぐらいしか入らなかったので、コレは大きな進歩。
サイドアームとして充分役に立つキャパシティでしょう。
ガスは満タンで2マガジン半ぐらい射撃可能です。
しかも・・・何処からもガス漏れしない!
(何を言っているんだとお思いの方が居るでしょうが、
前作の9mm拳銃のマガジンは新品でもガス漏れした)

分解はまずマガジンを抜いて(当たり前ですね)、
スライドストップをかけたらトリガーガード上のラッチを反時計回りに90度回転。

その後スライドストップを解除すればスライドとフレームが分かれます。
余談ですが実銃の9mm拳銃は弾が入っていなければ
マガジン入れたままでも分解可能。
昔、MGCのP220のモデルガンで試したら本当に分解できた。

各パーツどれも丁寧に作られており、手を加える必要性は皆無。
インナーバレルは先端1cmぐらいに段差があります。
スライドを引くと時々、ハンマーがスライドのブリーチに引っかかりますが、
射撃してみても特に不具合はないのでハンマーを削る必要はなさそうです。

スライドストップはスライドの切り欠きではなく、
スライド内のブリーチに引っかかって止まる方式なので、
スライドが無慈悲に削れる心配はしなくてもいいです。素晴らしい!

ホップの調整はチャンバー下のダイヤルを左右に動かすことで調整可能。
右回しで弱くなり、左に回すと強くなります。
ホップの性能も前作とは段違いで、0.2g弾で30mぐらい飛んでいきます。

ブローバックはマルイUSPほどハードなキックではありませんが、
マルイのP226と遜色ないぐらい気持ちよくスライドが動きます。
前作と比べると目からウロコが100枚ぐらい落ちそうなキレの良い作動に感動します。
命中精度も確かで、10mぐらいなら幅10cm以内に収まります。
射手の能力次第では20m先の人間に当てることも可能でしょう。
つまり、マルイのハンドガンと撃ち合っても負けることはないでしょう(断言)。
ただ、マガジンが薄いので気温が低い時に連射すると厳しいですね。
そこら辺はガスの入る量が少ないシングルカーラムならではの難点です。
前作の9mm拳銃と比べると見た目、作動、性能、全てにおいて優れる新作9mm拳銃。
自衛隊装備でサバゲーするプレイヤーのお供としては勿論、
コレクションの一つとしても価値ある逸品であると断言できる!
「いいゾ~これ」「ああ^~いいっすね^~」
タナカにはこの勢いでぜひ、ブローニング・ハイパワーもリニューアルして欲しい。